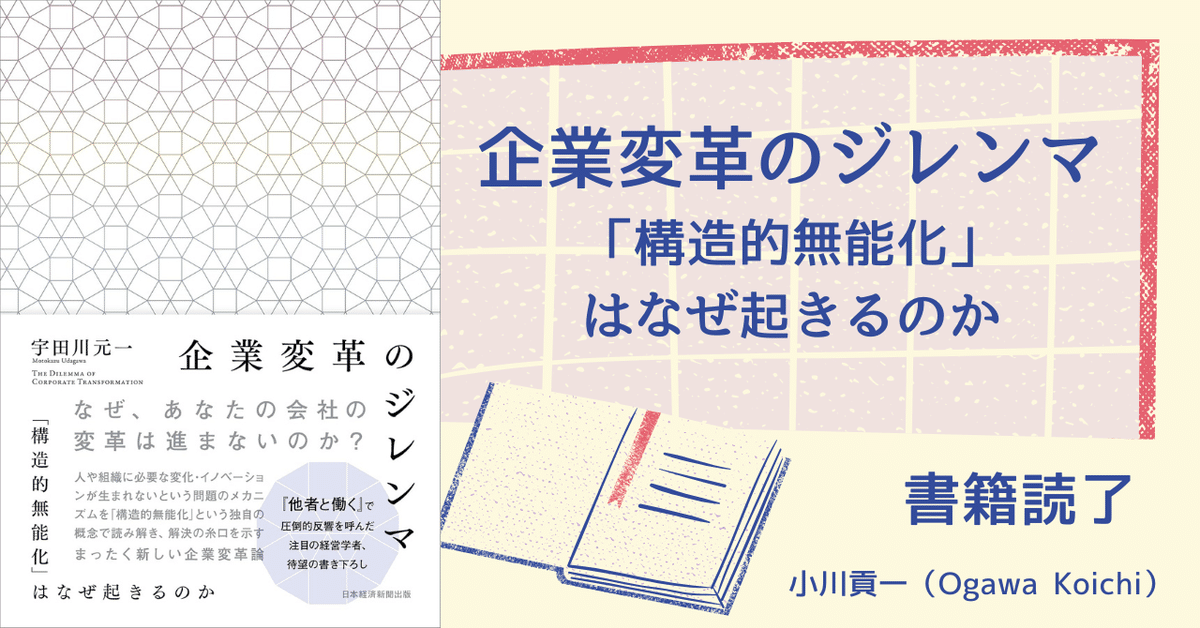
書籍【企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか】読了

https://booklog.jp/users/ogawakoichi/archives/1/B0D7M82K36
◎タイトル:企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか
◎著者:宇田川元一
◎出版社:日経BP 日本経済新聞出版
「構造的無能化」にはメチャクチャ納得。組織の「部分最適」が進めば進むほど「全体最適」からは遠ざかる。
これは宿命と言っていいのか。
本書では、これこそ「構造的」と言っている。
つまり仕組み上の欠陥だと、ズバリ言っているのだ。
なぜこんなことが起こるのか。
これは自分自身でも日常的に実体験として起こっていることのため、ものすごく共感できる。
変な話、仕事が細分化されて部分最適がなされ、自分の持ち場が与えられたら、真面目な人ほどそれを全うしようと思ってしまう。
不真面目では困るわけで、目の前のことを真面目にコツコツとこなす人が評価されることになる。
それでよさそうなものだが、実は真面目でコツコツが進めば進むほど、自分の仕事以外のことに、目が行き届かなくなってしまうのだ。
もちろん、日常的に回っている限りにおいては、それで問題はない。
自分の仕事が全体として何の役になっているかなんて、考える必要もない。
新入社員が社長に対して、「この仕事は無駄だと思うので、止めた方がいいと思う」なんて言った日には、社内の中間管理職全員がその場で凍り付くだろう。
(最近はこういう若手の意見も尊重される風潮かもしれないが)
つまり部分最適は、理由があってそうしている訳で、普段であれば部分最適こそが、組織を機能させる充分な方法論なのだ。
何もトラブルがなければそれでいい。
しかし緊急事態の時は、その「部分最適」こそが、事故の悪化を引き起こす要因になってしまう。
本書にも例示が書かれているが、ロンドンの地下鉄「キングス・クロス駅」の火災は、まさに部分最適が引き起こした悲劇だ。
自分の職務を全うすればするほど、「組織全体の中で抜け落ちてしまう仕事」を誰も拾えなくなってしまう。
これは、私の会社でもよくある話だから身に覚えがある。
緊急事態でなくとも、新しい仕事が舞い込んだだけで、「これは私の仕事ではありません」と言って、誰も拾わないことが往々にして起きてしまう。
これは当然で、自分の人事評価は、与えられた今までの仕事で計られる。
だから真面目にコツコツ積み上げている訳で、新しい仕事を引き受けたがために、今までの仕事に悪影響が出たら、自分の評価が下がってしまう。
こんなことになったら、損をするのは他でもない自分なのである。
だからこそ組織の管理職が全体を目配せし、穴がないように上手にマネジメントする訳であるが、これが簡単にはいかない。
「管理職=マネジャー」だから、マネジメントすることが本来の仕事であるが、マネジャー自身も、大きな組織の中では「全体の中のある部分」しか任されていなく、さらに上の上司にマネジメントされる側の人間でもある。
マネジャーの自分が、さらに上の上司から新しい仕事を任されたら、結局自分の組織に余計な仕事は持ち込みたくないと、後ろ向きな行動をとるのが普通だ。
だからこそ「構造上の問題」なのであり、これをどうやって乗り越えていくかは、とんでもない難問である。
果たして解決する方法はあるのか、ということになるが、難問である以上簡単な解決は望めない。
単純に何か「打ち手」を行って、それで解決するのであれば、昔からとっくに実行して解決しているはずだ。
これにはとにかく時間がかかることを前提に、少しずつでも変えていくしかないということだ。
面白いのは「解決しようとするのではなく、眺めてみる」という考え。
とにかく課題を掘り下げる。
◎なぜそんな問題が起きてしまったのか?
◎本当の原因は一体何なのか?
◎いつからそういう状態になったのか?
これを時間をかけて、問い続けてみる。
そこで「こうしよう」が生まれればよいが、掘り下げて眺めてみることが重要だと言う。
これは面白いアプローチだ。
課題が可視化されたのなら、解決したくなるものだが、行動する訳でもなく、放置する訳でもなく、「眺めて」みる。
そこで働く人たちが、それを見てどう感じるか。
感じた気持ちの流れに、意識を向けること。
なんだか集団瞑想のように思えるが、一歩引いて自分たちの組織と仕事を客観的に見直してみることが大事なのだろう。
改革には時間がかかる。
決して「時間をかけるべき」と言っている訳ではない。
時間がかかるのを前提に、改革をしていくということだ。
そこで話が出るのは、「そういう文化だからしょうがない」という言い訳であるが、文化のせいにしていたら、いつまで経っても変革することはできない。
それでは「企業文化を変えてやる」と息巻いたところで、そんなものはいくら急いでも今日明日に変えることはできない。
「時間をかけて眺める」ことに、企業側が耐えられるかどうか。
そんなことしている内に倒産してしまう、と焦りも出るかもしれない。
読み進めながらも、実行の難しさはやはり感じてしまった。
それでも眺めることのメリットは、短期視点から「長期視点」に、切り替えができることかもしれない。
分業が進むと、どうしても組織は断片化する。
すると、短期視点にならざるを得ない。
これが「構造的無能化」であるが、時間をかけて過去を眺めることは、長期の未来を見据えることに繋がる第一歩なのかもしれない。
とにかく変革には時間がかかる。
時間をかけてでも変革に取り組み続ける。これしかない。
(2024/12/16月)
