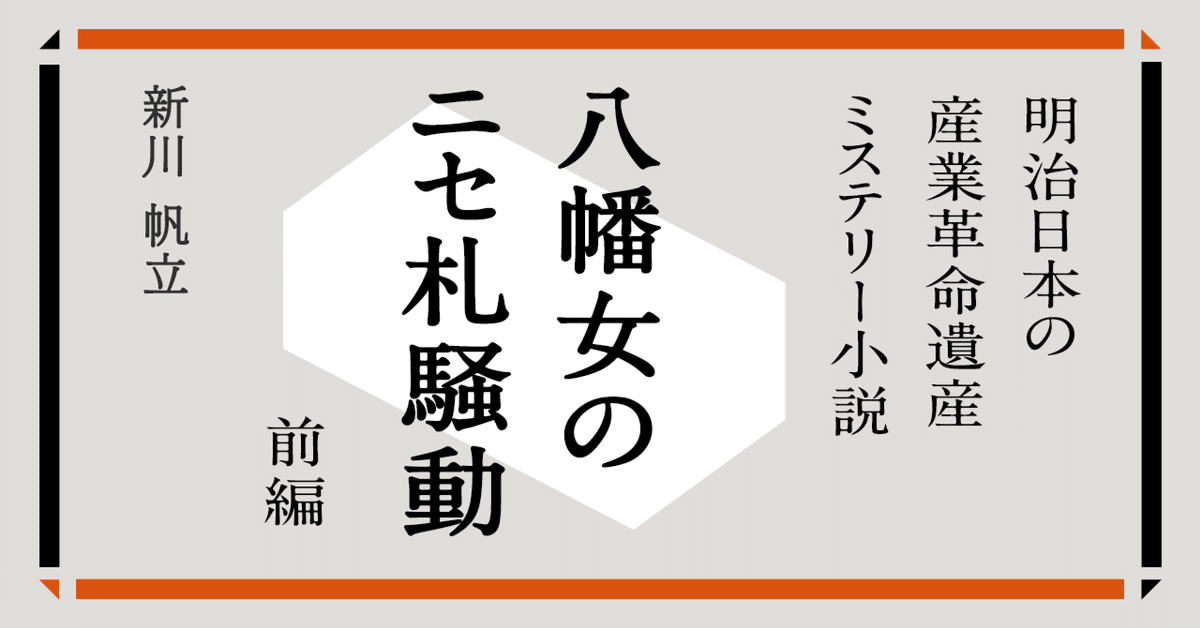
【世界遺産・短編小説】「八幡女のニセ札騒動」前編
明治日本の産業革命遺産ミステリー小説
新人ミステリー作家の登竜門『このミステリーがすごい!』大賞受賞者をはじめとした新進気鋭のミステリー作家たちが、世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の地を実際に訪れて短編のミステリー小説を書き下ろし。広域にまたがる構成資産を舞台とした物語をミステリー作家陣が紡いでいきます。
ものづくり大国となった日本の技術力の源となり、先人たちの驚異的なエネルギーを宿す世界遺産を舞台にした不思議な物語を通じて、この世界遺産の魅力をより多くの方に感じていただき、価値が後世に繋がっていくことを願っています。
八幡女のニセ札騒動
新川 帆立
玄関のベルが鳴るなんて何年ぶりだろう。ここには保険の勧誘人も、布団のセールスマンもこない。ずっと居留守をつかっていたら福祉の人もこなくなった。指を折って数える。十、十一、十二……すくなくとも十五年くらいは、誰も訪ねてきていなかった。
肩にかけていただけの浴衣に袖をとおし、床に転がしてあった小倉織の半幅帯をきゅっとしめる。すっかり薄くなった髪を片手でなでつけ、よろめきながら玄関に向かった。
「はァい」思った以上に朗らかな声が出た。

たてつけの悪い引き戸をひと思いに引くと、あたしより頭一つ低いところに、丸い顔が見えた。十歳くらいか。半ズボンと白いTシャツを着て、ナイロンのリュックを背負っている。
「あっ」と、目の前に立つ少年が声をもらした。目をいっぱいにひろげて、こちらを見ている。「すんません、えーっと、おばあさんが……えー」
「なんの用ね?」ぎろりと見かえす。
少年はヒィとおびえたような声をあげ、肩をすぼませた。
「おばあさんが、伝説の女スリ、里見さとだって、本当ですかッ?」
勢いこんだように少年は声を張りあげた。その鼻先に叩きつけるように、あたしは引き戸をぴしゃりとしめた。
「えっ、ちょっと、待ってください。えっ。おばあさんがあの『弁天おさと』じゃないんですか」
引き戸の向こうで小さい影が騒いでいる。
「野次馬はうせな」
唾をとばしながら言って、きびすを返そうとしたそのとき、
「ぼく、丹沢慎吾っていいます。丹沢刑事の孫です。小学五年生です」
息がとまるかと思った。
引き戸にふたたび手をかけ、おそるおそるあける。
真っ黒に日焼けした、焼きおにぎりのような顔が得意げに笑っていた。
「お話をきかせてもらえませんか。じいちゃんについて調べているんです」
「夏休みの自由研究かなんかね?」
「いやっ、えー、そうじゃなくて」慎吾はモジモジしながらうつむいて言った。「ただ気になって、調べてるんです。だから、だいじょうぶです。学校の先生にも言わないし、警察にも言いません」
心にひろがる苦いものを感じながらきいた。
「……丹沢さんは、元気しとると?」
「じいちゃんは、先月、死にました。八十八歳、老衰でした」
「そうか」短く言って、息をはいた。
あたしらくらいの歳になれば元気もなにもない。くしの歯が欠けるように知り合いがどんどん死んでいく。いまさら同情したり、悲しんだりしない。ただ、家族に見守られながら苦しまずに逝った人の話をきくと、そういう人生を歩んでみたかったものだと少しうらやましく思う。
「言っておくが、サツの前に出されても、こっちにはなんの弱みもないけんね。これまでやった犯罪は、全部自白して、懲役したもん。あわせて十九回刑務所に入ったんや。被害者の人たちには悪いことしたと思っとる。けどいまはスリをすっぱりやめて、働いて、この家を建てて、年金で細々暮らしとる。そりゃあ道のまんなかを歩ける身の上ではないにしても、お天道様に顔向けはできる」
「ニセ札のことも、警察は知ってるんですか?」
「ニセ札?」
「これです」
慎吾はリュックを前向きにからって、その中からビニール袋をとりだした。
あたしは首をかしげながらあごを突きだし、ビニール袋の中を見た。
千円札が一束入っていた。
「手にとって、見てみてください」
慎吾にうながされるまま、ビニール袋に手を突っこみ、それをまじまじと見る。
聖徳太子の千円札だった。
昔はこれが大金だった。小学校の先生の初任給が二万円くらいだったはずだ。モノクロのテレビの前にむらがり、洗濯機の絞り機ハンドルを力いっぱい回し、留守電もない黒電話の前で友達からの連絡を待つ。そういう娘らしい娘時代をあたしは送らなかったけど、国鉄のプラットフォームでひろった婦人雑誌を食い入るように読んだものだ。
「千円札が百枚、十万円分あります」
慎吾が淡々とした口調で言った。
「じいちゃんがタンスに入れて、持ってたものです。身体が悪くなってきて、もうやばいぞってなって、入院することになったんですけど。病院に行く前の晩、じいちゃんが僕を枕元に呼んで、言いました。『タンスの一番下、左奥の箱に入っとる札束、あれはニセ札や。誰にも見つからんうちに、焼いて捨ててしまえ』って。僕は驚きました。だってじいちゃんはずっと刑事をしていて、ズルは絶対に許さない人だったから。怖かったけど、自分にも厳しかった。毎日同じ時間に起きて、同じ新聞を読んで、散歩をして、掃除をして。死ぬ直前まで、きちんと、真面目に、暮らしていた。ニセ札なんて隠し持ってるわけないのに」
「あの人がどういう刑事だったか、知っとるんね?」
慎吾はこちらの反応をうかがうように上目遣いをしながら、うなずいた。
「じいちゃん本人は何も言いませんでしたけど、ばあちゃんが自慢してましたから。四十年くらいの刑事生活の中で、ホンブチョーショーってのを何百回ももらってるそうです。スリ逮捕競技で全国一位のレジェンドで――」
その先はあたしが引き取った。「この『弁天おさと』を唯一捕まえることができた男、『掏摸係の鬼』といえば、丹沢光亥だよ」
坊主頭で銀縁眼鏡、小柄だがたくましく鍛えられた男の背格好が脳裏にうかぶ。顔をしじゅうほころばせて人をそらさない愛想のよさがあった。だが目だけはスンと冴えている。いつの間にかすぐ横にいて、「アンタ、またやったね」と笑いかけてくる。
一度ふたを開けると、つい昨日のことのように記憶がよみがえった。
初めて会ったとき、丹沢刑事は比翼仕立ての灰色のコートを着て、黒っぽいハンチング帽をかぶっていた。そうあれは寒い日だった。
二月だった。それも、今からちょうど六十年前。
世界でも類を見ない五市合併でこのあたりが湧いていたころだ。
「ちょいと、外を歩きながら話そうか」
慎吾にそう声をかけて、草履に足をとおした。

戦争の真っただ中にあたしは生まれた。
父は出征先で死んだという。母は、まだ首もすわっていないあたしを腕に抱いて、八幡空襲のなかを逃げ惑った。官営八幡製鐵所を第一目標として、B‐29が初めて投入された空襲だった。
いまは市立中央図書館が建っている場所、あそこには昔、小倉陸軍造兵廠があった。あたしには年の離れた兄が二人いたらしいが、二人とも学徒動員で造兵廠にいたところ、B-29の直撃弾を受けて死んでしまった。
母は命からがら、着の身着のままで、なんとか終戦を迎えた。といっても、幼子がいてはまともな仕事につけない。若松にあった親戚の家にあたしを預けて、戸畑へ働きに出るようになった。最初の数年は毎週末、ポンポン船に乗ってあたしの顔を見にきてくれた。だけど、あたしが五歳になるころから母がやってくる回数は減り、いつのまにか音沙汰すらなくなった。外に男ができて、どこかで新しい家庭をつくったのだろう――と、子供ながらに分かった。
あたしは親戚の家を転々とすることになった。どこにいっても金食い虫といっていびられる。あたしはどんどんひねくれていった。
中学を出てからは、世話になっていた縁戚の雑貨問屋を手伝うようになる。住まいも商売もあるのはありがたいが、実際はただ働きをさせられるばかりで、どうにもしんどかった。
十八歳の春、あたしは店の金を五万円持って家を出た。
ちょうど世間はオリンピック前の好景気にわいていた。みんな嬉しそうに顔をほくほくさせて、大股で歩いていく。それを見ているとよけいくさくさした。
魚町をうろついていると、兼子という男と親しくなった。この男が「木鼠の勝」という名うてのスリだった。家には怪しげな男たちがひっきりなしにやってくる。兼子は男たちにスリの稽古をつけてやっていた。
上着やズボンの外ポケットから掏るのは初心者で、上着のボタンを外し、内ポケットから財布を抜いて空財布だけ元に戻し、ボタンまではめてやるような技もあった。まるで手品みたいに見事なものだった。
見ているうちに、あたしもやってみたくなった。門前の小僧で基本のキくらいは分かっていたから、ついむくむくと悪心を起こして、小倉駅で紳士の内ポケットから一万円を抜いた。こんなに簡単に大金が手に入るのかと興奮にうちふるえ、すっかり味をしめてしまった。次々と手を出し稼いでいた。
丹沢刑事に会ったのはそんなときだ。
枝光駅前にあった中華料理屋で、あたしは炒飯を食べていた。神棚におかれたテレビではTNCの「テレビ・インターハイ」をやっていた。高校対抗クイズの番組なのに、背広姿のおじさんたちがぞろぞろと出てきて、みんな嬉しそうに笑っている。
「何なの、このおっさんら」
と店主にきくと、店主は「お前知らんのか。五つの市が合併して、北九州市つうのに、なるんよ。新しい市の名前、募集しとったやろ。俺はてっきり、西京市になると思っとったわ」と言う。
どうも、新しい市名の全国公募では「西京市」がトップだったらしい。そのまま諮問会議でも西京市に決まる雰囲気だったところ、ひとりの長老が「天子様がおられた歴史がないのに、京と名乗っていいのかなあ」とつぶやいたそうだ。そう言われた途端みんなシュンとなって、公募で二番目だった「北九州市」になったという。
「そんで、このおっさんらは何なん?」あたしはテレビを指さした。
「合併する市の市長さんらよ。昨日合併がまとまって、報道にも出たから。重荷が下りたっつうことで、みんなニコニコ、テレビ出てるわけよ」
確かにおじさんの数を数えるとちゃんと五人いる。若松高校の生徒たちとクイズで対決し、ボロ負けしていた。高校生らは勝ち誇りつつ、照れたように両手を挙げた。会場がドッと笑いに包まれる。
あたしは舌打ちをして、上着のポケットからがま口財布を取りだして中を見た。
三千円入っているきりだ。それ以上の金はどこを探してもない。
オリンピックだ、五市合併だ、若乃花だ、鉄腕アトムだと、世間は騒がしい。けれどもあたしらの底辺の者の暮らしはちっとも変っていない。妙にいじけた気持ちになって、勘定をすませ、店を出た。
駅前を歩いてくる一人の青年に目をつけた。
外套の外ポケットが不自然にふくらんでいる。給料袋でも入っているのだろうか。靴も帽子も新品で、若いのにかなり羽振りがよさそうに見えた。
どいつもこいつも浮かれやがって、と再び舌打ちをした。
頭にかぶっていたベージュのフェルト帽を片手にとり、髪形をなおすふりをしながらサラリーマンに近づいた。フェルト帽を持ちかえて「幕」にして、相手の視界をふさぎ、もう片方の手で外ポケットに手を突っこんだ。やはり、パンパンにふくらんだ封筒が入っていた。青年はこちらの動きにまったく気づいていない。いい稼ぎになった――と思って、ほくそ笑みながらその場を離れようとしたところ、後ろから声がかかった。
「おさと、今のは見事な芸当だったなあ」
振り返ると、丹沢刑事が立っていた。
人相はスリの間で有名だから、すぐに彼だと分かった。おにぎりみたいに人の良さそうな顔でニコニコしながら、両手をポケットに突っ込んで、おちょくるようにいたずらっぽい目で見つめてきた。
丹沢刑事が声をかけたことではじめて、青年は金を掏られたことに気づいたらしい。慌てた様子で外套のポケットを裏返している。
あたしは捕まるのが初めてだった。内心かなり驚いていたけど、すぐにかしこまった顔をつくって、
「とんだところをお目にかけまして」
と、丹沢刑事に頭を下げた。
昔のスリは、今と違って逃げたりしなかった。捕まったら神妙にしておく。そうすると刑事さんもこちらに手錠をかけない。手錠をはめられないスリだというのは、仲間うちでも自慢できることだった。
丹沢刑事はあたしを放っておいて、被害者の青年と二、三分話をして、戻ってきた。
「あの青年が、その金はくれてやると言っている。ありがたく受け取っておくように。被害者がいいと言うから、この件は見なかったことにしとくよ」
手に握った封筒の中をのぞくと、千円札がぎっしり入っていた。これを全部もらえて、しかもおとがめなしなんて、いい話だ。だけど、あたしにもスリとしてのプライドがあった。
「いえ、いりませんよ」
青年にかけより、つき返そうとした。
「いらないなら、なんで盗るんだ」と丹沢刑事は笑った。
「盗ったものは自分のもんにしますけど、もらいたくはないんですわ」
すると青年が口をひらいた。
「そりゃ、あぶく銭だからくれるわ」
九州の人間とは違うイントネーションだった。関西弁のようにきこえるけど、大阪の人の話し方よりのったりしている。
「俺な、仲間内で、賭けてたさ。新しい市の名前が何になるか。みんな西京市に賭けていたが、おれだけ北九州市に賭けた。それで儲かったわさ。でもこんなところで運を無駄につかうのはかなんなあ。そんだから、それはくれますわ。俺は別に金に困ってねえし、お姉さんは困ってるみたいだし。金は天下の回りものでさあ。お気になさらず、とってください。そんじゃあ」
こちらの制止もきかず、青年は足早に立ち去ってしまった。
そういうことだから、と丹沢刑事もあたしの肩を叩き、どこかへ消えていった。
一人残されて、あたしの手の中には千円札の束が残った。
冷たい風が吹きつけていた。とぼとぼと裏路地を歩きながら、札束の枚数を数えた。ちょうど百枚、十万円分あった。
もうかったのだけど、どうもみじめだった。俺は別に金に困ってねえし、お姉さんは困ってるみたいだし――だなんて。青年は好景気に乗った実業家なのか、金回りがよさそうに見えた。十万円をポンと人にやれる身分なのだろう。対するあたしは、確かに金に困っていた。だからこそ、金をもらうのはみじめだった。盗みが成功していれば、丹沢刑事が現れなければ、こんな思いはせずにすんだ。
ふっと目をあげると、道の向こう側に八幡製鐵所の旧本事務所が見えた。
レンガ造りの立派な建物だ。もうつかわれていなかったみたいけど、地元の人がよく自慢をしていたから知っていた。レンガ積みはイギリス式で、屋根は和式の瓦葺だ。当時は第三高炉が戸畑で火入れを開始したころだったから、全国から技術者が集まっていた。
「三重の人やわ。あれは三重弁や」
独り言をつぶやいた。
三重からきた技術者と、枝光本町の飲み屋で一緒になったことがある。その男も「やる」という意味で「くれる」と言い、語尾に「さ」とか「わさ」とかつけていた。困るというような文脈で「かなんなあ」とも言っていた。つかう言葉、イントネーションともにさっきの青年に似ている。年ごろが違うから、同じ人ではないだろうけど、同郷の匂いがした。
「三重からわざわざきて、何の用なんやろ」
宙に向かって言うと、おずおずと家に帰った。
