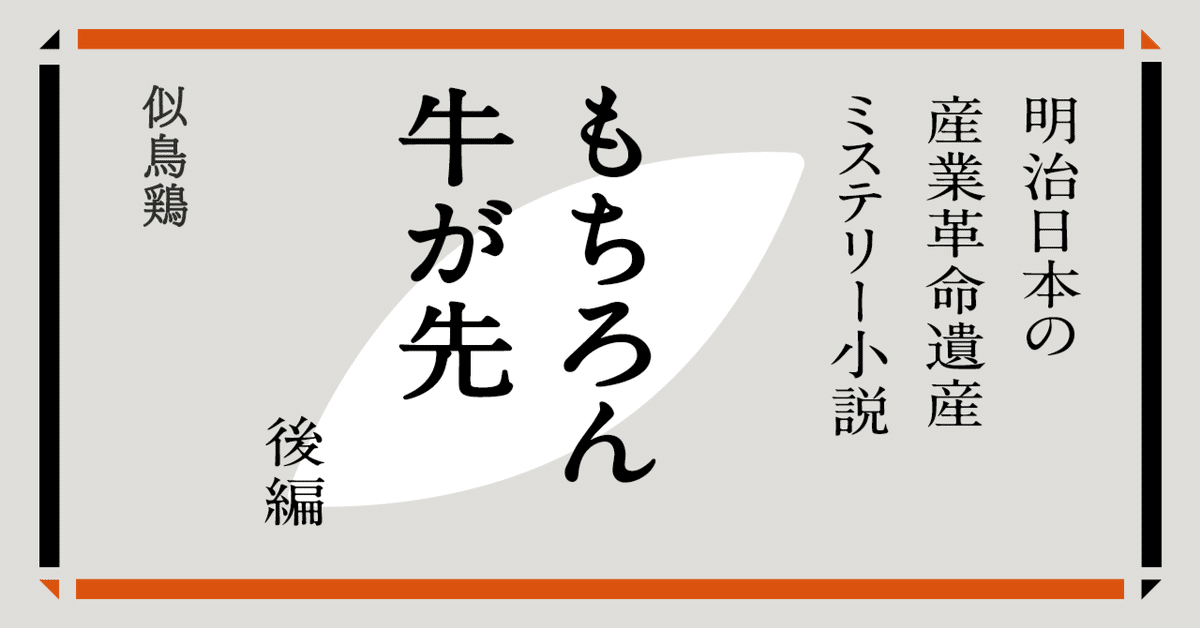
【世界遺産・短編小説】「もちろん牛が先」後編
3
歴史館を出ると、道を渡った向かいの川沿いに広々とした公園が現れる。土手の上に立つと周囲が広々と見渡せた。三重津海軍所の中心となる修覆場地区(ドック跡)、海軍の訓練を行った稽古場地区、実際にまだ使用されている船屋と並ぶ。修覆場に隣接する製作場の跡は一見、ただの草原だが、あちこちに遺構の平面表示や解説板があり、地形もそのまま残っているので、当時の施設のスケール感が実感できるようになっている。約百六十年前、まさにここで、この足下の同じ場所で、日本の未来をかけて蒸気船の開発が行われていたわけだ。土手の上に立つと、夏の風が吹き渡るのを感じた。後ろでクマゼミがしゅわしゅわしゅわと鳴いている。早津江川がゆったりと流れている。今は干潮に近いようだが、ここからどのくらい水が引くのか。地元の人なら分かるのだろうか。

さすがに周囲に人がいるとまずいので外に出たのである。平塚警部補はよほど気がはやっているのか、通話を切らずにずっと待っている。
「……ええと、今、出ました」携帯をスピーカーモードにすると、警部の声が急にクリアになった。
――了解。しかし、さすが名探偵ですな。もう謎が解けたと。
「はっはっは」唯さんは声色を変えた。「『四十一年前の赤子、ぴんぴんと致し候』」
――何です?
「すいません今、佐賀にいまして」急いで補足する。「唯さん、鍋島直正が気に入ったようで」
――はあ。
ぴんと来なくても無理ないだろう。元ネタがマニアックすぎる註5 。
――まあ、とにかくお礼を。助かりますよ本当に。何しろ現場にいた若い奴がね、辞表出しとるんですわ。犯人を逃がしたのは自分の責任だと。
「『死のうとは何事だ!』」
――何です?
「すみません。今、佐賀にいまして註6 」得意顔をしている唯さんに言う。「本題、始めてあげません?」
「事件当時はゲリラ豪雨で、かなり激しい雨が降っていたんですよね」唯さんはいきなり始めた。「……だとすれば、鉄道線路と交差するアンダーパスは冠水していた可能性があるのでは?」
――あ、ああ。はい。……ありうるとは思います。見た限り、わりと危険な構造ですな。
「犯人の視点で考えましょう。牛小屋に突っ込んでしまった。慌てて下笹窪林道に逃げ込んだ。でも出口付近で検問をやっていることに気付いた」
電話の向こうから反応はない。平塚警部補は傾聴モードに入ったのだろう。
「ゲリラ豪雨の中、犯人は追い詰められたはずです。戻れないし、林道には横道はない。袋のネズミだ、と。しかも出口手前のアンダーパスは冠水していて通行不可能だった」
アンダーパスの冠水については僕も知っている。まわりの土地より低いため、周囲の水が一斉に流れ込むことがあるのだ。ワゴン車が屋根までまるまる水没している映像を見たことがある。まして車は完全に水没しなくても、フロア面あたりまで水に浸かっただけで停まってしまう可能性がある。エンジンの空気取り入れ口が水で詰まるからだ。
「犯人は車を止め、アンダーパスに徒歩で入ってみたかもしれません。たとえば、そこで気付いた。アンダーパスの排水溝に物が詰まっているせいで冠水している。これを取り除けば水がなくなる。だが、もっと詰めればもっと水位が上がる」
――そりゃそうでしょうが、水位を上げてどうするんですか。
「軽トラの積み荷がペットボトルか何かだったとしたらどうでしょうか」
――えっ。
そう。三重津海軍所のドライドック。水が入れば船は浮き、出入りが可能になる。
「犯人は排水溝にごみを詰めて、冠水した水位を上げたんです」唯さんは言った。「ちょっと前ですけど、歩行中の女性が、急に冠水したアンダーパス内で溺死するという事故があったの覚えてます?」
アンダーパス=冠水で危険、というイメージが全国に普及したきっかけの一つだ。僕もニュースを見た記憶がある。
「歩行者が溺死するなんて、当時は考えられなかったんです。でも、検証してみるとそれがあり得ることが分かった。事故当時の映像を見ると、午前十一時の時点では地面が見えていたのが、その三十分後には見えなくなり、そのわずか三十分後には、水面が高さ二メートルの位置に設置されたカメラに迫っている。その後、水位は三メートル二十センチにまで上昇しました。何もしていない状態でも、アンダーパスはここまで急激に水位が上がることがあるんです。まして、意図的に排水溝を詰めたのなら」
完全に水没する。水面は、四メートル上の鉄道線路付近まで上昇する。
――しかし、車は水にゃ浮きませんよ。
「だからペットボトルなんです。犯人は、たまたま自分の車が今、荷台に山ほどペットボトルを積んでいることに気付いた。これを浮き具にすれば、軽トラを水に浮かせられるかもしれない」
学校で習った記憶がある。ペットボトルは浮き具としてかなり優秀で、溺れた人を見かけたらまず空に近くした(完全に空にしてしまうと投げ渡すのが難しくなる)ペットボトルを投げろ、と。
「『FOMM ONE』って御存知ですか。東日本大震災の経験から製作された、水に浮く車です。四人乗りで、車体重量は620㎏。四人乗ったとして、荷物込みで850㎏くらいはあるでしょう。おそらく、それでも浮く可能性があるように設計されています」
僕はすでに唯さんから説明を受けているので、平塚警部補の反応を待つばかりである。土手の上から早津江川の流れが見える。その上を有明早津江川大橋が通っている。行き交う車が小さく見える。
「浮力は体積に比例します。軽トラだとFOMM ONEよりやや体積が小さいので、はたらく浮力は750㎏程度だとします。軽トラの車体重量は1150㎏程度。つまり多めに見積もっても、400㎏ほどの浮力を足せば、水に浮くことになります」
草の中から飛び出したバッタが僕の足下を横切った。後ろでクマゼミがまた鳴きだしたようだ。
「概算ですけど、2ℓペットボトルの浮力は1本で2㎏。つまり2ℓペットボトル200本を車体にくくりつければ、追加で400㎏の浮力が得られることになりますよね」
――200本、ですか。
「40本セットを5ケース、と言った方がイメージしやすいかもですね。軽トラの荷台は1940mm×1410mmが普通です。二段にすれば200本は余裕で載せられます。たまたま犯人がそうしていたとしたら」
後ろが現場、前は検問と冠水で逃げ道なしだ。試せる手段はそれしかない。
「犯人はアンダーパスの排水溝にゴミを詰めた。そして水位が上がるのを待つ間に、ペットボトルを車体にくくりつけた。事業用のものを運搬していたなら数十本ごとにまとめてあったはずで、思ったより手間はかからなかったかもしれません。そして水位が上がりきり、水面が鉄道線路に近くなったら、車を水の中に発進させる。とてもゆっくりでしょうが、車輪が回れば水上でも前進はできたはずです。外輪船のように」
そういえば歴史館にも模型が置いてあった。凌風丸の試作品は、蒸気機関車をそのまま船体に載せたような形をしていた。
「重さを減らすため、アクセルペダルは固定して自分は降りていた可能性はありますが。……いずれにしろ軽トラは、アンダーパスの上を走る線路内に上がったでしょう。それを確認したら、排水溝に詰めておいたごみを引っぱって外す。あらかじめ、詰め物にロープを結びつけておいたはずです」
遺留品のビニールカバーだろうか? 鑑定すれば、痕跡は出てくるだろう。物証になる。
「……というわけで、問題の軽トラは線路内に侵入して、どちらかの方角に逃げた可能性があります」
あるいは下笹窪林道の捜索がもう少し早ければ、不自然に冠水したアンダーパスに気付いていたかもしれない。だが、話に聞いた状況では牛が優先だろう。そこは責められるべきではないと思う。牛は大事である。
――ありがとうございます。よく分かりました。
警部補は納得したようだったが、すぐに、うーむ、という唸り声が続いた。
――しかしそうすると、完全に逃げられてしまったことに。
「だから、もっとがっつり捜査態勢を敷かないと駄目ですよ。このトリックを実行したとすると、一時的にとはいえ往来妨害罪でもあるんですから」唯さんの声はすでに晴れ晴れとしている。「ただでさえ体感治安が下がって、検挙率も落ちてるんです。警察官同士で派閥争いなんてしてる場合じゃないですよ。そのキャリアとも協力してください」
――ううむ。そうですな。これは大事件だ。
「ずるい人になってください。それじゃ」
一方的に電話を(しかも人の電話機で)切るのはいつも通りだが、他人に説教をするとは珍しい。
珍しいので携帯で「ずるい人」を検索したら出てきた。幕末、倒幕派・佐幕派双方からの誘いをのらりくらり躱し続けて藩内の力を温存した鍋島直正を、徳川慶喜がそう評したらしい。だがそれは外からの評価だ。合理主義者の直正のことだ。欧米列強の脅威が迫る中、日本国内で争っている場合ではない、と考えていたのだろう。
註5 直正が四十一歳の時、教育係の磯濱に当てた手紙に書かれていた文句。磯濱は現代から見ても先進的と言えるほどの教育方針の持ち主で、遊ぶ際、殿様の子であっても接待プレイみたいなことはせず対等に負けさせたし、「危ない遊びをさせない」のではなく「重大な危険を排除した上で自由にやらせる」というやり方だったらしい。鍋島直正の先進性と合理性を育てたのは磯濱かもしれない。
註6 文献等では確認できないが、直正は鉄製大砲の鋳造失敗が続いたため切腹しようとしていた責任者を叱咤してそう言い、どうか研究を続けてくれるよう激励したという伝がある。他に人材がいないこと、研究には失敗が必要であることを理解していただけでなく、もともと部下に腹を切らせることをよしとしなかったらしい。
4
佐賀の空は、昨日より少し雲が多い。
通話を切って顔を上げた瞬間、ごう、と風が吹いて体が押された。海風かと思ったが潮の匂いはない。ただ単に天気が不安定になってきているがゆえの普通の風だろう。見上げてみると、さっきまで青空が広がっていたのに、いつの間にか半分近くが灰色の雲に覆われている。そういえばここに来る途中から、空の彼方にはこれから天気が荒れる伏線のように濃い雲が来ていた。

「……あれ、唯さん?」
さっきまで隣にいたのにまた消えた、と思ったら、唯さんは四つん這いになって干潟の土を覗き込んでいた。肩にかけたバッグが土の上にずり落ちそうになっているので後ろから持って支える。
「……平塚さんから?」
「はい。昨日言ってた問題の軽トラ、見つけたそうです。やっぱり水上走行は無理があったみたいで、線路から降りてしばらく走ったところでエンジントラブルを起こして立ち往生してたのを、近所の自動車整備工場の人が助けてました」
昨日、「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」でトラック消失の謎を解いてからまだ二十六時間ほどしか経っていないのだが、平塚警部補からはお礼の電話が来た。唯さんは昨日の電話を切った直後から完全に観光モードに戻り、佐賀市北方の古湯温泉で一泊した後、「東よか干潟」に来ている。干潟で潮をかぶりながら生育する「シチメンソウ」は冬場には赤く、春から夏にかけピンクから緑になり、秋に再び赤くなるという変わった生態をしており、十一月頃になると干潟が真っ赤に染まる異世界のような光景が見られるそうだが、今は大人しく、一面に干潟の泥が広がり、石がごろごろ転がっている。
だけではないのだった。よく見ると泥には無数の穴がぽこぽこ空いており、潮だまりに紛れてその主が、よく見るとここでもそこでもちらちらと動いている。あの大きな鋏。シオマネキだろう。それ以外にも何かいる。
「あっ、ほら! 今そこ! 動いた!」
指さす唯さんの隣にしゃがむ。目を凝らすと見えた。ムツゴロウより小型なトビハゼだ。大きな目をぱちくりさせ、胸鰭でよいしょよいしょと泥の上を這う姿がけなげである。
「トビハゼすごい普通にいるね! かわいい」
ちょっと考える。これは適切な「かわいい」である。あまり水を差したくはないのだが。
「えーと……一応、平塚警部補からの伝言で」唯さんを窺う。手短にしたかった。「好待遇を用意してるから、警察職員に加わって継続的に捜査協力をお願いしたい、と……」
頼まれた手前、一応訊きはしたが。「……断っときますね?」
唯さんはははは、と笑ってみせた。「痔でござってな」
「それですか註7 」
註7 典拠となる記録は不明だが、幕末、倒幕派佐幕派どちらにもつかなかった鍋島直正は、味方にしようとやってきた幕府からの使いにこう言って断ったという伝がある。
似鳥鶏(にたどり・けい)
1981年千葉生まれ。
2006年『理由(わけ)あって冬に出る』で鮎川哲也賞佳作入選、同作でデビュー。作品に「戦力外捜査官シリーズ」(河出書房新社)「育休刑事シリーズ」(KADOKAWA)をはじめとするシリーズや、『叙述トリック短編集』(講談社タイガ)『推理大戦』(講談社文庫)など多数。乗り鉄のため佐賀県内の路線はすべて乗ったことがあるが、ちょうど千灯籠まつりの時に松浦鉄道に乗ってしまい混雑に貢献する。ミステリを書くが説明が下手。ホラーを書くが怖がり。
写真提供:佐賀県観光連盟
