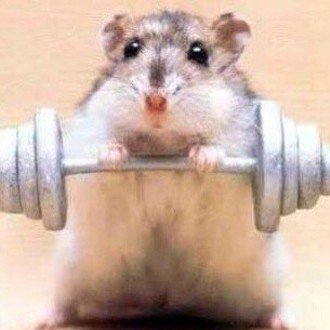街から本屋さんが消える日は来るのか
ネットニュースなどで「街から本屋が消えていっている」と報道されれば、必ずと言って良いほど「いや!街には本屋さんは必要なのだ!」という論調の記事が掲載される。
言ってることは良くわかる。
そう、確かにわかるんだよ。(逆に言うと、言われなくてもわかってるよ!ってくらい)
子供の頃から、商店街の中に本屋さんがある生活が普通だった。
漫画を買うにも、参考書を買うにも、何か情報を仕入れるにも本屋さんに行くのが当たり前だった世代ですからね。
物の売り場には独特な匂いがする。
デパ地下なら、当然のようにお惣菜の匂い。
デバートって言葉ももう古いかもしれないけど、デパートの1階は大抵は化粧品売り場。私の大して有能でもない鼻でさえちょっと堪える匂いがする。
2階以上になると衣料品などの売り場だ。特にバッグ売り場あたりは革製品の匂いがする。これは結構好き。
で、本屋さんには紙の匂いなのか、印刷の匂いなのか、はたまた糊の匂いなのか、これも「本屋さん臭」がする。
実は私はあの匂いがちょっと苦手。糊の匂いで気分が悪くなったこともある。(幼稚園での工作の時間は、今でいう酩酊状態だったのかもしれない)
でも、やっぱり本屋さんに行くのを辞めない。
本マニア(?って居るのか?)にはおなじみの神保町あたりの「古本屋街」。
学生の頃は、ちょっと遠出をしてでも本を「漁り」にいく。
街中に点在する古本屋さんに足を運んでは、探す本のジャンルだけしか決めていない本を片端から探しては辞め、辞めては探しをしていた。
SFマニアだったので、エドガー・ライス・バローズの火星シリーズや金星シリーズが「全巻1,000円!」とか書いてあると、衝動買いしたりする。
ラリイ・ニーヴンの「ノウンスペース(既知空域シリーズ)にもハマった。
で、時代は一気に30年くらいスリップし現代に至ると、通勤電車の中はほぼ全員がスマホでポチポチしてゲームをするか、ネットニュースを読んでいる。
文庫本や新聞を読んでいる人の数は1%も居ないんじゃないかってくらい。
この状況でどうやって本屋さんは対抗できるというのだろうか?
30年前の電車の中は文庫本と新聞と少年XX、ヤングXXという漫画雑誌の王国だったはずだ。
別に寂しいとは思わない。
新聞を大きく広げて邪魔だった中年サラリーマンの数が大幅に減ったことはむしろ嬉しい。あれは相当に邪魔で迷惑な存在だった。
大型の少年XXみたいな漫画雑誌で背中を小突かれることもなくなった。
ネットワークに繋がり、一瞬のうちに世界の情報を手元に引き寄せられる魔法の小箱を手にした人類が、簡単に紙の情報媒体に回帰するとはなかなか想像できない。
もちろん、災害時に電気が止まったりした非常時には本の地図やハンドブックはとても役に立つことはわかる。でも、あくまで緊急時なのだ。
先日遠出をして目的地がわからなかったときのGoogleマップの道案内にはひどく助けられた。あれは画期的だ。
本は無くしてはいけない物かもしれないが、日常生活で常時使用する品ではなくなっている気がする。
近所に、店内に喫茶コーナーを持つ大型書店がある。
喫茶コーナーはとても盛況だ。かなりリーズナブルな値段設定で、くつろげるソファー調の椅子と柔らかいがしっかり本が読める程度の照明。
適度なクラッシックな音楽が流れ、ゆったりと読書を楽しむことができる。
しかし、、、近年はそのスペースの大半が「スマホで電子書籍の類を読んでいる若年層」で占められるようになった。
喫茶コーナーも「書籍購入者限定」とかいう訳ではないので、格安のコーヒーを目当てに来る人でいつも満席だ。
本屋のレジで会計待ちをする列の長さも最盛期の1/3くらいか。
本屋は閑散としているのに喫茶コーナーは盛況。変な風景ではある。
かくいう自分も電子書籍を持っている。
最初は専用のリーダーを買ったが、次に「スマホのアプリでいいじゃん」ってことで、今はもっぱらスマホのアプリで読んでいる。
スマホに必要な全ての機能を集約することで、いつでも「ニュース」「動画」「漫画」「技術書」「ゲーム」を手元で実現できることは、文明を享受できている雰囲気がして気持ちが良い。
本屋さん、、、すまない。俺は誘惑に勝てないのだ。
A4版以上のサイズの技術書を通勤電車で読む腕力も衰えた。
満員電車ではスマホ分のスペースを確保することで精一杯だ。
片手でページ送りができる素晴らしさは、体験してみてわかった。
「紙の質感が心地よくて〜」とか、「ブルーライトが目に悪いから〜」とか言われてもですよ。
それでも、全部紙媒体の書籍が私の部屋から消えたのか?と問われると違う。
むしろ増えている時期さえある。
それは何故か?
ズバリ、値段だ!
電子書籍にも「キャンペーン期間は20%オフ!」とかあるが、電子書籍は古くなっても基本的に値段が下がらない。そう、つまりは「定価販売」が基本だ。
で、古本は?
目的の古本が街の本屋では手に入らないとしても、今では流通の覇者「アマゾン」や「楽天」があるだろう。
次々に発売される技術書はちょっと時間が経つと、価格ほ急落する。
読みたいと思った時に「電子書籍で買うと定価販売だけど、アマゾンで探すと10円とかで売っていたりする本」も結構ある。
で、私はネットから「古本」をポチるのである。
「あの本、読んでみたかったけど、今、いくらになっているかな?」
と思った時にネットで探し、格安古本としてゲットする。
これが私の最近の「紙媒体本」を読むスタイルになっている。
新刊本を買わないけど古本は買うってスタイルだと、
→新刊が売れない
→古本も増えない
→紙の本の発行が少なくなる
→「新刊が売れないなら、利益が上がらずに結局本屋さんは潰れる」って結論に達する。
自動車の発達した現代に人力車が主力になることはない。
ヴィンテージものみたいなコアな世界で生きていくことになるのか?
こんな記事を自宅のパソコンで書いている時点で、そう、時代は変わっていうのだと痛感するこの頃である。
いいなと思ったら応援しよう!