
アメリカ留学を振り返ってーMemorable Teachers (その9):Georgetown University Ph.D.取得、博士課程修了
TOEFL Web Magazine の筆者のコラムFor Lifelong Englishに2022年1月に掲載したものです。これからアメリカの大学院に進まれる方々の参考になればと思います。
別稿「アメリカ留学を振り返ってーMemorable Teachers(その8)」の続きです。1975年の年末から年始にかけ帰国し、友人らと楽しい一時を過ごしました。

明けて1976年、建国200周年に当たる年です。年明け早々からワシントンには祝賀ムードが漂い、社交界の中心地のGeorgetown地区もひときわ賑わい始めました。そんな中、論文執筆に向けresearchに着手しました。週日は8時から15時までGeorgetown UniversityとAmerican Universityで日本語を教えた後16時頃から、週末は10時頃からLauinger Library の個室に深夜閉館時までこもりきりです。
先ずはテーマを決め、論文指導主査1名、副査2名を選んでPh.D. dissertation committee(博士論文審査委員会)を組織してもらいます。次に委員会にプロポーザルを提出しなければなりません。テーマはA Generative Semantic Analysis of the English Modalsです。主査はWalter A. Cook先生 (Ph.D., Professor, Theoretical linguistics)、副査はRoss R. Macdonald先生(Ph.D., Professor, English syntax)および Charles W. Kreidler先生( Ph.D., Professor, English phonology)です。プロポーザルが認められるとすぐにCook先生の指導の下researchに着手しました。
Ph.D. candidate (博士候補生)と称されるこの段階では、Thesis Researchと称する科目に登録するだけで授業はなく、通常、主査のseminarには出席しますが、義務ではありません。Candidatesの多くは各地に散らばり、手紙で主査、副査とコンタクトを取っていましたが、Georgetownキャンパスで教職があった筆者は、Cook先生のSeminarに出席しながらresearchを進めることができました。

言語理論、英語学、英語法助動詞に関する研究書と論文を読みながら、並行して英語法助動詞のデータの収集、整理・分析・分類作業をします。参考文献(references)が膨らみ続け、とんでもないテーマに手を出したものだと後悔することしきりでした。
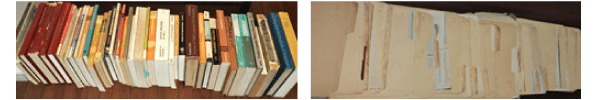
3月中旬のイースター・ブレイクのある日、毎年Georgetown言語学科が主催するGeorgetown University Round Table on Languages and Linguistics [*1] で、Cook先生を主査にPh.D.論文を仕上げたばかりのアメリカ人先輩に出会いました。筆者のテーマが英語の法助動詞であると聞くと、曰く、“Oh, man, why did you do that!” ネイティブ英語話者でさえ、英語以外の言語を取り上げがちであり、ましてや、主査、副査が英語スペシャリストであるので、今からでも遅くないから日本語分析に変えるべきだと親身になって言ってくれました。確かに、周りで英語を分析対象言語にする人はいませんでした。少し心が揺らいだものの、初志貫徹、英語分析以外にない!却って意欲が湧きました。
そうした事もあり、Cook先生、Macdonald先生、Kreidler先生と頻繁にアポイントメントを取り、進捗状況を報告するよう心がけました。特にBrown Corpusから集めた英語データについて先生方と意見交換をしました。意見が合わず討論したこともしばしばです。博士論文ですから、納得できないことを書く訳にはいきません。主査、副査の先生方だけではありません。医療で言えばセカンドオピニオンということになりますが、他の先生方ともアポイントメントを取りコメントしてもらいました。英語データの意味解釈については、先生方のみか職員、学生、特に、English as a Foreign Languageで英語を教えている博士課程のクラスメートと、ほぼ毎日意見交換しました。英語分析をするには最高の環境でした。
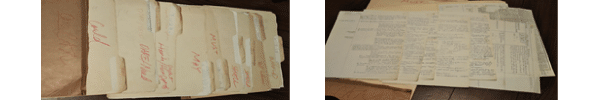
かくして建国200周年(Bicentennial)を祝う7月4日が過ぎ、猛暑の中をひたすらresearchに明け暮れる日々が続きました。Washington, D.C.の夏は蒸し暑くても最高です。Smithsonian Museums, Galleries and Zoo が様々な催しを行います。パリのルーブル博物館やロンドンの大英博物館はよく知られるところですが、Smithsonianはそれに引けを取らないコレクションがあり無料でした。日本からのビジターも多く、日本の大学の先生方ご一行を案内したことがあります。

秋になり、筆者のresearchも文献購読、データ資料の整理・解釈を終えて、提出したプロポーザルを基に練り直し、序論、結論を含めて全9章の章立て、参考文献を添えた論文abstractを作成し、3名の先生方に提出しました。
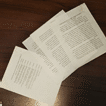
Goサインが出るや、10月から早速執筆に取り掛かりました。月1章ずつのペースで執筆計画を立てました。1977年8月末までに全章を書き終えfirst draft(初稿)提出→10月末先生方より査読結果受け取る→11月中に修正を終えsecond draft(第2稿)提出→12月中旬先生方より査読結果を受け取る→1978年1月中旬までに修正を終え、final draft(最終稿)としてthird draft(第3稿)提出→2月中旬先生方より査読結果を受け取る→2月下旬に論文審査会(defense)開催→5月Ph.D.取得し修了。修了時34才、日本で教職を探すことを考えるとこれがギリギリの計画です。当時の日本では海外Ph.D.取得者の採用例は少なく、職探しに2年以上必要だろうと言われていたからです。
正確には覚えていませんが、1976年12月暮れに序論と1章を書き終えCook先生に提出したと記憶しています。開けて1977年、計画どおり1ヶ月に1章のペースで、9月にfirst draft(初稿)を書き終え、3人の先生方に提出することができました。先生方からは1章ずつコメントが返され、それを基に修正し提出します。主査Cook先生のコメントはとりわけ厳しく、修正後も戻されることもあり、へこたれそうになりました。また、直ぐに返ってくることもあれば、時間が空くこともあり、その度に先生方の研究室のドアをノックしてやんわりと催促したりもしました。アポイントメントなど取っていたら埒が明きません。どの先生も複数のcandidatesを抱えており、こうでもしなければ割り込まれてしまいます。この段階に来ると、こうした駆け引きを駆使した交渉術も必須です。
それでも、1977年11月の段階での進捗状態はすこぶる良く、final draft(最終稿)の一歩手前と言えるthird draft (第3稿)を提出できました。そんなある日、ある日本の大学の先生が、慶應義塾大学経済学部で英語の専任教員を一般公募しているとの情報を寄せてくれました。早速応募することにしました。これと前後して、Kreidler先生がある州立大学とあるIV Leagueの大学が、日本語と言語学担当の専任教員を探しており、筆者が適任だと推してくださいました。州立大学からは人事責任者が来てくださいました。しかし、日本で英語を教えることが筆者の目標でしたから、ありがたいお話でしたが丁寧にお断りしました。その直後、慶應から1978年1月早々に面接に来るよう連絡を受けたので、帰国し面接を受けました。結果は合格、1978年4月から助教授(現在准教授)として赴任することになりました。面接でPh.D. dissertationを提出中で、5月には取得するつもりであると伝えしました。
面接を終えてGeorgetownに戻り、Cook先生にその旨報告すると大変喜んでくださり、他の副査の先生方にも声をかけ、筆者が提出した論文を査読し、1月中旬にはぎっしりコメントを返してくれました。それから、ほぼ連夜の徹夜で一つ一つのコメントに答えながら修正しfinal draftを仕上げました。筆者の住むアパート階下の住民は一晩中筆者の電動タイプの振動が伝わっていたかもしれません。そこからはトントン拍子です。1月末に無事final draftを提出すると、2月中旬に論文審査委員会(defense)が開かれました。
主査のCook先生、副査のMacdonald先生、Kreidler先生、ほか何人かの先生方、クラスメートの何人かが居たと記憶しています。それまであんなににこやかに対応してきてくれたMacdonald先生が、今回は一変して鬼の形相になり、微に入り細に入り矢継ぎ早に質問を投げかけてきました。論文で取り上げ、自分なりに答えているのにと思える質問もありましたが、defense能力を試しているのかもしれないと言い聞かせ、冷静に回答することができました。質疑応答は2時間ほど続いたでしょうか、終わると外で待つよう指示されました。どれだけ待ったかは憶えていませんが長く感じました。突如ドアが開き、中に入ると普段のニコニコ顔に戻ったMacdonald先生が仁王立ちで曰く“Congratulations! Dr. Suzuki!” そして括り棚からグラスとシェリー酒が取り出され乾杯です。先ほどまでの崖から突き落とされたような圧迫感が、トランポリンの上で飛び跳ねて空に突き上げられるような高揚感に変わりました。
30分程歓談した後で部屋を出て、Cook先生とエレベータに乗り込みむと、ここからが Cook先生です。“Here!”と言うや10ページ位の修正リストを手渡しながら曰く“Correct them!”メジャーなものではありませんでしたが、今のようなWordのようなソフトはありませんから修正したらもう一度タイプライターで打ち直さなければなりません。半月余り掛けてやっと提出することができました。
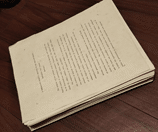
2年前に遭遇した例のアメリカ人先輩も、実は、あの日に修正箇所をタイプし直して提出しに来たと言っていたのを思い出しました。曰く、「New York Kennedy Airportに到着し、1時間でマンハッタン中心部に着くはずが、2時間以上かかる、いつ着くか、いつ終わるか、最後の最後までわからない、それが博士論文だ!」筆者は1975年秋から1978年春まで約2年半を費やしました。幸いにも大学キャンパスに教職があり審査委員の先生方と頻繁に会うことができたからこれで済んだのです。この先輩のように結婚して家庭を持ち、New York市の大学で教えながらの対応はさぞかし大変であったと思います。ましてや、外国で論文執筆をする人たちはさらに大変であったでしょう。仕事の都合で全米各地、全世界の様々なところで執筆する人が居ました。分析対象言語が英語以外、例えば、筆者の同級生の一人のようにオランダ語なら、インフォーマントが大勢いるオランダで執筆するのが一番ですから。筆者の場合、分析対象言語がアメリカ英語でしたから、この点でもキャンパスに残れたのは幸いでした。もし日本に帰っていたらインフォーマントは限られもっともっと時間が掛かったでしょう。
確かに、先輩の言う通りですが、母語を分析言語にすればより早く修了できるとの一言には同意しません。自分が本当に研究したいこと、筆者にとっては英語分析、から目を離さないことです。長い人生を振り返ると、やはり、何であれ自分が真に関心を持ってそのことに専念した人たちは長続きしています。Ph.D. dissertationは研究生活の出発点、そこから迷っていては仕方ありません。そこからの長い道中は途切れた道より、繋がっている道の方が確信して歩むことができます。
それから2年後の1980年、夏季休暇を利用して久しぶりにGeorgetownキャンパスに行く機会がありました。とりわけ懐かしく感じられたのは5年間お世話になったLauinger Libraryです。用あって1階の貸し出しカウンターに行き、名前を告げると、貸し出し係のアルバイト学生が“Are you Suzuki?”と聞くではありませんか。 “Yes.”と答えると、授業用にリザーブされている書籍棚を指し、筆者の論文がCook先生のSeminar in Generative Semanticsの指定図書になっていると教えてくれました。その日は図書館に行く直前にCook先生に挨拶しに行きましたが、そのことには一切触れませんでした。先生についてはまたお話ししますが、物静かで、厳しく、意見を述べる時には単刀直入、世辞は一切ありません。筆者ごときが褒められたことなどあるはずがありません。光栄なこととは思いつつも、身の引き締まる思いで、“Oh, is that right. I didn’t know that.”と言い残し、図書館を後にしました。続編を書くようにとの無言のメッセージを受け取ったからです。[*2]
筆者のPh.D.論文は、A Generative Semantic Analysis of the English ModalsはUniversity Microfilm Internationalに所蔵されています。[*3] 登録名はNathanael Yuji Suzuki、登録番号7901787です。この機関はUniversity of Michiganにあり、アメリカで執筆された全Ph.D.論文を所蔵されます。[*4] 博士課程留学を目指す読者は師事する先生方の論文を取り寄せ、読んでおくとよいでしょう。
2021年12月15日記
[*1] 毎年3月のSpring Semester brakeに開かれ、国内外から著名な言語学者が出席し論文発表をしていました。筆者が在籍した1973年〜1978年は言語学全盛期でWalsh Building一階大ホールは立錐の余地もなく、激論が繰り広げられていました。Georgetown 言語学関係者にはreunionの良い機会でした。G. Lakoff、G. Leechなど筆者が参考文献として引用した研究者の多くが訪れとても有益でした。
[*2] この事を受けて、その後Ph.D. 論文の結論で指摘した今後の課題について論文を書き、ヨーロッパの学術学会や、C注1で紹介したGeorgetown University Round Tableで発表しました。
[*3] KDP/Amazonでも入手できます。
[*4]現在は、名称を変えてPreservation Microfilm Orderでチェクできるようです。
いいなと思ったら応援しよう!

