
障がいのある子が不登校になったら行き場がどこにもない問題を解決したい
以前に、吹田市では特別支援学級に在籍している子どもたちは教育支援センター(一昔前は適応指導教室と呼ばれていた行政の不登校支援事業)を使えないという謎の馬鹿げたルールがある問題(近隣他市では吹田市だけの問題)を記事(今は有料マガジンの記事です)にしました。
今回は、その後の吹田市の動きと見えてきた現状・課題についてお伝えします。
障がいがあると不登校支援を受けれない?
特別支援学級に在籍していると教育支援センターを利用できないという吹田市の制度には、その他にも以下のような課題があります。
①特別支援学級に在籍している生徒が、教育支援教室の在籍資格を得るために特別支援学級を抜けた場合、教育支援教室の利用の可否、または 学校復帰の可否に関わらず、二度と特別支援学級に戻れない(教育支援教室に入れるかどうかも不明)。
②特別支援学級に在籍していると教育支援教室に通えないということを知らない保護者もおり、 子どもが教育支援教室に行こうと思ったタイミングで通わせることができずにずっと自宅で過ごさざるを得ない。
③教育支援教室を希望した場合、特別支援学級を抜けるか8月までに決めることを求められる。教育支援教室を利用できるのは次年度以降であり、 それまでのプロセスにかかる時間が長く、その間は不登校中のサポートが受けられず、先行きの見通しも立てづらい。
あれから何度も吹田市教育委員会と協議をしながらもなかなか事が前に進まないと感じたので、吹田子ども支援センターの森本先生とゆう・きっずの皆さんにもヒアリングにご協力いただき、2月に吹田市長と教育長に請願書を提出しました。
そして、前回の議会の2021年9月から5カ月ほど経ち、再び五十川議員がこの件について議会で質問をしてくださりました。
その答弁から、驚きの事実が判明したので記事にします。
2月定例会の答弁の内容
令和3年度2月定例会五十川有香議員答弁(吹田市)
※内容は三科が聞き取りをしたものです。
五十川議員:特別支援学級在籍の児童生徒が学びの森・光の森(吹田市の教育支援センター)に通えないことについて、この度当該児童生徒の保護者などから切実な実情をあらわす陳情が市議会に届きました。市長や教育長も読まれていると思います。保護者の言葉おひとつおひとつから現状は子ども自身の学ぶ意欲を減退させ教育の機会の不均等と言わざるを得ないです。吹田市が進めようとしているインクルーシブ教育の理念にも相反していると考えます。当初予算等に反映されていませんが令和3年9月定例会以降特別支援学級通常学級の子どもたちの教育機会格差是正に向けた具体的な検討状況についてお答えください。
教育監:支援学級在籍児童生徒の教育支援教室(吹田市の教育支援センターの呼称)活用に向けては関係室課による会議体において新たな教育支援教室の在り方や具体的な方策を決定することとしており、その前段階として現在担当室がこれまでの臨床心理に加え医療を含めた専門的知見を得ながら検討するための素案づくりに取り組んでおります。
五十川議員:提出されたこの陳情書の児童たちはこれまで教育委員会が具体的に把握をされていなかった数字に表れていなかった方々の貴重なお声です。指摘をしていた不登校のうち特別支援学級の子どもたちの内訳は把握できましたでしょうか。このような子どもやそのご家庭の実態に寄り添った対応を求めます。教育長の考えを聞かせてください。
教育監:まずは担当よりご答弁申し上げます。不登校児童生徒のうち支援学級在籍児童生徒の占める割合は小学校約18%、中学校約12%でございます。当該児童生徒への対応は通常学級担任及び支援学級担任が不安など個別の状況を把握し指導・支援を行なうことを基本としております。そのうえで今後当該児童生徒が学校復帰や社会的自立に向かうため教育支援教室で学べるよう課題の抽出と解消に向けた検討を進めてまいります。
教育長:支援学級在籍児童生徒に対する合理的配慮は学びや生活の場が教育支援教室に変わったとしても可能な限り適切に提供する必要があります。またその実現のためには慎重に検討を重ねて適切な体制作りを進めていかなければなりません。当該児童生徒を含め不登校状態にある児童生徒が学校復帰や社会的自立に向かえるよう教育委員会として関係室課で連携しながら検討を進めてまいります。
五十川議員:やはり通常学級の割合よりも特別支援学級の児童の方が断然多いということがわかりました。子どもたちの教育機会確保のために個に寄り添った適切な情報提供と迅速な対応を求めます。
という内容でした。
解説します。
支援級の中学生は10人に1人が不登校!?
まず数字で言うと、吹田市における不登校児童生徒数は2019年だと小学生175人、中学生345人で、2020年は小学校190人(0.8%)、中学校は359人(4%)です。
答弁では小学生はそのうちの18%、中学生は12%が特別支援学級在籍の子どもたちとのことなので、2020年に合わせると特別支援学級における不登校児童生徒数は小学生は34人、中学生は43人となります。
吹田市における全児童生徒数のうち特別支援学級在籍者数は、令和3年2学期の時点で、小学校が全児童数21,339人のうち1,407人で約6.6%、中学校、全生徒数8,937人のうち402人で約4.5%です。
つまり、特別支援学級在籍の子どもたちのうち不登校の子の割合は、小学校だと2.2%(34人/1407人)、中学校は10.6%(43人/402人)となります。
ちなみに、通常学級の不登校の子の割合は小学校だと0.8%、中学校は4%です。
結果として、通常学級と比べ特別支援学級在籍の子たちの不登校は、小学校だと約2.75倍、中学校は2.5倍ということが明らかになりました。

ただ、不登校の子たちの対応のために特別支援学級に在籍することを勧めるというケースもあるので、一概に特別支援学級は通常学級よりも不登校になりやすいとは言えませんが、そうだとしても特別支援学級在籍の子どもたちの中にもたくさんの子が不登校になり、学校ではない教育支援センターのような学びの場を必要としているかもしれないと考え支援を充実させることは、このような数字で判断してみても早急に必要だと言えるのではないでしょうか。
特に、中学校の特別支援学級在籍の子たちの不登校は10人に1人の割合という驚きの数字でした(というかそもそもこの数字も、何度も教育委員会と協議をしお願いをしないと調査がされてないどころか問題という認識すら持たれていなかったように感じました)。
令和3年の9月定例会以降、教育委員会は答弁で、
支援学級在籍児童・生徒が教育支援教室で学ぶことを前提とした課題の詳細な抽出と、その解消に向けた検討を改めて担当室に指示を行う。
と言っておられました。
5か月経った今回の議会でも教育長は、
当該児童生徒を含め不登校状態にある児童生徒が学校復帰や社会的自立に向かえるよう教育委員会として関係室課で連携しながら検討を進めてまいります。
「検討の指示を行なう」→「検討を進める」の違いが頭の悪い僕にはさっぱりわかりませんが、これだけ調査いただいたことで明らかになった課題をいかに迅速に、どのように解決するかは吹田市の教育の力が問われていると思います。
何年後かに「ようやく実現したね」なんてことになったとしても、今を犠牲にされた親子の時間は帰ってきません。
今後の吹田市教育委員会の動きをぜひ皆で注目し声を上げていきましょう。
ここからは僕の感情的な言葉です。
ここから先は
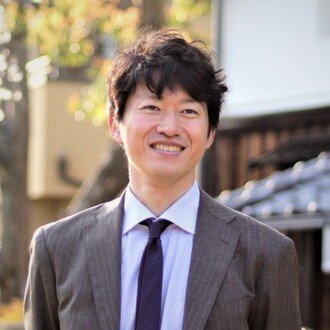
三科元明とフリースクール、そして不登校。
フリースクールの日常から、不登校に関すること、子どもたちへの想いや出来事を記事にします。また、それ以外にも不登校を経験した子どもやその保護…
よろしければサポートをお願いします。フリースクールの活動費の一部として大切に使わせていただきます。
