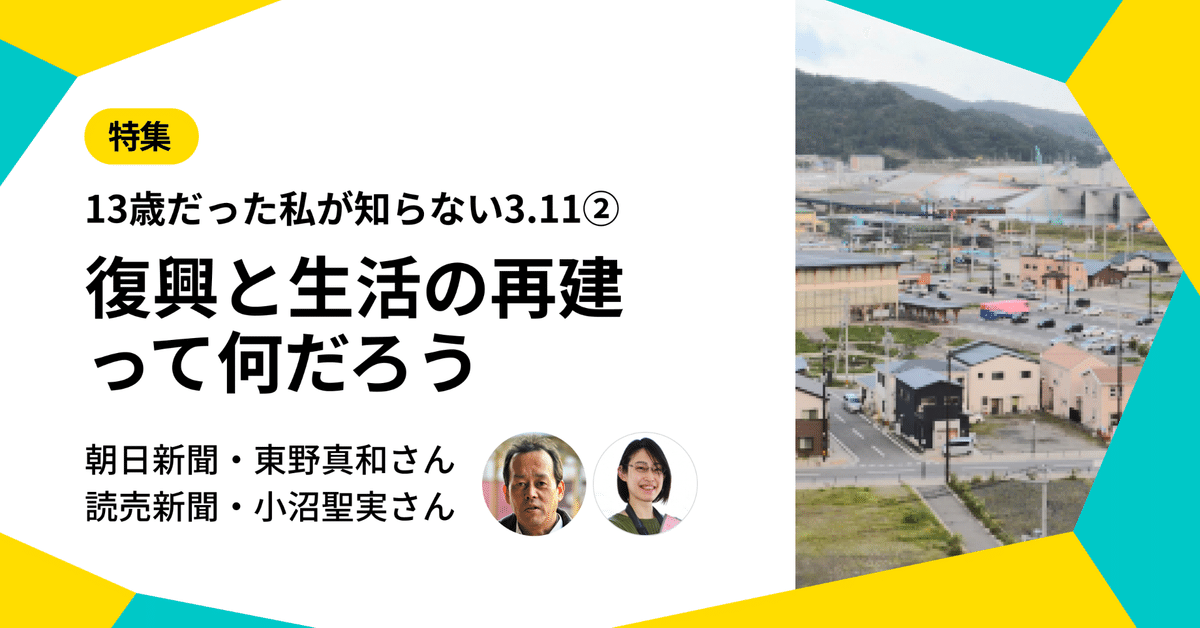
復興と生活の再建ってなんだろう【13歳だった私が知らない3.11②】
震災後、変化してきた町の景色と、いまだ影響を受ける人々の暮らし。第2回では、被災した地域や、影響を受けた方の生活の現状に寄り添い続けてきた二人の記者さんに、この10年間での地域と、一人ひとりの生活の変化をお聞きしました。
特別企画 13歳だった私が知らない3.11
大きな津波や原発事故。当時13歳だった私は東日本大震災を知っているけれど、直接の被害があったわけではなくて、語れるほどに濃い記憶や知識があるわけじゃない。今の私や日本社会が、どれほど震災に影響されているのかも、きっと分かっていない。
そこで、震災について取材してきた6人の記者さんにインタビュー。皆さんが被災地で見たこと、人に接して感じたことを通じて、私が知らない3.11に向き合ってみようと思います。
「何もなかった」町にインフラはできた。そして、21世紀の日本のモデルとなる町づくりは、今・ここから始まる。

東野真和さん
朝日新聞 朝日新聞記者(編集委員兼釜石支局長)
震災直後から3年間、岩手県大槌町に駐在。その後も災禍から被災地が復旧・復興していく様子を町民の視点で取材し続けている。熊本など全国の被災地取材も行う。
東野記者のTwitterはこちら
関連記事:震災8年、3つの視点への疑問 被災地・岩手県大槌町に駐在した記者が警告する風化
東日本大震災後、岩手県大槌町に駐在しました。以来、町民として10年間取材を続けています。大槌町は三陸特有のリアス式海岸に面した、自然豊かな海と山の町です。東日本大震災では町民の1割が犠牲になり、町長や多くの役場の命も奪われて町の機能がストップしました。現在、震災前と比べて事業所は4割減り、人口も3割減少しましたが、10年が経過した今、インフラ面の整備は終わり、町にも仕事は十分にあるような状態です。

現在の大槌町の市街地。街路は整備されたが空き地が目立つ
でも、理想的な復興ができているかというと全くそうではない。そもそも災害復興とは、単にもとにもどればいいというものではありません。特に東日本大震災については、2011年の6月に施行された東日本大震災復興基本法の中に「単なる復旧にとどまらない、21世紀半ばにおける日本のあるべき姿」を目指した復興を行うこととされています。東北の未来ではなく、日本の未来のための復興です。都市一極集中のこれまでの日本のあり方を変えるために、地方において新しい可能性を試す、それが復興の理念だったんです。
しかし、新しい取り組みはなかなか上手くいっていません。たとえば大槌町の基幹産業である漁業・水産加工業。大槌に限りませんが、震災前より漁業・水産業は衰退産業で、後継者問題も深刻です。本当はこの震災を機に、これまでのジリ貧の状態を打破するための新しい流れをつくっていきたかった。
勿論、変えていこうという動きはありました。実は漁業は国の補助金がとても手厚く出る分野です。震災後、まずは保障に頼って暮らしていこうという漁師さんも沢山いました。
そんな中、私が出会った若い30代の漁師の兄弟は「それではだめだ」と、震災後まだ補助金が出るか出ないかも分からないうちから自分たちで船を直し、養殖を再開させました。後に続く若い漁師が増えて欲しかった。また、宮城県石巻市では、これまでの漁業組合という形ではなく、会社組織で漁業を展開し、収入をより安定させる仕組みをつくろうという動きもありました。しかし、反対意見や、震災後の不漁の影響もあり、こうした取り組みは革新的な形では広がっていません。

復旧した大槌町の魚市場
そうはいっても私は、これまで東北全体に使われた30兆円を超す復興予算が無駄だったのか否かの判断は、これからだと思っています。自分が書いた記事のなかで「ぴかぴかの過疎地」という表現を使ったように、現在はやっとインフラが整備できたにすぎず、町を法律通りに「21世紀半ばの日本」のモデルにするための、スタートラインにも立てていないところばかり。
経済で支配しようとする東京と、どうしても受け身になってしまう東北との関係を、人々の意識から変えていくような町づくりは、10年経ったここからなんです。三陸には色々な資源があるし、自然豊かな環境が好きで、ここで働きたいという方も増えるかもしれない。東北に新しい価値が創造されるここからの10年を、一度何もなくなったところから町がどう再生していくのかを、残りの記者生活を使って、見続けたいと思っています。
私から皆さんに手渡せるものはあまりなくて、若い人から若い人へバトンを渡していってほしいですが、ひとつお願いするのなら、誰かひとりでもいいから東北に連絡できる人をつくってください。相手を持ち上げるでも自分を下げるでもなく、対等に、普通に、つながり合ってほしいと思っています。震災があったからではなくて、この町やここに住む人の魅力を単純に知ってほしい。これからの日本を一緒に作っていく仲間として、東北と関係を持ち続けてくれたら嬉しいです。
震災はまだ「終わっていない」。けれど、福島の街は「変わり続けている」。

小沼聖実さん
読売新聞 福島支局
震災時には福島支局にて勤務。その後東京本社を経て2020年再び福島支局へ。震災時より現在まで、障害者・高齢者ら災害弱者の支援、被災者の心のケア、福島からの県外避難者の生活再建など被災者に寄り添った取材を行う。
震災当時、福島で勤務していました。その後一度東京へ異動になりましたが、震災から9年目の昨年9月、再び福島に戻ったとき、「県外避難者」についての取材を始めました。「10年経ってもなお避難している人たちがいる」ということにフォーカスを当てた記事を書きたかったからです。原発事故当時、福島はどこのエリアまでが安全か分からず、避難指示区域に指定されていない地域からも自宅を離れ、避難した人が多くいました。そして、10年経っても、多くの方の避難生活は続いています。
たとえば、震災当時家族で福島に住んでいた女性・Aさん。彼女は「住むには問題ない」とされていた福島市から、大阪に避難しました。いわゆる「自主避難」です。自身の子どもの被ばくの恐れを心配してのことでした。しかし、夫は仕事のため、福島にとどまりました。数年間は自主避難者に対しても公的な支援がありましたが、打ちきりに。このとき、夫から「福島に帰ってきてほしい」と言われたものの、Aさんはすでに大阪の学校になじんだ子どもを連れて、福島に帰ることが出来なかったといいます。その後も家族全員が揃っての暮らしは実現できず、離婚に至りました。制度上、Aさんは避難が必要な人ではなく、実質的には「福島から大阪へ引っ越した人」という扱いです。そのため公的な金銭的支援を受けられません。Aさんは正社員の仕事を懸命に探し働いていましたが、仕事に対するプレッシャーなどから適応障害を発症。仕事を辞めざるを得ず、現在は失業手当で生活しています。
実は、自主避難者の多くが「子連れの女性」という特徴があります。父親は仕事があり福島に残りながら、子どもの健康を心配し、Aさんのように、妻が子どもを連れてなるべく離れた県外へ避難するというパターンが多いそうです。
このような事情で避難してきた方たちは、避難先でさらに困窮する状況に陥りやすいと感じています。特にシングルマザーの場合、子供の面倒を見るため、不定期な仕事にしかつけず、結果として収入が少なくなる傾向があります。シングルマザーで避難者という二重苦に苛まれ、さらに困窮してしまうのです。Aさんはたしかに、「福島に戻る」という選択もできたかもしれない。それでも様々な事情から、戻るという選択をせず、避難先に定住すると決めました。それをもって「安心できる場所に住めるようになった」から「よかったね」と言えるのでしょうか。避難を経験し、今も生活が再建できていない人にとって、東日本大震災による被害はまだ「終わっていない」。
一方で、復興した部分もあります。例えば、除染が進んで、避難指示が解除された地域では、大規模な施設が整備されたり、移住者がお店を開いたりもしています。この事実もまた、多くの人に正しく知ってほしいです。

福島県双葉町では、避難指示が解除されたJR常磐線の双葉駅と「東日本大震災・原子力災害伝承館」などを結ぶシャトルバスが運行されている。
提供:読売新聞社

福島県南相馬市ではメガソーラーが整備されている。 提供:読売新聞社
ただ、避難先から戻ってくる人の多くは高齢者です。街を支える若い世代が、福島の地から足が遠ざかってしまったようです。私は再び福島に戻ってきてから、避難指示が解除された地域を訪れた際、無意識に「ここのエリアは危ない」と思ってしまったことがあります。事故当時のイメージが10年後も当時のまま自分の中に残っていると気づきました。震災当時で止まった記憶と、現実との間にあるギャップ。案外多くの人の中にあるのではないかと思います。震災は「まだ終わっていない」けれども、福島は「変わり続けている」。U30のみなさんにはぜひ、今の被災地を知るために被災地を訪れてほしいと思っています。
*本記事中の画像は朝日新聞社/東野記者、読売新聞社に提供いただいています。
いいなと思ったら応援しよう!

