
両利きの経営 「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く
おはようございます。Shunzoです。
読んでいただきありがとうございます。
今日は【両利きの経営 「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く】を紹介します。
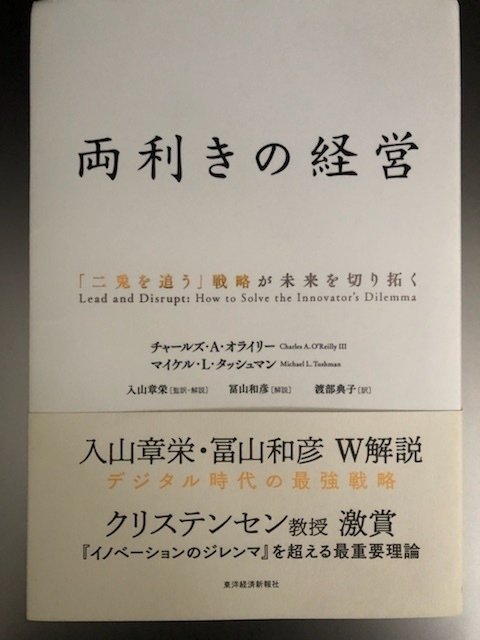
本書を読んでから、仕事で「探索」と「深化」という言葉をよく使うようになりました。
「両利きの経営」とは?
・知の探索
自身・自社の既存の認知の範囲を超えて、遠くに認知を広げていこうとする行為
+
・知の深化
自身・自社の持つ一定分野の知を継続して深掘りし、磨き込んでいく行為
本書に書かれていることは全て重要ですが、大企業勤務時代に新製品開発のプロジェクトに関わった身として、本書に書かれていることの中で特に共感が大きかった内容は、「経営陣の関与と支援」と「両利きのアーキテクチャー」です。
「経営陣の関与と支援」については、
資金や支援の供給母体として経営陣がきわめて重要なことだ。まさに上級リーダー側の積極的な関与がないと、探索型の製品やサービスは往々にして邪魔なもの、脅威、資源の浪費と見なされ、成熟事業の短期的な需要の犠牲になる。また、安定した資金が手当てされなければ、探索の取組みは必然的に資金不足に陥ることが多い。
とあります。
「両利きのアーキテクチャー」については、
組織設計に関するある研究では、革新的ユニットを構造上、分離させることは一連のイノベーションを成功させる鍵だとしている。
〜中略〜
構造的にユニットを分離させることは、概念上はシンプルだが、探索を追求していく際に、上級マネジャーが必要だとわかっていても統合しきれなかったり、悪くすると、古い事業のシステムや考え方を新規事業に押しつけたりする例が頻繁にみられる。この場合、探索ユニットは十分な資源を得られないまま、成熟事業に圧倒されることになりかねない。
とあります。
まさに在籍当時起こっていたことでした。
新規事業のメンバーは既存事業のメンバーから煙たがられる場面が多いのではと思います。新規事業の開始直後は収益が生まれず、キャッシュを消費するだけだったり、既存事業の評価の軸では新規事業に関わる社員を評価できず、そんな中で新規事業側の社員が高評価をもらったりすると不公平感が出ます。
退職後はプロジェクトの成否を知る由もないですが、数年経ってもまだニュースリリースに出てきていません。
本書に取り上げられていた日本企業の成功例としては富士フイルム1社だけでした。それも20年くらい前の話です。
多くの日本企業が両利きの経営を成功させて、社員がハッピーに働けることを願います。
【両利きの経営 「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く】の紹介でした。
過去の記事もご覧いただけたら幸いです。
