
「その勉強なんの意味あるんですか?」に対する長めの答え
「その勉強なんの意味あるんですか?」
塾講師のアルバイトをしていた4年間、耳がタコになるくらい生徒から問われた難問である。
「成績上げたいから塾来てるのにその言い草はなんだ」と、言わずとも心中では思っていた。大概の場合、親に行かされているのが9割5分である。「頭のいい子」というのはテストの点数が高いのはもちろんのこと、幼いうちから勉強することに意味を感じている子である。親からすれば、この上のない子の成長を感じると思うが、半ば家庭内での学習が厳しくなると塾に行かせるパターンへとなる。そして最終的には表題にある「その勉強なんの意味あるんですか?」へと繋がる。
元塾講師だった僕はアルバイトとはいえ、「成績を絶対に上げる」とは断言できないものの「勉強へのやる気」は上げることはできる。そのためにもなぜ今その勉強が必要になるのか常に考えていた。
しかし実際のところ、この難問に対する答えに端的でズバリの回答がない。なぜなら、何言っても「勉強へのやる気」は上がらないからである。それをあきらめた僕は「…まぁ、次のテストで点数をあげるためかな」としか答えられなかった。
僕はこの記事で
・人生の選択肢が広がる
・人生を豊かにするため
・自分自身の成長になる
みたいなことを言うつもりはない。
もうすでに諸氏が導き出したものであり、当の小中学生にそれを言ってもまるでもってピンと来ない話である。「YouTuberて夢がある思うけど、その裏ではいっぱいお勉強頑張ってるんだよ?」と、身近な話題をもってきても「ま、自分にはどうせカンケーねーし」となったらそれまで。
勉強がしたければすれば良いし、そこそこでいいならそれでいいし、勉強が嫌いならそれはそれでいい。誰もが平等に生きる権利がある以上、勉強ができるできないで優劣が決まる世界にいないのだから、今を生きる子どもたちはそれでいいのかもしれない。別に大人になってからでも勉強なんていくらでもできる。「今やるべきことをやる」か「その時が来るまでなにもしない」かだけの違いである。
「その勉強なんの意味があるんですか?」と問う子は往々にして読解力も乏しいように思う。
国語の授業で文章を読み、問いに対して適切に答え、正しく読み解く。すなわち読解能力を養う。
国語を適切に表現し正確に理解する能力を育成し,伝え合う力を高めるとともに,思考力や想像力を養い言語感覚を豊かにし,国語に対する認識を深め国語を尊重する態度を育てる。
塾講師のアルバイトをしていたとき、小6に体積を求める問題を解かせた。
「たてが6cm、よこが3cm、深さ10cmの水槽があります。この水槽が水でいっぱいになったときの体積を求めなさい。」
文章題とはいえ、計算に必要な数字はちゃんと示され、図もある優しい問題だ。すでに体積の求め方(たて×よこ×高さ)は学習済みで、応用の文章問題を解かせたところ
小6「せんせー、高さってどれですか?」

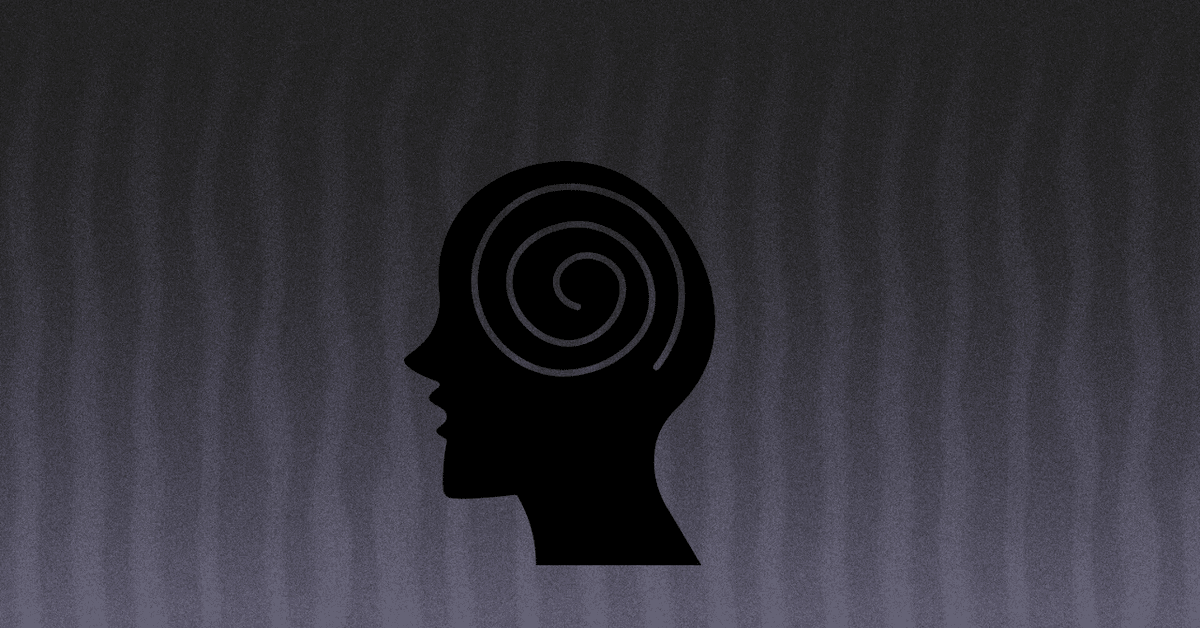
文字通り、頭を抱える。
高さ#とは
算数的・数学的思考を問うどころではなくなった。まずこの子は「たて×よこ×高さ」の公式が頭にこびりついているので、文章題で示されている「深さ」が「高さ」とイコールになっていないのである。
これは困った。時間にして15秒くらい悩んだだろうか。この時間が(アルバイトとはいえ)教育者としての真価を問われた気がした。この子は学校でちゃんとうまくやっているだろうか。この子は将来やっていけるのだろうか。教え子の人生に思いを馳せる日が来るとは思わず、驚いた。しかも「高さってどれですか?」でだ。そして同時に、人生の長い時間、誰かの人生を思う時間に使われるのだろうと。それがこの15秒間に反芻した。
「高さというのはここでいう深さのことだよ」と言えばすぐ解決するのだが、上記のように「この子は将来やっていけるのだろうか」が頭をよぎる。
僕がかつて勤めていた学習塾は進学塾ではなく、「お勉強が苦手な子が集まる」塾であった。お勉強が苦手なりにも頑張って問題を解こうとする姿をみると、この仕事にやりがいがある。ただ問題を解かせて解説すればいいというわけではないものの、時折、他人の人生までも思いを馳せることがある。教育者たる教育の本質はそこにある。
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
「せんせー、高さってどれですか?」ときいてきた子とは別に、ある日、中2の男の子に数学を解かせていた時のこと、その子も「お勉強が苦手」な子である。その子に限ったことをいえば、屁理屈を言う子であった。
中2「この問題解いて将来何の役に立つんですか?」

いつか来ると思っていた質問がきた。これも回答次第では教育者としての真価が問われる。
この質問に対する僕の回答は今思えば教育者失格だった。大学生だった僕はまだ未熟で若かった。血気盛んな若者だった。「成績を上げるために塾に来てるのにその質問はなんだ」とか「勉強ができないことを棚に上げて何を言ってるんだ」と、僕の脳内では憤怒、放漫、怠惰、強欲がめぐる。七つの大罪のうちのいくつかを犯しそうになる。平たく言えばその質問に少しイラっとしてしまった。それを表情には出さず、決死の覚悟でこう答えた。
「この問題も解けない君は将来何の役に立つの?」
……言ってしまった。教育者失格の烙印を自ら押してしまった。
それを言うと、中2の男の子は豆鉄砲を喰らったハトのような顔になってしまった。ポカーンとして「今、ぼく何を言われてたの?」状態になっている。
「まぁ……次のテストにむけて一緒にがんばろうや」と精一杯のフォローを加えた。
「せんせー、高さってどれですか?」と「この問題解いて将来何の役に立つんですか?」と、きいてきた子には申し訳ないが、今は算数や数学を解いてる場合ではない。
人が書いた文章を読むことをしないといけない。昔とはちがい、読みやすい文章は今ではごまんとある。他人が書いた文章を読み、どう考え、どう生きるかを自身に問う時間が必要だ。
「その勉強なんの意味があるんですか?」に対する答え、今の僕ならわかる気がする。勉強ができないこと、問題が解けないことに対してどう思うか考えるのだ。なんなら「勉強ができる人を羨ましいと思うか」まで問うてよい。もし「そんなのどうでもいい」と言われたら、子どもの意見を決めつけて判断しないで見守るということをしてあげたらいいと思う。もし勉強したいと言ってきたらいくらでも付き合ってあげるつもりで。勉強する意味はその子自身が見つけるものだから。
いいなと思ったら応援しよう!

