
リモートワークvsバック・トゥ・オフィスの決着はつくのか
この記事を読んであなたが得られるかもしれない利益:企業文化を必死で守ろうとする企業が存在するという事実。パンデミックの不確実性に持ちこたえた企業はなぜオフィスを大事にするのか。
痛勤のないリモートワークの魅力
アメリカではパンデミックで、リモートワーク派が圧倒的で、リモートでなければ会社を辞めるのも辞さない社員が珍しくないことを,ずいぶん紹介してきました。
労働者はリモートワークの心地よさに目覚めてしまった、それは確かでしょう。
何せ通勤が要らないのですから。
車社会のアメリカといっても、それが便利で快適かは一概に言えません。
渋滞もあるし、オフィスまで片道1時間のドライブなどは珍しくありません。
ロスアンゼルスの渋滞は嫌だ
かくいう私も、そうでした。もう30年も前になりますが、MBAを修えて1年間ロスアンゼルスのダウンタウンにある、コンサルティング会社に勤めていたことがあります。
自宅のアパートから車で一時間の道のりは、渋滞することもあり、結構大変でした。

アメリカはリモートワークに適した文化ではないか、と思うのです。
日本は大部屋にみんな詰め込まれて、かかってきた電話は手がすいていれば、誰もがとらなくてはならない。
しょっちゅう他の部署からの訪問者が来て、上司には常に「ちょっと」と呼ばれる。自分の仕事に集中などできません。
なぜか。
大部屋が削ぐホワイトカラーの生産性
その理由は、日本の職場にはあなたの職務の内容と、やるべき義務を記した、職務記述書(job description ジョブ・ディスクリプション)が存在しないからです。
アメリカいや、先進国ではこのジョブ・ディスクリプションにあなたのやるべき仕事がすべて書いてあり、それ以外のことをする必要がありません。
しかし、日本では他の部門の仕事もするし、本来の仕事でないこともやらされるし、仕事がなくても残ってつきあい残業をしなくてはなりません。
この文化は、あの忌まわしい大部屋システムがなくならない限り、消滅するわけもないでしょう。
大部屋でなく、自分の部屋、もしくはパティションで小さくても自分のお城をあてがわれる文化では、自分の仕事にいやでも集中できます。

リモートワークを”邪魔されないで集中してできる仕事”と定義すれば、アメリカ人にとって普段の仕事も、リモートワークのようなものです。
リモートワークはそれに加え、通勤がありません。
これではリモートワーク派が増えるも当然です。
対面から生まれる効率もある
もちろん、アメリカ人もコーヒーブレイクで、積極的に同僚とかかわりを持ちます。

会議もありますから、普段から顔を合わせている方が何かと便利というのはあります。
僕の勤めていたロスアンゼルスの会社では、社内旅行というのがありました。
日本の会社でもないのに、なぜと思っていましたが、“付き合い”という文化もアメリカのオフィスカルチャーにはあるのかもしれません。
さて、The Wall Street Journalのちょっと古い記事、パンデミックが昨年落ち着いて、多くの企業が再開を考えだした頃の記事が出てきました。
Office culture adjusts to the pandemic (オフィス文化がパンデミックに適応)というタイトルです。
内容はリモートワーク礼賛の、世の中の流れとは、異なるものです。
パンデミックが猛威を振るう中、流行の最初っからオフィスに一人とどまり、現場で汗を流す人々をサポートする女性たちの声を紹介する記事です。
なぜ、パンデミックの危険も顧みず、オフィスにい続けるのか。
それは、それこそジョブ・ディスクリプションで、どんなことがあっても毎日会社に来ることを義務付けられているからです。
もう一つの理由、これが今日の記事のハイライトなのですが、「会社の上の人たちが、パンデミックで企業文化がなくなることを恐れているから」だというのです。
ジョブ・ディスクリプションのせいか、ボスのせいかはともかく、彼女たち(記事に出てくるのは全部女性)こそ、会社の文化を絶やさないためにコロナ最前線で会社の文化を守る戦士なのだ、記事はそう読めます。
オフィスを守るということ
彼女たちは、何をやっているのか。
主に二つあります。一つはどうしても現場で働かなくてはならない社員へのサポート。
もう一つは、社員がスムーズに、リモートからオフィスへ、ソフトランディングできるように、企業の助けを得て様々なことを整えることです。
例えば空調設備、ベンチレーター(空気清浄機)を最新のものにする、ロボット衛生兵を稼働させ、消毒液をいつでもどこでも散布するなどです。

みんながみんな、コロナで快適にリモートワークができているわけではありません。
リモートで慣れないインターネットに苦戦したり、ズーム会議に毎回出てこれない社員もいます。

オフィスに帰ってきたときの、働き方を整えるのも彼女たちの仕事です。
検温、マスク着用、検査など、独自のルールを決めるのです。

会社も、企業文化を守るためには、ウェルカムバック作戦を全面支援しています。
新鮮な牧場の牛肉を供給することで知られる、サーティファイド・アンガスビーフ社(Certified Angus Beef)は、無事にオフィスに戻ってくるまで、社員に2か月の猶予を与えました。
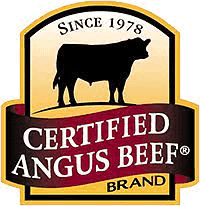
その間、無理せずにリモートからオフィスワークへ移行してほしい、との配慮です。
コロナの前線に立ち、企業文化を守るある女性社員は、こう胸を張ります。
「2年間私たちがオフィスに出ずっぱりで頑張れたこと自体が、会社がコロナに適応できた証拠よ。
さて、パンデミック時代の組織論の答えは、リモートワークなのか、バック・トゥ・オフィスなのか、それとも折衷案なのか。
答えが出るのは10年後かもしれません。
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
では、また明日お目にかかるのを楽しみにしています。
野呂 一郎
清和大学教授/新潟プロレスアドバイザー
