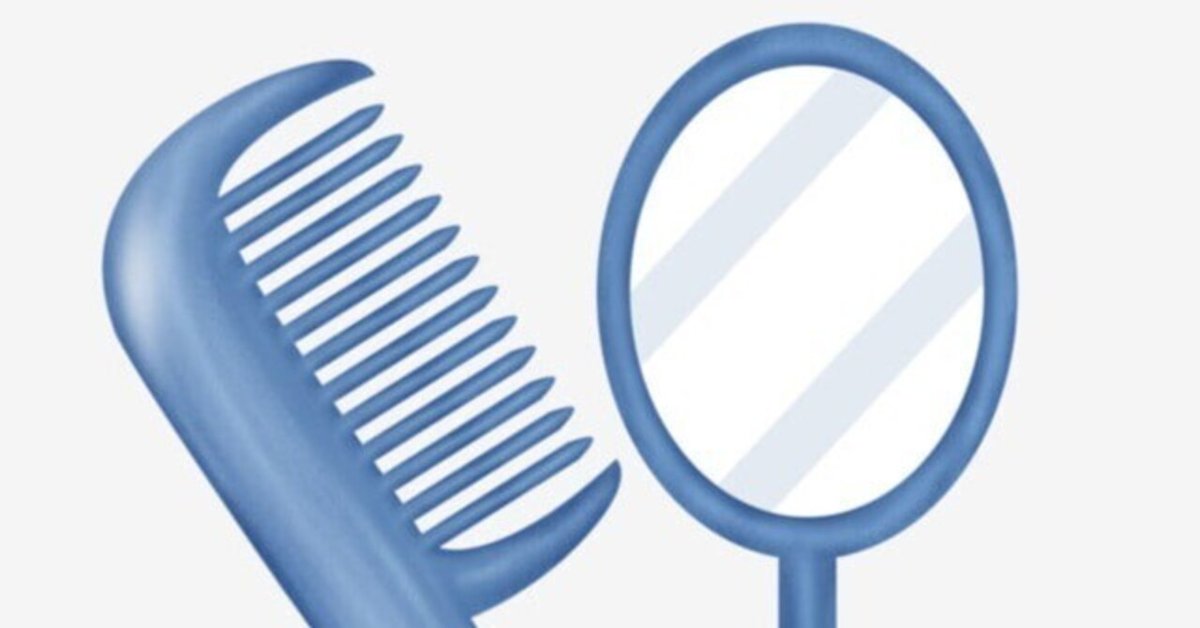
エッセイ 祖母への挽歌
病室の 百を越えたる わが祖母の
手鏡見つめ 髪くしけずる
私の祖母が104歳で死ぬ少し前に老人ホームのトイレでころんで、大腿骨を骨折して入院した時のことだ。私はもう退院できないだろうと思った。祖母の母親が、やはり自宅の庭でころんで腰の骨を折り、20年間寝たきりとなり、そのまま亡くなったからだ。しかし、現代医学はその頃から驚くべき進歩を遂げていた。100歳を越えている老婆の太腿にボルトを埋め込み、折れた骨を固定したのだそうだ。祖母の骨が太くて年の割には丈夫だったことも幸いした。じきに退院できるという。祖母自身もそのことを知っていた。
お見舞いに行った時はちょうど昼食時だった。ベッドで食べられるように、テレビ台の下から食事のトレーを置ける引き出しが出されるところだった。テレビは何も映っていなかった。祖母は目の前に引き出された何も映っていないテレビの画面をのぞき込んだ。鏡代わりに自分の顔を見るためだった。「ああ、こんなに髪の毛が少なくなっちゃた。」と言いながら手櫛で髪の毛を撫で付けだした。
私は愕然とした。何という生命力だ。私がもう退院は無理だ、そう長くはないだろうと思っていたのに、自分の身だしなみを気にしている。
「早く退院して老人ホームに帰りたい。」
私は嬉しいやら、自分が恥ずかしいやらで、いたたまれなくなった。それを一緒に見ていた私の妻が、「後でコンビニで手鏡と櫛を買ってあげようよ。」と言った。私たちは手鏡と櫛を買って祖母に渡した。
この歌はその手鏡と櫛を使って自分の髪の毛を梳いたであろう祖母の姿を想像して詠んだものである。
祖母が104歳で胆管がんで亡くなった時、葬式の祭壇の片隅に、この歌を半紙に書いてそっと置いておいた。
