
トーマス・ロックリーがとんでも日本史を創造していく過程を考えてみた❷
トーマス・ロックリーがとんでも日本史を創造していく過程を考えてみた❶の続きになります。
とんでも日本史に権威を与えてくれる肩書き
トーマス・ロックリーのバイオにも使われたTL的工作
さて、ここで質問です。歴史家を名乗る、トーマス・ロックリーの専門は何だと思いますか?
「歴史家を名乗る人の専門を聞くなんて!?」、と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、日本大学のサイトによると・・・

トーマス・ロックリーの研究キーワードは「言語内容頭語型学習」。「言語内容頭語型学習」という研究が何か全くわかりませんが、名前の下にある、彼の肩書きを示すところに”外国語科目”とあるので、英語を教えているのではないかと思います。ネットで流行っている弥助の歌コンテンツ?の波に、おばちゃん世代の私もがんばって参戦すると・・・。
国際的な視野からみた日本史じゃないんかーい!
ALTとして来日したとのことですから、キャリアパスとしてはあり得なくない転職かと思います。前々回のコメント欄のお返事で、私が「本が売れたことで、准教授になった」ような発言していたのですが、その前提として、てっきり彼が日本史での准教授かと思い込んでいましたので、この発言は適切ではなかったかもしれません。批判した日本大学にもお詫びします・・・と、思いつつ、「あれ?でも、歴史を教えている」って書いてあったよな?と、一番最初に見た、Amazonの書籍紹介でのトーマス・ロックリーのバイオは・・・。
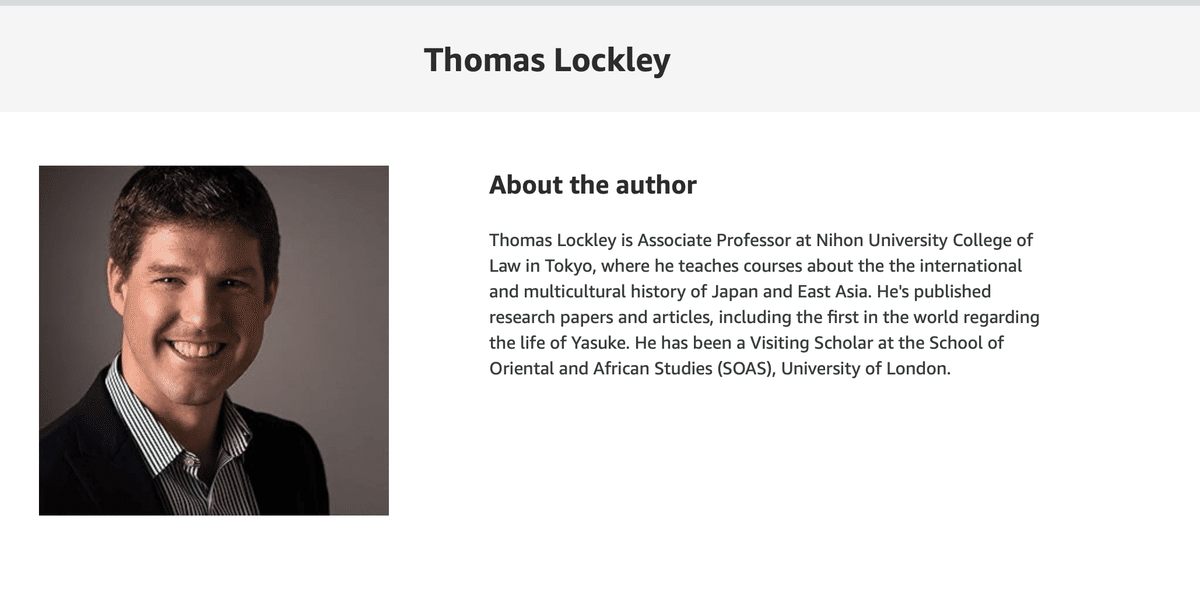
トーマス・ロックリーは東京の日本大学法学部の准教授で、日本と東アジアの国際的および多文化的な歴史に関するコースを教えています。研究論文や記事を発表しており、その中には弥助の生涯に関する世界初の論文もあります。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院(SOAS)の客員研究員を務めています。
やっぱり日本史を教えていたんかーい。
私の先ほどの訂正と、日大への謝罪は取り消しさせていただきます。
根拠のない日本史がそれっぽくなる肩書きの利用法
もしも、下記のような話が聞こえてきたら、どう思いますか?
「HIVって、怖い病気なんですよ。
何しろ、ハグや握手等、家族や友人間で交わされる、”日常生活の何気ない接触”が感染経路となってしまう懸念が十分あるのですから」
「もっと正しい知識を学んだ方がいいよ」とか「偏見から、差別につながるような発言は控えた方がいいよ」等々、思いませんか?
次にもしも、この発言がHIV の研究でロベルト・コッホ賞金メダルを2013年に受賞しているHIVの専門家で、アメリカ国立アレルギー・感染症研究所の長官を40年近く務め、大統領への助言も行っていた科学の権威、アンソニー・ファウチ博士の言葉だとしたら、どうですか?
馬鹿げた発言に対する印象が変わりませんか?そして、ファウチ博士についてご存知ない方により大きなインパクトを与えるのではないかと思います。ちなみに、この発言は本当にファウチ博士のものです(【ファウチ研】世界が信じている”科学”というもの)。コロナ禍では、多くの一般人だけではなく、専門機関までもがこんなとんでも発言をする人のアドバイスを、ありがたく受け取っていたのです。
肩書きの力ってすごくありません?
そんな前置きの後に、次の画像をご覧ください。前章の弥助の出自のところでも引用させていただいた、毎日新聞の記事。この記事では、「10年以上にわたりこのアフリカの侍を研究してきた日本大学法学部のトーマス・ロックリー准教授」と紹介されています。

さらに、この肩書きがどのような形で紹介されているか?といえば、弥助の新出自”について語られるくだりで、「弥助について10年以上も研究をしている研究者」が挿入された形の文章構成。わざとそのような文章構成にしたのか、たまたまなのかはわかりません。しかし、日本よりももっと学歴(権威)主義であるアメリカ人がこれを読んだら、おそらくこの肩書きだけで、「肌の色から南スーダンってわかったのか、すげー」と思う人が相当数でてきてもおかしくないと思います。
さらにこの文章構成だと、それまで日本にあった通説を覆すような学説を出している、勢いのある研究者っぽい印象も出てきます。
もちろん、「生活費を稼ぐために普段は外国語を教えていますが、余暇を使って弥助研究しているんです」ということもあるかもしれませんし、それ自体は、全く問題のないことです。ただし、この場合、彼の紹介文はかなり問題になると思います。
例えば、私はこのコラム(NOTE)で”ファウチ博士研究”をしてきました(笑って書こうと思いましたが、半分本気)が、そのご縁でメディアの取材を受けたとします。その記事内のファウチ博士の嘘を暴くくだりで、”ーー社〇〇部役職名で、4年以上にわたりファウチ博士の研究を続けている、GO TEXANの指摘によると〜」なんて挿入文を入れられたら、記者の人にクレームを入れます。ファウチ研究は、会社での仕事や役職とは全く関係ないためです。業務上で知り得た情報ではありませんし、会社の総意と言うわけもありませんので、そんな誤解を与えてしまっては、信用問題に発展すると思います。
そして、この写真下のキャプションですが・・・。
Nihon University associate professor Thomas Lockley uses a map to talk about the African samurai Yasuke in Tokyo's Chiyoda Ward on April 25, 2022.
日本大学のトーマス・ロックリー准教授が地図を使ってアフリカの侍「弥助」について語る。
紹介文だけではなく、この写真、キャプションも・・・全体的に、これから語られるとんでも日本史の信憑性を上げる効果があるものだといえます。
しかし、こんな演出をしておきながら、”大学では歴史を教えていません”なんてことは、まさかないですよね?その場合、この記事の信憑性に関わってくる問題ですから、部分的な訂正では収まらず、記事の取り消しはもちろんのこと、取材に対する姿勢や社内校正の甘さ等にまで関わってくる問題ではないでしょうか。
以上のとおり、トーマス・ロックリーの問題は、「悪気があったわけではないのだから、大目にみてあげて」では済まされない、意図的な印象操作が含まれた話だと思います。
日本大学の責任
トーマス・ロックリーの学術?(言論)活動に、”日大准教授”の肩書きを利用されている限り、日本大学には、この問題に関して相応の対応を行う責任があるように思います。どのような責任か?については、彼が日大で教えている教科は何か?に関わってくると思います。
TLが歴史を教えている場合:
一般的に大学教授になるためには、院に行き、博士号をとり、講師をしながら論文を発表し、それが認められていく中で、教授になっていくのではないかと思います。一方で、経済界や政治界で一定の成果を収めた人の中にも、それが認められて大学教授になるケースもあるかと思います。
そのような中、学歴欄が空欄のトーマス・ロックリーは、どのような形で准教授として、日本史を教えることになったのでしょうか?
弥助の本が売れたから?
しかないと思うのですが、仮にそうであれば、ちょっとおかしくない?なのです。というのも、トーマス・ロックリーはあくまでも歴史研究した結果として、著作物を出版しているからです。元ネタは、彼が学術論文だというものです。だとすれば、他の教授たちが教授になった過程をショートカットしての採用ということになります。それほど彼の学術論文が価値のあるものだったということでしょうか?
査読なしなのに?
根拠を明らかにしない、新説を並べた歴史書なんて、見たことがないのですが、日本大学としては、このような”斬新な手法”を受け入れての、採用なのでしょうか。「戦国時代の日本では黒人奴隷が流行っていた」「最強の黒人侍弥助が日本の歴史を変えた」という学説を日本大学の名前の下、広めても問題ないという風に考えているのでしょうか。
日本大学の准教授の肩書きを使って展開するトーマス・ロックリーによるあり得ない日本史の世界拡散は、STAP細胞疑惑と同じくらいネガティブなインパクトがあることだと思います。日本大学の名前が使われている以上、早急に何かの対応する必要があるのではないでしょうか。
TLが英語を教えている場合:
記事を読む中で、私たちはなぜ肩書きを気にするのでしょうか?
それは”その人の考えがどういった専門分野からの視点なのか?””発言の確からしさは何か?”等を知り、情報を判断する上で重要だからです。
トーマス・ロックリーが日本大学で英語を教えている場合、彼のバイオでは、自分があたかも歴史の専門家として、日大で教鞭をとっている印象操作を行なっていることになります。つまり・・・
日本大学が准教授として雇っている人物
=
彼の研究について、日本大学が一定の評価を行なっているという印象操作
大袈裟?そんなことは、ないですよ。コロナ禍の時に、コロナに既存の市販薬を利用した治療法があることを知らしめたり、ワクチンの安全性を疑問視した発言行うような教授らは、それが大学としての総意ではないことを明らかにするように指示したり、その教授を解雇したりしていたではないですか。
(この辺りはアメリカのコロナファシズム記事で紹介しています。)
そのまま放置していて良いのでしょうか?
せめて彼がいうことは、日大の歴史認識ではないこと、また、彼は歴史学の教授ではないことを発表するべきではないでしょうか。
”日本”大学という名前だからこその責任
冗談に聞こえるかもしれませんが、真面目な話。トーマス・ロックリー問題では、所属大学の名前に”日本”が入っているのが致命的になる懸念があります。NihonがJapanの意味だと知っている外国人で、日本の大学事情を知らなければ、国の名前が付いた大学は、日本のトップの大学かつ国立大学だと思われてしまう可能性があるからです。大学のランク(印象)も、その大学に所属する研究者の発言を権威づける重要な要素の1つです。
”日本”と名前が入った大学の、日本史の准教授がとなえる新説だというのですから、それがまさか、”根拠=自分の空想ストーリー”をもとにした学術論文だとは想像できないと思います。
そんなバカな?
と思った方は、ぜひ過去記事のファウチ博士研究をパラパラっと読んでみてください。そんなバカな!というとんでも理論が、権威付により、それが科学だと信じられてしまったのがアメリカのコロナ禍です。
「ワクチン接種した方が感染しない」ということは、世界的な統計に出てこなかったところか、統計上では真逆?とも思えるような結果が出てきたのですが、このような結果を見ても、科学者や医師の多くは、私の説を信じないでしょう。それは私には科学に関する肩書きがないからです。少なくともアメリカは、どんなに論理的に成立した意見であっても、そこに権威がなければ、権威あるとんでも意見の方が正しいとする人が多い国です。
考えさせられるコロナ・グラフ:各国の”収入”別・感染率(2022年3月)
アフリカのコロナ政策:ワクチン接種率と新規感染者数の関係(2022年1月)
”黒人奴隷は戦国時代の日本で流行った”が史実になってしまわないように・・・。
まずはトーマス・ロックリーが使用する肩書きの正しいものは何か?日本大学は説明する責任があるのではないでしょうか?
