
〝死〟と〝生〟が同時に存在する聖地・熊野の魅力を綴る名著です──五来重『熊野詣 三山信仰と文化』
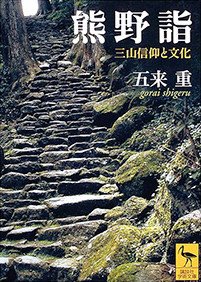
中世にいやそれ以前からかもしれませんが、なぜ貴賤を問わず数多くの人びとが熊野詣を行ったのでしょうか。隘路にもかかわらず彼らがたずねた熊野とはどのような〝世界〟であったのか。さらに熊野は霊場だけではありません。源平合戦の壇ノ浦の戦いで勝利の鍵になった熊野水軍を生んだ〝世界〟でもありました。
「南紀のあの明るい風光の奥にはこの世とは次元のちがう、暗い神秘がのぞいている」と始まるこの本は、五来さんがその〝世界〟の謎、「熊野と熊野詣の謎」を解き明かそうとしたものです。
この熊野は『日本書紀』に初めてあらわれます。伊弉冉尊の葬られた地として「故れ紀伊国の熊野の有馬村に葬りまつる」と記されています。それにふれて五来さんは伊勢神宮と対をなすものとしてこう考えています。
「もちろん伊弉冉尊の実在など考えられぬとしても、伊勢を表とすれば、熊野は裏であるという感覚がすでに奈良時代以前からあったとだけはいえるだろう」として熊野の語源を「「くまの」は冥界を意味する「くまで」、「くまじ」とおなじ「こもりの」の変化であろう」と推測しています。
熊野はまずなによりも「死者の国」として歴史に登場してきました。その視点から五来さんは烏にまつわる神事、信仰に触れています。なぜそのような信仰が生まれたのか……、
「烏と死者の関係は、おそらくわが国の古代葬法に風葬が多く、死屍にあつまる悪食の烏が、さながら鳥葬の観を呈したからであろうと、私はかんがえる」
もちろん熊野の烏といえば神武天皇を導いた八咫烏を忘れるわけにはいきません。河内から大和へ信仰した神武軍が行く手をはばまれ、大きく新宮の地へ迂回し、熊野の本宮をへて南大和へ侵攻し、新たな王権を確立したといわれています。この八咫烏ゆえに烏が霊鳥とされたといわれていますが……、
「神武天皇伝説の成立する七、八世紀以前から熊野と烏の関係はできており、この烏をミサキ烏というところから、神武天皇の嚮導者に仕立てあげられたというべきであろう。(略)熊野には古墳時代の古墳が存在しないことから、風葬が卓越しており、そのためにとくに烏が神聖視されたものであろう推理される」
けれども、それは五来さんによれば逆立ちしていることになります。神武伝説のためにすでにあった民間風習を利用したものだったのです。
こういう推理の裏には五来さんの
「私は熊野詣といえば熊野御幸の数だけをとりあげ、熊野文化といえば貴族ののこした遺物だけをかたることには、我慢がならない。むかしも今も熊野は庶民のためにあるのだし、庶民の涙と汗が熊野街道にはしみこんでいる。おそらく貴紳の熊野詣でも、庶民の熊野詣の流行に刺激されておこったものだとおもう」
という信念があるのではないかと感じ取れます。
〝死〟は山や森でけではありません。
「熊野が死者の国であったのはひとり山と森だけでなく、海までもそうであった」
補陀落渡海に触れて五来さんが記した一文です。海の彼方の極楽へと向かったともいわれていますが
「補陀落渡海の真相はまったく謎である。しかし私は水葬と入水往生の二面をもつ宗教的実修と推定して、大きなあやまりはあるまいとかんがえている。もちろん古代葬法としての水葬が先行し、熊野の中世浄土教化にともなって入水往生がおこなわれるようになったのだとおもう」
この〝世界〟は確かに〝死〟を思わせることが多い〝世界〟です。
ではなぜ多くの人たちがその〝世界〟を訪れたのでしょうか。熊野詣の困難さはこの本でも後鳥羽上皇にお供した藤原定家の『後鳥羽院熊野御幸記』を引きながらそのようすを紹介しています。それであっても多くの人びとは熊野詣を続けていきました。
そこにはこのような信仰があったと五来さんは記しています。
「日本の民族宗教には「擬死再生」の論理があって、山の他界は、そこで一旦死んで生まれかわってくるところであった」
〝死の国〟を訪れることは、実はそのまま新しい生をうけて文字通り〝蘇ってくる〟ということだったのです。
くわえて
「よく死者に出会うという熊野道の怪異は、あまりの難路にあえいで呆然としたときの幻覚でもあろうが、また熊野を死者の国とした古代信仰の残像であるかもしれない。そして熊野詣での苦行は、死者に代って罪障を消滅し、後生安楽ならしめようという、代受苦の苦行であった」
という庶民の願望も込められているものだったのです。
死がそのまま生でもある〝世界〟が熊野信仰の根源にあるものなのではないでしょうか。そしてこの信仰の特異性は「熊野別当」でも指摘されています。
「熊野別当と熊野大衆は熊野修験道教団を形成していたのであるが、ここに三山信仰の特異性があるといえる。すなわち三山信仰は神道でもなければ仏教でもない第三の宗教だったのである。しかも比叡山や高野山とは違った教団組織をもち、妻帯世襲の半僧半俗の別当家にひきいられた山伏の黒衣武士団と、全国的な散在山伏の勧進組織から成っていたといえよう」
さらに五来さんは、この熊野別当家に「結婚と相続も近親婚的では母権制的なものがあった」と推測しています。ここにも古代の名残があったのかもしれません。
もしそうだとすれば、中世において、現世的な権力を喪失した天皇家が古代にふれることで権力(の源泉ともいえるもの)を回復するために行ったのが熊野詣なのかもしれません。それは救済を願う庶民の願望とは異なったものではなかったでしょうか。
今の私たちはどのようにその〝世界〟を接すればいいのでしょうか。
「合理主義に徹した文化人、知識人の心は、合理主義の公式で解ける。しかし非合理的、前論理的な庶民の心は、公式では解けない。熊野の謎はそのような庶民の心の謎である。それは神道理論も、仏教理論も、美学理論もうけつけない。ただ熊野三山の歴史と遺物を虚心にみつめ、熊野三山の一木一石一径をあじわうよりほかはないのである」
知ることではなく、感じること、ということはたやすいですが、今の私たちにそれが可能なのでしょうか……。
五来さんが火祭りを見て「火竜のような火の集団が山上にのぼり、神門内で祈祷ののち一斉に走り下る。このとき神倉山は那智の滝の水を火にかえたような「火の滝」をかけるのである」と感じるような感性、畏敬の念はまだ残されているのでしょうか。名著といえるこの本を読みながら、ふと中上健次さんの〝路地〟の消滅を思い出してしまいました。
書誌:
書 名 熊野詣 三山信仰と文化
著 者 五来重
出版社 講談社
初 版 2004年12月10日
レビュアー近況:昨晩「夢の続き」を立て続けに二本見ました。「明晰夢」というものらしいですが、それを見るための鉄則は「夢を自覚した段階で起きてしまわない」とのコト。その掟を守って二度寝どころか三度寝して寝坊した訳なのですが……。
[初出]講談社BOOK倶楽部|BOOK CAFE「ふくほん(福本)」2015.07.08
http://cafe.bookclub.kodansha.co.jp/fukuhon/?p=3723
