
100年企業の「らしさ」を可視化して未来をデザインしよう
この記事は2023年10月1日に開催されたDesignship 2023 Day2でお話した内容を資料共有の代わりにアップした記事です。

自身が創業60年のデザインカンパニーでキャリアをつんできている中で感じている日本企業の強さと、その強さの根幹にある「らしさ」を可視化することが持続的に社会に価値を届けられる企業をデザインする再現性を高めるのではないかと考えていることについてまとめています。
日本企業は世界一
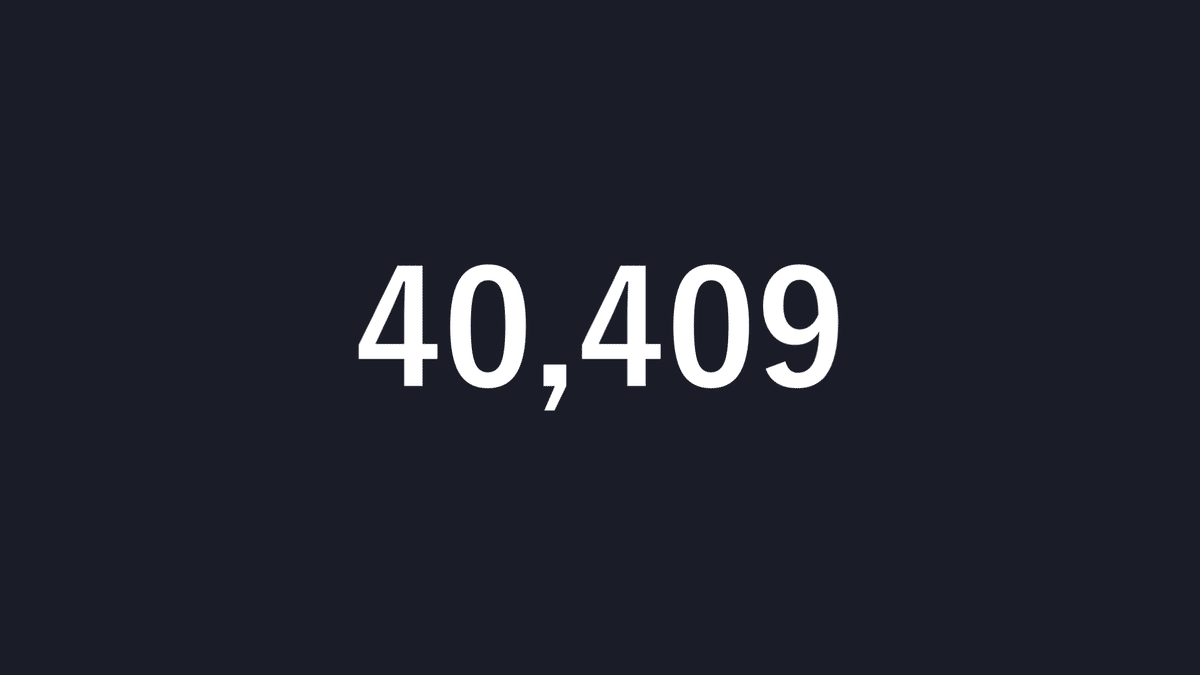
「40,409」この数字は100年続く日本企業の数です。
世界中にある100年企業の約4〜5割ほどが日本企業と言われており、日本は世界一の長寿企業国だ。

有名なのでご存知の方も多いかもしれないが、世界最古の企業も日本企業。お寺や神社などの建設をしている金剛組という会社です。
創業はなんと飛鳥時代!西暦578年に聖徳太子から招聘された宮大工らが立ち上げたと言われています。
長寿企業こそサステナブル

長寿企業が多いということは、本業を通して社会に価値を提供し続け、社会から必要とされ続けてきたってことだと私は解釈しています。
時代の変化や技術革新に適応をしながら、企業として変化と成長を続けられたからこそ100年を超える長期間にわたって持続的な成長を実現しながら生き残ってきたのだと思います。
つまり、日本にはサステナブルな経営を行ってきた会社が多いということではないでしょうか。(少し飛躍しすぎかもしれないけど)
これからの企業活動においてこの長寿企業の歴史から学べることがたくさんあるはずなんです。
なぜ日本に長寿企業が多い?
こちらは既に色々な研究がされているおり、様々な研究資料や書籍が出ていますが、調べてみると日本に長寿企業が多くなった理由はこの2点が大きく影響を与えているようです。
1点目の理由は、島国だった土地柄。
日本は外国からの侵略を受けて支配を受けるようなことはほとんどありませんでした。
そのため、戦後に外部の力によって企業が再編成されることは多少あれど、継続がしやすい環境があったのでしょう。
2つ目の理由は、国民性。
日本人の国民性は勤勉です。
海外から学び、独自の工夫を取り入れることによって、社会の急速な変化にも適応し続け、成長してきました。
また、「家柄」を守る風潮が強いのも重要な要素であり、血縁を残すことができなくても優秀な養子や婿を迎えいれて、家の存続を計る。
武家の時代の話のようにも聞こえますが、一族経営の企業においても優秀な人物を家族に迎えいれることによって成長し続けてきた企業もあると言われています。
日本企業が長生きの秘訣

これまでの話から、日本企業が長生きできてきた秘訣は「自社らしさを大切にして、デザインし続けてきたこと」だと私は考えています。
社会が変化して新しい事業に舵を切らないといけなかったとき、
事業承継で経営者が変わったとき、
この「自社らしさ」が変化に適応しつつも軸はブレない強さにつながったのではないでしょうか。
長寿企業にも課題はある

一方で、長寿企業は経営者の高齢化や後継者不足の課題を抱えることが増加しており、事業承継が社会的にも課題となりつつあります。
アトツギでの承継、持株会社をつくって社員で承継、M&Aなど、色々な選択肢はあれど、どのケースでもこれまで暗黙知としてデザインされてきた「自社らしさ」は承継時の変化を乗り越えるために非常に大切な要素だと、私は思っています。
なぜこの話を私がするのか
アトツギに生まれた訳でもない私がなぜこのような話をするのか?
Designshipといえば、独自の物語ということで少しだけ私の話をさせてください。
私は新卒で入社した創業60年のデザインカンパニーで同様の後継者問題を最前列でみてきました。
ファミリー企業だった当社はM&Aで資本提携して承継する選択をしたのですが、様々な変化も当然求められるなかで、これまで大切にしてきた「理念・MVV・クレド(行動指針)」を拠り所として「変えていいところ」「変えてはいけないところ」を見極めながら、さらにいい会社になっていくために変化し続けている真っ最中です。
自社の話は別記事にまとめてますので、ご関心あればご覧ください。
100年企業のらしさを可視化する

ここからは、私自身が自社での経験を踏まえて、実際に支援した事例のお話です。
創業から100年以上続く愛知県の製缶会社 側島製罐さんと行ったプロジェクトです。
時代の変化とともに年々売上が減少している状況を打破するために事業承継前のアトツギが様々な変革を推進するなかで、拠り所とできるものがない課題を抱えていました。
そこで、これまで言語化されてきていなかった
「自分たちがどこから来て、どんな未来をめざしているのか。そして、どんな価値観をもって日々行動していくのか。」を改めてMISSION・VISION・VALUEとして言語化し、会社と社員の皆さんで共有できるツールを整備していきました。
まずは率先垂範、宝物を託す体験から

ツールはただカッコイイもの、オシャレなものを作ればいいというわけではありません。
どうすれば、忙しい普段の業務の中でも「会社と社員さんで進べき方向を日々すり合わせられるだろうか」「成長につながるような新たな気づきを得るきっかけを作れるだろうか」とか使い続けられるツールとするために徹底的に考えて、ツールへ落とし込んでいきます。
側島製罐さんのツールでも、色々なしかけが盛り込んであるのですが、その中から1つピックアップして紹介します。
言語化したMVVはブックとカードに分けて可視化し、それを缶にしまうキットとなっています。
なぜ缶に入れたのか?
側島製罐さんのVisionは「宝物を託される人になろう」
このVisionを実現していくためにも、まずは自分たちの宝物であるMVVを自分たちの手で作った缶へ託すことからスタートさせて、自社の提供価値が変化したことを体験して欲しかったから。
そして、この経験を通じて自分の言葉でMVVを語れる社員さんが増えれば、できたばかりのMVVにさらに魂が込められていく、そう信じていたからでした。

このプロジェクトはアトツギの方と一緒に推進したプロジェクトでしたが、大切にしてきたのは社員の皆さんにもプロジェクトの一員として参加してもらうこと。
一緒に意見を出し合って作りあげることによって、
プロセスを通じて自社理解を深めていくことができるだけでなく、関わってきた当事者意識によって、完成後に率先して実践するアンバサダーになってくれます。
実際にこのプロジェクト後、MVVを起点として社員さんが自律的に行動をしていくような変化のきっかけとなり、年々悪化していた業績も回復。
ビジネス的なインパクトもでたと聞いています。
注)可視化はあくまできっかけであり、この成果は社員さんらの努力の賜物です。側島製罐さんは今も仲良くしていただいてますが、本当に素敵な尊敬している会社さんです。
側島製罐さんのビジネス的な変化や可視化後の取り組み等を詳しく知りたい方は代表 石川さんのnoteや中企庁サイトに掲載されている資料をご覧ください。
使い倒すには「しかけ」と「しくみ」が大切
可視化したものは額縁にいれて壁に飾っておくだけでは、何も意味がありません。

社員全員で使い倒すための「しかけ」と「しくみ」づくりが超大切です。
・公式の場
・非公式の場
・制度やツール
色々な接点で、何度も何度も触れることによって
理解が深まってようやく少しずつ行動へと反映されていくものです。

そして、使い倒せるものとするために可視化・言語化するときのポイントは自分たち「らしい」独自の表現を取り入れること。
歴史は未来をデザインするための資産
この「らしさ」は可視化したら、社会に対して共有していくことが必要になっていくのではないでしょうか。
自分たちがどんな価値観を持ってて、どんな未来をつくりたいか、
お客様やビジネスパートナーとも共有して、共感でつながりながら、一緒に実現していくような社会ができたら素敵じゃないかと思っています。
100年企業が築いてきた「歴史や文化」を資産と捉えて、そこから「らしさ」を深掘りする。
そして、どんな未来に向かっていくのか語っていく。
「らしさ」を可視化することが、これからの未来をデザインする一歩目になります。
最後に、会場で直接聞いてくださった皆様ありがとうございました。
緊張しつつも楽しみながらお話することができました。
また色んなデザインについて語り合いましょう。
