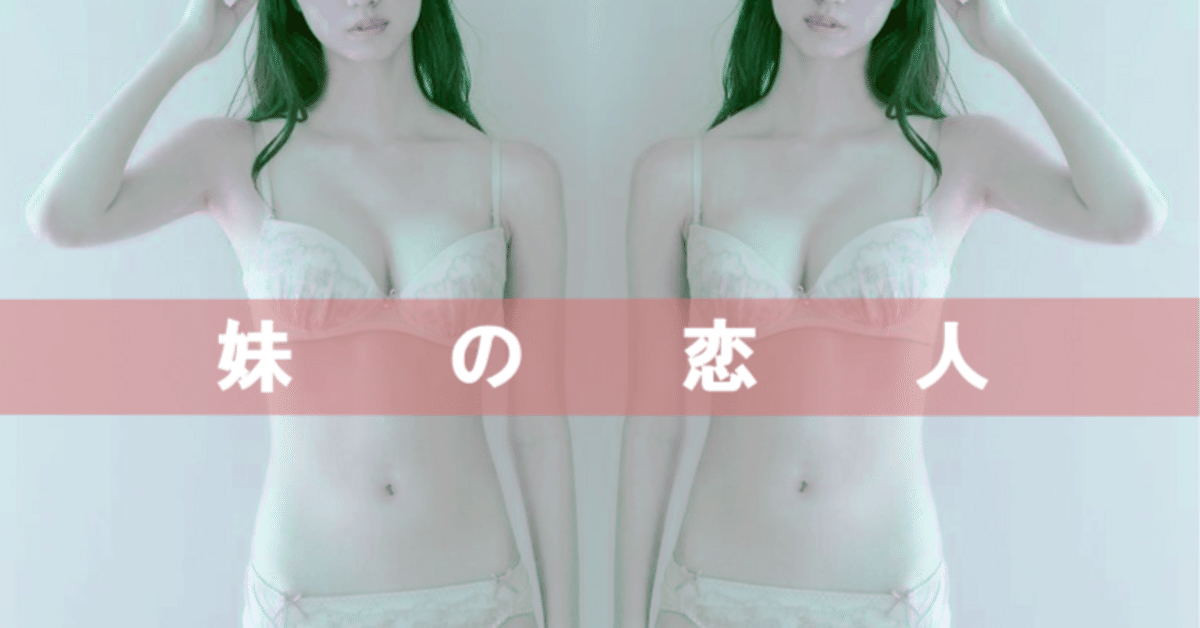
妹 の 恋 人 【25/30】
■
それからどうなったか……?
お姉ちゃんはあたしから目を離さないようにするため、大学をやめて、地元の印刷会社に就職した。
そして、実家から二駅離れた街に2LDKのアパートを借りて、あたしにそこで一緒に住むように強要した。
あたしはいやとは言えなかった。
そして今も、あたしとお姉ちゃんは一緒に暮らしている。
「これからはぜったい目を離さないからね」お姉ちゃんは言った。「これからは、わたしの目の届かないとこでヘンなことしないでね……あんたの問題は、わたしの問題なんだからね……わたしとあんたは、一心同体なの。あんたが傷つけば、わたしも傷つく。あんたが悲しめば、わたしも悲しむ。それを肝に銘じて生きいこうね」
あたしはそのときも……確か曖昧な返事をしたように思う。
それから、二人で暮らしはじめて3年になる。
そうすることによって、あたしは変わったか?
……ぜんぜん変わらなかった。
あたしはむしろ、より濃い孤独を感じるようになった。
お姉ちゃんと食卓で顔を合わせ、膝と膝をつき合わせて食事をしても、そこに会話はない。
お姉ちゃんは相変わらず……あたしにほとんど口を効かなかった。
はじめのうちはあたしも、お姉ちゃんの気を引くためにいろいろな会話を持ちかけたけど、お姉ちゃんは面倒くさそうに適当な相づちを打つか、あたしの話を鼻で笑うだけだ。
あたしはつらかった。
一人で暮らしているときより、ずっと寂しかった。
こんなことなら、どこかへ逃げて、たった一人で暮らしたほうがましだと考えるようになった。
でも、お姉ちゃんがそんなことを許してくれるわけがない。
家に居るのが苦痛で、大学に通っている間はしょっちゅう外泊した。
バイト先の先輩や同僚、友達の友達の友達が紹介してくれた友達の家に。
たぶん、改めて言わなくてもいいと思うけど……全部、男の人だった。
そうすることで、あたしが身体を重ねた男の人の数は、みるみる増えていった。
不思議なことに、これまで男の人に泊めてくれと言って、断られたことはない。
みんなが快くあたしを受け入れてくれた。
たぶん、男の人はみんなそうなのだろう。
当然、そうすると必然的に身体を求められてしまう。
それにもあたしはちゃんと応じた。
あまりよく知らない人といやらしいことをするのは気が引けたか……?
いや、ぜんぜん。
まったくそんなことはない。
そのままお姉ちゃんの待つ家に帰って、あの無愛想と冷たい態度による拷問に耐えるよりは、ずっとましだった。
それに、あんまりそんなことを認めたくはないけれども……
男の人といやらしいことをするのは、そんなに嫌いではない。
……というか、むしろ大好きだった。
キスされたり、愛撫されたり、はたまたそれ以上の行為をされたりしたら……あたしは無条件でその人のことを好きになってしまうらしい。
そして、そういうことをされる前からその人のことが好きだったのか、そういうことをされたから好きになったのか、順番が分からなくなってしまう。
まるで、誰にでもクッキーひとつで手なずけられるアホな洋犬みたいだ。
朝帰りすると、お姉ちゃんはかんかんに怒ってあたしを罵った。
「アホ! バカ! マヌケ! 淫乱! あばずれ!」
……その他いろいろ。
お姉ちゃんが恐いことに変わりはなかったけど、あたしにしてみれば、罵っているお姉ちゃんのほうが、無視するお姉ちゃんよりずっとましだった。
ボロクソに貶され、酷いことを言われながらも……あたしはその瞬間だけ、この部屋で孤独を忘れることができた。
あたしの身体の上を通り過ぎていった男たち(なんて言うとすごく月並みだけど)の中には、何人か一晩限りの関係では許してくれない人も居た。
しつこく言い寄られ、関係だけを求められて、あたしはその相手に幻滅したか?
ぜんせんそんなことはない。
むしろあたしは、それだけあたしにこだわり、求めてくれるその人たちのことをますます好きになった。
とんだ勘違いだということは、痛いほどわかっている。
現に、そういう男の人たちには必ず、本命の彼女さんや、奥さんが居た。
そういう男の人たちとあたしは、どこか似ているのかも知れない。
あたしは、求められれば求められるほど、愛されていると勘違いする。
男の人たちは、応じられれば応じられるほど、自分を大したものだと思える。
それもまた勘違いだ。
……そこまで判っていて、あたしはなんで自分を止められないのだろう。
彼女や奥さんがいて、あたしとの関係を続けることを上手く隠し通せない不器用な人も何人かいた。
当然、その人とあたしとの関係が明るみに出れば、修羅場になる。
そしてあたしは要領よく逃げ出すことも出来ずに、自分では到底処理できないトラブルを抱え込んでしまう。
そのたびに、お姉ちゃんは怒り狂った。
あの一七歳の江田島さんのときみたいに、自分の小指にヒビが入るくらいあたしをぶった時みたいに、怒りを爆発させる。
わたしを罵り、時にはぶち、そしてトラブルの相手先に怒鳴り込んでは、すべてを焼き尽くさんばかり勢いで、めちゃめちゃにする。
お姉ちゃんは、すべてをめちゃめちゃにすることの天才だ。
それは高校一年生の内藤先生のときから変わらない。
大学卒業後に入社した文房具メーカーの小さな会社では、入社三ヶ月で、先輩である妻子持ちの男性とそういう関係になり、奥さんにも、会社にもバレて、どうしようもない修羅場になった。
詳しくは言わないけど、お姉ちゃんはそれもめちゃめちゃにした。
わたしの会社に乗り込んできて……思い出すだけでも怖い。
わたしは社会人一年目そうそう(というか3ヶ月目)に“一身上の都合”で会社を辞めることになった。
それから今日まで、あたしはだらだらフリーターをやりながらお姉ちゃんと暮らすこの部屋の生活費を、ごくわずかだけど入れている。
それでもあたしは、男の人に求められれば、それに応じ続けた。
佐々木さんとはこの部屋ではじめて関係を持ったのだけれども、それはお姉ちゃんが出張で家を空けていた日のことだった。
やがてあたしは妊娠した。
どうしていいかわからなくなって、全てをお姉ちゃんに打ち明けた。
その時、あたしは言わなくてもいいのに、初めて関係を持ったのはこの部屋であることをお姉ちゃんに明かした。
お姉ちゃんの激怒ぶりときたら、まるでこの世の終わりのようにさえ思えた。
あたしは激しく罵られながらも、ぞくぞくする自分を抑えられなかった。
あの感覚は……かなり常識離れしているので、わかってもらうのは難しいと思う。
もしくはあたしは、いつの日かお姉ちゃんに完全に見捨てられることを、恐れながらも待ち望んでいるのかもしれない。
今度こそ、今度こそ絶対に見捨てられる……。
間違いを犯すたびに、あたしはそう思った。
お姉ちゃんはすさまじい勢いで怒り狂うけれども、あたしは決して見捨てられることはない。
嵐が去ったあとには……また、適当な相づちと冷笑しか見せないお姉ちゃんとの、息が詰まるような毎日が待っている。
結局、何も変わりはしない。
いつまでこんなことが続くのだろうか……?
それは、あたしが賢くなるまで続いて止められないのだ。
と、そんなことを考えていたら、玄関のベルが鳴った。
ドアを開けると、なんとそこには、佐々木さんが無邪気な笑顔で立っていた。
「サっちゃん……元気?」
佐々木さんが笑う。
目眩がした。
今度こそ、なにもかもおしまいにできるかも知れない。
そんなことも考えた。
あたしは力なく、佐々木さんに笑い返してみせた。
