
【前編】その競合…本当に“本質的な競合”ですか?
おはようございます!週の中日ですね。
今日も皆さまの1日が楽しくなりますように。
さて、今回は「競合」について2本立てでおおくりします。
前編では、「“本質的な競合”とは?」と「本質的な競合の見つけ方」について書いていきたいと思います。
自社の競合…それは“本質的な競合”ですか?
一般的に、自社の“競合”とは「同じ市場カテゴリの商品を販売している他社、ブランド、および商品」のことを指しますよね。
例えば
・「化粧品会社」なら…資生堂の競合はナンバー2の花王(・カネボウ)やコーセーなど。
・「化粧品ブランド」なら…資生堂「マキアージュ」の競合は、同価格帯のカネボウ「コフレドール」、花王「プリマヴィスタ」、コーセー「エスプリーク」など。
・車なら…BMWの競合はフォルクスワーゲン
といったところでしょうか。
しかし、競合をとらえる際に同市場の商品を見ているだけでは、”本質的な競合”を見落としている可能性があるんです。
”本質的な競合”とは…感情や行動の奥の「インサイト」に隠れている
P&Gジャパンや西友を経て、現在サンリオのCMOを務める木村氏は、登壇したセミナーで「ブランディング戦略」について次のように述べています。(下記記事から引用)
人が商品やサービスを買うのは片づけたい用事=ジョブを解決するためである
彼はこれを「ジョブ理論」と呼び、次のように説明しています。
たとえばミルクシェイクを買うのは、「通勤の自動車で手を汚さずにお腹を満たしたい」というジョブのため、という顧客のインサイトが見えてくる。
そうすると、ミルクシェイクの競合は、アイスクリームやジュースではなく、手を汚さずにお腹を満たせる別のモノである可能性に気づくことができる。つまり、ジョブの発見が市場を定義する第一歩となるのだ。
ここで言う「手を汚さずにお腹を満たせる別のモノ」こそ、”本質的な競合”と呼べるものではないかと私は考えています。
言い換えると、”本質的な競合”=同市場以外の商品で、顧客が真に求める目的が達成できるものです。
もちろん、同市場のアイスクリームやジュースも大切な競合なのですが、顧客インサイトを見つけ出す視点としてより本質に近い方を、ここでは”本質的な競合”と呼ぶことにします。
”本質的な競合”はどうやって見つけるの?
昨今のマーケティングの世界では、「人は商品そのものだけでなく、その商品によって得られる体験価値(=ここでいうジョブ)にお金を払う」と言われており、ジョブ理論もまさにその考え方に則ったもの。
上記のミルクシェイクの例に当てはめると、
①その商品が与える体験価値(=手を汚さずにお腹を満たす)に焦点を当てる
②その行動の奥にあるインサイト(=通勤時の自動車では手を汚したくない)をとらえる
③「そのインサイトを解決する手段で、同様の体験価値を生む商品はなんだ?」という逆算思考で、”本質的な競合”を発見しにいく
(ああ、、これ↑↑は後編で図にして分かりやすくしたい…)
これが”本質的な競合”の見つけ方、といえると思います。
インサイトの考え方については、USJを劇的なV字回復に導いたCMO・森岡氏の著書「USJを劇的に変えた、たった一つの考え方」が非常に参考になります。
「人々は4分の1インチのドリルを欲しいのではない。人々が欲しいのは4分の1インチの穴である」
(※マーケティング界の巨匠・レヴィット博士の言葉)
消費者が欲しいのはアトラクションではないのです。…(中略)そのアトラクションを体験したときに巻き起こる「感情」です。
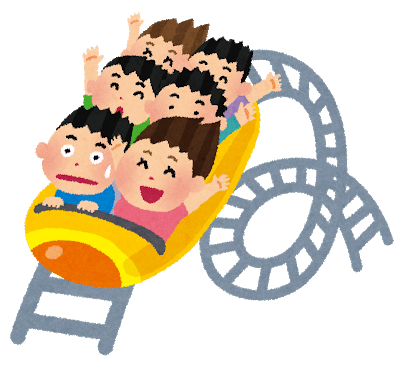
これも、単なる解決手段(ドリルやアトラクション)ではなく、インサイト(穴が欲しい、~という感情を感じたい)の大切さを説いている考え方です。
さらに、この本には「インサイトから逆算してその悩みを解決する商品を考え、体験価値を生み出す」実例が書かれています。
USJの大ヒットイベント、「ハロウィンホラーナイト」。
このイベントは、若い女性をメインターゲットにして企画されたものです。
日頃、日本の女性はその国民性から、本音をさらけ出すことは決して多くはない。知らず知らずのうちにストレスをためている可能性もあるのではないか。
それならハロウィンの夜にゾンビに遭遇する、というイベントがあれば、誰にも遠慮せず大声で叫ぶ場が(=口実が)できるし、ストレスの解消にもなるのではないか。
そんな仮説を立ててイベントをリリースしたところ…予想を超える大ヒットとなったそうです!
これもまさに、女性のインサイト(=日頃のストレスを解消したい)から逆算して、解決手段(=イベントアトラクション)を導き出した好事例ですね。
そしてここでの体験価値は、「ストレス発散」ということになります。
体験価値は“感情”(幸福感、スリル感、爽快感など)の場合と、“行動”(~という不便が解消された、など)の場合とがあります。(両方ある場合も。)
USJの例は感情、ミルクシェイクの例は行動が体験価値になりますね。
ぜひ、自社商品によって得られる体験価値を、今一度洗い出してみてください。
それをヒントにインサイトを導き出せば、その体験価値を提供する別の”本質的な競合”もおのずと見えてくると思います。
※ちなみにUSJ森岡氏のこちらの本、マーケティングの思考・実践について実践から得たかなり有益な知見がたっぷり載っているので、マーケッターは見ない手はありません。
私のマーケティング系おすすめ本TOP5に入ります!!
まとめ
今回の要点を以下にまとめます。
■“本質的な競合”とは
同市場以外の商品で、顧客が真に求める目的が達成できるもの
■本質的な競合の見つけ方
①自社商品が与える体験価値(顧客にとって良い体験や、そこで発生する感情)を洗い出す
②その奥にあるインサイトをとらえる
③「そのインサイトを解決する手段で、同様の体験価値を生む商品は何か」という視点で”本質的な競合”を見つける
次回の予告
本当はこの後、そのまま続けて
・例えば本質的な競合って、どういうもの?
・なぜ本質的な競合が大切なの?
という疑問について例を出しながら考察を書こうと思っていたのですが、全体的にボリューミーになりそうなので、前編と後編に分けることにしました!
つづく
後編はこちら
