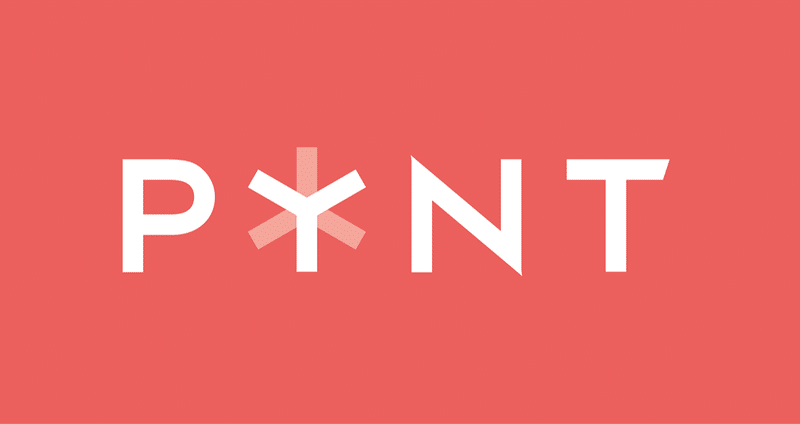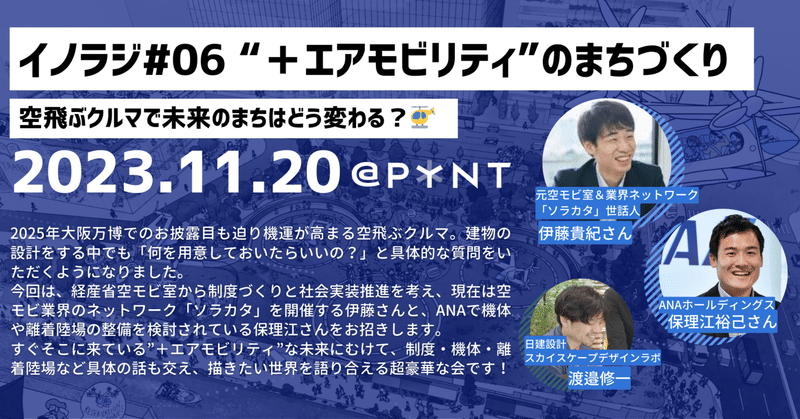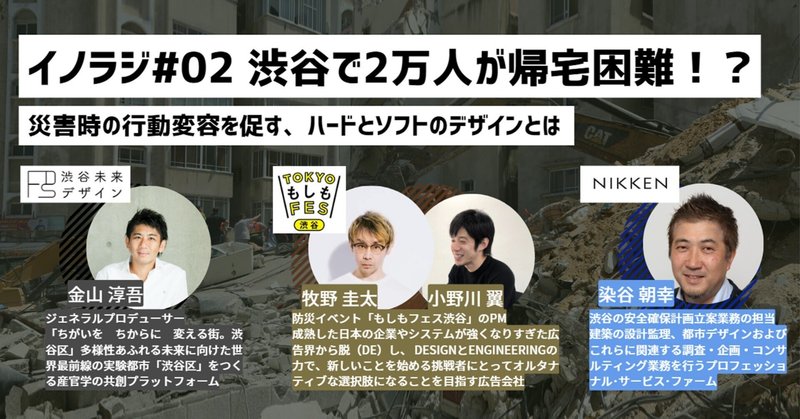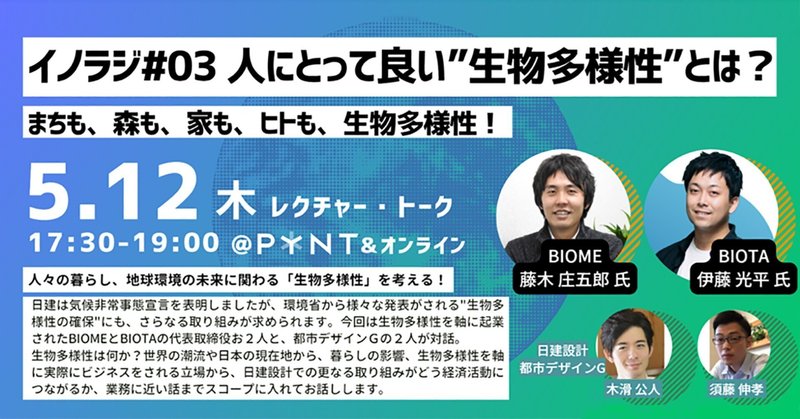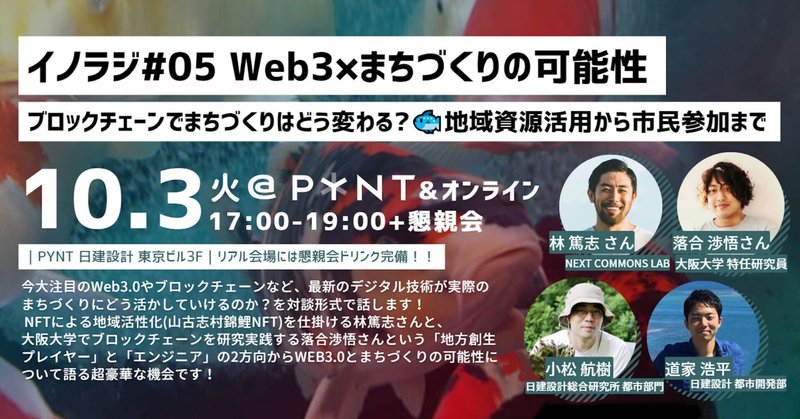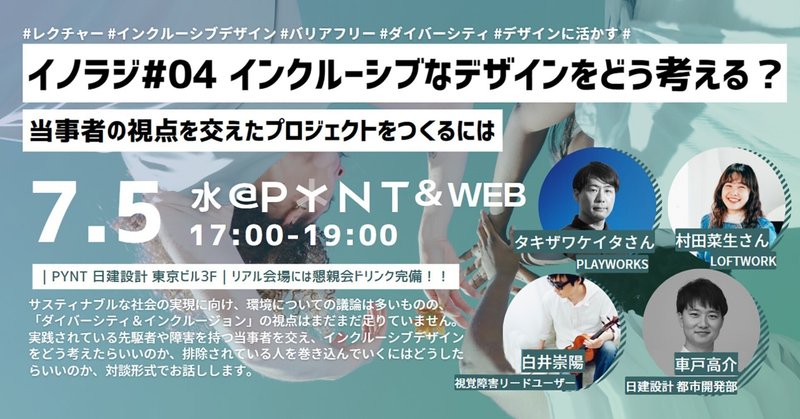記事一覧

2050年のリジェネラティブな都市とは ~新たな繋がりをいかにデザインするか?「NIKKEN NEXT MISSION」3rd SEMINAR
石川 貴之 日建設計総合研究所 取締役所長 リジェネラティブな都市 2050に向けた萌芽金行美佳:まずは日建グループから、金行、佐藤の順でインプットをいたします。現在、都市づくりを取り巻く課題として、「都市の均質化」「生活スタイルの多様化」があげられます。また、自然災害など予測不可能な事象が多く発生する中、「自立した都市づくりの必要性」も説かれています。そこで、環境や社会・経済の持続可能性を超えて、積極的に改善し再生する「リジェネラティブな都市づくり」が注目されています。

2050年の自然とコミュニティ 「みどり」を「Commons」に変えるには?〜都心と地域のデザインアプローチ 「NIKKEN NEXT MISSION」2nd SEMINAR
石川 貴之 株式会社日建設計総合研究所 代表取締役所長 これからの未来は「不確実」で「非連続的なこと」が起きると言われる今、そのような未来の社会や都市を見据えた時、私たち日建グループは「どのような中長期的な視点を持ち、どのような市場と課題を捉えて都市・環境ビジネスに取り組むことができるのか?このような問いを立て、社内外の人々と議論していくこととしました。 「NIKKEN NEXT MISSION SEMINAR」と名付けたこのイベント。第2回目のテーマは「2050年の自