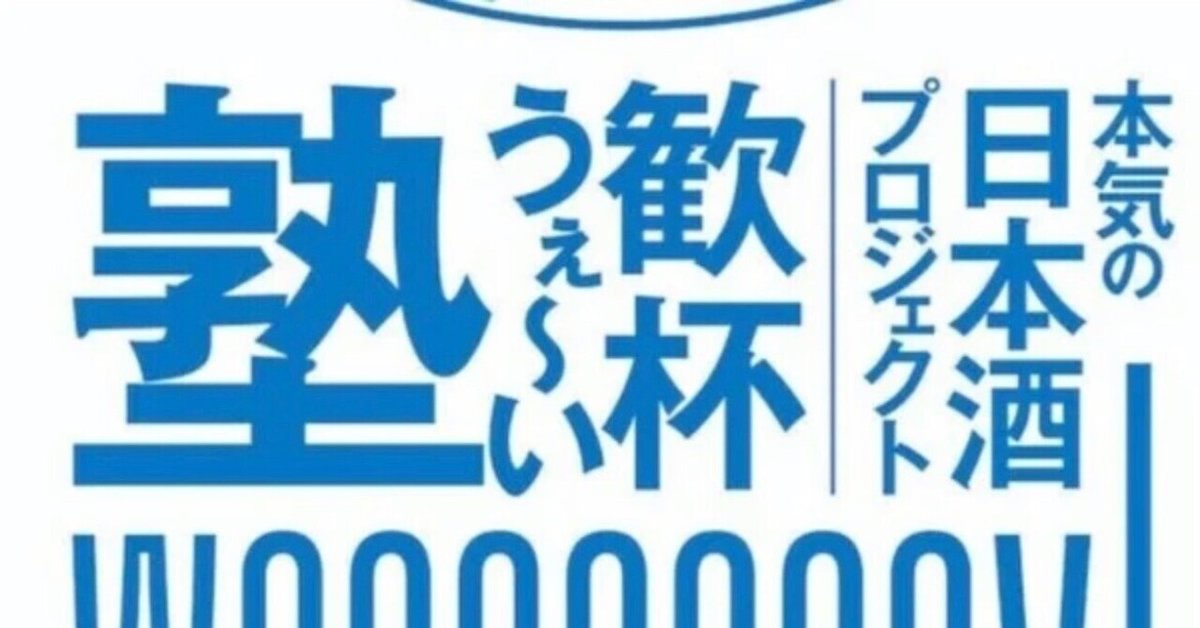
「つなぐ」ということ
前回も少し触れたAI。
ここ数日で、あなたは何度スマホに話しかけただろうか。音声アシスタントは誕生してから既に10年以上経過している。
そんなAIが出てきてから楽になったことは数知れない。今まで人間がやっていた作業を正確に着々と進める様は頼もしさすら感じる。
そんな中、未だ手で作業をしている業界もある。時に人は、それを伝統と呼ぶのだろうか…。

ーーーーーーーーーー
何度か書いてきた本プロジェクトの代表のひとり、かばちゃん。
彼女は日本に40人程しかいないと言われている女性蔵元杜氏のひとり。
なぜ女性杜氏が少ないのか。
日本酒を作る蔵には女性の神様がいて女性が入ると嫉妬をし日本酒の味が落ちると言われており、ずっと蔵の中は女性禁制だったのだ。1人目の女性杜氏が生まれたのはなんと1970年代。

そんなかばちゃんは、八千代酒造の長女として生まれ、育ち、紆余曲折ありながらも、100年以上歴史のある同蔵を継いだ。
それは、萩・阿武地区初にして唯一の女性杜氏の誕生だった。
彼女は、今まで八千代酒造で作られていた商品(代表銘柄「八千代」)だけではなく、自身のオリジナル銘柄『ROOM(ルーム)』も発表。
「家に帰り、テレビを見ながら、ひとりの時間。そんな時に飲んでほしい。」という思いから、『ROOM(部屋・空間)』という名前をつけた。
今では他代表商品に負けず、『ROOM』もお店に卸せば、すぐに完売になってしまう程の人気商品になった。

そんなかばちゃんを見てプロジェクトメンバーのひとりは言った。
「人間国宝になってもいいと思う。だって希少性も半端なくないか?今も手作りで作ってるんだよ?」
大袈裟と思う人もいるだろうか。
しかし私には一笑に付すことはできなかった。
注目すべきは、八千代酒造では、このAIが発展した現代でも手作業で作られている、ということ。


ここで、日本酒の作り方を確認しておく。

上記を見ていただければ、直接酒造に関わったことがない人でも想像できると思うが、機械化できる部分は多々ある。
洗米、温度管理、酵母作り、深夜も続行されるかき混ぜ、搾り。等等。
やろうと思えばいくらでもできるのだ。
だが八千代酒造では、今も、昔も、もちろん今年も、手作業で作っていった。
書くまでもないが、人間より機械のほうが正確だ。
人は忘れる。人は間違う。人には感情や気持ちがあるから、その日によって変化する。
正確さだけを追求するなら、機械の方が数段良い。
実際、ほぼ機械化して単価を下げた日本酒を作っているところもあるのだ。
だが、それをしないのだ、あえて。

なぜかと問えば、責任ある蔵元杜氏の顔をして、かばちゃんは言った。
『蒸し米を冷ます作業も手作用だし、搾るのも手作業。昔ながらの槽という機械を使って搾る。醪をひとつひとつ酒袋に入れて丁寧に酒袋を折り込み何段も重ねて時間を掛けて。搾り機の主流である藪田式じゃない槽搾りの良いところは、時間を掛けることでお酒に負担がかからずまろやかに仕上がるところ。」

なんてことはない。こだわっていた理由は、他でもない日本酒の品質のためだったのだ。
時間がかかっても、労力がかかっても、それでもこだわるのは、品質のため。
引いては、お客さんの笑顔のためだろうか。
昔ながらのやり方を見ると、人によっては「古臭い」「コストがかかる」等の意見もあるだろう。
だが、何事も一長一短はあるが、譲れないものは譲れない。
いや、譲ってはいけないものが時にはあるのだ。
そんな譲れないものを引き継ぎ繋げていった、その先の未来を日本では『伝統』と呼ぶのではないだろうか。
そんな伝統のひとつに、きっと彼女もなっていくのだと思う。

これはオンラインサロン・田村淳の大人の小学校内日本酒プロジェクトのnoteです。
【発行・日本酒プロジェクト内日本酒うぇいうぇい広報部】
リスク先ーまとめー
