
【パリ旅行記】ナポレオンの墓があるアンヴァリッドへ~文豪達も憧れたナポレオンというカリスマを考える
パンテオンでルソーやヴォルテール、ゾラ、ユゴーのお墓参りをした後に私が向かったのはアンヴァリッド。ここにはあのナポレオンが葬られている。

パンテオンもそうだったのだが、この建物も元々はキリスト教の教会だった。ルイ9世の遺体を安置するために作られたのがそもそものきっかけで、1706年に完成した。
その建造物がフランス革命後、1840年にナポレオンの墓所として転用されることになったのである。
それにしても、この堂々たる立ち姿にはため息が出るほどだ。これほどの建築物がある意味ナポレオンの墓石なわけである。そう考えるとナポレオンという人物がいかに巨大な人物だったかを思い知らされる。

さすがはフランス王のために建てられた教会。中の空間も厳かで豪華に作られている。正面の祭壇はバチカン、サン・ピエトロ大聖堂のバルダッキーノにそっくりだ。バチカンのバルダッキーノが作られたのは1620年代。時代的にはこれを参考にしていたことは大いにありえることだろう。
そして上の写真で何人かが下を見ているのに気づかれたと思う。ここは地下から吹き抜けになっていて、ナポレオンの墓を上から見ることができる。

柱に立つ女神たちの像に囲まれ、ナポレオンはこのドームの中心で眠っている。その棺はなめらかな色大理石で形どられ、静かな威圧感を感じさせる。

私も地下に降りて行こう。
やはり正面からナポレオンにお参りしたい。

これがあのナポレオンの棺か・・・。恐ろしいほどにシンプル。だが、そこにこそ彼の魅力や個性が感じられるようにも思える。ごたごたした空理空論に時を過ごさず、明晰な頭脳でずばずば決断し、自ら先陣に立って武勲を上げたカリスマ。そのナポレオンらしさがこの無骨な棺からも感じられはしないだろうか。この棺を考案した人物のセンスのよさに驚く。
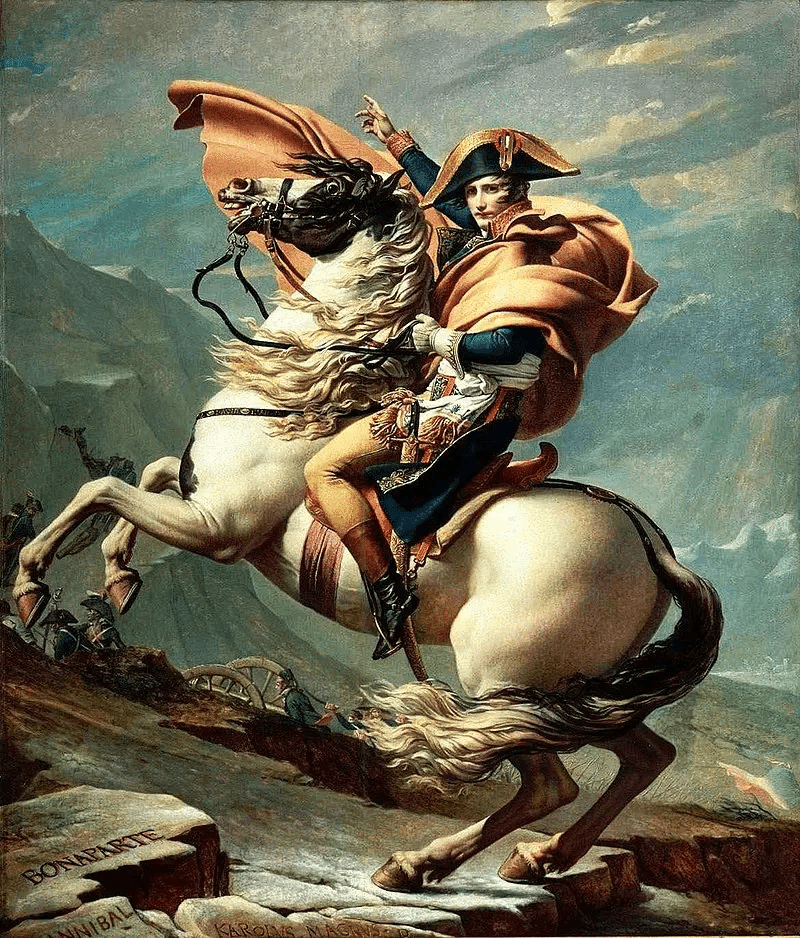
ナポレオンはヨーロッパの政治経済、軍事、国際情勢にとてつもない影響を与えたが、その影響は文学にも及んでいる。
トルストイの『戦争と平和』しかり、バルザックの『ゴリオ爺さん』しかり、ユゴーの『レ・ミゼラブル』しかり、そして何と言ってもドストエフスキーの『罪と罰』だ。
主人公ラスコーリニコフは人間を世界の大多数を占める凡人と極々少数の非凡人に分け、ナポレオンのような歴史を変えるほどの非凡人はたとえ人を殺そうとも何をしても許されるという思想を生み出す。つまり非凡人=天才には善悪、罪と罰は存在しないという思想だ。
彼の殺人はこうした思想が原因の一つとなって行われたのだ。彼は次のように言う。
ああいう人間はできがちがうんだ。いっさいを許される支配者というやつは、ツーロンを焼きはらったり、パリで大虐殺をしたり、エジプトに大軍を置き忘れたり、モスクワ遠征で五十万の人々を浪費、、したり、ヴィルナ(訳注現在リトアニア共和国の首都)でしゃれをとばしてごまかしたり、やることがちがうんだ。それで、死ねば、銅像をたてられる、―つまり、すべてが許されているのだ。いやいや、ああいう人間の身体は、きっと、肉じゃなくて、ブロンズでできているのだ!
本文でさらっと出てくるこの言葉は流してしまいがちだが、ナポレオンが歴史上行ったこれらの出来事を知れば、よりラスコーリニコフの言わんとしているところが見えて来るのではないだろうか。このことについては以下の記事でもお話ししているのでぜひご覧になって頂ければ幸いである。
そしてナポレオンは単にナポレオン・ボナパルト一人にとどまらない。
彼の影響はその死後もフランスで根強く生き続け、1852年からは彼の甥ナポレオン三世がフランス第二帝政を始めることになる。
ドストエフスキーが訪れたパリは、まさにこのナポレオン三世のフランス第二帝政真っ盛りの時期だった。あらゆるものが近代化し、産業や資本主義システムが驚くべき速度で発展していった時代である。シベリア流刑から帰ってきたばかりのドストエフスキーにとってはまさに驚天動地の世界だっただろう。
ちなみに「松村昌家『幕末維新使節団のイギリス往還記―ヴィクトリアン・インパクト』幕末明治の日本人が見たイギリスとは!」の記事でもお話ししたが、ドストエフスキーがパリを訪れた1862年の5年後、あの渋沢栄一がパリを訪れている。ドストエフスキーが見たパリを渋沢栄一も見ていたと思うと私は胸が熱くなる。
そのような大変革の時代がナポレオン第二帝政のパリであり、その時代を余すことなく描き出したのが何を隠そう、エミール・ゾラなのだ。
私はドストエフスキーを学んだ縁からエミール・ゾラを知ることになった。もしドストエフスキーを学んでいなかったらゾラに出会うこともなかっただろう。
エミール・ゾラはフランス第二帝政のあらゆる社会や人々を描き出す。
この時代は私達日本人にも全く他人事ではない。現代人たる私たちのライフスタイルの源流がここにあるのだ。私達の生活がどのような仕組みで成り立っているのかを学ぶのにゾラほど適した人物はいない。彼の著作は一作一作が驚異の分析に満ち溢れている。
ドストエフスキー自身はゾラのことをあまり好いてはいなかったが、どうしても気になる存在ではあったようだ。1876年のドイツ、バートエムスでの療養中にも彼はゾラを読んでいるし、『カラマーゾフの兄弟』に何度も出てくる「ベルナール」という言葉はまさにゾラの文学スタイルに直結するものである。
ゾラについてお話しするとどんどん長くなってしまうので詳しくはこれまで当ブログで紹介してきた記事を読んで頂ければと思う。
これまで述べてきたようにナポレオンはフランスだけでなく、世界全体に大きな影響を与えた。
彼のことを学べば学ぶほど彼の巨大さを感じることになる。ドストエフスキーを学ぶまでは名前しか知らない存在だったが、今やどうだろう。この人物の天才、カリスマにはひれ伏さざるを得ない。
ただ単に戦争で勝ちまくった将軍というだけでは説明のつかない奥深さがこの人物にはある。
フランスが生んだ巨大な人物、ナポレオンはドストエフスキーや文学を学ぶ上では絶対に避けられない人物であることを私は今や感じている。
そしてこのナポレオンを考える上で非常に重要な書物が1941年にオクターヴ・オブリによって編著された『ナポレオン言行録』という作品だ。
この作品を読んでいて印象に残ったのはやはりナポレオンの言葉の強さだった。ナポレオンといえば軍人というイメージが強いかもしれないが、驚くべきことに圧倒的な文才も兼ね備えていた。
ナポレオンの伝記では必ずと言ってもいいほど若きナポレオンの猛烈な読書ぶりが紹介される。
ナポレオンは内気で、クラスの人気者というタイプではなかった。そうした性格や彼の置かれた境遇からも彼は本の世界にのめり込む。
そして後に皇帝となって世界を席巻するようになってからもその読書人ぶりは変わらなかった。
もちろん、ナポレオンは戦場でも武勇を見せ、兵士たちを鼓舞した。だがそのカリスマもやはり彼の思想や言葉があったからこそなのである。背中を見せるだけではどうしても限界がある。背中を直接見せることができる人数には当然ながら物理的に限界があるのだ。
それでもなおナポレオンがカリスマになれたのは彼の言葉が人々の口や紙媒体を通して一斉に広まっていったからだった。ここに言葉の力の偉大さがある。
天才とはおのが世紀を照らすために燃えるべく運命づけられた流星である。
平凡人が規則の枠内でしか動けないというのはそれでよろしい。有能の士はどんな足枷をはめられていようとも飛躍する。
革命の中には避けがたい革命がある。それは火山の物理的な噴火のように、精神的な噴火である。火山の噴火を起こす化学結合が完成すると火山が爆発するように、精神的な機が熟する革命が勃発するのである。革命を予防するには、思想の動きを監視しなければならない。
それにしても、私の生涯は、何という小説(ロマン)であろう!
これらはナポレオン語録の一部だが、この本は手紙を中心に編まれているのでそれらではもっと直にナポレオンの声を聴くことができる。
兵士たちの心を震わせた手紙や愛するジョゼフィーヌへの恋文であったりと、内容は多岐にわたっている。こうした言葉を読めるこの本は非常にありがたいものがある。
そしてこの本を読んでいて私が思ったのはなぜ名だたる文豪たちがナポレオンに憧れたのかということだった。
彼に憧れた最たる例がバルザックだが、スタンダールもユゴーもまさにそうである。上でも述べたがトルストイやドストエフスキーも強烈な影響を受けている。
なぜ文豪たちはナポレオンに影響を受けたのか。
この本を読んでいて、私は「ナポレオンが若い頃ひたすら本に没頭する文学青年だったからかもしれない」と思ってしまった。
ナポレオンは学生時代はどちらかというと冴えないタイプの学生だった。そして本の世界に浸り、ひたすら読書の日々を過ごすという内向的な青年だった。そんな若者が自分の才覚で立身出世しついには皇帝になった。しかもその原動力は圧倒的な読書であり、言葉の力だったというのである。
当時の文学青年たちにとってこんなに夢のある話はないだろう!
ナポレオンがマッチョな大男で、筋肉を頼りに武勇を重ねたのであるならばきっと彼らはナポレオンに憧れることはなかったのではいか。
ひ弱な文学青年が文学、言葉の力と共に成り上がったことに意味があるのではないだろうか。
もちろん、ナポレオンの軍事や統治の才能も大きな要因の一つだろう。だがそこに読書家ナポレオンという側面があったからこそのナポレオン人気なのではないだろうか。
思えば歴史に名を残すリーダーや偉大な発明家たちもその多くが猛烈な読書人として知られている。
やはり読書を通して学べることは大きい。
よくよく考えてみればそうでないだろうか。何十年に1人、いや、何百年に1人の天才の言葉を本では聴くことができるのだ。しかも本のいいところは著者と一対一で自分のペースで向き合うことができる点にある。
歴史に名を残すほどの偉人と面と向かって語り合うことができるなんて、なんと贅沢なことか・・・!
本というと、ただ文字を読むだけのように思われてしまうかもしれないが、言葉とは「その人そのもの」だ。
言葉を読んでいくということは「その人自身を知っていくこと」に他ならない。
歴史に残る偉人の言葉を通して、私たちはその人と出会うことができる。
そういう読書になっていくとこんなに貴重なレッスンはない。もしナポレオンがマンツーマンで話を語ってくれたならこんなありがたい講義はないだろう。
読書に本気でぶつかっていくとそれはもはや著者との真剣勝負、一騎討ちになっていく。著者の言葉に対して自分はどう思うのか、そしてそれに対して著者はどんな反論を用意しているだろうか。本を読んでいると頭がフル回転するのはこうしたガチンコの戦いがあるからだ。
もちろん、本にも様々なものがあり、楽しく読める本もたくさんある。そういう本はこの話とは別なジャンルなのでご容赦願いたいのだが、古典や名著と呼ばれるものの真価はこうした真剣勝負に耐え得る点にあるのではないかと私は思うのである。
ナポレオンが鬼のような読書家であったこと。そしてそこから多くのことを学び、人々の心を動かし皇帝にまでなったということ。
それを後の文豪たちはしっかり見ているのではないだろうか。文学の力、言葉の力を知っている彼らだからこそ、文学青年だったナポレオンから目を離すことができない。だからこそ憧れてしまう。
そんなことをこの本を読んで感じたのであった。
もちろん、彼ら文豪がナポレオンに憧れた理由はそれこそ千差万別、複雑なものがあるだろう。だがナポレオンが文学青年だったという側面も少なからず影響を与えていたのではないかと私は思ったのである。

フランス文学やロシア文学だけでなく、ヨーロッパの歴史を考える上でもナポレオンはあまりに巨大な存在だ。
アンヴァリッドで墓参りすることができたのは私にとって忘れられぬ経験となった。
今回の記事は以前当ブログで公開した以下の記事を再構成したものになります。
関連記事
