
行きそびれていた街を歩く
歌舞伎町で忘年会をすることに。
せっかくなので、あちこち寄り道していこうと考えました。
今回は、行きそびれていた街を歩く二泊三日の旅です。
【常磐線で南下】


【水戸を歩く】
江戸期には度々歴史を賑わせた水戸。
南下のルート上にあり、初めて下車しました。


ペリリューの征服は、ひどい苦戦の物語りである。(中略)
日本軍をペリリューから一掃することはいっこうにはかどらず、実に次の年の二月まで高価な作戦を続けなければならなかった。





【谷根千(やねせん)を歩く】
翌日は、谷中・根津・千駄木の下町エリアを歩く。
学生時代に行きそびれていた東大の「三四郎池」が目的地です。





【本郷を歩く】



ふと眼を上げると、左手の岡の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、池の向う側が高い崖の木立で、その後が派手な赤煉瓦のゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日が、凡ての向うから横に光を透してくる。女はこの夕日に向いて立っていた。(中略)
二人の女は三四郎の前を通り過ぎる。若い方が今まで嗅いでいた白い花を三四郎の前へ落としていった。

【神保町を歩く】




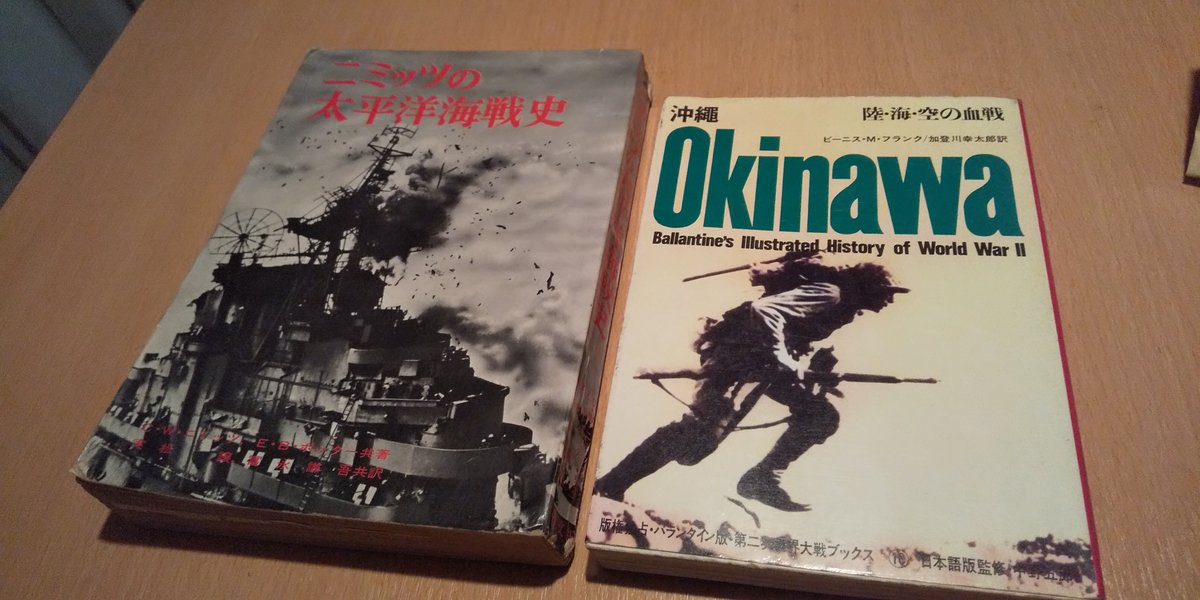
【歌舞伎町】

【館林へ】









東北地方はとっくに冬ですが、関東はまだ秋でした。
年々秋を好きになりつつある私にとって、再び秋を体感できたのはとても嬉しいことです。
来年あらためて「日本列島 秋の旅」を計画したいと思います。
【追伸】
今回うまかったもの。

ではまた…。
