
怒り・悲しみ・疑問 誰もが“声”を発信できる場所へ 「みんなの国際ニュース」立ち上げの思い
「この戦争はどこかで止められなかったのか やり場のない怒りや悲しみが沸いてきます」
「このまま“第5次中東戦争”になってしまうのだろうかー」
「なぜアメリカはイスラエルの後ろ盾になっているのか、理由を詳しく知りたい」
これらの声は、BSで夜10時から放送している「国際報道2024」に視聴者の皆さんから届いたものです。
ご紹介した3つの声は中東情勢に関するものですが、「国際報道2024」では、ウクライナ情勢や、アメリカをはじめ世界で広がる「分断」など、混とんとする国際情勢をどのように見ていけばいいのか、皆さんの「声」をもとに深掘りする番組づくりを進めています。
スローガンは「みんなの声でつくる、みんなの国際ニュース」。
取り組みを始めて1年、このスローガン通りに、だんだんと番組が「みんなの国際ニュース」に近づいてきているのではないかと感じています。きょうは、いつも声を寄せて頂いている皆さんへのお礼も込めて、担当してきた私の思いを共有したいと思います。
きっかけは、「ガザ地区」の惨状を前に何もできないもどかしさ

改めましてこんにちは。
「国際報道2024」でデジタル展開を担当している野田淳平です。
「みんなの声」とは、番組が、視聴者の皆さんからアンケート形式で募集している国際情勢についてのご質問やご意見のことです。
企画を立ち上げたきっかけは、去年10月に始まったイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘でした。
当時、「国際報道」にデジタル担当として異動してきたばかりだった私は、日々の仕事に慣れないだけでなく、連日ガザ地区から送られてくる映像を見ることがとてもつらく、番組を制作しながらも現地の惨状を前に何もできないもどかしさを感じていました。
いま振り返れば私だけでなく、毎日原稿を読むキャスターや周りの制作スタッフも精神的にしんどかったのではないかと思います。
そうした中、衝突から1か月となる去年11月、番組を「90分拡大版」として放送することになり、私がディレクターとして番組を構成することになったのです。
ちょうどイスラエル軍がガザ地区への地上侵攻を始めるかという緊迫したタイミングでした。
このつらい状況に、視聴者の皆さんはどう向き合っているだろうか、番組として何を伝えていけば少しでも役に立てるのだろうか…、考えている中で出てきたアイデアが皆さんの「声」を集めて、番組内で共有していくということでした。

「人道危機を止められなければ、新たな紛争につながりかねない、世界の二極化が進むと思う」(30代)
「心が痛み、つらいです。けれどまずは、自分の子どもや家族と話し合ってみます」(50代)
「地上波にはない、BSならではの深い報道を期待します(40代)」(←中には私たちへのメッセージも…)
皆さんの声を集めてみると、いまの国際情勢を前につらい思いをしているのは自分たちだけではない。
世界で起きていることに対して、現状や背景をもっと理解したい、何か行動を起こしたい、など「国際ニュース」を専門に伝えている私たちの番組を“拠り所”にしてくれている視聴者が多くいるということに気付かされました。
皆さんから寄せられた「声」は、混とんとする世界を生きていく中で、私たち取材・制作者と視聴者をつなぐ役割を担ってくれたのです。
デジタル音痴の新任デスク デジタル時代の「新たなニュース番組」を考える

「野田さん、これってまさしく『エンゲージメント』の高まりですよ」。
「拡大版」の放送を終えた後の反省会で、こうささやいてくれたのは国際報道のキャスターの1人、栗原望アナウンサーです。
しかし、この「拡大版」と「エンゲージメント」(=コンテンツに対するユーザーの関心度などを示す指標)がどうつながっていくのか、すぐには具体的なイメージがわかず、「はて?」という状況でした。実は私、デジタル担当になるまで、X(旧ツイッター)をはじめとするSNSをほとんど使わない、いわば“デジタル音痴”の人間だったのです。
ここでちょっと固い話をすると…。
NHKは経営計画の中で「デジタル連動の新しいニューススタイルの開発(信頼)」を掲げています。
新任デスクとして「デジタル」の勉強を始めたばかりの私にとって、当時、この目標のもとで何に取り組んでいけばいいのか悩んでいました。
そうした中で、この「拡大版」で生まれた私たち制作者と視聴者の皆さんのつながり。
栗原アナとも議論を重ねる中で、「デジタル」を通じて皆さんの「声」を聴き、放送の中で共有していくことが「エンゲージメント」を高めることになると考え、この“つながり”を育てていこうと動き出しました。
そして生まれたスローガンが、冒頭に紹介した「みんなの声でつくる、みんなの国際ニュース」というわけです。

以来、国際報道では、皆さんから寄せられた声をもとにスタジオに招いた国際政治の専門家や特派員と議論する「拡大版」を2か月に1本程度のペースで放送してきました。
今年(2024年)は「台湾総統選挙(1月)」「ウクライナ侵攻から2年(2月)」「ガザ衝突から半年(4月)」「欧州議会選挙(6月)」「アメリカ大統領選挙の行方は(7月)」「緊迫する中東情勢(10月)」などをテーマに放送。
これまでに寄せて頂いた声は、のべ2000件にのぼります。
そしてこのnoteを書いている現在(11月)は、8回目として「アメリカ大統領選挙後の世界」を深掘りするべく準備をしているところです。
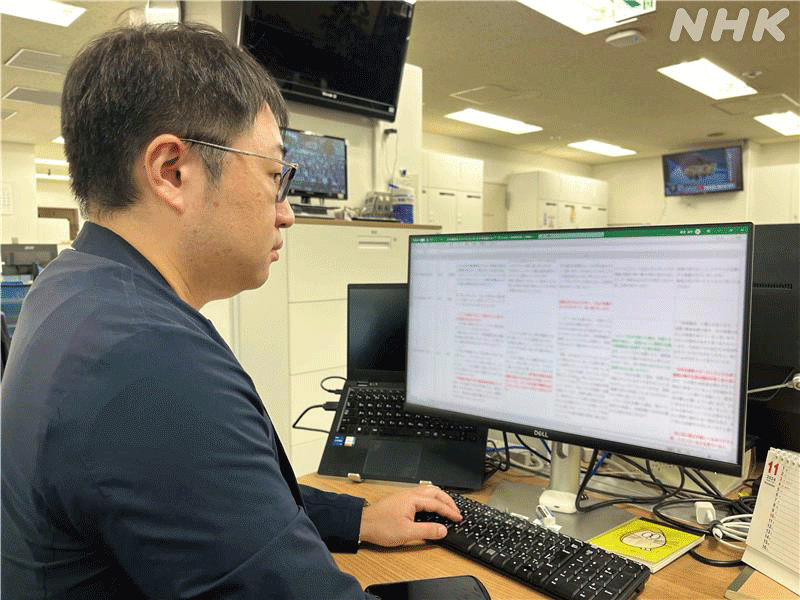
私たち国際報道のデジタル班は、毎日まず皆さんから送られてくる声を読み込むところから業務が始まります。
中には1つの設問に対して1000字を超える回答を下さる方も。
とにかく、どの声も「熱量がすごい!」というのが、この1年間の私の印象です。
いまの国際情勢に対して怒りをもっていたり、やり場のない悲しみを訴えたり、また「国際ニュース専門」を掲げるならもっと深掘りをしてほしいという番組に対しての叱咤激励も頂戴します。
皆さんの声を読むたび、これだけの「熱」をもって普段から番組を見てくださる方が多いのかと、本当に頭が下がる思いです。
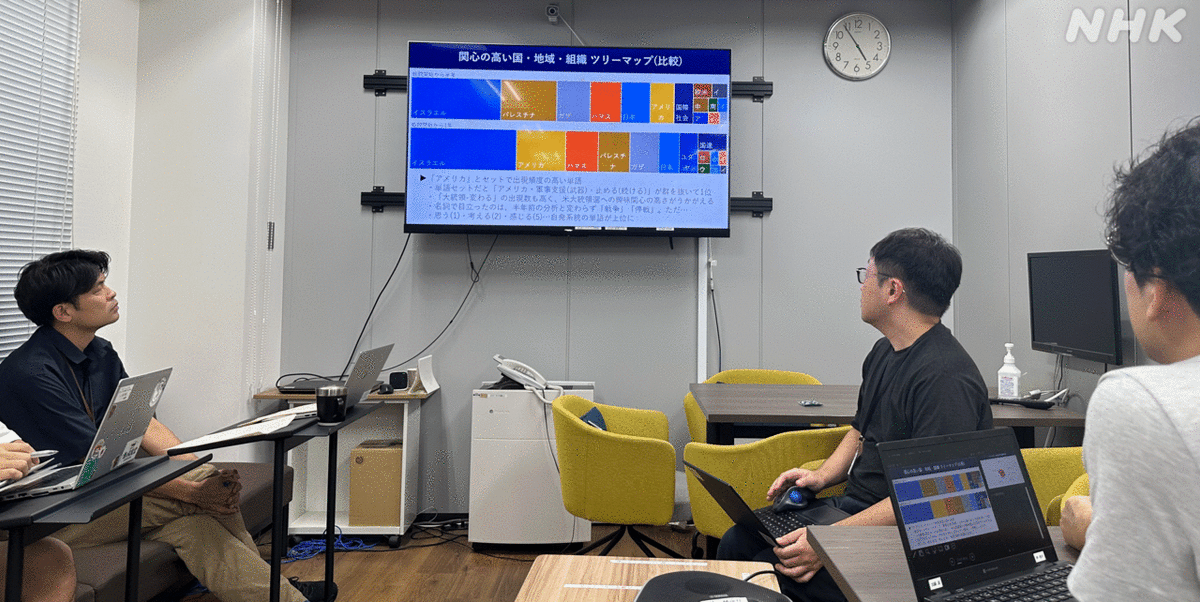
こうした声をどのように番組に反映させていくのか。
この写真は、10月7日放送の拡大版「緊迫する中東情勢」に向けた打合せのようすです。
寄せられた200あまりの声を分析して、視聴者の皆さんはどのような現場を取材してほしいと考えているのか、スタジオではどのようなテーマで議論を進め、専門家に質問するのかなど、番組の構成について議論をしています。
このときは、戦闘開始から1年がたった「ガザ地区の現状」に思いを寄せる声が多かったことから、現地でNHKの報道を担うパレスチナ人カメラマンに視聴者の声に答えてもらうVTRを制作したほか、イスラエルの後ろ盾となる「アメリカ」についての疑問が多く寄せられたことを受けてこの点を深掘りすることにし、油井キャスターはワシントンでアメリカ政治とユダヤ系ロビー団体の関係について取材して現地から伝えました。
「みんなの声でつくる、みんなの国際ニュース」をスローガンに掲げる背景には、私たち制作者が伝えたい内容だけではなく、皆さんの関心に沿った議論になるように番組をつくっていきたいという思いがあるのです。
「みんなの声」に後押しされ、コンテンツは増えていく

「国際報道」の居室ではいま、サイネージ画面で皆さんから寄せられた「声」を掲示して、キャスターから制作スタッフまで全員が常に「声」に目が届くようにしています。
当初は、2か月に1回程度放送する「拡大版」の中でのみ「声」を紹介していましたが、皆さんの「熱量」に後押しされるようにコンテンツも拡充してきました。
1つは、海外29の総支局で取材している特派員に皆さんの「声」を次々とぶつける、いわば「ポッドキャスト的なテレビの企画」です。
NHKは、国内メディア随一の海外取材体制があります。
日々現地で取材を続けるからこそ感じる温度感や、普段のニュースからは伝わりきらないディテールを知りたいという声を多くいただいたことから企画が実現しました。
実際に「声」に答えた特派員は「取材したディテールを、いかにかみ砕いてわかりやすく伝えることが大事か、再認識するようになった(ベルリン支局長)」、「普段のニュースでは『戦況』や『政治家・指導者の発言』を伝えることが多いが、視聴者は『一般市民の考え』ももっと知りたいのだと感じた(エルサレム支局長)」などと、話しています。

また、この秋からは、国際報道の通常放送でも「声」を紹介するようになりました。
例えば、ガザ地区やレバノンで続く戦闘のニュースを伝えたあと、スタジオでキャスターが、皆さんが抱く疑問や感情を読み上げ、番組内で共有していくという取り組みです。

目指すは、SNSとも違う「視聴者が“安心できる”プラットフォーム」
この1年、「声」を通じて視聴者の皆さんとのつながり=「エンゲージメント」が確実に高まっていると感じていますが、さらに「公共メディア」だから果たせる役割があるのではないかと考えるようになりました。
それを認識させてくれた視聴者からの「声」を最後にご紹介させてください。

「現在はSNSを通して自分の意見を自由に述べることができますが、そこでは自分が思わぬ方向で炎上してしまう可能性もあり、安心して想いを発信することができません。
一方、このような番組ではそのような事がないので心配せず自分の考えを伝えることができます。相手に伝える事によって、考えをまとめ、またさらに考えを深めることができます。
今後もこのような視聴者の意見を基にしたコーナーを実施してほしいです」(20代 大学生)
この声は、ガザ地区での衝突から半年となることし4月に届きました。
ウクライナ情勢や中東情勢のように多くの市民が亡くなっている現状を前に“感情的”になるケースもあるかと思います。
また、現在のアメリカに象徴されるように「分断」も進む中で、SNS上では、国際ニュースをめぐっても、互いを非難し合ったり、レッテル貼りや炎上が起きたりしていると感じます。
この声を寄せてくれた大学生も、同じように感じているのかもしれません。

私たちが番組内でご紹介する「声」は、SNSのように互いの意見がダイレクトにぶつかり合うのでは無く、「公共メディア」という枠組みを通しているからこそ、皆さんが安心して「声」をあげられる=発信できる「プラットフォーム」として存在し得るのかもしれないと考えています。
「分断」を加速させるのではなく、さまざまな意見を「共有」していく「みんなのための言論空間」。
SNSとも違う、デジタル時代の「プラットフォーム」の1つのカタチに、私たちの番組がなれるのではないか…。
その可能性と責任を感じながら、日々皆さんの声と向き合っています。
最後になりますが、改めて、番組に「声」を寄せて頂いた視聴者の皆さんに感謝を申し上げるとともに、この記事で私たちの取り組みを知ったという方はぜひ一度、私たちに「声」を届けていただけたら嬉しいです。

野田淳平(のだ じゅんぺい)
2007年入局。沖縄放送局・大阪放送局などを経て、報道局 政経・国際番組部に所属。
ディレクターとして、報道番組やドキュメンタリー番組を制作してきたほか、現在は国際番組のデスクとして「国際報道2024」の制作やデジタル展開を担当している。

