
エンタメ業界の継続的な課題であるチケット不正転売、明るい未来に求められるものとは? 〜ビジネスプロデューサー、半田勝彦氏に聞く~
個人のデータを個人がコントロールする非中央集権型のweb3。本連載ではweb3がもたらす新たな可能性について、専門家の視点から考察していきます。第一弾はビジネスプロデューサーの半田勝彦氏。エンターテインメント業界にはびこるチケット不正転売問題、ファンマーケティングの進化をテーマに、新たな経済圏・経済活動の推進をサポートするweb3の可能性を探ります。
進むエンタメ業界のフラット化、一方でルール作りが重要に
――長くエンターテインメント業界に携わってきた半田さんから見て、昨今のエンタメの潮流をどのように捉えていますか。
半田 キーワードは“フラット化”です。私は若い頃に秋元康さんの事業会社でコンテンツビジネスを経験し、その後の博報堂DYメディアパートナーズでは東京ガールズコレクション(TGC)を運営するF1メディア(現W TOKYOの前身)を社内起業しました。その過程で目の当たりにしたのが、ブラックボックスがオープンになっていく時代の流れです。

ご存知のように秋元さんは劇場で直接会えるアイドル「AKB48」を誕生させ、手の届かなかった存在のアイドルを民主化しました。TGCのコンセプトもこれに近い。それまでファッションイベントはクローズドが常識で、ショーを開催しても会場を訪れるのはバイヤーやメディア関係者のみでした。その常識を覆し、チケットを購入すれば誰でも参加できるようにしたのがポイントです。それ以降、どんどんフラット化、オープン化が進んでいると実感しています。
――2010年代にはスマホが本格的に普及し、SNSは社会に不可欠なコミュニケーションツールになりました。テクノロジーの進化はエンタメやコンテンツにどう影響したと思いますか。
半田 フラット化に関しては、テクノロジーがきっかけとなって進展することが数多くありました。アプリやSNSを通じた顧客接点によって、新たなファン体験を提供できるようになったことはまさに好例です。
一方、テクノロジーだけでフラット化が進むわけではありません。そこには法規制や国の政策などが深く関わってきますから、ルール作りがとても重要です。
前職のドリームインキュベータ時代、私は電子チケットサービス「ticket board」を展開するボードウォークに取締役COOとして就任し、電子チケットビジネスに関わるようになりました。ドリームインキュベータは霞が関に本社を置くこともあって、行政とのパイプが強い特徴があります。
今回のテーマであるチケットの不正転売についても我々の問題意識を行政などに共有し、法律のもとでルールを作っていくべきだと主張してきました。2019年6月には文化庁がリードして「チケット不正転売禁止法」(正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)が施行。我々は法律制定に至るまでの業界のロビイング活動に積極的に関わらせていただき、制定されたルールに沿った対応をしてきた経緯があります。
それでもなくならない不正転売の現実と対策
――チケット不正転売禁止法の施行から5年が経過。一定の抑止力となってはいるものの、依然としてチケットの不正転売がはびこっています。
半田 それこそ「ダフ屋」行為と呼ばれる昔からある根深い問題ですから、一朝一夕には片付きません。電子チケット推進の目的の一つは不正転売の防止ですが、テクノロジーが進化するたびに裏に隠れるイタチごっこが続いており、業界が目指す透明化とは逆に進んでいる印象を受けます。
未だにこの問題が解決されないのは、“何としても好きなアーティストの公演を観たい”という強烈なモチベーションによって、あり得ない需給関係が成立してしまうからです。アーティストや音楽事業団体が公認するチケットのリセールサービスは定価トレードですから何の問題もない。でもマッチングサービスで1万円のチケットが10万円で売られていても買う人がいることも事実。結果的にファンに負担をかけているわけですから、アーティストや主催者は納得が行かないのは当然です。

――東京ガールズコレクション(TGC)でも深刻だそうですね。
半田 1枚1万円のチケットが5万円以上で売られることもあり、とくにランウェイ周辺の最優良席は高騰します。しかもイベントは長時間のため、自分が興味のないモデルやアーティストが出ている時間だけを切り売りして転売する行為が多発しています。SNSを使い、「16時〜18時まで譲ります」といったやり取りが現場で交わされるのです。
TGCは電子チケットを採用しているため、客同士はスマホごと交換します。数時間とはいえ自分のスマホを知らない人に預けるなど信じられないかもしれませんが、本当に行なわれています。もちろん、エリアごとにリストバンドをつけて区別し、スタッフが目視して確認するなど時間帯の転売ができないように対策を取っていますが、根絶までは至りません。
――解決に向けての対策はどんなものがあるでしょうか。
半田 業界全体の仕組みを整備したうえで、どのように行政を巻き込んでいくかが重要になってくるのではないでしょうか。我々もデジタル庁とともに、「TGC 2024 SPRING/SUMMER」(2024年3月2日開催)の一部チケットをマイナンバーカードと紐づけて本人確認を行ない、不正転売を防止する実証実験を実施しました。業界の足並みがなかなか揃わない現実もありますが、ロビイングを含めてルール作りを進めていけば業界も変わっていくと考えています。
それにアーティスト自身も意識が高い。例えば福山雅治さんはご自身のオフィシャルサイトで継続的に問題提起をされている一人です。当事者たちと連携しながら、いかにネットワークを構築していくのかも今後の重要なテーマです。

アーティストの発信で、世界が変わる
――やはりアーティスト本人の発信は大きな効果があるのでしょうか。
半田 それは間違いないと思います。アーティストが声を上げれば、ファンにも「不正に加担したくない」との気持ちが働くからです。福山雅治さんのほかにも宇多田ヒカルさんやMISIAさん、サザンオールスターズなど、チケット入手が困難な大御所ほど強い問題意識を持っているように感じます。
チケットを入手しやすくするための方法としてはファンクラブへの加入があります。まずはファンクラブ先行があり、そこでだめなら二次先行、三次先行と続き、一般販売までに何度も申し込みができるのが一般的です。
そのため、チケット不正転売を防ぐことでファンクラブの価値が上がりアーティスト側は会員へのメリット提供とともにビジネスとしてもうまく回ります。つまり、社会課題の解決とビジネスの価値向上の両輪をいかに上手く回していくかが鍵を握るのです。
――ファンとの結びつきを活かした事例はありますか。
半田 強固なファンを持つ矢沢永吉さんは、2018年にすべて電子チケットに切り替えました。当時のインタビューで「いずれそういう時代が来る。今やるべきだというのがYAZAWAの勘」と発言して話題を呼びましたが、矢沢さんのファンは年齢層が高いことでも知られています。ファンのスマホ普及率は決して高くなかったにもかかわらず、電子チケットにするとなった途端にスマホに乗り換えた人たちが多数いたと聞きます。電子チケットを表示できないなど入場口での混乱はごくわずかのようで、とてもスムーズに移行した好例と言えるのではないでしょうか。
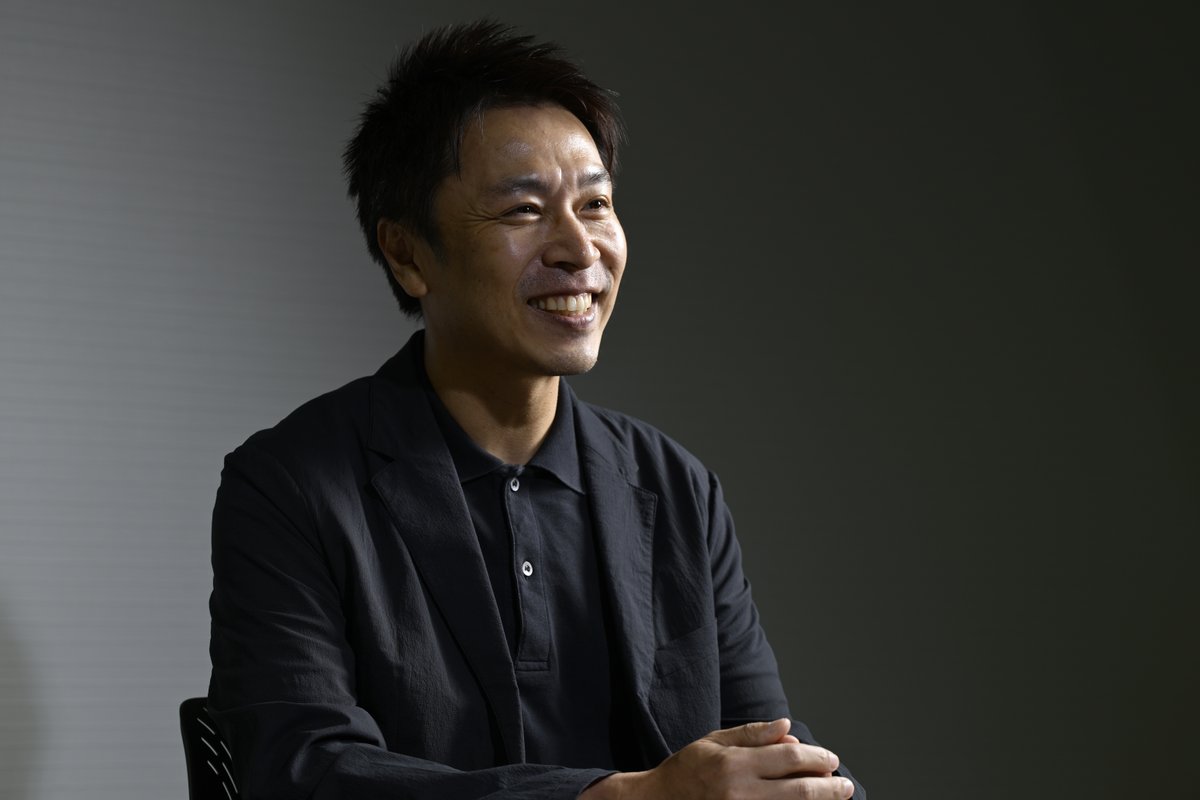
このように、これからはファンが自発的に行動するケースがどんどん出てくると考えています。前回のTGCでは、チケットの不正転売を抑止するための「通報QR」という取り組みがありました。時間帯で切り売りしている人を見つけた場合、ファンが会場に貼られたQRコードを読み込んで不正をすぐに通報できるシステムです。そして通報を受けたスタッフが該当席に行って注意する。実際に数件の通報があったと聞いています。
そもそもファン同士は、濃密な情報を頻繁にやり取りしながらコミュニティを形成しています。その情報の重要事項として不正転売が位置づけられ、アーティストの思いをコミュニティが牽引するようになれば、それこそフラット化された構造になってより健全になっていくはずです。
web3とファンマーケティングの可能性
――web3は真正性を担保するテクノロジーの1つとして期待されています。不正転売とも関わってくると思いますが、その可能性についてどう思いますか。
半田 問題意識の高いアーティストが試験的に導入し、成功事例が積み重なれば、普及するスピードが早まる可能性は高いと見ています。実装に関しても、まずはボリュームゾーンの世代で一般化することでUI/UXが洗練され、あまり馴染みのないシニア世代でも使いやすくなるはずです。サービス側のサプライチェーン、あるいはコスト面などさまざまな課題もありますが、新たなテクノロジーの導入に障壁はつきものですから、徐々に最適化されていくでしょう。
そうした新技術を組み合わせながら、オーガニックにファンコミュニティが機能する流れが生まれるのではないかと予想しています。今後のファンマーケティングの文脈では、自然発生的なコミュニティを適切に運営していくためのプロデュース力が大事になってきます。企業経営においても、社員が自主的に発案して活動する体制を後押しするサーバントリーダーシップ時代にシフトしています。そのニュアンスに近いかもしれません。
――ファンマーケティングも進化しているのですね。
半田 はい。芸能プロダクションやアーティスト事務所が、「ファンとの直接的なつながり」を意識しているのは確かです。ファンクラブを通じた直接的な交流が可能になり、アパレルで先行しているD2C化(Direct to Consumer(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)の略)が加速しているのがその証です。web3のような画期的な技術と仕組みによって不正転売ができなくなれば、ファンは安心して適正価格で電子チケットを売買でき、観たい公演を観ることができるようになる。これにより、さらにアーティストに対するファンのロイヤリティが高まっていきます。

ファンマーケティングにおける究極のUI/UXは、どのステークホルダーにも負担がかからないことです。入場時の本人確認作業は来場者、運営側の両者に負担がかかっているのが現状です。例えば「顔パス」チケットなどを導入することで、本人確認と顔情報の事前登録により通過するだけで済んでしまうシステムがあれば誰にも負担がかかりません。さらに、決済機能との連携による「顔パス」決済でグッズ購入ができたり、パーソナルにターゲッティングされた情報がデジタルサイネージに配信されたり、1つのテクノロジーでUI/UXを向上させる様々な可能性があると思います。不正転売の防止を機に、体験そのものが変わるテクノロジーの浸透を期待しています。
<取材を終えて>
アーティストの発信で、世界が変わる。半田さんのインタビューの中で印象に残った言葉です。業界構造が変わっていく中でも大切にすべき不変の要素が見えてきます。この言葉がチケット不正転売の現状とこれからの対策を象徴しています。web3の新たな技術はどうやってその課題解決に貢献できるのか。自問しながら、その未来の先にアーティストとファン、関係する会社それぞれが望む世界を実現する。これからの動き方に対する示唆に富んだ取材でした。

インタビュイー:ビジネスプロデューサー 半田 勝彦 氏
中央大学理工学部卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科エグゼクティブMBA(経営学修士)。博報堂および博報堂DYメディアパートナーズを経て、2017年にドリームインキュベータに入社。インキュベーション担当執行役員として、主に事業投資先の発掘、投資実行、投資先企業などへのハンズオン支援を行なってきた。これまでに、株式会社ボードウォーク 取締役COO(~22年3月)、ピークス 株式会社代表取締役(~22年12月)、株式会社ADDIX 取締役(~23年4月)を経験。2024年4月に独立起業し株式会社知開を設立、代表取締役に就任。
企画・制作・編集:IISEソートリーダシップweb3チーム(塚原督、鈴木章太郎、石垣亜純、名和達彦)
関連リンク
NEC
https://jpn.nec.com/web3/index.html
MetaStep(メタステップ)
