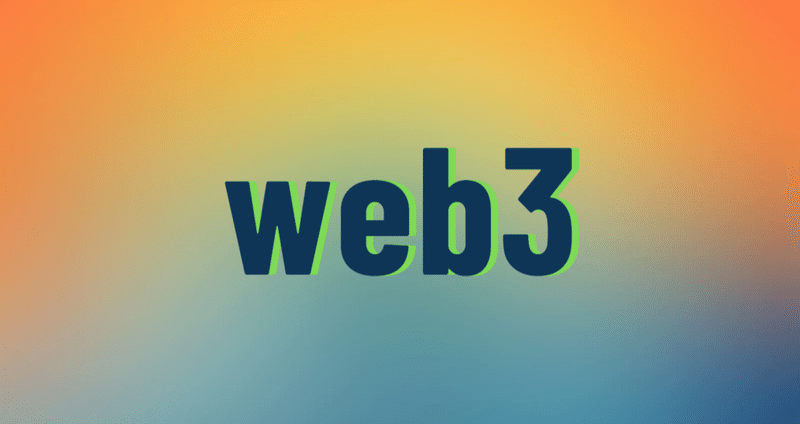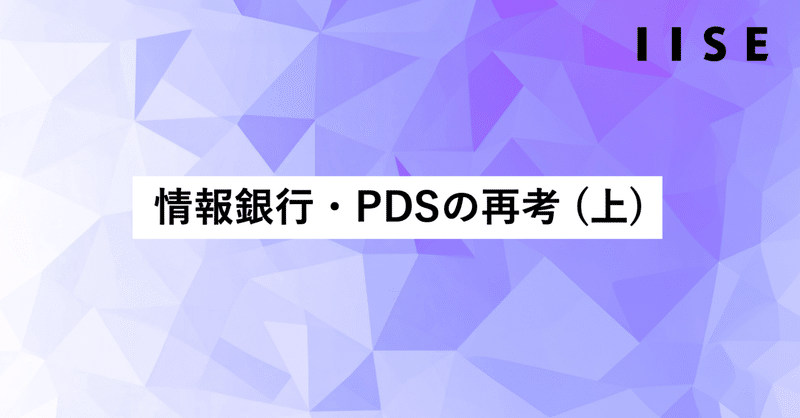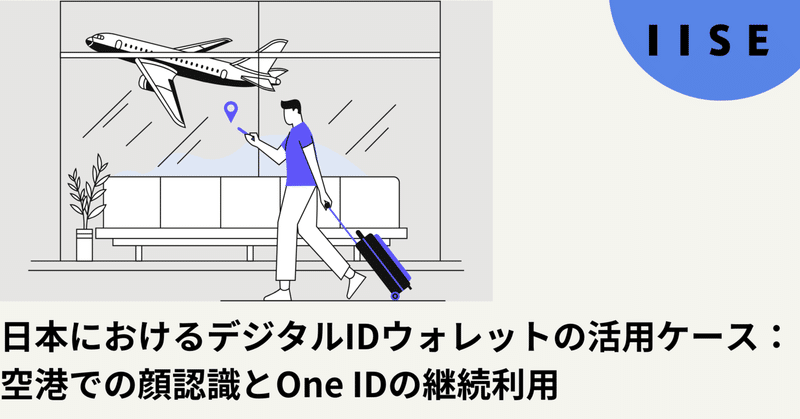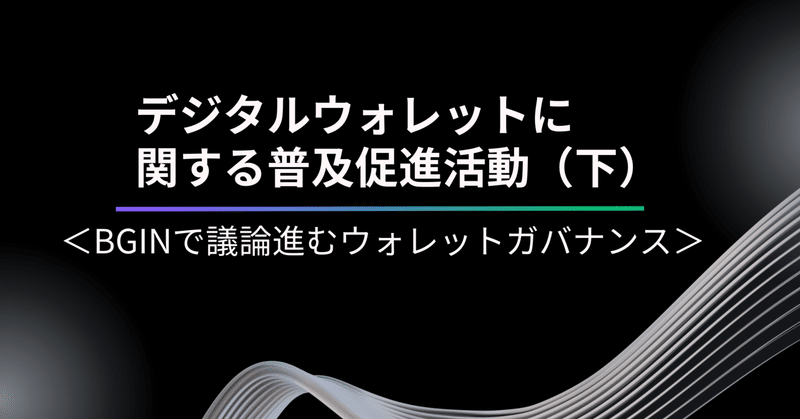記事一覧

ファンとアーティストが特別な“つながり”を持てる未来――。~EX(エンターテインメント・トランスフォーメーション)とは~
SNSやライブストリーミング環境の普及、イベント等の参加・体験の価値化などにより、「推し活」というファン行動のもと、アーティストとファンは直接つながる時代になってきました。また、NFT (Non-Fungible Token、非代替性トークン)やweb3を利用したデジタルグッズやファントークン、スペシャルイベントの参加権の購入などを通じて、ファンはアーティストの活動を直接支援できます。透明性と信頼性を保ちながら、アーティストとファンが特別な“つながり”を持てる未来はもうすぐそ

マイナンバーカードの本人確認が不正転売防止に寄与、デジタル技術が“健全な場”を提供する 〜デジタル庁 国民向けサービスグループ、鳥山高典氏に聞く〜
個人のデータを個人がコントロールする非中央集権型のweb3。ソートリーダーシップ(Thought Leadership)活動を推進するIISEでは、web3がもたらす新たな可能性について、各専門家へのインタビューを通じて多角的に考察しています。第4弾はデジタル庁 国民向けサービスグループで参事官補佐を務める鳥山高典氏が登場。鳥山氏はマイナンバーカードの利活用を推進する立場で、2024年春には東京ガールズコレクションにおけるチケット不正転売の実証実験にも携わったキーパーソンです

「推し」はいかにして生まれたか? “内から外へ”と行動変容した歴史とファンマーケティングの関係 〜エンタメ社会学者、中山淳雄氏に聞く〜
個人のデータを個人がコントロールする非中央集権型のweb3。本連載ではweb3がもたらす新たな可能性について、専門家の視点から考察していきます。第三弾はエンタメ社会学者の中山淳雄氏が登場。推しが誕生した背景、消費活動における女性のパワー、Z世代のコンテンツ受容行動など、エンタメにおけるファンマーケティングの変遷を鋭い洞察力で分析していただきました。 自分たちでカルチャーを作り上げる風潮が推しの勃興につながった ――まずは日本の「ファンマーケティング」における変遷について教え

ステークホルダーとの強固な結びつきが基本、未来を見据えて“一歩先”のテクノロジーを活用する 〜TGC実行委員会 チーフプロデューサー、池田友紀子氏に聞く〜
個人のデータを個人がコントロールする非中央集権型のweb3。本連載ではweb3がもたらす新たな可能性について、専門家の視点から考察していきます。第二弾は東京ガールズコレクション(以下、TGC)実行委員会 チーフプロデューサーを務める池田友紀子氏。“プラットフォーム”として多くのステークホルダーとともに進化してきたTGCの歴史を踏まえ、テクノロジーとの関係やデジタル庁をはじめとする各官公庁との取り組みなどについて話を伺いました。 TGCは時代に伴ってアップデートするプラットフ

エンタメ業界の継続的な課題であるチケット不正転売、明るい未来に求められるものとは? 〜ビジネスプロデューサー、半田勝彦氏に聞く~
個人のデータを個人がコントロールする非中央集権型のweb3。本連載ではweb3がもたらす新たな可能性について、専門家の視点から考察していきます。第一弾はビジネスプロデューサーの半田勝彦氏。エンターテインメント業界にはびこるチケット不正転売問題、ファンマーケティングの進化をテーマに、新たな経済圏・経済活動の推進をサポートするweb3の可能性を探ります。 進むエンタメ業界のフラット化、一方でルール作りが重要に ――長くエンターテインメント業界に携わってきた半田さんから見て、昨今