
ITパスポートに独学で挑戦!勉強方法や難易度についてレポート(2024年6月受験)
こんにちは。
大阪担当の蒲郡みかです。
私は名古屋の出版社で編集者人生をスタートし、名古屋・福岡・大阪で編集者&ライターとして活動。そして、現在はIT企業所属のライターとして、大阪に住みながら活動しています。
そんな私ですが、先日、人生初の国家試験にチャレンジしてきました。
それは「ITパスポート」の試験。
国家試験というと難しそうですが、ITパスポートは簡単に取得できるともいわれている資格…。
実際どうだったのか、今回はITパスポート受験のお話をしたいと思います。
なぜITパスポートの資格試験にチャレンジしたのか―。
受験の理由や、勉強方法、試験本番のこと、結果や感想を書き綴ります。
よろしければ、最後までお付き合いくださいね。
※当記事につきまして、所属企業・グループとは関係なく、あくまでもライター個人の主観的な意見・感想です。ご了承ください。
ITパスポートを受験した理由
「なぜライターがITパスポートを?」と思われるかもしれませんが、それは「会社で取得を推奨されていたから」というのが大きな理由です。
当社はIT企業なので、ITの知識を求められるのは当然といえば当然なのですが、会社として社員のITリテラシーや情報セキュリティリテラシーの向上を目標に掲げているので、取得が推奨されています!
これまでなかなか取得に向けてのアクションを起こせずにいたのですが、他部署でも多くの人が取得していたり、入社前に取得している人がいたり…と、社内に取得している方がたくさんいるので、これは私も取得しておかなくては! と思うようになりました。
そして、MBOの個人目標に設定したことも、取得に向けての原動力になりました。
「MBOって何?」と思われるかもしれませんが、MBO(Management by Objectives)は企業における目標管理制度のことで、個人やグルーブごとに目標を設定し、達成度合いで評価が決まる制度です。
私が在籍する会社では半年ごとに部署やグループの目標、個人の目標を設定しています。
個人目標では資格取得やスキルアップなどの目標を設定することになっているのです。
少し硬いお話になってしまいましたが、MBOの目標に設定したことで「今期中にITパスポートを取得します!」と、会社に宣言したということ。
そして、取得できないと自分の評価にもダイレクトに影響が…。
評価を下げないためには、期間中の取得は必須! ということですね。
これくらいしないと、仕事や日常の忙しさを理由に勉強を後回しにしてしまいそうなので、
今回は勉強せざるを得ない状況に自分を追い込むことにしました。
受験勉強は、多くの人が実践している方法で!
ITパスポートは本当にたくさんの方が受験されていて、検索すると山のように合格のための勉強法が出てきます!
参考にすべくチェックしてみると、だいたい皆さん同じアドバイスをされています。
それは…
・ITパスポートのテキストを一通り読む
・過去問をひたすら解く(アプリを活用)
この2つ!
非常にシンプルです。
テキストは「いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集」を挙げている方が多かったので、私も同じテキストを購入。
最初からじっくり読み込むというよりは、まず軽く読んでみる!
という取り組み方を推奨されている方も多かったので、同じように進めていくことに。
過去問はスマホで手軽に問題にチャレンジできる「ITパスポート過去問道場」を利用していくことにしました。
毎日少しずつ×約45日間の勉強
合格された方の学習期間の設定で、多く目にしたのが1カ月という期間。
一日どれくらいの学習時間を持てるかで変わってくるとは思いますが、少し余裕を持って1カ月半くらい先の受験日を設定することにしました。
購入した「いちばんやさしい ITパスポート」のテキストは、561ページもあって辞書のようなボリューム。
全15章もあり「試験までに、読み終えられるの?」と、思うほどの存在感ですが、少しずつでも読み進めることを日課にしました。
資格勉強は1日あたり10分~90分くらい、一人になれる時間に集中して勉強。
全く何もできない日もありましたが、1カ月弱でテキストを一通り読み終えることができました。
テキストと平行して、スマホのアプリで過去問にもチャレンジ。
外出先や移動中など、テキストを開けない状況ではスマホで問題を解くようにしました。
ITパスポートは非IT系の社会人も親しみやすい!?
意外だったのは、試験範囲にITとは直接関係ない内容が数多く含まれているということ。
なかでも「ストラテジ系」という分野は、経営全般に関する内容で、企業と法務、経営戦略など、ITとは直接関係のないものです。
出てくる用語は、教育訓練を意味するOJT、売上高、当期純利益、知的財産権など…、社会人が理解しやすい内容が多いです!
ITパスポートは高校生や大学生もチャレンジしている資格ですが、ストラテジの分野は社会人に有利な内容だと感じました。
テクノロジ系の分野は数学的な要素やプログラミングが登場
文系出身の私が最も苦手意識を持っていたのが、テクノロジ系の分野でした。
テクノロジ系は、ネットワーク、セキュリティ、データベースなどIT技術に関する基本的な考え方、特徴などの問題が出題されます。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/reference/faq.html
この分野は計算やプログラミングが入ってくるので「難しそう、解けるの…?」と不安でいっぱい。
でも、テキストを読んでみると、理解&暗記で乗り越えられる内容もあることが分かりました。
知らなかった言葉もたくさんありましたが、一つずつ理解していけば、そんなに難しくない印象です。
インターネットやデータなど、日常生活や仕事で触れる内容も含まれているので「何のことかさっぱり分からない」ということはないと思います。
もちろん、数学的な内容も出てくるのですが、中学~高校の数学レベルで対応できるかな…という感じです。
プログラミングについては、テキストで分かりやすく解説されているので、何となく分ったような気持ちになる(しっかり理解できている状態ではない…)という手応えでした。
過去問アプリの活用について
私はテキスト読了前から、過去問アプリを併用するスタイルで学習を進めました。
テキスト読了前なので、知らない内容も出てきますが、分からないなりに考えて解いてみると「どうしてそうなるんだろう?」と、頭に残るので、テキストを読んだときの理解が深まる気がしました。
また、自分の苦手な分野や理解できていない内容が浮き彫りになるので、試験対策にも便利です。
注意点は、何度も繰り返し解いていると、同じ問題が出てきたときに、頭で考えずに答えを選んでしまうということ。
答えを覚えているだけなのに、理解しているような気になり、結局頭に入っていないので要注意です。
試験直前は計算問題対策&テキストを読み返し
試験まであと数日というタイミングで、過去問アプリを使って本番と同じように100問連続で解きました。
75%くらいの状態だったので、理解がしっかりできていない部分は、テキストを読み返すようにしました。
テキストには「この内容はよく出題されます!」というアドバイスも書かれているので、その部分は付箋を貼り、試験直前にも確認しやすい状態に。
そして、苦手意識の強い計算問題の分野は、アプリで計算問題の過去問だけに絞り込み、連続で解いて対策をすることに。
勉強時間はあまり確保できなかったので、トータル10~15問くらいしか解けませんでしたが、少しは計算問題に対しての耐性ができたように思います。
いよいよ試験当日! 試験開始までの過ごし方と流れ
私が試験会場に選んだのは、大阪の「天満橋駅前OMMビル試験会場」。
OMMビルは行ったことがある場所(分かりやすい)で、駅直結でビル内にカフェもあるという利便性もあって、この会場に決めました。
時間にゆとりを持ってOMMビルに到着し、開始時間までビル内のカフェで最後の確認をしながら、ゆったり過ごすことに。
OMMビル内には座って待てるスペースはほぼなかったので、ビル内で開場時間まで待つ場合はカフェ利用がおすすめです。
開場時間が近くなったら、試験会場のフロアへ。
入口にはITパスポートのロゴマークの紙が貼られていたので、迷うことなく会場の受け付けにたどり着くことができました。
受け付けでは、プリントアウトした受験票と身分証明書を提示します。
スタッフの方が受験票に座席番号を記入し、試験を行う部屋に案内されるまでの説明を受けます。
そして、試験の説明が書かれた書類(透明な下敷き状のファイルにはさんである)を渡され、座席番号と同じ番号のパイプ椅子に座って待つように案内されます。
試験開始15分前までに、ロッカーに荷物を入れ、座席番号の椅子に座って待つように案内されますが、それまではテキストを見たり、トイレに行ったりするのはOKでした。
ちなみに、OMMビルの4階女性トイレは、なぜか他のフロアのトイレよりもきれいでした!
リノベーションされているようで、モザイクタイルも貼られていて、清潔感がある空間なので、4階トイレの利用をおすすめします。
試験開始15分前になると、試験会場入室前のチェックが1人ずつ行われます。
身分証明書以外に持ち込みが許可されているのは、ハンカチ・目薬・マスクのみ。
ハンカチもマスクも裏表をスタッフの方に見せてから入室します。
チェックを終えると試験会場に入室。
全席、しっかりと左右にパーテーションがあり、隣の席が全く見えない状態になっていました。
椅子は回転式で、高さの調整ができるタイプ。
デスク上には、大きなモニターと、キーボードとマウス、スタッフの方を呼ぶためのブザーがセットされていました。
あとは、試験中に使用するシャープペンシル1本と、A4サイズのメモ用紙1枚も用意されています。
試験が始まるまでは、モニター画面に表示されている説明を見たり、文字サイズや色の調整をしたりして過ごします。
私は白い画面が眩しく感じたので、グレーの背景に変更し、文字サイズも見やすいサイズに調整しました。
試験開始までは、画面の時計を見ながらカウントダウン。
時間になったらスタートボタンを押して、試験開始です!
ITパスポート試験の本番で戸惑ったこと
いざ試験が始まると、気になること、戸惑ったことがありました。
こればかりは、気にせずに集中するしかないのですが、情報共有としてまとめておきたいと思います。
【環境について】
・モニターが大きい
私がいつも仕事で使っているのは、コンパクトなノートパソコン。
そのため、会場の大きなサイズのモニターに慣れず、文字サイズを調整したものの、画面の左上に表示されるので、読みにくく感じました。
・モニターの安定が悪い
モニターの安定も悪く、クリックするたびにぐらぐら画面が揺れるのも、気になりました。
揺れがなかなか収まらないので、左手で画面の揺れを抑えながら解いていました。
※あくまで私が試験を受けた会場に関する感想です。ご参考までに…。
【試験内容について】
・テキストには書かれていなかった内容に遭遇
テキストでは見たことのない用語や内容が含まれている問題がいくつかあり、「えっ…分からない。この内容テキストにあったかな…?」と、焦りました。
ITパスポート試験のサイトのシラバス(試験要項)をしっかり確認していなかったので、そこは良くなかった…と反省。
また、100問のうち8問は今後出題する問題を評価するための問題が含まれているそうなので「見たことのない問題が入っていて当たり前」と思っておいたほうがいいかもしれません。
総合評価は92問、分野別評価はストラテジ系32問、マネジメント系18問、テクノロジ系42問で行います。残りの8問は今後出題する問題を評価するために使われます。
・ここまで掘り下げてくる!? という問題に当たる
用語と意味だけ抑えておけば大丈夫だろう…と思っていたら、深い理解を求められる問題に遭遇。用語と意味だけでは太刀打ちできない問題に苦戦しました。
・内容が重複する問題が出てきて戸惑う
問題の形式が少し違うものの、同じことを問う問題が出てきてびっくり。「これは結局、同じ問題では…?」と心のなかでつぶやいてしまいました。これが簡単に解ける問題だったらよかったのですが、残念ながら自信のない問題で、2つともダメかも…と思うと、精神的なダメージも大きかったです。
※問題については、一人ひとり違う問題が出題されているという説もあるため(注意:公式な情報ではありません)、偶然そうなったのかもしれません。
・一筋縄ではいかない計算問題やプログラミング問題
過去問で少し対策はしていたものの、想像の上を行く、見慣れないタイプの問題に心が折れそうに…。
テキストは分かりやすく解説するために、やさしい問題を例題にしてくれていたのだな…と痛感。本番の試験は全くやさしくないと感じる問題で、最後の最後まで戦うことになりました。
私が解いた問題の詳細は書けないのですが、難易度の近さでいうと、「令和6年度分 ITパスポート試験」で公開されている次のような問題です。

【問題】 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/openinfo/pdf/questions/2024r06_ip_qs.pdf
【回答】 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/openinfo/pdf/questions/2024r06_ip_ans.pdf
試験時間120分は長い? 短い?
ITパスポートの試験時間は120分。
選択式の100問を120分で解けばOKなので、計算問題や悩んで手が止まってしまう問題を飛ばして解いていくと、1時間以内に全100問に目を通すことができると思います。
時間がかかる問題を除けば、1時間で解ける問題を全て回答することは余裕だと思います。
実際、1時間程度で試験を終えて退室する人もいたので、120分は十分な試験時間ではないでしょうか。
ペース配分さえ間違えなければ「時間が全然足りない!」ということはないと思います。
私も場合、1時間ほどで一通りの回答を終了。
スタート時は画面のサイズや揺れが気になったりし、問題がなかなか頭に入ってこず「どうしよう…」と焦りましたが、だんだんと落ち着いて解けるようになってきました。
余った時間で、回答に迷った問題の見直しや、計算&プログラミングなど、時間がかかる問題に着手。
テクノロジの分野(アルゴリズムとプログラミング)は難しく、最後まで分からない問題もありましたが、選択肢を絞り込めるところまで絞って、勘を頼りに選びました。
試験時間終了まで問題と向き合ってみましたが、残念ながら解けないものはどんなに頑張っても解けないので、最後は回答の選択ミスがないか見直すくらいしかできませんでした。
やってよかった試験対策&やらなくて後悔したこと
試験を終えて振り返って、やってよかったと感じたことと、やっておけばよかったと後悔したことをまとめておきたいと思います。
【やってよかったこと】
・テキストをしっかり読み込む
苦手な分野、理解しにくい部分は、繰り返しテキストを読んで理解する。
私の場合は、暗号技術やコンピューターシステムのルートディレクトリ、基礎理論(2進数・10進数・16進数)などを重点的に読み返しました。
・テキストのアドバイスをしっかりチェック
テキストの「よく出題される」というアドバイスが的中していた問題もありました!
・計算問題やプログラミング問題も諦めない
計算やプログラミングは時間がかかるので、敬遠しがちですが、じっくり考えれば解ける問題もありました。最初から諦めて解くのをやめていたら、合格できなかったかもしれません。

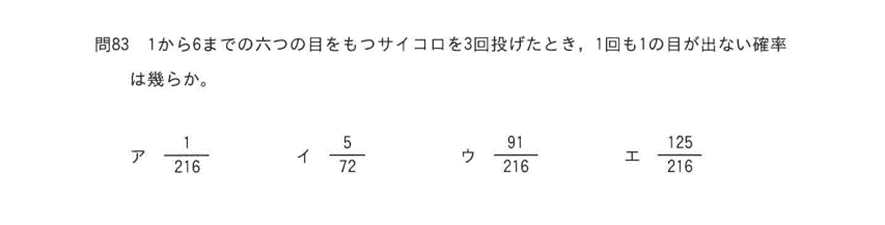
【問題】 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/openinfo/pdf/questions/2024r06_ip_qs.pdf
【回答】 https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/openinfo/pdf/questions/2024r06_ip_ans.pdf
・過去問題のアプリで問題に慣れておく
試験問題では判断に迷う言い回しの選択肢が入っているなど、「受験者を合否のふるいにかけている?」「ひっかけ問題?」というような、少し意地悪な問題もありました。独特な言い回しに過去問で慣れておくことも大切だと感じました。
【やらなくて後悔したこと】
・シラバスの確認
終始テキストに頼りきっていて、シラバスの確認をせずに受験を迎えてしまった私。当日は、テキストで説明されていなかった内容が出題されて焦りました。
試験後にシラバスを見たら、しっかりその用語が掲載されていたことが判明…。
シラバスを確認して、分からない用語も理解しておけばよかったと思いました。
ITパスポート試験のサイトに試験内容・出題範囲が明記されているので、これから受験予定の方は、受験までに必ずチェックされることをおすすめします!
試験内容・出題範囲の詳細は下記をご参照ください。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/range.html
・用語の完璧な理解
用語をしっかり理解していないと、正しい答えが導き出せない問題があります。なんとなく覚えるのではなく、できる限り完璧な暗記を目指すことが大切だと痛感しました。
・パソコンで問題を解くことに慣れておく
私はスマホで過去問を解いていたので「パソコンの大画面モニターで問題を解く」という環境になかなか慣れず、最初は問題が頭に入ってこない(集中できない)という状態になりました。
スマホだと顔を下に向けた状態で考えるスタイルになりますが、当日はずっと顔をあげた状態で回答するので、その点も落ち着かない要因だったように思います。
ITパスポート試験のサイトでは「CBT疑似体験ソフトウェア」が提供されているので、CTB方式で過去問を解いておけばよかったな…と受験後に思いました。
※ITパスポートのCBT疑似体験ソフトウェアの詳細は下記をご参照ください。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/guidance/trial_examapp.html
試験の結果と合格基準について
試験を終了すると、モニターに得点が表示されます。
その場で合格基準を超えているか分かるので、どきどきする瞬間でもあります。
合格基準を満たすには、総合評価点が600点以上であるとともに、すべての分野別評価点が300点以上である必要があります。
分野別評価点のうち一つでも300点未満の分野があると、合格基準を満たしません。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/reference/faq.html
合格基準のデータは、受験後にダウンロードが可能になりますが、合格発表は受験翌月の中旬頃になるので、それまでは合否は確定していない状態です。
正式な発表を待ちましょう!
受験者端末に表示される試験結果が合格基準を満たしていても、その時点で合格とはなりません。
経済産業大臣が合格者を決定します。
経済産業大臣による合格者の決定後、合格者の受験番号を官報に掲載するとともに、ITパスポート試験のホームページに掲載します。
https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/reference/faq.html
試験の翌月の発表日になると、ITパスポートのサイトで合格者の受験番号が発表されるので、正式に合否が分かります。
私も、何とか合格できました!
計算問題とプログラミング問題は、最後まで諦めずに取り組んだので、その姿勢は良かったのかなと思います。
ITパスポートの難易度は低いと言われているけれど…
「ITパスポートは簡単」と聞いていましたが、知識が無い状態から合格するにはそれなりに勉強が必要だと感じました。
社会人には身近な用語や内容も出題範囲なので、高校生や大学生よりはアドバンテージがあると思いますが、ちょっと勉強しただけで簡単に合格できるという試験ではないという印象です。
選択式とはいえ、正しい知識を持っているか揺さぶりをかけてくるような問題もありますし、計算問題でも用語を正しく理解していないと解けない問題もあります。
例えば「このアローダイアグラムでクリティカルパスの日数は?」と聞かれた場合、クリティカルパスの意味が分からないと、正解の日数が導き出せません。
※クリティカルパスは、プロジェクトで最も時間のかかる経路のことです。
そのため、用語の正しい理解が重要になってきます。
多くの合格者の方が実践しているように、1カ月ほどかけて、知識をしっかりインプットすることが合格につながるよう思いました。
ただ、ITの知識を持っていなくても1カ月くらいで合格ラインにたどり着けるので、国家資格としては難易度が低いという意見も、確かにそうだな…と思います。
ITパスポートの合格率や平均点は?
>見出し
ITパスポートの合格率や平均点は?
2024年4月~6月の合格率は51.7%。社会人の合格率は54.3%、学生の合格率は40.7%でした。
平均点のデータはありませんが、「評価点分布(2024年6月分)」のデータが公表されています。
評価点分布でボリュームゾーンを見てみると、0点~1000点の分布のなかで最も多いのが600点~649点(18.5%)、次いで650点~699点(14.2%)と、600点台の人が全体の32.8%に上ります。つまり、合格者のなかでも600点台の方が多かったということですね。
その次にボリュームが多かったのが、550点~599点で、全体の14%。
合否ギリギリのラインに点数が集中していることが浮き彫りになりました。
参考資料:ITパスポート試験「統計情報」
ITパスポートは意味がない!?
私も現在の会社に入るまでは、ITパスポートの資格に興味を持つこともなく、取得してもあまり意味がないものと思っていました。
でも、実際にIT企業に勤めることになり「自社のサービスを理解するうえでも、基礎的なITの知識は持っていないといけない」と思うようになりました。
実際に勉強してみると「こういうことだったのか!」と、ITに関する分野に理解が深まったり、技術者の方との会話で「この単語の意味は分かる!」という場面が増えたり…と、仕事にもプラスになっています。
会社で取得を推奨されている理由も分ったように思います。
社会人を長く経験していると、今さら取得しても…と思われるかもしれませんが、もし会社で推奨されているようでしたら、ぜひチャレンジされることをおすすめします。
また、これから社会に出る学生の方は、学校で取得を推奨されているかもしれませんが、たっぷり勉強時間を確保できる&頭が柔らかいうちに、チャレンジされることをおすすめしたいです。
社員にITパスポートを推奨している会社であれば、入社前にITパスポートを取得していることはアドバンテージになると思います!
私も、今回の受験で終わらずに、次なる資格取得に向けて勉強を続けていきたいと思います。
あなたの日常にフレッシュな彩りを!
いつでも「Bitter Orange Radio」でお待ちしています。
蒲郡みかでした。
note「Bitter Orange Radio」を運営する、株式会社No.1デジタルソリューションのコンテンツグループは、紙媒体の編集・執筆経験を持つライターと、さまざまな媒体の撮影経験を持つフォトグラファーで構成されたプロ集団です。
ホームページ制作のための取材・執筆はもちろん、自社コンテンツやパンフレット・冊子など、さまざまなテキストの取材・執筆、取材なしのテキスト作成、リライト、ブログ用記事作成、文字校正など、さまざまなライティング業務および写真撮影を承っております。
ライティング・撮影に関するご要望がございましたら、ぜひお問い合わせください。
★下記お問い合わせフォームより、ご連絡ください。
