
群像 2025年1月号 「本の名刺」白岩英樹
群像2025/1 本の名刺 『ぼくらの「アメリカ論」』 白岩英樹
大ボリュームの新年号のご恵贈にあずかりました。
「本の名刺」特集での白岩英樹氏のエッセイ。前回も登場したネコちゃんとの共住みエピソードが人類の共生問題へと敷衍されています。
重症ネコアレルギーの人間がネコと人生を共にするという超難題は、「宿命」と「運命」の考察を通して、「compassion……ままならない他者の他者性を全身で受けとめ」あう模索の道を開きます。
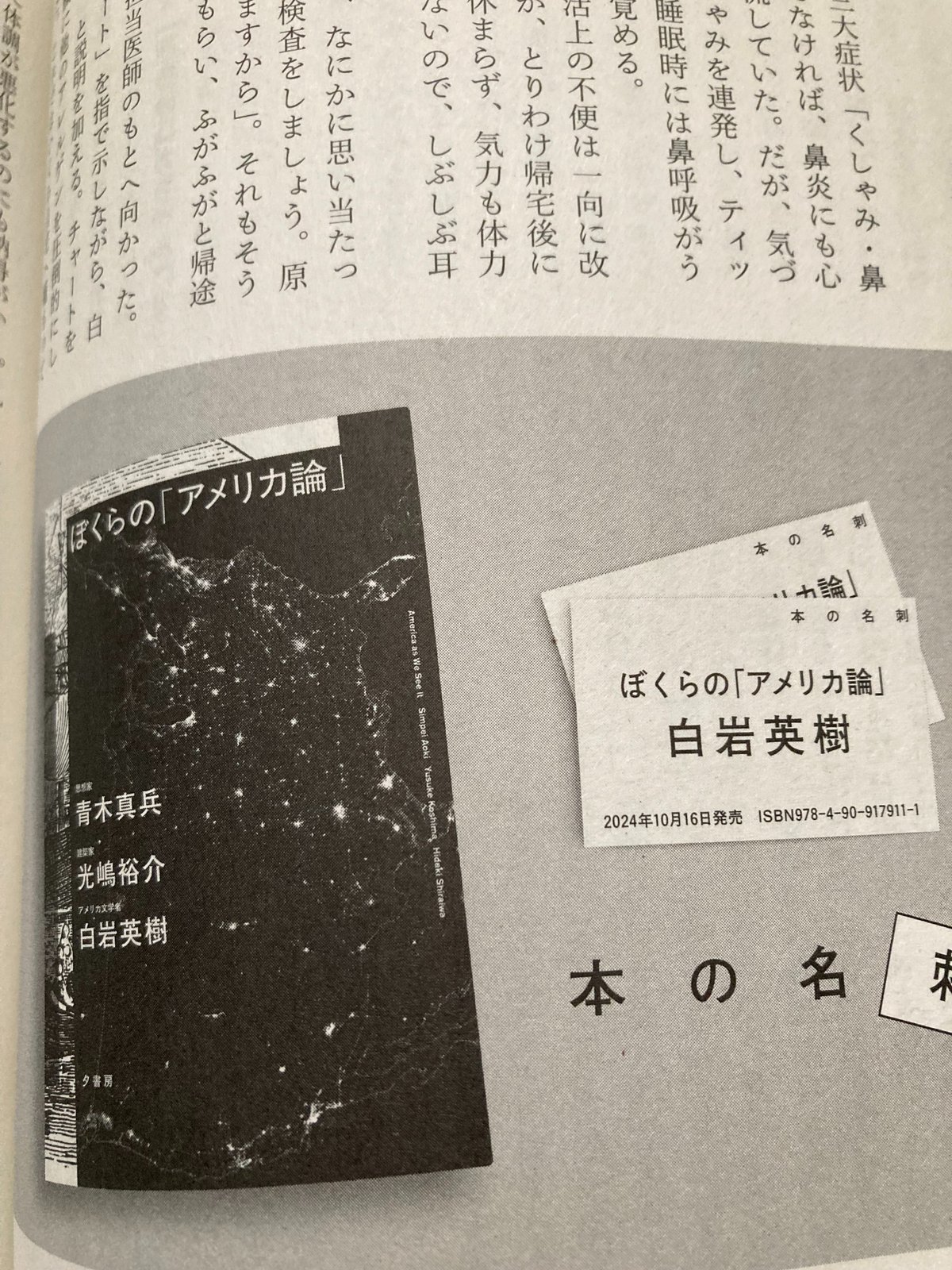
「うつくしく優しい檄文」(勝手に命名)の書き手、白岩氏。
うつくしさはもちろん文学者の詩情と美意識に、そして優しさは「身体性」という概念に帰するのではないか。『ぼくらの「アメリカ論」』のたとえば#12「モグラの手つきで」を読むと、手つき、手当て、耳をすませる、まなざす……という言葉が使われています。他者を抽象化せずレッテルを貼らず、自分と他者の「身体性」そのものと向き合い、「共苦」を試みることが、分断の時代を乗り越えるひとつの鍵なのですね。
うつくしさと優しさ(でも檄文)。繊細で逞しい世界との向き合い方は英文学者小川公代氏のケア論に通じるものがあり、文学の可能性を改めて認識させられます。
次期米国大統領の身体性を欠く言説に副大統領の「cat ladies」発言(猫ってところがまた…)。自己の延長だけで突き進む道のあとには瓦礫しか残らない。
四六時中肉体の問題に対峙させられる鼻水・鼻づまりとの戦い。すり寄り喉を鳴らす猫。身体はたしかにそこにあります。誰にも絶対に捨てたり無視したりできないのです。

