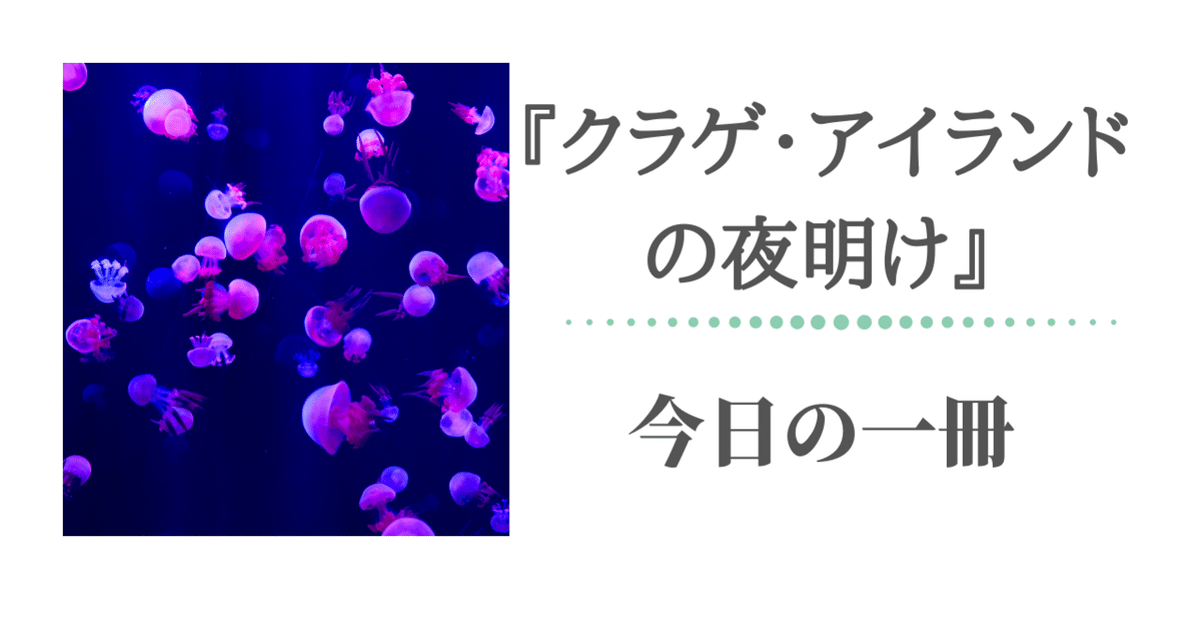
【読書】『クラゲ・アイランドの夜明け』
こんにちは、ナカちゃんです。
5冊読んで、3冊目のご紹介です。
今回は、これ
1 『クラゲ・アイランドの夜明け』 渡辺優 著 中央公論新社
渡辺優さんのデビュー作は、こちら。
2 「クラゲ」と「コロニー」と「ゲノム編集」
フィクションとはいえ、読んでいて「リアリティー」が感じられるか否かというところが、大事。
で、エンタメ小説として、「フィクション」のさじ加減も大事。
「ありえへん」ことを、「ちょっとありえるかも?」と思わせるのが、おもしろい小説に欠かせない要素でもあります。
この作品のキーワードは、 「クラゲ」と「コロニー」と「ゲノム編集」
主人公の女の子 ミサキ は、本土(日本)に生まれ、母と離別し、父親と姉とともに、海上につくられた「コロニー」という人工的な集落に住んでいます。
そこに住むためには、高い倍率を勝ち抜いた、選ばれた日本人になるしか方法はありません。
コロニーは、殺人、傷害、交通事故、違法薬物、違法労働、虐待、自殺者がゼロ。通称、[楽園]。
「海上の楽園」に、「正体不明」の「クラゲ」が発生するところから物語は始まります。
そのクラゲは、「人を食らう」殺人クラゲ。主人公のミサキは、異様なまでにクラゲに執着します。
新種のクラゲを何とかして確かめようとするミサキ。
幼なじみの僕(ナツオ)に、そのクラゲを捕獲しにいくと言い残して、彼女はクラゲの海に落ち、命を落とします。
「事故死」という理由で、片づけられたミサキの死。
その最期を見ていたナツオは、「彼女は自殺だったのではないか?」と疑うようになっていきます。
殺人クラゲは、「つくられた生き物」であり、そのクラゲをつくったのは、ミサキ 本人であったことが明かされます。
科学者である母親に贈られた「ゲノム編集」の子ども向けキット。
そのキットを入り口に、ミサキはゲノム編集に没頭していきます。
本土に残してきた友人と、60年前(!)に使われていたコンピュータネットワークを隠れて使い、このゲリラ的な作戦を秘密裏に進めていたのです。
本土で高校生が起こした連続爆弾事件も、科学好きな少年達が自作の爆弾をつくって起こした事件でした。
科学の力で、命の形を変える。
科学の力で、社会を変える。
実は、ナツオ自身も、母からの遺伝病を、ゲノム編集で無いものに書き換えられた人間だったのです。
クラゲをつくったミサキは、コロニーで行われている農業にも関わっていました。ソウマは、ミサキに禁止されているはずの「ゲノム編集」を施した農産物の開発を依頼し、無断で栽培していたのです。
自分の家の地下室で、彼女が育てていた植物は、彼女がつくり出した(ゲノム編集を施した)植物でした。
ミサキの死後、姉がすべての植物を枯らしてしまいますが、そこにある植物たちは「この世に存在してはならないもの」だったのです。
「自分のつくり出した生物」が、人間を攻撃し、滅ぼす事に繋がってしまったとしても、「神の領域」に踏み込みたいと、願ったミサキ。
新種の殺人クラゲに、自分の名前をつけられたナツオは、独りコロニーから脱出する決意をします。
3 なぜ「クラゲ」なのか?
クラゲは、特異な増え方をします。
ウィキペディアからの、引用です。
基本的に雌雄異体である。多くのクラゲでは、卵から幼生(プラヌラ)が生まれると、幼生は基質上に定着してポリプというイソギンチャクのようなものになる。新しいクラゲは冬季になるとポリプが御椀を重ねたような「ストロビラ」になり出芽、エフィラ幼生となって泳ぎ出す。また変態、ストロビレーションなどによっても生じる。ポリプは無性生殖によって増殖するので、これを無性世代、クラゲを有性世代と見なし、世代交代をおこなうものという場合がある。カラカサクラゲやオキクラゲはプラヌラからポリプにならずそのままエフィラとなる。ヒドロ虫綱のクラゲでは、ポリプがよく発達し、群体となるものがあり、その場合はクラゲは特に分化した生殖個虫から作られるものもある。全くポリプを形成しないクラゲもある。
彼女は、自分でつくったクラゲのポリプを隠し持っていました。
ゲノム編集でできあがったポリプを、海にまき、大量発生する時期を待っていたのです。
いつ、どこで、どのように、クラゲが生体となるのか。大量発生するのかは、人間にはわかりません。
「ゲノム編集」された命が、どんな影響を自然界に及ぼすのかは、未知の領域でもあります。
そこに、入り込んでしまったミサキ。
ナツオが、コロニーを脱出する決心をした後、この殺人クラゲがどうなっていくのかは、描かれていません。
「人間によって作られた楽園」は、「ホントウの楽園なんかじゃない。」
瓶の中にいる「最強のクラゲ」の欠片を握りしめ、楽園から出ていく決心をしたナツオ。
感情を表に出さず、クラゲのようにぼんやりと生きてきた彼が、「怒り」にも似た感情、「人間らしく、生きよう」とする熱を得て、これからどう生きていくのか。
読後に、余韻を残すラストシーンです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4 まとめてみると・・・・
今、私たち人類は、自然界で「踏み込んでしまってはいけない領域」に入り込んでしまったのかもしれません。
新型コロナウイルスは、収束するどころか、様々に変異を続け、私たちの日常を侵略し続けています。
さらに、今後は、「未知のウイルス」が、人間の社会に蔓延することも予想されているのです。
人間が、野生動物のエリアに入り込み、侵略していくことで、感染しないはずの病気が、人間に感染してしまうリスクがあります。
地球温暖化、砂漠化、化石エネルギーの枯渇、農業の衰退による食糧不足、水不足。。。。
山積する「人類の課題」に、私たちはどう向き合っていったらよいのか。
そんなヘビーな問題意識にも、つながってしまうテーマではありますが、
ちょっと、それは置いておいて。。。。。。
この作品は、純粋にエンターテイメント文学としても、十分に楽しむことができる小説です。
SFテイストもあり、アニメテイストも感じられるこの作品。
秘密がどんどん暴かれていくラストのスピード感が、読後の爽快感につながります。
ぜひ、アニメ映画化してほしいなあ。
おすすめです☆
いいなと思ったら応援しよう!

