
『精霊の残り火』最終話
「この星と歌う、最後の歌を」外伝 ~後日譚~
『精霊の残り火』
最終話 残り火
僕と、隼人と、浩太さんは、子供の姿になった白手毬を連れて、ブロック塀の小道に向かった。
隼人が事件と遭遇した曜日、時間帯、を選んで。
白いふわんふわんの髪の毛に青い目の少年は、なぜかずっと微笑んでいて非常に愛くるしい。
愛くるしい少年は、小さな手で僕の手を握って、離さない。
アンジェリカに会えるか、不安でもあるのだろうか。
なんだかんだで、白手毬は、どんな姿でも、ものすごい寂しがりなのだ。
月がのぼり、暗がりが増え、いっせいに街灯がついた。宵の風は、わずかに涼しい。涼しさとなまぬるさが、順番にやってくる感じ。
「まだ来ないみたいだね」
浩太さんが言うと、白手毬はしょんぼりする。
「このあいだ事件が起こったのは、俺のバイト帰りで、もうちょい時間が経ってからだったぜ」
「じゃあ、がんばってまつよー」
僕は白手毬のふわんふわんの髪を撫でてやる。うん、なぜか僕のほうが癒されるな。
「ああ!!!」
白手毬が何かに反応し、僕の手を離して駆けだした。
と、少し走ってから戻ってきて、僕らのほうを向いて、深々とお辞儀をした。
「ありがとう。かいと、はやと、こた。てま、行くね。さようなら」
鈴を振るような声音で僕たちにお礼を言い、愛らしい笑顔を残して、また駆けていく。
さようなら?
その響きが、不穏に思えてならない。
「アンジェリカ―。僕だよー!」
たたたたたっと、数メートル先でこちらに向かって歩いてきていた女性に、白手毬は飛びついた。
「アンジェリカ?」
女性は立ち止まり、白手毬の手をやさしくとって、しゃがみこみ、目線を合わせて首をかしげる。
「君、迷子かな? 私はアンジェリカじゃないよ」
「アンジェリカだよ。あのね聞いて。アンジェリカ、怖いっていってたからね、僕、神様になったんだよ。だから、もうね、神様怖くないよ」
「神様?」
「みめぐみじゃー」
少年の突拍子もない物言いに、会社帰りらしい女性は、笑いをこらえきれなくなって、口元をおさえる。
「ほんとだ。神様だ。ふふふ。かわいいね。君、天使みたい」
「天使じゃないよ。ユニコーンでした」
「ユニコーンって名前なのか。じゃあ今から私が、一緒にお父さんとお母さんを、探してあげるね。さあ、行こう、ユニコーン!」
女性は立ち上がり、白手毬の手をひいて歩き出そうとする。
白手毬は、首をふった。
「だめなの。もうね、僕には力が残ってないの。ここでは、長くは生きられそうにないんだ」
綺麗な青い瞳から、涙が流れる。
白手毬、そうだったのか。
「だから、アンジェリカ。これからは、君のそばにいるよ」
白手毬は、魔法で毛の長い犬みたいな姿になり、そして今度は、誰が見てもユニコーンのこどもだとわかる、角の在る白い仔馬の姿になった。
僕たちは、はらはらとその成り行きを見守る。
女性は、驚いてはいるけれど、怖がってはいない様子だった。
ユニコーンのこどもは、少しずつ、青く輝く炎に姿を変えていく。
これは、魔法存在の格だ。もっとも純粋な力に、自身を結晶化させたときの姿。
青い炎は、女性の胸のあたりで、すーっと消えていった。
僕には、白手毬が女性のエネルギーの一部になるために、自身を昇華させたように見えた。
不意に、女性は両手で顔をおおって、泣き出した。
声をおさえて、小さく嗚咽をもらしながら、電灯の下で泣き続ける。
白手毬、この人、アンジェリカで間違いなかったんだね。僕にはわかるよ。
彼女には、今、心で、白手毬の声が、想いが、響いているのだろう。
このまま彼女を見守り続け得ていても、僕ら三人、不審者みたいだな。
誰からともなく、僕、隼人、浩太さんは、何も言わずに、静かにその場を離れる。
てまちゃん、さようなら。
アンジェリカと、幸せに。
僕は心で大きく声をかけた。
地球で最後のユニコーンが消えてしまった都市に、なんの予兆もなく、霧のような雨が降り始めた。
やさしい、涼やかな、気持ちのいい雨。
浄化の気配だ。
水の精霊たちが、泣いているのか、祝福しているのか。どちらだろう。
後日。
僕は、白手毬がくれた緑のすりガラスを、麻で編んでネックレスにした。
みめぐみじゃーと言っていたけれど、たしかに。
これをつけていると、水の守護の気配がある。猛暑が、ほんのわずかに涼しくなる。
川べりを歩いても、森を散歩しても、白手毬の姿を探してしまう。
これが、ペットロスという感情なのか。
特に僕が事件を解決したわけじゃないんだけど、浩太さんと廉さんからもらったアルバイト代。
それで、父にプレゼントを買いたいと思い、街にでる。
夏休みの終わりごろに、藍那ちゃんと遼君とはるさん、そして、遼君のお父さんが、田舎のお屋敷に泊りに来ると言っていたから、いくつか小さなプレゼントでも買っておこうかな。
せっかく田舎から出てきたけれど、結局、僕はこれから何をすべきか、何になるべきかは、見つからなかったな。
職業、魔法使い。
は、やっぱり無理があるしな。
自分は何をしたいのか、お屋敷に帰って、改めて考えてみよう。
今日は快晴。
暑すぎる都会とは、これでしばらく、さよならだ。
エピローグ
あんなに怖い思いをしたのに、他の道を選ぶと遠回りだからと、妥協して選んだ道。
昔から、無性に怖がりで、あなた霊感があるよねとか言われると、なぜかそれも怖くて、どうしようもなかった。
でも、あの道で、可愛い外人の男の子は、目の前で犬に変わり、ユニコーンになり、青い炎となって消えていってしまったけれど、不思議とこわくなかった。
むしろ、今まで怖いと感じていた、様々なものが、怖くなくなった。
お墓も、闇夜も、いろんな迷信も、怖くない。
何かを怖いと感じた瞬間、可愛い男の子がイメージの中に出てきて笑って、そっと頭を撫でてくれる。
そんなとき、なぜか、すごく懐かしくて、少しだけ悲しい気持ちになる。
やさしい、懐かしい思い出というものは、どんなものであっても、過去のものだからだろうか。
あの子は、過去にしかいないんだ。
私の心の中のほかには。
それが悲しいのに、不思議とあたたかい。
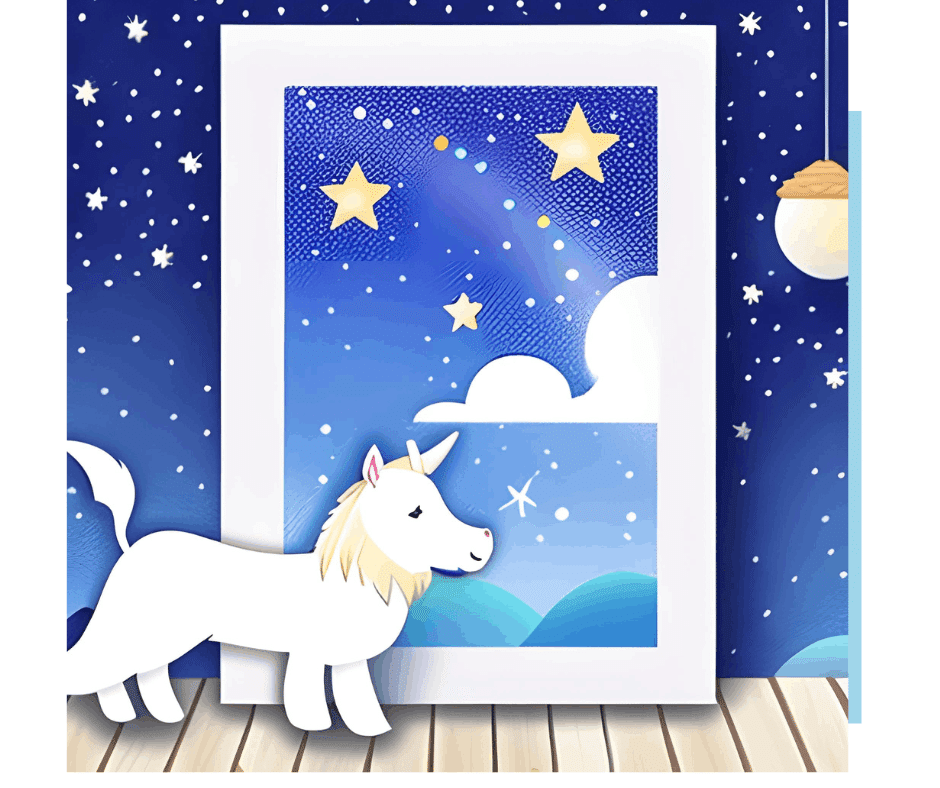
おわり
本編「この星と歌う、最後の歌を」はこちら
