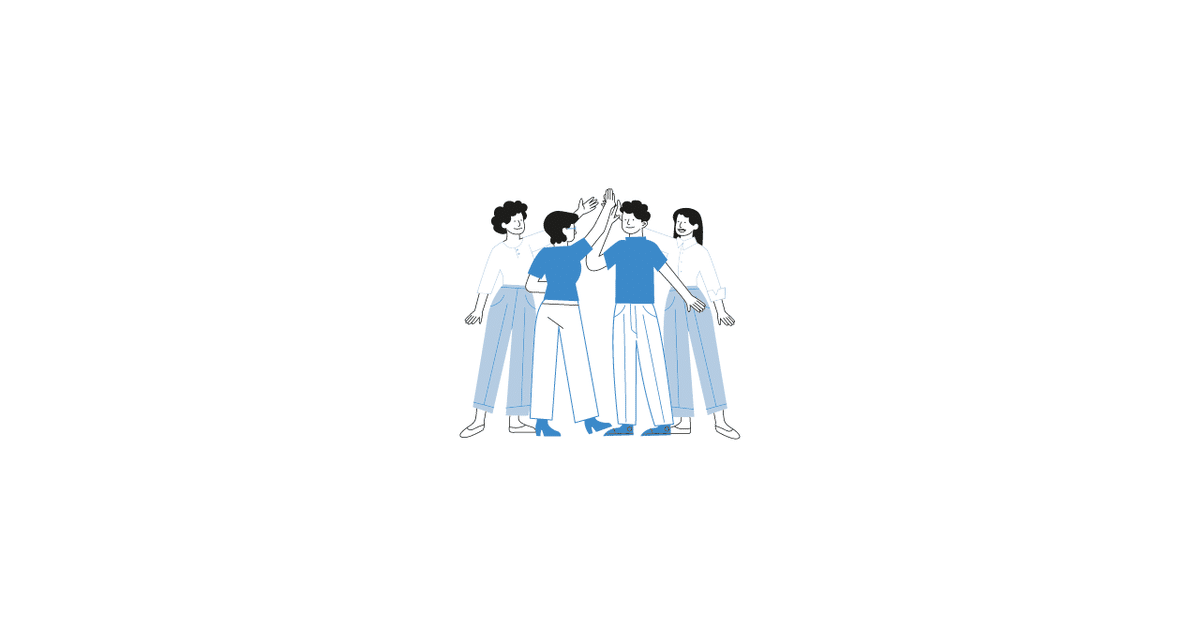
2022年 95冊目『チームワーキング』
立教大学の中原教授に今度中尾塾でお話し頂きます。
その際の課題図書にしました。
いやー面白い本でした。
まずチームワーキング。
「チーム」に「ワーキング:物事がダイナミックに、常に動いている状態」を付け加えたキーワードです。
チームワーキングの状態とは
1)チームメンバー全員参加で、
2)チーム全体の動きを俯瞰的に見つめ、
3)相互の行動に配慮し合いながら、
目標に向けてダイナミックに変化し続けながら、成果創出をめざすチームの状態
成果が出ないチームは
1)1人のリーダーだけがチーム全体の事を考え
2)リーダーが中心となってチームの目標と各自の役割を設定し
3)それ以外のメンバーはお互いの役割や仕事の状況にはさして関心を示さず、自分に与えられた役割をただ黙々とこなしている
優秀なリーダー1人がいれば何とかなるのではなくて
チーム全員の賢い振る舞いこそが、チームの成果の成否を決めます。
この本のエッセンスは、著者の感覚ではなく統計データから導き出したものだというのが類書との大きな違いですね。
で、成果の出るチームワーキングできているチームは次の3つの視点と3つの行動原理を持っているというのです
3つの視点
1 チーム視点:Team View
チームメンバー個々人が「チームの全体像」を常に捉える視点を持つこと「私」「あなた(たち)」の視点だけではなく、「私たち」は何を目指しているか?
「私たち」は何をしているのか?を考える。
2 全員リーダ視点
機会があれば全員がリーダーになるという前提で、当事者意識を持ってチーム活動に貢献する
≒シェアド・リーダーシップ
つまり、場面、場面でリーダとフォロワーが入れ替わる
3 動的視点←最も重要
チームを動き続ける、変わり続けるものとして捉える
~ing思考を持ち、変化を捉えながら自分自身も行動を変えていく
3つの行動原理
1 Goal Holding:目標を握り続ける
Goal設定するだけではなく、メンバー全員が目標を握っている状態を維持
環境や状況が変わった場合でも目標を確認し続ける!
データによると
高成果チーム群の初期→最終の目標コミットは
87%→93%
低成果チーム群は
82%→57%
やる気のないメンバーは高成果チーム群にもいるが
低成果チーム群に多い(両方とも後になると増える)
高 20%→23%
低 56%→59%
同じく高成果チーム群は低成果チーム群と比較して
目標に立ち戻り、目標を見直す割合が高い
2 Task Working:動きながら課題を探し続ける
解くべき課題を仮決めし、振返り、修正し、継続する
アクションしながら課題の精度を高めていく
1問題が何かを定義し
2問題を構成している課題を洗い出し
3課題の中で解く必要がある課題と特定する
データによると
高成果チーム群の初期→最終の綿密な計画は
67%→88%
低成果チーム群は
51%→64%
高成果チーム群の初期→最終の全員アクション
74%→83%
低成果チーム群は
64%→62%
高成果チーム群の初期→最終のリフレクション
76%→78%
低成果チーム群は
64%→49%
低成果チーム群では
緊張感が低く、みなに同調してさぼっている
※優秀な人がいるのでよりかかる割合は同じくらい
3 Feedbacking:相互にフィードバックし続ける
チーム全体で相互に何を感じているのかを相互に伝え合う
≒製造業のすり合わせ力
高成果チーム群の初期→最終の相互フィーフィードバック
70%→78%
低成果チーム群は
72%→36%
※できない、しにくい、意味が無い、間に合わない、面倒くさい
仲良し→個業化→ブラックボックス→チーム視点喪失→コケる
高成果チーム群の初期→最終の仲良くすることの目的化
30%→23%
低成果チーム群は
38%→54%
3つの行動原理はG-POP版GCで実施している事とまさに一致していますね。
データでも成果が出る理由が分かり、嬉しいです。
