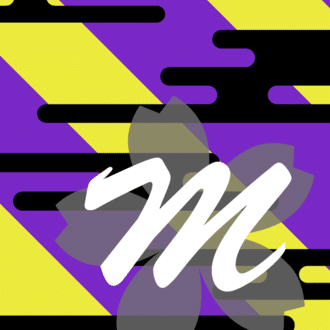「ヒ」のコツ
発した音の余韻をひゅんと下げる奏法、箏にもあります。「引き色」。
「ヒ」と楽譜にあったら、それ。
エレキギターほど大がかりに派手派手しく音が下げられるわけではありませんが、これも、「何か違ったことをしている」とお客さんに気がついてもらえると、楽しいので、しっかり音を作れるコツを書いておきます。
引き色の目的
音を下げる=押さえの逆。
柱よりも右側の部分の、絃の張力を緩めることで、音をさげます。
掴み方
これができればあとは力加減の問題なので、ここをしっかり。

指をそろえてふつうに持つと、滑ります。
滑らないようにするには、指のかける位置をずらして、力を入れて絃を「S字」にゆがめるように持ちます。
(*親指を、人差し指と中指の間に置くようにして、三本で持つやり方もあるみたい。私は上記で教わったのだけど、そのやり方の方がしっかり掴めるのかも。いろいろ試してみてね)
しっかり掴んだら、右手の支え(薬指)で箏がずれないように上から押さえつけながら、左腕を動かします。ひじで押し込むような感じ。
(指で引っ張ると力が分散して固定が弱くなるから、掴むパーツと駆動パーツは別の方がよいんだと思います)
■がっつり下げたいとき
絃を掴む手の固定に、小指をプラスしてもいいかも。
図には描きませんでしたけど、こういうときは、小指は、キツネザルの尻尾みたいに絃に巻き付けるような感じで、第1関節の部分を使って指一本で握ることも。
三点で絃を固定するので、かなり安定します。ただ、絃に手をかけるのと外すのに多少時間を食うので、速度対応はできないのが難。
(この手の時にやりやすいのが、親指を支点にして小指を引っ張ってしまうパターン。支点になる親指が沈んで押さえの形に近くなり、逆に音は上がってしまいます。手元の操作ではなく、左腕丸ごとを龍角方向へ引っ張る(押し込む?)感じですよ)
ユリとの使い分け
ちょっとしたことなんですけど、ユリ(ビブラート)の時に、①絃を押さえて上方向の音程の変化を使うか、②絃を引いて下方向の変化を使うか、というので印象に違いがあったりします。
短調の場合は引き色の方が、という人もいたので、一応、メモ。
あと、古曲はだいたい引き色と先輩から聞いたこともあるのでそれもメモ。
(こういう細かな技法は、音源を聴くよりも演奏を見た方が手元が分かりやすいかもしれないので、お手本を探すときは映像で探すのもいいかもしれない。手が絃をつまんでいればヒキ、手が立ってる形なら押し)
尺の演奏だとメルとかカルとかありますけど、尺の人のビブラートで上下どっちにかけているかにそろえたりもするかもしれないなーと、ちょっと思ったり。
ちょっと特殊な奏法「ヒ」のやり方でした、参考になればいいな。
いいなと思ったら応援しよう!