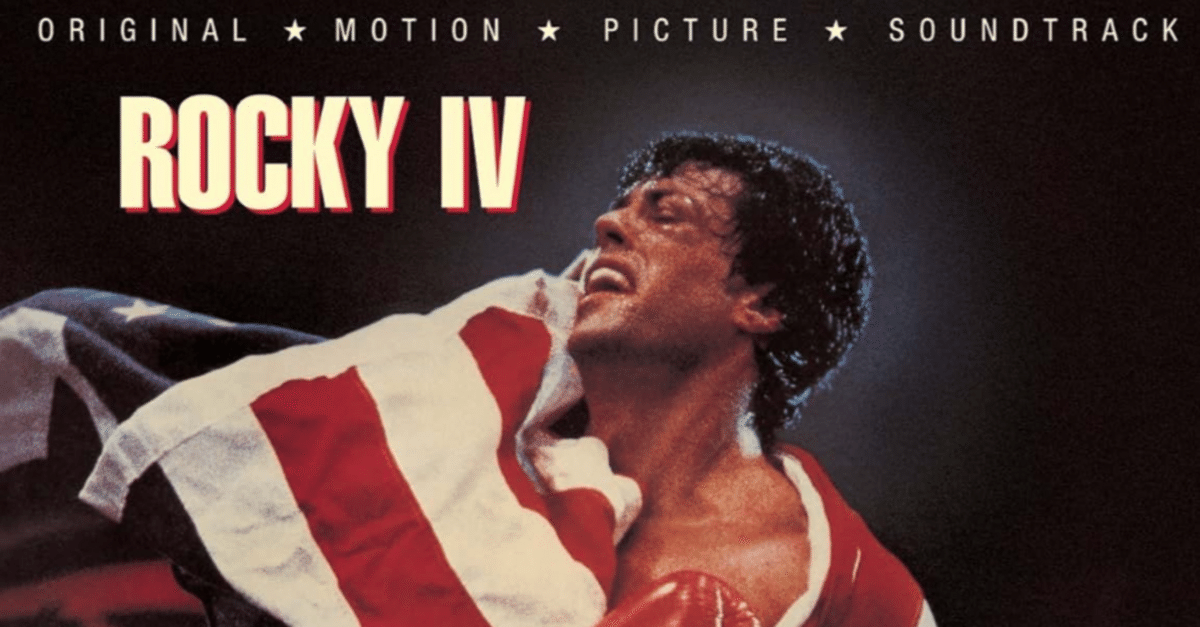
19851127 ROCKY IV ロッキー4/炎の友情 /オリジナル・モーション・ピクチャー・サウンドトラック(2006リマスター・バージョン)
シルヴェスター・スタローンの代表作映画ロッキーシリーズ4のサウンドトラック
アメリカのロック・バンドのサバイバーの「Eye of The Tiger」、「Burning Heart」の2曲は現在でも耳にするクラシック・ロックのスタンダードであり、映画同様1980年代を代表するナンバー。
他にもスタローン自身が直接オファーをかけるアーティストも存在し、彼のロックに対する並々ならぬ情熱とアンテナの感度がリアルに伝わってくる。
アマゾン・ミュージック、YOUTUBEで視聴可能。
曲目
Burning Heart - Survivor
Heart's on Fire - John Cafferty and the Beaver Brown Band
Double or Nothing - Kenny Loggins and Gladys Knight
Eye of the Tiger - Survivor
War Vince - DiCola
Living in America - James Brown
No Easy Way Out - Robert Tepper
One Way Street - Go West
The Sweetest Victory - Touch
Training Montage - Vince DiCola
曲目抜粋感想
Burning Heart - Survivor
サバイバーの2曲のうちの本作品映画用にレコーディング。
ジミ・ジェイミソンという新ボーカリストが歌っている。そして彼のボーカルは何回か聴いていくと、ハイ・トーンやその高音の持って行き方や、コブシを入れる力点、力加減がジョン・リン・ターナーを彷彿させる。
この声の特徴に沿うようにピアノ、ギター、ベース、ドラムとシンプルな構成を1980年代特有のエコーや残響音で当時の先端的であったであろうアプローチで仕上げている。
実は意外にも隙間がある音の空間。この空間によって映画の視聴者やリスナーにとってストイックな高揚感や固唾を飲むように誘発されていく。
終わり間際のマイナー・ペンタトニックのギターソロもフェイドアウトしてしまうがソロ構成やトーンが良いのでもう少し長く聴いていたい。
Heart's On Fire - John Cafferty
ジョン・キャファティ&ザ・ビーバー・ブラウン・バンドが本来の活動形態だが本作は本人名義のソロ・ナンバー。
本来のバンド形態だと初期のジョンクーガー・メレンキャンプに近いバンド・サウンドがある。
しかしここではマッチョさを強調するせいか、シンセサイザーがビショビショに漏れるくらいに挿入されている。
当時の知名度からするとスタローンが一本釣りしてオファーした可能性が高い。※別作品の刑事映画「コブラ」でも彼は採用される。
ボーカルはスタローンの「強い男」というイメージに合致している。ジョン自身も映画用と割り切ったからこそソロ名義なのだと推測する。
Double or Nothing - Kenny Loggins & Gladys Knight
当時のケニー・ロギンスは、直近の映画「フット・ルース」の主題歌の特大ヒットで自身の過去の経歴がほぼロンダリング状態なっていた。
あまりにもロギンス&メッシーナとの音色や音楽性に乖離が有り過ぎて、綺麗さっぱり宗派変えしている。むしろ中途半端にやるより180度方向転換した方が却って清々しさを感じさせる。
本曲もモロに1980年代中盤のたっぷり装飾されたサウンドで全身を身にまとっている。しかし、伝説の女性シンガー、グラディ・ナイトとのブッキングを実現させているので魂をギリギリ売ってないのも伝わる。
名門モータウン・レコード、ファミリー・グループのグラディ・アンド・ザ・ピップスのソウル・シンガーが歌うことで話が違ってくる。
マッチョでストイックな映画において多少陽気なAORとパワーポップが融合した楽曲になっている。
ケニー・ロギンスがグラディ・ナイトの歌い方、ソウル・シンガー的に寄せて来ている。2人のボーカルが交互に歌われるが、あくまでも両者対等な立ち位置で展開していく。
平坦な曲構成だがサビ部分での2人のハモリがその相乗効果を発揮し、お互いを光らせている。この辺が曲のポイントになっている。
タイトルを訳すと「イチかバチか」であり、ロッキーの妻エイドリアンとライバルで盟友のアポロが、ソ連(ロシア)の(国製)アマチュア・ボクサー、ドラゴとの試合受諾について話し合うシーンから来ている。そのため男女デュエット曲になっているのだろう。
Eye of the Tiger - Survivor
前シリーズのロッキー3からの楽曲を再収録。スタローンがサバイバーのセカンド・アルバムを聴いて楽曲を依頼。
オファーの一因に当時のボーカリスト、デイヴ・ビックラーの声に何か特別な魅力や可能性を感じたのではないだろうか。
彼のストレートに綺麗に伸びる高音は存在感があり、歌の表現スキルが非常に高い。そして細面のキリっとしたルックスはバンドの象徴でスター性も感じる。
サウンド面では、同じギブソンのギターでも木材の詰まったレスポールとは違う音が聴ける。変形シェイプのエクスプローラーから繰り出すイントロのCのルート音のシンプルなリフレイン。
リング・ロープにもたれ掛かるしなりや縄跳びやスピードボール、リング・インする花道を黙々と歩むボクサーの入場シーンなど色々目に浮かぶ。
そこからすかさず入るCとBbの交互に区切って弾くコード・バッキングは打撃シーンを即座に連想させる。
このバッキングのギターも同様にエクスプローラーの音だ。よく聴くと2つのコードのバッキングの瞬間「チャカッ!」と空ピッキングが挿入されている。これがリング・シューズをボクサーがキュッと鳴らす感じもありカッコいい。
1982年リリースで、「バーニング・ハート」より3年ほど前の楽曲だ。1980年代前半はまだエコーや残響音が少なく、生音勝負で仕上げている。
よって同バンドで2曲はボーカリストも、サウンド構築やアプローチも異なっている。それでも統一性があるのは「ストイック」に耐え忍ぶという作品の共通イメージが共有できているからだ。
War Vince - DiCola
インスト曲につき割愛
Living In America - James Brown
何と本サントラの裏のメイン・イベント的に御大ジェームス・ブラウンが登場!しかもダン・ハートマンのカバーという想像斜め上のサプライズ。
ダン・ハートマンが得意のディスティーク・ポップスの代表ナンバーを採用。実際のシーンではアポロ対ドラゴのエキビジョン・マッチの際の入場曲で、JB御大が会場で実際に歌うというヤバめなゴージャス仕様!
これがメチャメチャにカッコいいのだが、ストーリー設定で当時の米ソ冷戦下の対立構造を明確になるように現わしている。
あえて陽気にというか「ドラゴという若造に負ける訳がない」という見下した態度のお祭りシーンにこの「(パリピ的)アメリカ賛歌」を粛々と脇役を演じるJBがクール。
そして1つ気づいた点があり、ジェームス・ブラウンの経歴はドラマーからボーカリストに転身している。
この曲を聴くとドラムのスネアと歌とがリズムが一体になっているように聴こえる。ドラムのビートにジャストに乗っかって歌っている。この正確なリズムの気持ち良さから、リピートして聴いてしまう。
普段1コードのリフレインでうねってリズムを繰り返す元祖トランス・ミュージックだと気づかないJBの凄さを新たに認識してしまった。
No Easy Way Out - Robert Tepper
曲を聴いて本曲を採用したいとスタローンがオファーしたナンバー。
「 No Easy Way Out」=楽な道(解決策)は無い、つまりアポロの仇を取るのはオレしかいないという結論に至る導線的な回想シーンにマッチした既存曲。
曲調はボーカルに関してもサバイバーとは違ったストイックさがある。
これから戦う準備にモードが切り替わる心理描写に即していながら1980年代中盤特有のサウンド仕様になっている。
イントロのチリチリとしたシンセサイザーの音色、白玉コード全開のキーボード。ドシャーンとしたスネアのコテコテ感があの頃の煌びやかさを象徴している。マイナー・コードの曲からシンプル・マインズの「Don't You Forget About Me」の展開というか音色を聴いた瞬間彷彿させる。
One Way Street - Go West
※アマゾン・ミュージックでは視聴できない為割愛
The Sweetest Victory - Touch
サントラ収録だが2021年ディレクターズ・カット版で陽の目を見る曲。今回割愛。
Training Montage - Vince DiCola
インストにつき割愛
まとめ
本作品は映画と楽曲がぴったりと合致している。
シルヴェスター・スタローンはこの映画に関する筋書き、構成、コンセプトをバンド側にかなりの情報を与えている。サバイバーの様なオーダー・メイドにしたことで大成功した例がある。
それ以外に割と(当時の)最近の既存曲やアーティストを主体的に発掘してアプローチしている。※今回はマッチョな詞と曲調が多い。
またサントラでしか接点が持てないであろうジェームス・ブラウンやグラディナイトなどゴージャスなブッキングをさりげなく実現させている。
スタローンの音楽に対する価値観や捉え方というものを実際に聞いてみたく、インタビューがあれば興味深いコメントが絶対に出てくる筈だ。
未だ楽曲共に格闘シーンでの活用やモチベーション・アップなど現在進行形で影響力を持つ名盤。
終わり
