
意外でした。『国家はなぜ衰退するのか』を読んだら、とるべき教育方針がみえてきた件
子育てをしていると、日々悩みがつきないものですよね。
「子どもの意思を尊重して自由にさせるのと、ルールを定めてきちんと運用するの、どっちがいいのかな」
「子どもを自由にさせるとゲームはやめないし宿題はしないし…というのが現実!」
「怒りたくないのに、最後は怒らないとやらないのよね」
……なんて思ったことはないでしょうか。
あるいは
「子育てで多少怒るのはしょうがない。時間がないのだし、それで親子関係に問題おきてないし」
「朝のプリントに放課後の塾、ゲームや携帯の制限。きっちりルール決めてうまくいっています」
ということもあるかもしれません。
でも、どこかモヤっとしてスッキリしない…のではないでしょうか。
今日はそんなママにおすすめな意外な1冊を読んだので、海外教育6年目のYuriko流解釈をわかりやすくシェアしますね、というお話です。
え?『国家はなぜ衰退するのか』が子育てのヒントに!?
いま、『国家はなぜ衰退するのか』という本を読んでいます。
(正確にいうと、読んではいないです。Audibleで聞いています。それなら無料だしラクなので)
ノーベル経済学賞を受賞し、国内外の名だたる大企業や名門大学院の教授らが絶賛の声をあげている本書。難しくて、普通のママにはご縁のない本かと思いきや、いえいえ。
これがなかなか身近な話なんです。
中学受験で人格を壊されてしまう子ども。
あるタイミングで無気力になってしまう子ども。
不登校の子どもが増えている現状。
そんな現状にカチッとはまって、合点がいくんですよ。
(そもそも、私が読もうと思ったのも、とても好きでいつも共感してしまう野本響子さんが「読んだ(聴いた)」と話しておられたからなのですが)
新浪剛史さんというビジネスマン(サントリーホールディングス株式会社の代表取締役社長)の方が
国家と企業の衰退の驚くべき共通点の指摘。収奪的組織か包括的組織か。秀逸の書。
と評しておられるのですが、私からすれば「それと、子育てのあり方の驚くべき共通点の発見」です。
国家も企業も人の集合体。
人の集まりの最小単位は家族。
この本は、そうした「人が複数いるところ」ではこういうふうに物事が進むんだよ、ってことが書いてあります。

「自由」と「意志」のないところに「発展」はない
さて。
そんな『国家はなぜ衰退するのか』ですが、内容多くは事例と繰り返しなので、そのエッセンスをママ的に解説しますね。
この本は「自由な世の中じゃないと発展が望めないよ」っていうことを言っている本です。
少数の特権階級の人が富と権力を総取りして、国民に主権もなければ富の分配もない(本では「収奪的な」と表現されています)国、かつ、その特権階級層が固定されて新しい人が豊かになりづらい仕組みをもつ国は発展しない、と歴史的事実と事例を用いて述べています。
つまり、そうした環境では人々はこう考えるんですね。
・改善や工夫をしようとする意欲がおきない。だって、やってもやらなくても同じだから
・だって、がんばっても、その結果で得をするのは「支配者側」だから。そして自分は「支配者側」には絶対いけないから
・新しくてイノベーティブなことを提案しても、どうせ採用してくれないから(新技能を採用して効率化したり世の中が変わってしまうと支配者層が現状の支配力を維持できなくなることを恐れるため)
・いうことを聞いていれば、生きてはいけるから
・いうことを聞いて動くだけでしんどくて、それ以上の力が残らないから
でも、そういう世の中も、最初はすごく発展するんです。
かつてのソ連や中国、ハイチなどを本書では例に挙げています。
最初、単純に生産量を増やせばいいような局面では、支配者が人々に強制的にやらせる、というのはとてもうまく機能します。生産性の高い分野に集中投下すればいいので(歴史的にいえば、砂糖のプランテーションとか、鉄鉱石の採掘とか)。
これって、何かに似ていません?
私は、小さい頃に勉強(的なこと)を「やらせる」ことと似ているなあ、って思ったんですよね。
「支配的な子育て」は小さい頃はとてもうまくいく
小さい頃って、親に対して子どもはとても従順です。見てほしくて、褒めてほしくて、がんばります。
そんな時期に、じゃあ計算ドリルやろうね、文字をかこうね、公文たくさん進めようね、お受験の問題集やろうね、幼稚園生だけど小学生の算数やっちゃおうね、ってやると、けっこううまくいきます。
やっていればできるようになりますから、2歳や3歳で100までの数が言えたり、小学校入学前から文字を読み書きできたり、九九をいえたりするようになるのは、さして難しいことではないです。
すると、他人から
「○○ちゃん、すごい!もう字が書けるの!?」
「もう100までの数字が言えるの!?」
なんて言っていただけます。
そうすると、
「私の子育て・教育はうまくいっている」
「私はこの子のよい面を引き出している」
「この方法でいけ、いい学校に入れる優秀な子に育つ」
と思ってしまいがちです。
そこへ、小学校1年生からの中学受験塾の勧誘がきます。
早期英語教育の無料体験レッスンのお知らせが届きます。
右脳ナントカ、○○式、いろいろな商業的お誘いがきます。
流されるとも気付かぬまま、お受験や中学受験に傾倒するようになったり、英語の習得にかなりのお金をつぎ込んだり、勉強量を増やして先取り学習をしたくなったりしがちです。
そのこと自体がいい・悪いを言っているのではなく、
小さい頃(発達段階として初期である時期)に、強制的にやらせると、うまく習得しちゃうし見違えるほど成長しちゃう、ということと、結果、それが正解だと思ってしまうことがある、ということですね。
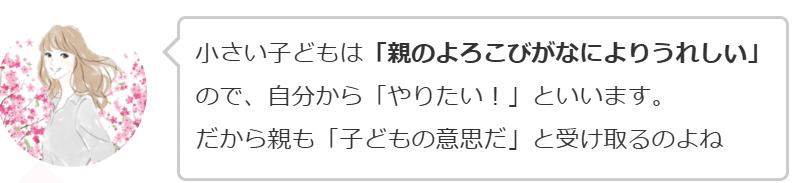
でも、これ、11~15歳以降くらいで逆転現象が起こってくるのです。
「子どもの自由」のない子育ては、思春期以降の成長に課題が残る
『国家はなぜ衰退するのか』では、衰退する国家は「自由がないから」ということを言っています(Yuriko的意訳)。
自由がないところでは人は「工夫や改善をしたり、がんばったりしない」です(しても得がないから)。
そのため、単純労働のフェーズをすぎて新しいこと(イノベーション)が求められる時代になると、目に見えて失速するんです。
これ、子育てにも同じことが言えると私は思っていて、子ども自身が自分の自由意志に基づいて行動していないと、その子の能力はどうしても伸び悩みしてしまうように見えるんです。
いろいろな国で、いろいろな話を見聞きしますが、総合するとそんな感じ。
最初は、ほんとにうまくいく
小さい頃は親が決めたこと(ドリルとか、ゲームは1日15分以内のルールとか)に喜んで、または疑問を持たずに従ってきた子どもも、そのうち勉強内容が難しくなっていき、また他の世界の刺激を知るようになると、別の選択をするようになります。
「やらされる」ことに従順にしたがう時期はやがて終わります。
それが、早い子は小学校低学年、通常で高学年~中学生くらいかな、と、観測的・経験的に思います。
親のよろこびよりも、自分がやりたいこと・やりたくないことにフォーカスが移ります。発達の健全な経緯としての自我が出てくるんですね。
毎日のドリルをやりたがらない。隠れてゲームをしたり、答えを写すなどのズルをしたり、ウソをついたりすることを始めます。

そのあと、「やりたいことをやる(能動的)」人になるか、「やりたくないことをやらない(回避的)」な生活になってしまうかにわかれます。
これってけっこう、岐路だと思うんですよね。
「やりたくないこと」を「ただ避けるだけ」の人になるリスク
「やりたいこと」を持つには、「自分で考えたこと、自分が好きなことをいろいろやっていい環境」が必要です。
親が決めたこと・親が了承したことしかできない環境だと、やりたいことも育ちにくいです。稀に「親が決めたこと」と「子どもがやりたいこと」が自然に合致する場合もありますが、そうでないケースの方が圧倒的に多いと思います。
○○なんてダメよ!
それより○○をしなさい。そのほうがためになるよ。
っていってばかりだと、子ども自身の「やりたいこと」が見つけづらくなり、仮に何かに興味をもっても「言ったら怒られる」「どうせ許してもらえない」と諦めるようになります。
やりたいことがないと、勉強の面でいってもそれ以外の面でいっても、高校生以降くらい、けっこうきつくなるんじゃないかなあ、と思います。
例えば親としては勉強をさせたい、いい大学に入ってほしい、海外留学して英語を習得してほしい、なんて思います。
でも、高校受験や高校以降の学習、大学受験や大学以降の学問、留学先での学校や生活は、もう自力でやっていかないとならないです。

そして、「やりたくないことを回避するだけの生活」になっていくと、どうなるか……
「決められたことだけをする」ことが当然になる。
工夫や打開が苦手。
時間がかかること・工程が多いことが苦手。
すぐによい結果が出ることだけを好む。
失敗が怖い。失敗するくらいならやらない。
それが、昨今の日本の教育関連の社会問題の根っこのように、私には思えるのです。
結局、どうすればいいのか。教育移住6年目の私の結論
じゃあ、結局どうすればいいのかな、って考えますよね。
ひとことで結論をいうと、「バランスをとること」。
これに尽きる、と思っています。
私はママとして日本で普通の日本式の教育も経験しているし、
マレーシアの緩い空気の中でのイギリス式インターナショナルスクールも経験しているし、IBの教育もみているし、今はカナダの現地校に子どもたちが通っています。
いろいろな場所でいろいろな教育をみました。
何年もかけてさまざまな立場の友人・知人に話を聞きました。
時には「取材」として、専門家や経営者、芸能人など「成功者」の話を聞いたりも。
いろいろな親がいるけれど、今いるカナダで周囲を見渡してみると、カナダの親は日本の親と比べて「子どもを個人として扱っている(親の支配下におかない)」っていう点は基本としてあるように思います。
(ガチ中華系除く)
もちろん、それが絶対的にいい、といっているわけではないです。良い点も悪い点もあります。

小さな子どもである時代に、規律やよい生活習慣をつけるのも大事。
好きなことだから、ってゲームやスマホばっかりさせてていいわけない。
学校の成績もいいに越したことない。将来の選択肢が広がる。
それは確かです。
でも、この本を読んで、子育ても国家と同じように「今までうまくいっていた」方法に終わりが来て次のフェーズに入る、ということを、子育て中の親は見逃しがちなんじゃないかな、って思ったのです。
そのときに「あ、今がこのときかも」と自覚して、子どもの意思を確認したり、自分の方針を顧みたり、自分も新しい考えを取り入れたりすることが、「バランスをとる」ことに役に立つと思うのです。

っというのが、意外に『国家はなぜ衰退するのか』が子育てに役立つ、って話でした。
この本、言葉がわりと堅いし分量が多くて、読むのはちょっと億劫なので(眠くなっちゃう)、お洗濯やお掃除のときにイヤホンできくとちょうどいいです。
Audibleでママ業が充実、といっても過言でない、かもなくらい活用中なので、ほんとオーディブルおすすめ。無料ってやっぱりうれしいです♡
いま見たら、あの『Wimpy Kid』(邦題:グレッグのダメ日記)が無料になってるし、読みたい(聴きたい)本がホントに多い。3か月99円のプロモ中だそうなので、今がおすすめかもです。
(3か月以内に解約すればそれ以上かからないです。思ったより使わないなと思ったら、また次のプロモ時期を選んで再加入すればOK)




ちなみに、この本の個人的なおすすめは第三章「繁栄と貧困の形成過程」。
この章は、韓国と北朝鮮を例に、ある兄弟(医師と薬剤師の兄弟)が内戦で韓国と北朝鮮にわかれわかれになって50年ぶりに再会すると…というドラマ仕立てで語られ、おもしろいです。
いいなと思ったら応援しよう!

