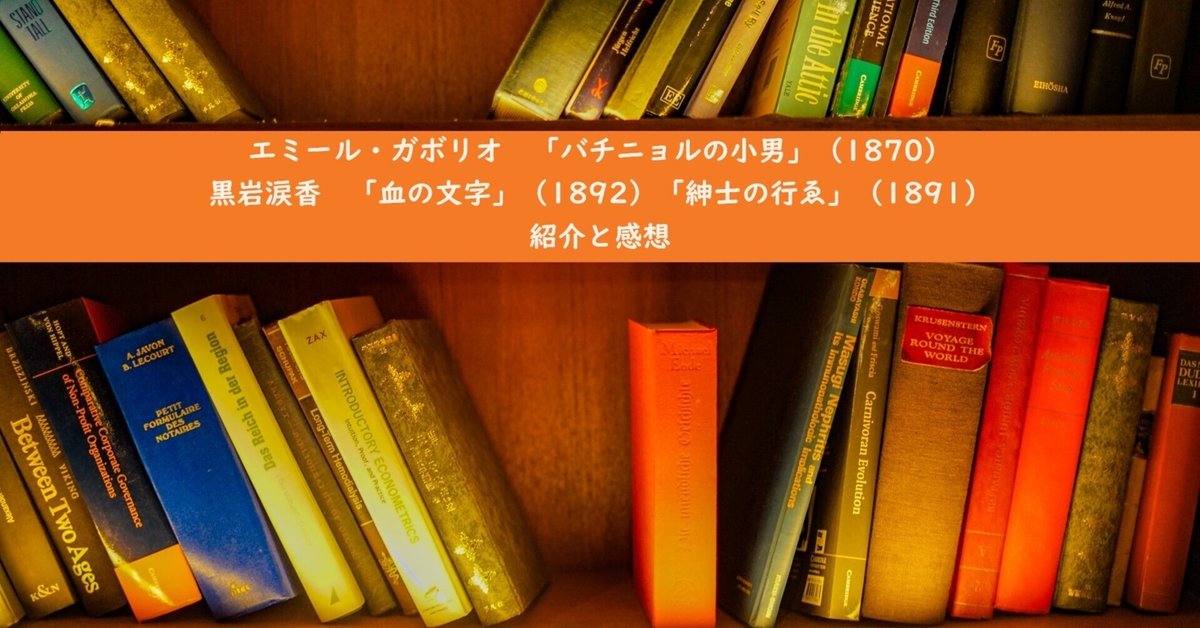
黒岩涙香「血の文字」「紳士の行ゑ」+エミール・ガボリオ「バチニョルの小男」 紹介と感想
黒岩涙香著『黒岩涙香探偵小説選Ⅱ』論創社, 2006
各務三郎編『クイーンの定員Ⅰ 傑作短編で編むミステリー史』光文社, 1992, p.127-203
今回は、エミール・ガボリオの作品を翻案した2作品と、「血の文字」原作である「バチニョルの小男」を紹介したいと思います。
カボリオの原作もホームズとライバルたちの時代に負けない面白い物語ですが、それを涙香がどう調理したのかを観ることで、涙香が論理的な考え方を重視していたのが分かるものとなっていました。
エミール・ガボリオ「バチニョルの小男」Le petit vieux des Batignolles(1870)
あらすじ
J・B・カジミイル・ゴオドユイルという男が新聞社へ持ち込んだ『バチニョルの小男』という原稿。
それは、ゴオドユイルが23歳時、犯罪捜査に関わった際の思い出だった。
ゴオドユイルはメシネ氏という男と知り合いになる。掴みどころのない男に興味津々になったゴオドユイルだが、意外なことからその正体を知ることになった。
メシネ氏に誘われ、モニストロルという男が殺害された現場に同行したゴオドユイル。
死体の傍には血文字が残されており、甥が犯人で片が付くと思われていた。
しかし、ゴオドユイルは死体の表情や血文字の違和感から、事件はそんなに単純ではないのではないかと感じる。
メシネ氏も同意見であったが、甥のモニストロルは犯行を自白していた。
二人は、疑問点が解決されなければ真実は分からないと捜査を始める。
紹介と感想
エミール・ガボリオは、フランス探偵小説の父と呼ばれ、探偵ルコックで知られる作家です。今作が表題作の短編集『バチニョルの小男』(1876)はクイーンの定員にも選ばれています。
本作はフランスの新聞『Le Petit Journal』の1870年7月8日~19日に連載後、上記短編集に収録されました。
現代の目で見ても面白い短編ミステリーだと思いました。
文庫本にして80ページ程と中編程度の分量があり、メシネ氏とゴオドユイルの事件捜査を丁寧に描いています。
ゴオドユイルは頭の切れるワトソン役ですが、経験豊富で大人のメシネ氏は更にその上を行っていました。変な奇人ぶりもなく、落ち着いた探偵役です。
新聞連載だったこともあり、章毎に明確に動きがあるのも読みやすさに繋がっています。
ゴオドユイルが気づく違和感に、物語上でしっかり説明がつけられ、しかも血文字の扱いは物語的にもよい利用のされ方でした。
20年ほど後に発表されるホームズ譚にも負けず劣らずの面白さを兼ね備えており、クイーンの定員に選ばれるのも納得の一作となっています。
また、メシナ氏の妻の存在も重要だと思いました。
今作での議論は短い物でしたが、想像力と柔軟性がある妻と事実を重んじるメシナ氏は分担された探偵であり、分かりやすく事件の可能性を読者へ提示しながら、物語上で様々な議論をするための仕組みとして機能できたと思います。
もしシリーズが続いていたら、この部分を強化して一つの物語上に探偵役、探偵の少し後ろを付いていく語り手、更に別の軸で考えるもう一人の探偵がいる面白いミステリーになったのではと想像しました。
物語上の重要な断片の一つが、当時のフランスの事情を知らなければ難しい箇所があること、犯罪を芸術に例える犯人が凶器を分かりやすく隠しすぎだろうと感じる所はありますが、それを考慮しても現在読んでも違和感なく楽しめる一作となっています。
※『クイーンの定員Ⅰ』所収のバージョンでは、現在ネット上で読む事が出来る原文やkindleで出版されている翻訳とは、一部文章に違いがある箇所があります。
『クイーンの定員Ⅰ』は、メシネ氏の最後の発言の後に後者2つにない文章があることで、ちょっと不自然な感じになっています。
連載時の新聞紙面を確認してみると、該当部分にあたる文章が後者2つと同じく無いので、直前のメシネ氏の発言を受けて翻訳時に拡大解釈をしたのかなと思いました。
多分、メシネ氏の発言は、犯罪を芸術だと思っている犯人へ向けた皮肉だと思われるのですが、真面目に受け取りすぎたのかもしれません。
ただ、『クイーンの定員Ⅰ』の方では、単独刊行の際には省略されている、編集部からの前書きが収録されているのが良い所です。
ちなみに、1870年7月7日の『Le Petit Journal』1面から2面の初めにかけて、この前書きに当たる部分が掲載されており、実際の本文では『クイーンの定員Ⅰ』で訳されている以上の分量で、小説が描こうとしているものや、パリの街並み、ゴオドユイルの凄さについて等々が記載されており、本短編以外のメシネ氏の活躍も示唆されているので、シリーズが続いていたら面白そうという気持ちが湧いてきます。
ゴオドユイルが思い出をつづるという性質上、ゴオドユイルが一人前の探偵となる成長記録としての側面も出たかもしれないと思い、シリーズが続かなかったのが残念です。
本短編が面白かったと思った方は、こちらも読んでみると面白いと思います。
この犯罪記録を書くに当り、小説的な粉飾はすべて剥ぎとり、事実だけを綴った。それにしても、この記録を読めばお判りだと思うが、卑怯、卑劣、醜悪といった、背筋にさむ気が走る、ゾッとする要素が含まれている。
社会に戦を仕掛ける狂人ほど、その結果は正に悲惨な末路をたどらなければならないと、証明しているのである。
参考URL:Le Petit journal | 1870-07-07 | Gallica (bnf.fr)
血の文字(1892/明治二十五年)
あらすじ
ゴヲドシルは、隣人の目科のことを怪しき男と思い興味を抱いていた。
ある時、バチグノールで梅五郎なる老人が殺される事件が発生し、目科が探偵吏であることを知る。
現場にいる警察は、血文字でMONISと残っている事から、甥の藻西太郎が犯人だと検討を付ける。
しかし、血文字が左手で書かれている事、死体が即死で間違いないことから、これは仕組まれたものでは無いかと目科とゴヲドシルは疑いを持つ。
そんな中、逮捕された藻西太郎は事件を自白したのだった。
果たして、この複雑怪奇な状況には、どのような真実が隠されているのだろうか。
紹介と感想
「バチニョルの小男」の涙香による翻案作品です。物語の大筋など、基本的に原点に忠実な作品となっていましたが、だからこそ変更点が目立つものとなっています。
全体的に、ミステリーとして論理の補強をしようとする方向で変更がされており、最も大きいのは本書解説でも触れられていたように、中盤のゴヲドシルと目科の妻とが事件について話し合う場面での追加です。
「なぜ左手で血文字を書いたのか」の部分に議論が足されており、藻西太郎が本当は賢い犯罪者なのではとの疑いを強めるようになっています。
また、原作でのメシナ氏の皮肉と思われる終盤のセリフ部分は、犯人のセリフへと変更されており、「捜査陣が右利きと間違えたまま捜査をしているせいで事件が明るみに出た、完璧にやりすぎてもだめなのだ」と〈芸術家としての犯人像〉を強くするとともに、〈当時のフランスでは字は右手で書かねばならない〉との風習を知らなくても意味が通るようになっています(どちらにしても、即死の時点で犯人の行ったことは無意味なのですが)。
ミステリー部分以外では、最後の場面において、原作以上に倉子が犯罪に関わっているだろうことが匂わされ、事件後の藻西太郎と倉子の人生が直接的に零落していると描かれているのも特徴的な改変でした。
原作から変えた部分をみることで、涙香が論理を意識していたことが分かるようになっており、その部分において価値のある作品となっています。
「人を殺して後でその血で文字を書き付けるほど落ち着いた曲者がまさかに老人の左の手を右の手とは間違えますまい。ですから藻西のほかに曲者があるとすれば、その曲者は決して老人の左の手へ血は付けません。必ずどう見ても老人が自分で書いたに違いないと思われるように右の手へ付けて置きます。ところがこれと事かわり、その曲者を私の言う通り藻西自身だとすれば全く違ッて参ります。どうでも左の手へ血を付けて置かねばならぬのです」
目科の妻が語る、血文字の議論についての一部分
紳士の行ゑ(1891/明治二十四年)
あらすじ
巴里府マレー区の豪商・塩田丹三が失踪した。
事件に乗り出した探偵・散倉は、入念な聞き込みを続け、容疑者として虎太夫妻を割り出した。
塩田丹三が失踪当時持参していた五千法を隠し持っており、犯人に間違いなしと思われたが、取り調べで否認を続ける二人。
未だに塩田丹三も見つからず。散倉は更に事件を調べて行く。
紹介と感想
原作は『バチニョルの小男』所収の「失踪」(Étienne Émile Gaboriau)です。
読者は推理が出来るわけではなく、散倉の捜査過程を読みながら事件の行方を追っていく事になります。
真相は、現在では誰もが考え付くほど様々な小説で使われた内容になりますが、発表年代を考えると十分に驚きがあったと思われます。
冷静に考えると、犯人(あえて犯人と書きますが)の策略は、結構悪辣なものだと感じました。
「ハイ成績の報告に参りました。それとも一夜の間に探ッたのが早過ぎて粗末だろうとおっしゃれば、これから帰宅してお気に入る刻限まで昼寝するだけのことです。私の探ッたのが早過ぎますか」
一日で事件を調べ自信に溢れる散倉老人の言葉
