
【ノーベル文学賞 2024】 レイチェル・カスク 『アウトライン』 Rachel Cusk "Outline"
[0] ノーベル文学賞2024
これから、私が今年2024年のノーベル文学賞に最も近いと考えている作家とその作品を、ひとつずつ紹介していく。もちろん、先日動画と記事で私が発表した予想リストに載せた作家が中心となる。
5位予想 Germany ドイツ
★Jenny Erpenbeck ジェニー・エルペンベック
・Yoko Tawada 多和田葉子
・Esther Kinsky エスタ・キンスキー
4位予想 United Kingdom イギリス
★Rachel Cusk レイチェル・カスク
3位予想 France フランス
★Hélène Cixous エレン・シクスー(エレーヌ・シクスー)
2位予想 United States アメリカ
★Joyce Carol Oates ジョイス・キャロル・オーツ
・Marilynne Robinson マリリン・ロビンソン
1位予想 Denmark デンマーク
★Naja Marie Aidt ネイヤ・マリー・アイト
・Solvej Balle ソルベイ・バッレ
早速紹介していこう。
一人目は、イギリスの レイチェル・カスク Rachel Cusk 氏。
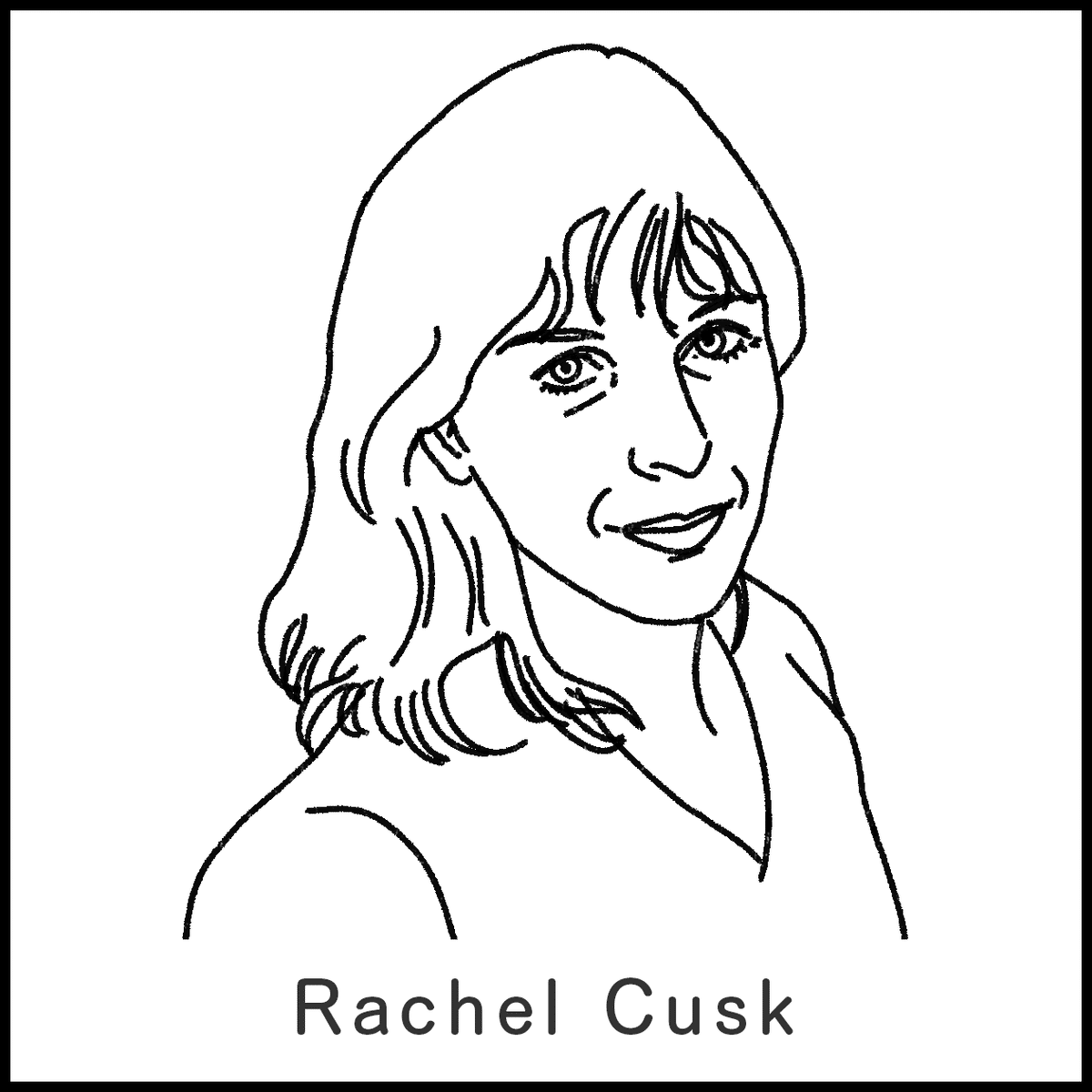
Rachel Cusk レイチェル・カスク
ノベル・コミッティの前議長で、昨年までノーベル文学賞の選考委員6名のメンバーのうちの一人を務めていたペール・ヴェストベリ Per Wästberg 氏のお気に入り。今年発売されたばかりの最新作『parade(パレード)』が早速6月15日にノーベル図書館に所蔵された。
彼女の名を一躍広めた Outline 3部作の1作目『Outline(アウトライン)』を読んでみることにした。

邦訳が出ていたのでチェックしてみたのだが、これは読みにくいので私はオススメしない。出版社の入れ知恵かもしれないが、邦題の『愛し続けられない人々』も的外れだ。(これについては後ほど触れよう。) あまりに不自然な日本語で、私は10ページが限界だった。 原書の英文にあたってみたところ、この翻訳者は冒頭1行目から構文を取り違えていたことが判明した。(直前まで黄リー教をやっていたタイミングなのが幸いした。)ところどころ「上手いな!」と感じさせる訳もあったのだが、おそらくAIによる自動翻訳でも使っていて、たまに出るまぐれで上手く訳せた文章の一つだろう。とにかく不自然なのだ。1冊全体を通してこの日本語を読み続けるのは私にはキツかった。結局、原書のペーパーバックとkindle版で読むことに落ち着いた。
[1] レイチェル・カスク 『 アウトライン 』
Rachel Cusk "Outline"

この作品のAmazon販売ページのレビューに「退屈」という感想がいくつかあった。たしかに、劇的な、ドラマ性の高い物語を期待して読むと拍子抜けするだろう。この作品は、主人公である語り手フェイが様々な人物の語りを聞いていく、という形をとっていて、フェイの物語自体を期待して読み進めても、彼女のストーリーはなかなか進まない。
そして、読み進めていく中で徐々に気づかされるのは、この作品の主眼は「主人公の物語」の方にではなく、むしろ主人公が話を聞いていくことになる「登場人物たちの語り」の方にあり、それらの語りを主人公が間接的に描写していくことにあるのではないか?という可能性である。
つまり、わくわくする展開を期待してストーリーを追いかけるような読み方から、何らかの別の形に読み方を変える、「読みの意識の切り替え」を求められているような気がしてくるのだ。(これはプルースト『失われた時を求めて』にも同様のことが言えるだろう)
ここに気づかなかった人は、この作品を「退屈」と感じてしまっただろう。
一方で、この違和感のようなものにいち早く気づいて、読み方を切り替えた人にとって、本作には今まで見えなかった新しい文学の景色が広がっていく。
[2] レイチェル・カスクが『アウトライン』で生み出した文体は斬新なのか?
まず目につくのは、この作品の記述形式。 おおまかに、次の三つのタイプの文が、不規則に入り乱れた形になっている。
[1] 主人公フェイによる、自身に関することや自身の視点で語った地の文
→ F
[2] フェイが物語内で出会った人物の語った内容を【フェイの語りの中で】間接文で(鍵カッコを用いずに)記述した、「間接の間接」の形をとった文
→ F(x)
[3] 上記[2]に近いが、ある人物からフェイに語られた内容を【フェイの語りの中で】直接文の形で(鍵カッコを用いて)記述した文
→ F(y)
人称で考えるなら、Fは一人称の文、F(x)とF(y)は一人称の語りの中で描写された三人称の文、といったところだろうか。
私は文学の専門家ではないので正確には分からないが、これはあの有名な「自由間接話法」と呼ばれるものと同じなのだろうか?
上記のF(x)がそれに該当すると思うのだが、このFとF(x)とF(y)が入り乱れる形は、自由間接話法と呼ばれる手法とはまた微妙に異なる、地味に斬新な記述スタイルではないかと思うのだ。
ぼーっと読んでいると見過ごしてしまいそうな仕掛けではあるが、そこに気づいて、意識しながら読んでいても、これらFとF(x)とF(y)が入り乱れた文章と付き合っていると、徐々に、どこからどこまでがフェイ自身のこと【F】で、どこからどこまでがフェイの語る他の人物のこと【F(w)やF(x)】なのか、「人称の境界線」が曖昧になっていくような不思議な感覚を味わうことになる。
[3] 読み方の角度を少し変えてみる
本の読み方は人それぞれであるが、本作のような、いわゆる「典型的な小説」を読む感覚でページを捲っていくと、何らかの読みにくさを感じさせる作品に挑む際、読み方の角度を少し変えてみて、勝手に楽しんでしまう、という方法を私は提案オススメしたい。
その一つとして「繰り返している部分をみつける」という方法がある。作品をある程度まで読み進めた段階で、何らかのパターン、繰り返し、周期性のある部分を見つけ出して、勝手に「お決まりの流れがある」と見立ててしまうのだ。
この方法を本作に当てはめてみるなら、最初の1、2章までを読み進めた段階で、下記のような、「基本形」とでも呼びたくなるような型がある気がしてこないだろうか。
[1] ある登場人物からフェイに語られた概要がF(x)とF(y)の形で、フェイの語りの中で描写される
[2] それに対してフェイが、
[2-1] Fの形、またはF(x)の中で(!!)指摘していく
[2-2] 何も触れずにFとF(x)とF(y)の形で描写に徹する
この「基本形」が各章ごとに繰り返される構造になっている、と勝手に予想を立てて、読み進めていく。
つまり本作は、次々に登場する人物の語る概要をケース1、ケース2、ケース3… というふうにケーススタディの各事例のように捉えて、それらの各ケースに対してフェイが反応したりしなかったり… という視点で読んでいくことも可能な形になっているのだ、と。
このように見做して、読み方を切り替えると、本作は「退屈な作品」から一挙に「続きが気になる作品」に、見え方が変わらないだろうか?
次はどのような人物が登場して、どのような概要が語られ、それに対してフェイがどのような反応をするのか、あるいは反応せずに描写に徹するのか。
[4] 人は要約してしまう生き物なのか
もう一つ、この作品を語る上で非常に重要な仕掛けがある、と私は考える。
それは、本質的に「語り」というものは疑わしい、という視点の導入である。 実は、本作は最初から最後まで延々とそこを指摘しているのだが、残念ながら、他のレビューなどをざっと確認する限り、この点に気づいている人は私以外にはいないようだ。
この作品の登場人物たちは、自らの人生や、自身に起こった出来事の概要(Outlineアウトライン)をフェイに語っていくが、それらは、事実の通りに、時系列順に、正確に、描写されたものではなく、何らかの意思や都合によって加工されたものになっている。
私は最近、文学について(というよりも本を読むこと全般についてかもしれないが)、ある一つの気づきを得た。
それは「他人の要約は不快である」ということだ。
これは私のような捻くれた人間に特有の、個人的な感覚なのかもしれないが、本作を読んでいると、まさにこの「他人によって要約された概要」の不快さのようなものが延々と指摘されていることに気づかされるのだ。
最終章に登場した アン Anne という人物が、種明かしのように、これらの不快さ、疑わしさを summing up(要約)という言葉で端的に言い表している。
※ただし、ここで言及されている要約は、「他人からされる要約」ということだけではなく、様々なものごとを簡易にひとことでまとめようとしてしまう、要約という「行為そのもの」についてであることは注意が必要だ。(誤読しないように。)

本文の最終章から少し引用をさせてほしい。
(日本語訳は私の直訳。構文のとり間違え、誤訳などあったら申し訳🙏)
Lately, since the incident ‒ now that things had got harder to explain, and the explanations were harsher and bleaker ‒ even her closest friends had started to tell her to stop talking about it, as though by talking about it she made it continue to exist.
最近、その事件以来 - 今や物事がより説明しづらくなり、 説明がより不快さ、暗さを増してきたので、彼女の最も親しい友人達でさえ、 彼女がそれについて語るのをやめるよう言い始めていた。 まるで、それを話題にすることによって彼女がそのことを存在させ続ている、と言わんばかりに。
Yet if people were silent about the things that had happened to them, was something not being betrayed, even if only the version of themselves that had experienced them ?
しかし、もし人々が自分に起こったことについて黙るのであれば、 何かが裏切られていないのであろうか? たとえその起こったことを経験した彼ら自身のversion(見解?)のみであったとしても。
It was never said of history, for instance, that it shouldnʼt be talked about; on the contrary, in terms of history silence was forgetting, and it was the thing people feared most of all, when it was their own history that was at risk of being forgotten.
例えば、今までに歴史についてこんなふうに言われたことは一度もない。 それは話すべきことではない。 むしろ、歴史という観点から見てみれば、沈黙は忘却であり、 そしてそれは人々の最も恐れることであった、 それが、忘れ去られる危機にあるような彼ら自身の歴史である場合には。
And history, really, was invisible, though its monuments still stood. The making of the monuments was half of it, but the rest was interpretation.
そして歴史は、実際には目に見えないものであった、 その記念碑がまだ立っていたとしても。 記念碑を建てることはその半分であり、残りは解釈であった。
Yet there was something worse than forgetting, which was misrepresentation, bias, the selective presentation of events. The truth had to be represented:
しかし、忘却よりも悪い何かががあった。
それは、誤った解釈、偏見、出来事の選択的な提示、である。
真実が提示されなければならなかった。
人の「語り」とは、自身の偏見から、実際に起こった出来事に対して事実とは異なる誤った解釈を施し、その出来事の全体ではなく、恣意的に部分を選択して提示して、話を筋道立てるものではないだろうか。
もちろん、この「偏見」や「誤った解釈」というのは、様々な程度があるはずだ。 事実とほぼ同じだが微妙に細部が異なる、というものから、事実とは大きくかけ離れたようなものまで。 が、その程度が事実に近い「微妙なズラし」であればあるほど、語りの疑わしさは増すように思われる。
現在、私が主な活動の場としているYouTube上では、様々な配信者が文学作品を解説した動画を配信している。その中でも例えば、中田敦彦が2020年に配信したドストエフスキー『罪と罰』を解説した動画の中で、中田は該当作品を「漫画の『デスノート』と同じなんですよ!」と断言調で雑な要約をしている。
『罪と罰』を読んだことのある人であれば、思わず首を傾げたくなる危うい発言に感じるだろう。たしかに上記二作は部分的に内容が重なるような箇所もあるだろうが「同じ」ではない。ラスコーリニコフの心理はひと言では説明できない。ひと言では説明できないから、何百ものページを割いてその心の動きを追っていき、ラスコーリニコフ本人、また、ズヴィドリガイロフなど別の者の口を通して複数の角度から語らせることで、直接ではなく、間接的にその輪郭を浮かび上がらせるようなアプローチがとられているのだ。
つまり、『罪と罰』の内容、ラスコーリニコフの心理は、
ひとことでは【 要 約 で き な い 】
作品の中に入りこみ、一つ一つの言葉をじっくりと味わいながら、『罪と罰』の世界を冒険した者であれば、中田の雑な要約は「不快」以外の何ものでもないはずだ。 なお、中田は『罪と罰』の原作の小説を読んだのではなく、二次創作された漫画版を読み、上記の解説動画を出している。 つまり、漫画版に「要約」されたものを読み、その内容をさらに「要約」しているのだ。『罪と罰』の中で実際に語られた言葉のニュアンスを感じ取れていないのも当然であろう。
いま、雑な要約の代表例として中田敦彦に言及したが、これは「書評」と呼ばれる行為全般にも指摘できる危うさであろう。
私には一貫したポリシーがあって、文学YouTuberという名前で活動していながら、「書評」という行為は基本的には行わない。理由は様々あって一言では説明が難しかったのだが、上記の気づきを得て、「他人から聞かされる要約が不快なのだから、自分からはやらない」という理由が今のところ最も腹に落ちたものである気がしている。
本作に話を戻そう。
第1章でフェイは、アテネに向かう飛行機の中で、隣の席に座った男性から、彼の人生の概要を聞かされる。(この人物は本作では名前が与えられず、最後まで「隣の席の人」と記述される。)この「概要」は、彼にとって都合の悪い事実が巧妙に省かれていたことが途中で判明する…
[5] 邦題 『愛し続けられない人々』 について
本作で人生の概要(Outline)を語る登場人物たちは、離婚した中年が多い。
なぜか?
これは私のいち解釈に過ぎないが、おそらく、その人物が「概要」を語る際に、離婚した相手側の詳細を伏せて、自分の都合の良い方向に概要を整形しやすいからではないか、と私は思っている。
つまり、作品の設定上、本作の特性上、離婚を経験している人物を登場させた方が都合が良いからでないだろうか。
本作の発表直前、2013年夏のガーディアン誌のインタビュー記事にて、カスク氏は、自身の結婚生活における暴露的な側面の強かった前作『Aftermath(余波)』を creative death (想像的な死)と述べて、Outlineへ向けての文体改造の過程を語っている。
Finding form as a writer, she argues, has always been her most important task – it took two years to hit upon Outline's outline.
作家としてフォームを見つけることは、常に自身の最重要タスクであった、と彼女は主張した - "Outline"のアウトラインに辿り着くのに2年かかった。
"Just as a person, don't you sometimes get sick of being yourself and want to be the thing you aren't? But you are the thing you are – to me, that is style. It is relatively bonded to self and there is not a lot you can do about it. Form is different."
「人として、時々、自分自身であることに嫌気がさして、自分自身でないものになりたくなることってない?だけど、あなたはあなた自身なのよ - 私にとって、それがスタイル。それは比較的自分自身と結びついていて、それについて自分ができることは多くない。フォームは異なる。」
"I'm certain autobiography is increasingly the only form in all the arts. Description, character – these are dead or dying in reality as well as in art."
「私は確信しているが、オートバイオグラフィはますます全てのアートにおける唯一のフォームになりつつある。描写、人物像は - それらは死んだ、あるいは死につつある、現実の世界と同様、アートにおいても。」
この抽出も「要約」ではないか?と言われると参ってしまうが笑。
(より正確な記事内容については原文を自身で見つけて参照してほしい。)
ともあれ、本作『Outline(アウトライン)』は、オートバイオグラフィの形を採用した、カスク氏の自伝的な側面が強い作品のようだ。
さて、ここまでお読みいただいて、本作の邦訳版につけられた邦題、『愛し続けられない人々』をどう思うだろうか?
「離婚した男女の愛の物語」という感想を書いてしまっているレビューをいくつも見かけたが…
こういった、安易に対象の内容をひとことでまとめる行為は、まさにこの作品の中で批判的に指摘されていた「要約(summing up)」の一種ではないのか?
何とも皮肉なものである。
2024.07.01 文学YouTuber ムー
