
【大学講演】様々な文脈を持つことが”しなやかさ”と”強さ”を持つ
まずはじめに
今回の記事は少し長くなります。記事を書くつもりはなかったのですが、今回講演をさせていただいた大学生の皆さんの感想文を1枚1枚読んでいると、自分の方が心を動かされていることに気づき、この感情を何らかの形で出したいと思い、備忘録のように綴りたいと思い、思うままに書いています。
書いていて少し恥ずかしい部分や、わかりにくい箇所などもあるかもしれませんが、飛ばしながら読んでもらえたら嬉しいです。
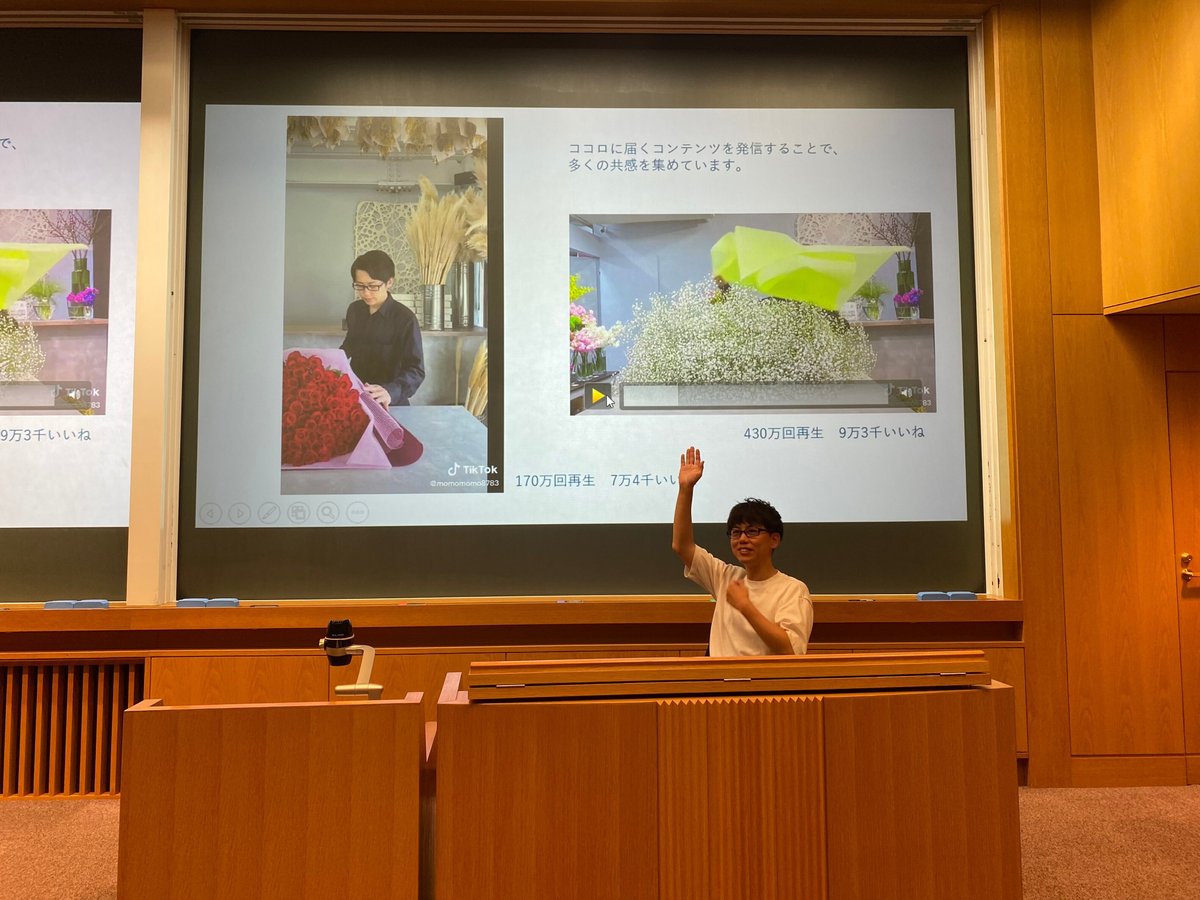
私は大阪でフラワーギフトや花装飾を専門とするMORIYAの代表をしている森俊弥といいます。
その傍らで、公益社団法人吹田青年会議所理事長(2023年度)、一般社団法人Creator Agency代表理事、その他、地域の団体の代表や、いくつかの行政機関の審議員・アドバイザーなどを務めており、今回は大阪学院さんから吹田で活動している人から大学生に対して講演をする【吹田学】の担当として依頼を受け、お話をさせていただきました。


活動内容
➀吹田青年会議所では、様々な公益的な活動を紹介し、社会に対して今足りていないと自分自身が感じる課題の根本的な原因を追究し、その解決のために実験的な思考、実験的なアクションを通じて社会をポジティブな方向に変える活動について
②同時に吹田市内で2023年すいたフェスタ実行委員長や、吹田市シティプロモーションアドバイザー、メイシアターの評議員、IKiRUフェスティバル実行委員長など、地域での様々な役割や活動について
③MORIYAでは、新型コロナウイルス感染症下で実施した、桜の無料路上配布、吹田市内の幼稚園、保育園、小中学校へのお花の寄付(2度で約15000本の寄付)、飲食店向けのテイクアウト支援のためのお花の寄付などについて
④Creator Agency代表理事として、インフルエンサーが100人以上集まるSNS EXPO 2023 実行委員長としての活動
などの様々な活動を、別のコミュニティごとに行っていることを冒頭で説明した上で(ここはそこまで重要ではない)

それぞれのコミュニティで活動している
自分は、中学時代、高校時代、大学時代、クラスや部活、バイトの自分が少しずつ違う自分のキャラがあるのと同じように、それぞれが別個の役割を担っていることに応じて違う自分がいると思う。ただ、それは全て本物の自分の姿であり、そこの整合性を取ろうとしなくても大丈夫。言語化せずに、そのままを複雑性のまま受け入れることがとても大切で、その先に、一つのコミュニティに依存することなく、多様な価値観に触れながら、一つの答えにこだわりすぎない、強くしなやかな竹のような自分を見出すことができる。
そして、それぞれのコミュニティでは、自分に求められる能力や役割が異なっていて、それはRPGで言う、勇者、魔法使い、戦士、僧侶、剣士、盗賊、遊び人などの役職や、それに伴う、ちから、ぼうぎょ力、知恵、すばやさ、かしこさなどの能力値があり、コミュニティごとに、それぞれの経験によって自分の能力値が積み重なっていく
その先に
自分だけにしかない特有の役割であったり、能力、考え方を持ちうることになる。それこそが希少性であり、今の世の中を自分らしく生きるための、強みにもなってくると思う。単一のコミュニティだけに属していると、確かに心地いい部分もあるかもしれないですが、それだけに抜け出すことができず、外からの要因に脆く、様々な状況が変わるスピードが速まってきている今ではデメリットが大きくなってしまう。
また、心地いいだけではなく、役割として、そこのコミュニティにいることがストレスになっている場合であっても、同じように抜け出すことが難しく、新しいコミュニティに行くための一歩も踏み出しにくくなっているとも思う。
仕事であればお得意様が一社だけの事業ほど、何かがあった時の状況に脆い商売はないというのは多くの人が同意するように、コミュニティにおける自分も同じような側面があります。
だからこそ、いきなり新しいコミュニティに属するということは難しくとも、そのために、新しい刺激を自分に与え続けてほしい。例えば、学校への通学中の道を少し遠回りしてみるとか、行ったことがない土地を訪問したり、食べたことがないものを食べたり、本を読んでみるなど、なんでもいいのでやったことがないことをやって欲しいと。
好奇心を持つ
そうすると、世の中にあるたくさんのことに好奇心を持つようになります。それが自分の好き嫌いの分野内であっても大丈夫です。そうしている内に、知らず知らず新しいコミュニティに属する一歩を自分から踏んでいることに気づくことができるようになります。

好奇心を持って行動をしていると、自分の外側にある色々なことに目がいくようになります。あれがもっとこうなればいいのにと。自分の周りや、コミュニティ内、社会の中で、もっとこうなったら良いのにと、課題感が出てきて、もしかすると、それに対する行動を取りたくなってくるかもしれません。
そうなると、社会に対して何らかのアクションを起こそうということになるのですが、どうしても自分ひとりだけでは、社会や世の中を変えていく事は難しいです。それは、コミュニティや社会が人の集まりだからです。自分ひとりだけの行動では、その課題感は共有されませんし、場合によっては自分よがりに見えて、協力してもらえないばかりか、足を引っ張られる可能性もあります。
RPGでも触れましたが、人はそれぞれに得意・不得意があります。自分の得意と、他の人の得意を掛け合わして、自分の不得意を補ってもらい、他人の不得意を補うことで、自分だけでは行くことができない遠くの目的地まで行くことが可能になります。社会を変えるためにはそれだけ、仲間の存在が必要となってきます。
そのために、自分が持っている課題に対して【共感】を持って人を集め、課題を解決した先の未来を一緒にワクワクしてくれるビジョンを一緒に共有していくことがとても重要です。
ただ、その共感も、自分のエゴばかりだと、共感の押し売りになってしまいます。人に共感を求めるならば、自分が共感を持ちやすい自分になることも重要です。それは、なんでも受け入れるのではなく、〇〇でなければならないという単一の答えに縛られるのではなく、様々な可能性などを勘案した上で、ベターな答えをその場その場ですり合わせしていくということです。自分が変わることも、社会が変わることも、それが自然であるということでそのまま受け入れられる自分を持ち、相手と自分の共通点を見出しながら共感し合うことは、強さと柔軟性という一見異なる性質のものを一緒に合体させることにも繋がります。それが日本人的な美意識で【竹】と表現しました。
まさに、多様な価値観があるということを認め合うダイバーシティとは、日本人の美意識の中に存在していると思っています。だからこそ、僕たちは仲間と共に楽しみながら、共感し合いながら、世の中を変えられる可能性を持っていると信じています。
どこかで大学生の皆さんとも、仲間として一緒に活動できる機会があることを祈りつつ、このようなことをお話させていただきました。
最後に
アンケートでは、講演内容をそのまま、まとめただけの感想文もありましたが、自分自身の言葉で、こうなっていきたい、社会と関わりたい、避けていた地元のコミュニティに積極的に参加しようと思う、新しいことに挑戦していきたい、仲間と共に新しい社会を創っていきたいと、多くの大学生の方が書いてくれました。講演後、SNSのDMで質問をしてくれたりと、熱を込めてお話をした結果が少しでもあったのかと胸が熱くなりました。
僕もまだまだやりたいけど、試していないことばかりです。それに、試していないことをやってみても、また新しいやってみたいことがどんどん生まれてくると思います。それを全部実行しようと思うと、やっぱりたくさんの仲間が必要です。これからも、たくさんの仲間の皆様と共に実験的な挑戦をし続けていきます。
