戦争は一国ではできない。
秋田茂、桃木至朗編著『グローバルヒストリーと戦争』(大阪大学出版会、2016年)
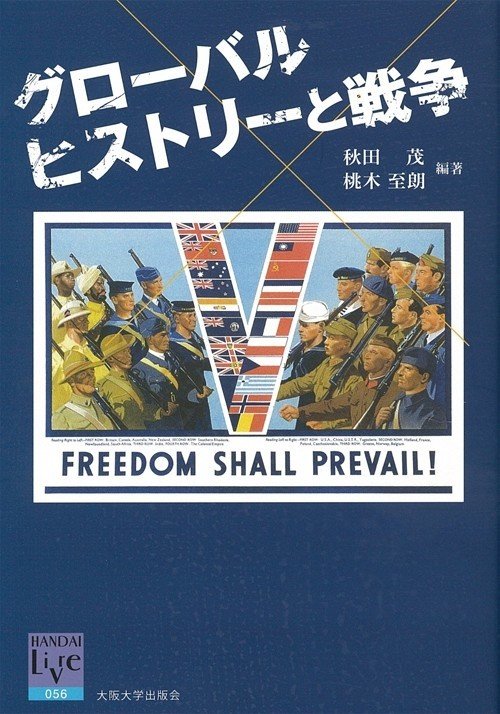
1 「国民国家」の限界
まだまだ気になる中東の情勢。戦争なんて、誰も望んでいない(…はず)と思いますが、人間の歴史は戦争の歴史とはよく言われることです。いつになったら、戦争の恐怖から人は解放されるのでしょうかね。
さて、今回の一冊は、その「戦争」を切り口にして、グローバルヒストリーを俯瞰する論文集です。
世界を見渡してみますと、ブレグジットが迫り、アメリカファーストやそれを真似する国が増え、ロシアや中国の覇権指向は強まるばかりです。多国間協調の時代から、一国独走を目指す枠組みに世界がシフトしているように感じます。
歴史の逆行、という向きもありましょうが、歴史は直線的な進歩を意味しません。むしろらせんを描いてゆっくりと前に進む、そんなものでしょうか。もしかすると、グローバル化という趨勢が歴史の徒花となることもあります。今のところ、それを判断することはできませんが…。
歴史学の分野においては、従来の「国民国家」をベースにした一国史研究の枠組みでは見落としてしまう事象が多く、研究のパラダイムが変わる時期に来ています。もちろん、地域史の研究は重要な研究分野でありますが、近代以降に成立した国民国家という条件の中で歴史を研究することでは新しい歴史像を結ぶことができません。
そのような視点から、最近の歴史研究では一国内や一地域内の事象にとどまらず、多国間の関係や交渉を俯瞰的に研究する、グローバルヒストリーが志向されています。本書もそのような視点に立つ研究を集めた論文集です。
2 内容
本書に収められているのは、次の12の論文です。少し長くなりますが、目次をご紹介します。
序章 グローバルヒストリーと戦争 (秋田 茂・桃木至朗)
一 戦争と秩序形成―地域秩序から国際秩序へ
二 戦争と歴史認識、自意識・他者認識、世界像
三 本書の構成
第一章 戦後七〇年と二一世紀の東アジア―「戦争の語り」と歴史認識― (田中 仁)
一 東アジア地域秩序の再編と中国政治
二 一九九五年、東アジア・メディア空間の交錯
三 二一世紀日本における日中戦争史研究
四 戦後七〇年と東アジア
第二章 冷戦とアジアの経済開発 (秋田 茂)
一 冷戦と脱植民地化・経済開発
二 開発援助とインドの工業化―B・K・ネルーの活躍
三 ジョンソン政権と駐米大使B・K・ネルー―食糧危機への対応
四 「アジアの開発の時代」と主体性
第三章 太平洋戦争後の知的交流の再生―アメリカ研究者とロックフェラー財団― (中嶋啓雄)
一 原初的アメリカ研究コミュニティとロックフェラー家
二 戦後日米知的交流の起源
三 国際文化会館とロックフェラー財団―自由主義的国際主義と冷戦の狭間で
四 安保騒動と知的交流の動揺
五 一つの時代の終わり
第四章 第一次世界大戦と現代グローバル社会の到来―アメリカ参戦の歴史的意義― (中野耕太郎)
一 世界史の「断絶」―第一次世界大戦の衝撃
二 アメリカの参戦―ウィルソン外交とモンロー主義のグローバル化
三 アメリカの「海外領土」と総力戦
四 国内の「周縁」と総力戦― 人種マイノリティの戦争
五 もうひとつの国際主義と新国際秩序
第五章 軍事か経済か?
―帝政期ロシアの義勇艦隊に見る軍事力と国際関係― (左近幸村)
一 ロシア義勇艦隊とは何か
二 一九世紀の義勇艦隊
三 セルゲイ・ヴィッテの改革案
四 日露戦争後の方向転換
五 義勇艦隊の連続と断絶
第六章 山に生える銃―ベトナム北部山地から見る火器の世界史― (岡田雅志)
一 山地から見る火器の世界史
二 東部ユーラシアの火器の時代とその後
三 華人の世紀と山地における「火器の時代」
四 火器を通じた山地社会と国家の関係
五 山地の火器の帰結
第七章 もうひとつの「黒船来航」―クリミア戦争と大阪の村々― (後藤敦史)
一 グローバルからローカルまでの四つの層
二 中田治左衛門が生きた時代―ローカルな層
三 クリミア戦争と極東海域―グローバル/リージョナルな層
四 ロシアの対日外交とクリミア戦争―ナショナルな層 その一
五 幕府の大阪湾防備とディアナ号来航―ナショナルな層 その二
六 動員される村の人びと― 再びローカルな層
七 四つの層からみたクリミア戦争
第八章 財政軍事国家スウェーデンの複合政体と多国籍性―コイエット家の事績を中心に― (古谷大輔)
一 そこにスウェーデン人がいた―ゼーランディア城包囲戦
二 近世ヨーロッパにおける複合的な政治秩序と財政軍事国家
三 財政軍事国家と外来家門―コイエット家の事績
四 財政軍事国家を支える多国籍性―技術・情報・資金
五 財政軍事国家としての経験のヨーロッパへの還元―軍事と外交
六 財政軍事国家スウェーデンが提供した信用―軍事から学術へ
第九章 ポルトガル人はなぜ種子島へ上陸したのか (伊川健二)
一 日欧関係成立の世界史的意義
二 多国間関係史という方法
三 ポルトガル人たちはいつ、どこへ上陸したのか?
四 グローバルヒストリーのなかの一六世紀日本
五 ポルトガル人はなぜ種子島へ上陸したのか
第十章 「戦後五〇年」と「戦後七〇年」―抗元戦争後の大越(ベトナム)における国際秩序・国家理念・政治体制― (桃木至朗)
一 抗元戦争と大越陳朝の変容
二 世界戦争としてのクビライの大越侵攻
三 戦後の陳朝
四 陳朝国家の脱戦後レジーム
五 近世ベトナムにおける「伝統」の範型
第十一章 モンゴル帝国の東アジア経略と日中交流 (中村 翼)
一 西嶋定生「東アジア世界」論の視座
二 モンゴル時代以前の東アジア海域世界と日中交流
三 モンゴル帝国の東アジア経略と日本
四 元末明初の倭寇と「不臣之国」日本
五 日本と東アジアの「つながり」を考える
第十二章 「白村江の戦い」再考 (市 大樹)
一 白村江の戦いに関するイメージ
二 倭国の朝鮮半島への派兵
三 白村江の戦いの歴史的位置づけ
目次をご覧になって分かる通り、現代から時代を遡っていく構成となっており、どの論文も大変読みごたえがあります。通読しなくても、興味のある論文を拾い読み、というのも面白いのではないでしょうか。
第5章で取り上げられている「ロシア義勇艦隊」なんて、この論文を読むまでは浅学にして知りませんでした。第9章も、日本への鉄砲伝来も1543年という年代を必ず覚えているほど有名な事象ですが、その年代確定にも疑義があることが本論文からわかります。そもそも、なぜポルトガル人は種子島を目指したのかを、当時の東アジア海域をめぐる多くのプレイヤーを俯瞰しながら論じていくミステリーのような趣です。
私が研究していた時代に最も近く、そして、卒論などでも大変参考にさせていただいた古谷先生の第8章が個人的にはもっとも興味深い論文でした。17世紀の台湾はオランダ植民地でしたが、1662年に明の遺臣である鄭成功がオランダの本拠地、ゼーランディア城を落として台湾を奪います。この時、台湾を収めていた行政長官がフレデリック・コイエットというスウェーデン人でした。なぜ、スウェーデンの名門貴族がオランダの東インド会社に雇われ、台湾の長官まで勤めていたのか。彼をめぐるネットワークを解き明かすことで、当時のスウェーデンの国家の特質に迫っていきます。ちなみに、このフレデリックですが、台湾に来る前には出島のカピタンとして日本に着任しており、最初期に日本に訪れたスウェーデン人でもあります。
第10章、第11章も続けて読むと、13世紀から14世紀において、元朝がいかにアジア世界にインパクトを持っていたかがよく分かりますし、第12章も日本史でおなじみの白村江の戦いを東アジア史の文脈に置くことで、違った姿を見せてくれます。
3 実際はけっこう、難しい…
いずれの論文も、一国や一地域にとどまる歴史ではなく、複数のプレイヤーの関係性を見ることで、今までのイメージとは異なった歴史像を結んでいます。
多くの地域にまたがる歴史研究は、成果については確かに豊富かとは思います。ですが、実際に手を付けるとなるとなかなか覚悟がいることです。そこに立ちはだかるのは語学の壁…
複数の国や地域を扱うとなると、それだけ読む史料、文献も多言語に及びます。おまけに、時代が古くなればなるほど、文法なども現代とは違うため、実際に史料を読むのは一苦労です。外国語を一つ習得するのも大変ですが、複数の国の歴史を同時に扱うための語学の習得というのは想像を絶するものがあります。
ですが、これからはこのような歴史研究がますます重要であり、そして、主流になってくるものと思われます。一つの国、地域からでは見えない歴史は、現代を生きる我々にも多くの示唆を与えてくれるはずです。
ちなみに、大阪大学出版会からは、本書に関連して、『グローバルヒストリーと帝国』、『歴史学のフロンティア―地域から問い直す国民国家史観』という本も出ておりますのでご参考に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
