
Tokyo Undergroundよもヤバ話●’70-’80/地下にうごめくロックンロールバンドたち第6話『“鵺院”〜“The Ding-A-Lings”/中村清●後編』
取材・文◎カスヤトシアキ
話/中村清(ミュージシャン)
V T R◎Andy Shiono
『真夏の蝉時雨』
子供の頃は夏の日が何よりも好きだった。
蝉が鳴き始め、森を見上げると、空に浮かぶ雲がぐるぐると回っている気がして、わくわくしたのを覚えている。日暮れ時に景色が赤くなるまで、時間を惜しむようにして遊んだ。家のまえが芝生畑だったので、ずっと寝転んでいたのだ。あの時はいったい何を想っていたのだろう。何気なく雲を眺めていたあの時間は、もう随分と昔のほうに流れて行ってしまった気がする。
繰り返す毎日を意識するようになる頃、やらなくちゃならないことが次々に出てきて、夏の日差しを邪魔した。一日が短くなり、日陰だけが長く伸びていくのだった。やがて生活をするようになると、夏の暑さは余計な汗になって、仕事と現実の隙間を流れていく。大好きだった日差しを避け、涼しい部屋で息を潜めるように過ごしだす頃、あれだけ長かった夏の日が、あっという間に過ぎていくのだった。
そんな夏は大切な人たちを見送った季節でもある。
お見送りは、もはや夏に限らずなのだが、僕にとってはお袋を見送ったのが一昨年の夏。そして、10年前のお盆のまっただ中に冨士夫が旅立った。もうお盆なのだから、化けて出てくるのを待っているのだが、そうもいかないのだろう。あっちの世界も仲間が増えたので、ワイワイと酒盛りに余念がないのかも知れない。
そして、6年前は小山耕太郎が突然に逝った。
知り合ったばかりで、これから仲良くなるところだった。駅のホームに立ちつくし、予期しなかった特急電車を見送ったような気分だったのだ。マネージャーを買って出たものの、その年の春まで何もしない僕に対して、「それじゃ、トシさん、まずLIVEを1本ブッキングしてよ」と耕太郎は、ちょっぴりやさぐれた高校教師のような顔をして言ってきた。その次は耕太郎がブッキングすると言う。「代わりばんこにブッキングするところから始めようよ」と気を遣ってくれるのだった。そう、明らかにコチラが気遣ってもらっていたのである。僕自身が音楽界の浦島太郎だったので、どこに何のライブハウスがあるのかもわからずに、数週間が過ぎ、“そろそろ耕太郎に連絡をとっておいた方がいいな”と想っていた矢先の訃報なのであった。
唖然としたまま、真夏の葬儀に列席したのを覚えている。やはり今のように蒸し暑い夏日で、蝉の鳴き声がやり切れない想いを掻き回すように響いていた。
僕にとっては、そんな蝉時雨の中で見送った、小山耕太郎の七回忌にあたる『サンキューべリーマッチ小山耕太郎vol.6』が、新大久保のアースダムで行われた。
参加したバンドは●藻の月●Saybow & the R+X+S●aka-jam●marron aka dubmarronics+田畑満+JUICY●The Ding-A-Lings●凄いジャングル+内藤幸也●DJ:Higo●DJ:Eraである。
さすがにどのバンドも熟練していて、どこからでも、どの角度で見ても巧みな演奏でノらせてくれるのだ。“音楽をやり続けるということはこういうことなのだな”と思った。久しぶりに再会する人物も居て、貴重なる機会を与えてくれた耕太郎に感謝するばかりである。
“意外なほど楽しかったな”
例のごとくイベント後は酔っぱらいながら帰った。駅から自転車に乗り、公園の城跡脇の細道を行くと、日中は木々のカーテンから降り注ぐ蝉時雨で、耳鳴りがするほどなのだが、夜も更けると寝息のような切れ切れの蝉の音がするだけである。
その静寂の中で、
突然に耕太郎の声が心の隙間から聞こえてきた。
「それじゃ、トシさん、まずLIVEを1本ブッキングしてよ」
約束を果たせなかったかのように、“じじっ!”という蝉の単音が耳の奥で鳴る。それが優しさだけを残して、いつまでも心に留まっている鳴き声に聞こえるのだった。
今日は雨
中村清/談『子供の頃は韓国部落にお世話になり、外国の子供たちと遊んでいたんだ』
「横浜の近く、神奈川区神之木台というところにある韓国部落に親父は世話になっていたんだ。前にも話した通り、親父は岩手県生まれの東北人なんだけれど、駆け落ちした北海道から、今度は出稼ぎで、神之木台の韓国部落にあるはつり屋(工事現場などで、製品を削る、切る、壊すなどの作業全般のこと)に住み込みで働いていたんだよ。それで、俺が3つか4つの時に母親と共に呼ばれ、晴れて一家揃っての新生活が始まったんだけどね。その時の我が家は、韓国人部落に養ってもらっている東北人家族ってテイだった。そのおかげで俺は、韓国人だとか外国人に対する一切の偏見も、特別な意識もないし、逆にお世話になっちゃっているくらいだからね、親近感さえ湧くんだ。
その次に移り住んだ本牧では、本牧のチンチン電車を撤去して新しい道を作る仕事に親父は従事していた。だから、俺たち一家は工事現場にある飯場に住むことになる。本牧っていったら山手だからね、そこらの日本人の子供たちは俺たちを相手にしないんだ。だから、ここでも俺の友達は外国人の子供が多かった。ちょうどベトナム戦争真最中だったからさ、兵隊の子供たちが多かったんだろうな。俺はそいつらとばかり遊んでいたよ。そんなだから、俺自身は差別もコンプレックスもないんだ。逆に一般の日本人の子供とは、ちょっと目線が違っていたのかも知れないけどな」
◉横浜市電が開通したのは、1921年(大正10年)4月1日。戦後、市街地が急拡大し、また交通量も増加。輸送力や路線網、渋滞の原因となった路線敷等、あらゆる意味で市電は中途半端な存在となり、根岸線の開通や交通局の財政悪化も相まって、全線廃止への一途を辿った。

◉ベトナム戦争が激しさを増していた1967年は、米海軍横須賀基地(横須賀市)に寄港中だった米空母「イントレピッド」から、反戦を訴えて4人の米兵が脱走した出来事も起こっている。日本の反戦団体「ベトナムに平和を!市民連合」(ベ平連)の支援を受けてひそかに出国した彼らは、所属艦名にちなんで「イントレピッド(勇猛)の4人」と称された。当時のアメリカは徴兵の時代だった。公民権運動の主導者キング牧師が「米国の誠実さに懸念を抱く者はこの戦争を無視できない」と訴えた演説や、プロボクサーのモハメド・アリ氏が良心的徴兵拒否を表明したニュースも、当時の人々の心を打った。

◉前回はキヨシが『森の月』に入るまでのストーリーだった。今回はその次の展開になる『鵺院』から始まるのだが、キヨシがサラッとしていながら、妙に人懐っこいところ、よれているのに変に曲がっていない人間性は、この子供時代に起因するような気がする。それでは、中村清の2008年、『鵺院(ヌエイン)』に飛んでみたいと思う。
●キヨシ(中村清)プロフィール

■『The Ding-A-Lings』『GOD』『aka-jam』『LAPIZ TRIO』/Dr
1962年生まれ。北海道・釧路の出身。神奈川県厚木市で育つ。中学時代から『不正療法』のドラマーとして『東京ロッカーズ』ムーブメントで活動する。川田良と『ジャングルズ』を組んだのが17歳のとき、ジョージの『コックサッカーズ』に加わったのが20歳過ぎであった。その後、『GOD』→『GODOUT』→『OUT』→『Canon』→『WAX』→『ラブレターズ』→『森の月』→『藻の月』→『ヌエイン(鵺院)』→『シスター庵』→『The Ding-A-Lings』→『lemonsours』と活動を展開して、現在は複数のバンドでリズムを刻んでいる。ジョージとは40年来の友である。
『“森の月”と並行して耕太郎と始めたバンドが“鵺院(ヌエイン)”だった』
「言い忘れていたけれど、『森の月』をやる前に『ラブレターズ』という川田良が率いるバンドに入ったんだ。シバイくん(Sax)がやっていたバンドを見に行ったら、偶然にも対バンが『ラブレターズ』で、その時、良とも久しぶりの再会だったんだけれど、急遽誘われてさ、ちょうどシバイくんのバンドがツインドラムだったから、そのセットを使わせてもらって、『ラブレターズ』もツインドラムでやったのがきっかけだね」
◉ちなみに『ラブレターズ』のメンバーは、川田良(Gu)、マッチョ(Vo.Gu)、ユービン(Ba)、本間(Dr)、キヨシ(Dr)である。
「『鵺院』を始めたのが2008年。原っぱ祭りに出演した『フールズ』の再結成LIVEを見に行った時の4人の仲間で作ったんだ。耕太郎(小山耕太郎)とは『森の月』も一緒にやっていたから、並行して始めたことになる。ベースはナガタっち(永田也寸志/dip、ワーテルロー)で、ボーカルが土肥ちゃん(土肥ぐにゃり/弥勒JOURNAL,MUDDY FRANKENSTEIN)。2010年にGoodlovin’でアルバムとシングルを出したんだけど、それまでにCD-R盤とCD-RのLIVE盤を出しているんだ」

trk.1, OPEN THE хорошо GATE (5:44) trk.2, MUDDY WATER NEWS (6:27)
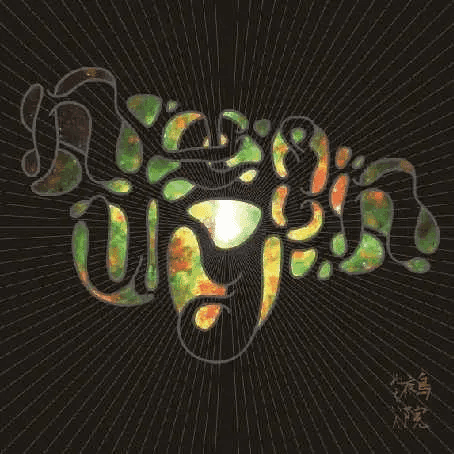
収録曲 1,十万億土の鐘が鳴る 2.MISSINGをしってるのかい 3.666BLVD. 4.smell 5.ファンファーレ 6.ASCENCION PLEASE 7.ピースな方法 8.clear spot light 9.すみれ 10.catch as catch can 11.Line 12.noble rotの森 13.鵺院
Goodlovin’ production
「『鵺院』をやって改めて思ったことは、歌い手さんは大変だってこと。ボーカルはある意味、自分のために生きているっていうかさ、自分のことが好きでやってくれて良いと思うのね。だからさ、『ルージュ』のタコだって、『自殺』の川上だって、『※1じゃがたら』のアケミだって、みんな自分と向き合っているというか、真正面から対峙しているから、とんでもなく深いところまで持っていかれる気がする。楽器を鳴らすのとか、ギターを弾きながら歌うのとかとは別で、のめり方もいかれ方もダイレクトなんだよね。だから、立ちボーカルって大変だと思うよ。オスだって、ジョージだって、最初は立ちボーカルと一緒にやっていたんだけど、気がついたら自分で歌わざるをえない状況になったギタリストじゃん。でもさ、ある時、オスが言っていたんだけれど、いざ歌ってみると、それはそれで楽しいんだって。まぁ、今更だけどな(笑)。そういった意味じゃ土肥ちゃんも大変だったと思うんだ。結局彼は2011年の震災後に北海道に行っちまった。それで『鵺院』は解散さ。土肥ちゃんは今でも自分と向き合っていると思うよ。その風景は伝え聞こえてきているんだ。
『鵺院』は俺が最年長のバンドだった。子供の頃からずっと先輩ばかりとやってきたから、俺にとっては初めてのシーンだったんだよね。だから、ブッキングも全部俺がしたよ。そういった意味じゃ貴重なバンドだよね。『The Ding-A-Lings』につなげる原石と言ってもいいと思う」
hallelujah ハレルヤ (鵺院)
Everyday People 鵺院nueyin(Guest川田良,AIKO)2/3
じゃがたら (JAGATARA)
『“aka-jam”は俺の人生で一番長く続いているバンドなんだ』
「『aka-jam(アカジャム)』も耕太郎が仕組んでできたようなバンド。俺(Dr)と耕太郎(Gu)とアカ(※2赤間哲彦Ba)が基本。そこに誰でも入ってジャムセッションができるようにって、“jam”がバンド名についているんだよね。サックスを入れたり、パーカッションを入れたり、踊り子さんが入ったり、詩人を入れたりしてさ、楽しくやっていたんだけど、肝心の耕太郎が逝っちゃって、どうしようか? なんてところに、ブラボー小松(Gu)、小滝みつる(Ky)が新たに参加してくれて今でも続いている。
何気に俺、『aka-jam』が人生で一番長くやっているバンドなんだよね。今年は“獏原人村”で行われる『満月祭』という野外イベントに『aka-jam』で参加するんだけど、以前は数年にわたり、福島に行ってたりしていたんだ。印象に残っているのは、震災後の2年目くらいに原発リサーチに行ったときのこと。ガイガーカウンター(放射線測定器)がまだ大きな音を出している時で、ことの重大さを音で感じていたんだけれど、その測定器のスイッチを止めると、あたりに何の音もしなくなるんだ。真夏なのに、鳥の声も、虫の音も、生き物が発する一切の音が無く、シーンとしているんだよ。その時はさすがに怖くなった。そんな記憶があるよ。実は今回はそれ以来の福島訪問。実に10年ぶりになるのかも知れない」
aka-jam 「テンキューベリーマッチ! 小山耕太郎 vol.3」
獏原人村公式HP
満月祭 獏原人村Facebook
【風見マサイ(獏原人村)】ヒッピーという生き方がもたらしてくれた自由。
◉僕が山口冨士夫のマネージャー(見習い)をやり始めた頃は、まだ会社員で広告の仕事をしていた。そこにジュニア(コウノ)と呼ばれていた兄貴から電話がかかってくる。そこで当時、細野晴臣さんのマネージャーだったIさんに会いに渋谷クアトロに行ったり、乃木坂にあったインクスティックに出向いたりした。ジュニアは恰幅の良い髭ズラの男で、いかにもヒッピー風の押しの強いタイプだった。「お前にマネージャーのイロハを仕込んでやる」と言いながら、(どこで仕入れたか知らないが)冨士夫に高価なギターを買ってくれたりするのだが、それがなんともイカサマっぽくって格好が良いのだ。それで“コレだな!”って、冨士夫のマネージメントに対して気が乗ったところがある。僕はそういうマンガのような話が好きだったのだ。
ある日、そのインクスティックで某イベントがあると言う。内容はなんだったか残念ながら忘れてしまったのだが、ジュニア曰く、「今の時代の最先端を行く輩が集まるイベントなんだ」と言うのだ。まずは、顔を売ることが大事ということで、毎週のようにジュニアの後にくっついて、業界の会う人ごとに名刺を渡していたのだが、このイベントには「冨士夫を連れて行こう」とジュニアが言い出した。“業界の奴らに冨士夫復活の存在を知らしめて、いっぺんにメディアの仕事をいただいちまおうぜ!”というわけである。その時の僕はまだ、音楽業界のイロハどころか、山口冨士夫のイロハも知らない27歳のガキだったから、すぐにその話に誇大妄想した。ついには、自分を分かった上で“イヤだイヤだ”する駄々っ子のような冨士夫を車に乗せ、無理矢理にインクスティックで行われていたイベントに登場させたのである。当然のごとく会場はザワついた。冨士夫の存在感は十分なのだが、どうもスポットの当たり方が想像していたのとは違う気がするのである。突然にパーティ会場に現れたライオンと言ったら言い過ぎだろうが、少し離れたところからみなさんが冨士夫に接してくる。そのうちにあろうことかライオンは、会場のスクリーンの横で作業をしていた主催者の一人に殴りかかったのである。原因はわからない。その人もライオンに反撃して取っ組み合いの喧嘩になった。その相手がマサイさん(獏原人村主催/風見マサイ)だった。この時以来、本人にもお会いしていない。今回のキヨシの満月祭の話で思い出したのである。その節は大変にご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。
帰りの車の中で「何があったんだよ、どうしたの?」って冨士夫に問いかけたら、「だから、行くのがイヤだって言ったじゃねぇか」とだけ答えていた。
【山口冨士夫 / 渋谷屋根裏 1983(2CD)】9/13out💽
83年の完全未発表ライブ、初音源化/
幻の未発表曲「雨だから」を収録した2枚組CD!
『“Lapiz Trio”は本当はパーティバンドなんだよね』
「ラピス(※3)はいいよ、最高だよ。昔、フリクションをやる前に1人でやっていたって話を本人から聞いたことがある。冨士夫や水谷(※4裸のラリーズ)さんとも遊んでいたよね。『Lapiz Trio』を始めるきっかけは、知り合いの誕生パーティだった。そのイベントのためにでっちあげたバンド。だから、最初のうちは誰かのパーティ・イベントのたびに演奏していた“パーティ・バンド”なんだけど、そのうちラピスが体を崩しちゃって病気になったのを機に音源を残そうということになった。それで、アルバムを作ったことをきっかけにパーティ以外にもLIVEをするようになったんだよ。ステージに上がったその場の空気感でアレンジできる即興性を持ったバンドでもあるんだ」
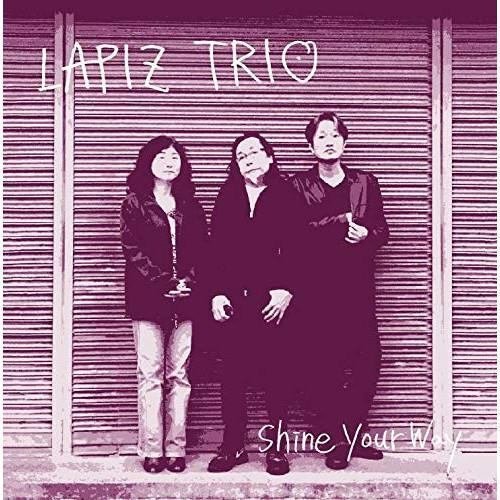
Shine Your Way/ LAPIZ TRIO
フリクションのオリジナル・ギタリスト、LAPIZ、現THE GOD、THE DING-A-LINGSなどで活動する中村清、古くはREAL、山口冨士夫、チコ・ヒゲとのセッション・バンド"FUJIO CHIKO-HIGE & REI"で知られる横山玲のトリオによる作品は、 1972年から2017年に作られたLAPIZの新作スタジオ作品。
LAPIZ TRIO at 高円寺 HIGH 2012.7.1③
『俺がいくつものバンドを掛け持ちしている理由(ワケ)』
「俺はあまり自分を出すようなタイプじゃないから、自身は前面に出なくてもいいんだけど、聴いている人たちを踊らせたいとか、楽しませたいとかはいつも思っている。まぁ、自分自身のエゴを無くしても楽しめるタイプだから、色んなバンドでアレコレとやりたいと思うんだよね。誘われたら取り敢えず試してみるし、楽しかったら続けていくのが俺なりのスタイルなんだ。だから、演奏するバンドが増えていくのかも知れない。俺自身は緊張しないしね。緊張したらそれが客にも伝わって、客も緊張させちゃう気がするからさ。色んなビートを叩きたいんだよ。ひとつのバンドじゃ似たようなビートになっちゃうし、ひとつのバンドで他のビートを出したいとか要求すると、割とモメるんだよ、うまくいかないの。言い訳もあるのかも知れないけどね(笑)。ボーカルのいるバンドだったら歌に合わせるし、インストだったらそれなりのリズムを出すようにしている。
そんなわけで、若い頃からついつい複数のバンドでやっちゃうんだけど、良(川田良)はその点、面倒くさかった。割と嫉妬するんだよね。『ジャングルズ』をやっていた頃、『EDPS』のボーイ(※Dr)がやらなくなったから、ツネマツさん(※恒松正敏/フリクション・EDPS)と一緒にやったことがあって、ベースも『ジャングルズ』から『EDPS』に移った井出さんだったからさ、“なに『ジャングルズ』みたいなことをやっているんだよ!”って文句を言うわけだ、良がさ。だけど、それ以上にツネマツさんと一緒にやるのは面白かった。音源の作り方も絵描きっぽいっていうか、カセットに作った曲を入れて持って来るんだけど、リズムも打ち込みで簡単なベーシックが作ってあるわけよ。そこからみんなでアンサンブルを作っていく感じ。まるでデッサンから、線画にして着色していく世界観があって、それぞれの曲の作り方ってあるんだなぁって思ったよ」
◉先日、キヨシに、「いっそのこと今やってるバンド全部集めてイベントにしちゃえばいいじゃない」って、ほとんど完全な冗談を浴びせてみたら、「いやぁ、実はそういう話が以前にあってさぁ」って、冗談じゃない答えが返ってきた。会場まで抑えたのだが、どうしてもイヤになってNGにしたと言う。そりゃあ、そうかも知れない。いかに客を踊らせるのが好きでも、演奏のしすぎで、自分の足が踊ってしまってはどうしようもない。僕はキヨシのバスドラのリズムが好きなのだから。
E.D.P.S. - It's Your Kingdom (Studio Live)
『“The Ding-A-Lings(ティンガリングス)”から若いバンドへ』
「『The Ding-A-Lings』は、メンバー的には『鵺院』からの流れだけれど、(土肥ぐにゃり/Voが抜けて、オスVo/Guが入った形)サウンドはぜんぜん違う。耕太郎とオスの2人の個性が交わったり、弾けたりして始まったバンドなんだ。ジョージと一緒にやっていた頃の耕太郎は曲を作らなかったみたいだけれど、町蔵(※5町田町蔵)と一緒にやっていた頃の耕太郎はすでにコンポーザーだったし、さらに『鵺院』で耕太郎は自身を確立したんだと思う。それが『The Ding-A-Lings』で勢いに乗ってジャンプしたところだったんだよね。実に残念です。(2017年8月9日没)」
町田町蔵
「耕太郎亡き後、しばらくは3人編成で続けていたんだけれど、一昨年からクリ(栗原)が入って『The Ding-A-Lings』はまた4人編成でやっているんだ。最近のオスは調子良いよ。先日も東高円寺『UFO』で、『フーテン族(※6)』という若手のバンドなんかと一緒にやったんだけど、実際に生で接するオスの音を聴いて、彼らは度肝を抜かれてた。そんな風に若手のバンドが喜んでくれるとコッチも嬉しいよね。彼らはオスのことは情報として知ってはいるのだろうけど、それだけなんだと思う。そりゃそうだよね、接したことがないんだから。オスは演奏に対する向かい方がすごい柳腰っていうか、のらりくらりとした人なんだけれど、音を出した瞬間にわかるんだよね、今のオスがどんなにすごいかが。エフェクターなんか通さないで、マーシャル直結のテレキャスであんな音を出せる人はそこらにはいないと思う。居合わせた若い奴らが「凄いっすね!」とか言って寄って来たりすると、こっちもバンド冥利に尽きるし、これからも長くやってやるか!なんて気にもなるんだ。だから、来年は『The Ding-A-Lings』のLIVEを増やそうと思っている。若い奴らと交わってお互いの音が出していけたらと思っているんだよね」
あそぼうぜ/
フーテン族 僕の犬 Live
『若いもベテランもないよ、音楽好きは一緒だよ』
「パンタさんもいなくなっちゃって、冨士夫とかフールズとか、仲間達がいなくなっていく中で、俺たちはまだまだバンドを続けている。だけど、なんかさ、昔と比べたら俺たち、凄い真面目になっているんだよ、ほんと。そんな自分を感じるんだ。それは音楽が好きだからって、つくづく思うわけなのです、はい。
今は昔と違って、ライブハウスもギスギスしていないし、とてもフレンドリーだよね。俺だっていつの間にか優しいおじさんになっているもんな。だからってわけでもないけど、若いバンドと対バンになっても偉そうなことを言わないようにしている。ダメ出しとかもしたくないし、音楽好き、ロック好きで良いじゃんって感じ。昔はバンド同士の潰し合いとかあったもんね。楽屋なんか緊張感が漂っていた。でもさ、俺は子供がいないからわかんないんだけど、親の影響ってのもあるんだろうな。親がロックを聴いてて、子供の頃から耳馴染んでてさ、親子でロックを聴いちゃったりする世代。子供がバンドをやることにも肯定的で、家族でロックンロールしちゃったりするわけだ。それが今の20代なのかも知れないね。そんな若いバンドは聴いていてとても楽しいし、良いと思うんだけど、少しストレートすぎるのが気になるかな。『すばらしか(※7)』のギターとは顔見知りだけれど、彼のバンドは、それこそ“すばらしい”と思うよ。それとは別に、若いバンド全般に思うことは、ベーシックな部分がもう少し歪んだ方が面白くなる気がする。思い込みとか勘違いがある方がロックは面白いと思うんだ。僕らはよれちゃってどうしようもないし、パンク系のロックだから“反抗”が根っこにあったから、また違うんだけどね。
でもさ、今の世代の若い子たちと対バンできるなんて、改めて最高だと思うよ。自分の子供って言ってもいい世代とやることになる未来があるなんて、想像もしてなかったんだから。」
すばらしか - 生きてる(Subarashika - IKITERU)
◉去る13日、偶然にもキヨシが言う『フーテン族』と『すばらしか』のツーマンが『クロコダイル』であったので覗いて来た。お盆の台風という悪条件に関わらず、満杯の客入りも大したものだが、演奏がそれにも増して凄かった。特に毎回変化する『すばらしか』のステージは、遊び心と共に凄みというか、独特の迫力があった。客層も若い男女が半々で、この2つのバンドのカップリングは今後も注目されるに違いない。帰り際に西さん(クロコダイルの店長)に挨拶をしたら、「今日の2つのバンドは、俺たちの時代を思い出させるねぇ〜」と目を細めていた。
『改めて振り返ると、やっぱり若い頃のシーンを思い出す』
「ここまでの自分の音楽人生を振り返ると、やっぱり若い頃のシーンが思い浮かぶよね。東京ロッカーズ・ムーブメントがあったから、そこでたくさんのミュージシャンと知り合えたのがラッキーだった面もあるけど、良と出会えたのが俺にとっては衝撃的だった。幸運だったとも言える。それまでに『S E X』とか『サイズ』とか『スピード』とかを見に行っていて、良のことは好きだったんだけど、あの怖い圧のある良と一緒にバンドができるなんて、思いもしなかったからさ、嬉しかったよ。彼には感謝している」
運命の糸 from『FUJIO,CHIKO HIGE & REI / ABSOLUTELY LIVE(CD+DVD)』
※山口富士夫・チコヒゲ&レイのゲストに川田良が加わっている
「その川田良の『ジャングルズ』で動き始めて、ジョージの『コックサッカーズ』でいろんなことが進んだって感じ。ジョージは面倒見がいいんだよ。自分が主軸なんだよね。音楽だけでなく、バイト先でも当時、“ジョージ軍団”って呼ばれるグループがあってさ(笑)、ジョージは“音楽”と “バイト”、両方とも同じ土俵で仕切っちゃう親方肌だった。景気がいい時代はバンバン仲間をバイト先に呼んじゃってさ、それこそみんな一緒に働いたよ。みんなでワイワイやっているのが大好きなんだよな。だから、ジョージは凄い人だって俺は思っている。分け隔てがないんだよね。音楽に関しても仲間のバンドを大切にして生きている。若いレンやカノンと普通にやれるのもジョージの持ち味だよね。だけど、ジョージ自身は、冨士夫やフールズの流れや気持ちを背負っているというか、意識しているところがある。俺なんか何にも背負ってないもん(笑)。気楽に楽しくやって良いんじゃねぇかと思うよ」
REN/2021/11/29 fourfouty440 下北沢
MONOTSUKI/誰かおいらに(花音/山口冨士夫)
『耕太郎は人生最大のパートナーだな』
「俺のバンド人生で最もリスペクトするのは耕太郎(小山耕太郎)だな。ずっと先輩ばかりと接してきたバンドマンの流れの中で、“初めてできた仲の良い後輩”って想いがあるんだ。2つ年下なんだよね。彼とは何の説明もなしに、何でも一緒に楽しめた気がする。人生最大のパートナーだよ。『The Ding-A-Lings』を始めたときは、オスが伴侶を亡くして気を落としている時だったんだけど、耕太郎はそんなオスを励ましながらバンドを引っ張っていた。いつも意欲的で凄い奴だったよ。亡くなる前も意欲的にソロ活動をやっていて、それをまとめて1枚のC Dを作ったんだ。是非にでもみんなに聴いて欲しいと思っているんだ」
candy boogie
『これからやっていきたいこと』
「もともと音楽ってさ、自分の部屋でさ、自分と向き合いながら一人で聴くもんじゃん。それが実はいちばん“熱い”んだよ。それにもかかわらず外に出て、社交的っていうか、みんなと共有したりすると、なんか違ってくるじゃない。そこら辺が難しいよね。
俺がつくづく思うのはさ、俺は音源を残しているからここまでやってこれたんだと思う。もちろん、音源を残していない素晴らしいバンドもいっぱいあるのは知っている。でも、それを伝えるのは伝説だろ。口伝えに伝わるんだけど、それって歪むじゃん。
だから俺自身は音源を残す仕事をしていると思っている。そのアイデアでライブをやってみんなを楽しませているんだけどね。それは言うなれば未来なんだよ。未来を想像することができるんだ。だってそうだろ?俺たちが死んでも俺たちの音は聴けるんだぜ。俺は、誰かが俺たちの音を聴いている姿をいつも思い浮かべている。それが俺の描く未来なんだよね」
The Ding-A-Lings / 夢をすてるなよ
◉キヨシは意外なほど雄弁だった。きっと常に自分の立ち位置を確かめながら生きているタイプなのだろう。今回はジョージの流れからのインタビューだったので、それを踏まえた内容になったが、きっと別の角度から訊いたら、また違うストーリーが現れたのかも知れない。ちょっと、ほろ酔い加減のキヨシに対して、最後に青ちゃん(青木眞一)のことについて訊いてみた。次なる『7話』は、今は亡き青ちゃんの内容を予定しているからである。
『青ちゃんは俺たちのカリスマだったんだ』
「東京ロッカーズが始まった頃、『スピード』は別格だったんだよ。それはバンドに青ちゃんがいたからなんだよね。京都で起こった『村八分』神話みたいなものが、あの頃の東京にはあってさ、その存在感がものすごくデカかった。冨士夫は何にもやっていない頃だったから、青ちゃんだけがその神話を背負っていたわけさ。だから『スピード』が注目されていたんだよね。その『スピード』に川田良が入るってことになって、俺たちの狭い世間は大いにざわついた。『ZOO』って雑誌(後に『Doll(※8)』になる)があったんだけれど、そこで一大ニュース記事になって、めちゃくちゃ持ち上げていたのを覚えているよ。あれは’79年頃の『スピード』だね、ほんとうに別格だった。
当時の青ちゃんは俺たちのカリスマだったと言ってもいい。それは『ウィスキーズ』でジョージと一緒になったことで、ちょっと身近になるんだけれど、俺は青ちゃんの、あの“すかし方”が好きだった。冨士夫は分かりやすくて、オーバーアクションだから、ガーンとやるパフォーマーなんだけれど、そんな時も青ちゃんはシカトしているのが分かる。そんな青ちゃんを俺たちは“格好良い”って見ていたんだよね。それはある意味、幻想でもあるのさ。勝手に俺たちが描いている神話の続きだってこと。そういう意味もあって、あの頃の高円寺の連中が思っている青ちゃんに対するリスペクト感は凄かったんだよ。
青ちゃんのリズムギターに良もマーチンも合わせていた。正直、青ちゃんのギターはあまり上手くないんだけど、ノリは青ちゃんなんだ。それは『ウィスキーズ』でも同じ。俺たちはいつも青ちゃんのリズムに合わせてノっていた。理屈抜きに最高だったのさ。」
ギタリスト青木真一さんインタビュー
フラフラ from CD『TEARDROPS LIVE 1989 'KYOTO MUSE' - Vintage Vault Vol.1』
(第6話『Canon〜藻の月へ/中村清●登場!』終わり▶︎第7話に続く)
次回は、青木眞一を予定しています。
■※1じゃがたら(アケミ)
江戸アケミをリーダーとする日本のファンク・ロックバンド。1979年3月活動開始。1982年にアルバム『南蛮渡来』を発売。1983年から1985年にかけては江戸アケミの精神的不調により活動休止。1989年にはアルバム『それから』でBMGビクターよりメジャーデビュー。1990年1月27日江戸アケミの入浴中の事故死により、解散した。その後も数度に亘り散発的に「JAGATARA」を冠した公演が行われ(後述)、江戸アケミの没後30年である、2020年1月27日(江戸アケミ命日)より「Jagatara2020」として再始動している。。
■※2アカ(赤間哲彦)
ベースと電子トランペットを演奏するミュージシャン。インプロのjambandで、ダンスミュージックを演奏している。Aka-jamの支柱。
■※3ラピス
LAPIZ TRIO (バンマス)/SANDADA(サンダダ)・バンマス/荒涼天使・バンマス/忘我’z・バンマス/MAJIKA~NAHARU(Vo.Guitar)/DJ
■※4裸のラリーズ(水谷)
ヴォーカル、ギターの水谷孝を中心に、1960年代から1990年代にかけて活躍した、日本のサイケデリック・バンド。
■※5町田町蔵
町田 康(まちだ こう、1962年1月15日 - )日本の小説家・ミュージシャン、武蔵野大学文学部教授。旧芸名は町田 町蔵(まちだ まちぞう)。本名は町田 康(まちだ やすし)。大阪府堺市出身。1981年、バンド「INU」のボーカリストとしてアルバム『メシ喰うな!』で歌手デビュー。同バンド解散後もさまざまな名義で音楽活動を続けるかたわら、俳優としても多数の作品に出演。1996年には処女小説『くっすん大黒』で文壇デビュー。2000年に小説『きれぎれ』で第123回芥川賞受賞。以後は主に作家として活動している。
■※6フーテン族
注目のよみがえるフーテン・バンド
歌 山下大輝 @yamashita19998/ギター 髙田勘吉 @kankichis/ギター 小杉宗太郎 @koss_1226/ドラム 藤野真之介 @fujinos/ベース 小野寺だいき @dep0099
■※7すばらしか
最注目される、東京・神奈川を拠点に活動する4人組ロック・バンド。
■※8 Doll
『DOLL MAGAZINE』(ドールマガジン)は、かつて発行されていた日本の隔月音楽雑誌。過去には『DOLL』の誌名で月刊誌として発行されていた。発行元は株式会社DOLL。1980年創刊。『FOOL'S MATE』と並び、1980年代から1990年代にかけての日本のパンク・ロックシーンを代表する音楽雑誌であった。邦楽・洋楽を問わずパンクを中心に、ロック、ハードコア、ガレージ、スカ、メタルなどを取り上げていた。ラモーンズやセックスピストルズ、クラッシュ、ミスフィッツ、グリーン・デイなど、海外アーティストの特集なども数多く組まれていた。2009年休刊。
■INFORMATION 【WHISKIES/CD】 2023年7月12日発売!
※青木眞一(TEARDROPS)、ジョージ(自殺)、マーチン(フールズ)、宮岡(コックサッカーズ)による、ウィスキーズ唯一の音源であるシングルリマスターを初復刻!山口冨士夫のカバーを含む未発表ライブを2CDに収録!

●カスヤトシアキ(粕谷利昭)プロフィール
1955年東京生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。イラストレーターとして社会に出たとたんに子供が生まれ、就職して広告デザイナーになる。デザイナーとして頑張ろうとした矢先に、山口冨士夫と知り合いマネージャーとなった。なりふり構わず出版も経験し、友人と出版会社を設立したが、デジタルの津波にのみこまれ、流れ着いた島で再び冨士夫と再会した。冨士夫亡き後、小さくクリエイティブしているところにジョージとの縁ができる。『藻の月』を眺めると落ち着く自分を知ったのが最近のこと。一緒に眺めてはどうかと世間に問いかけているところである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
