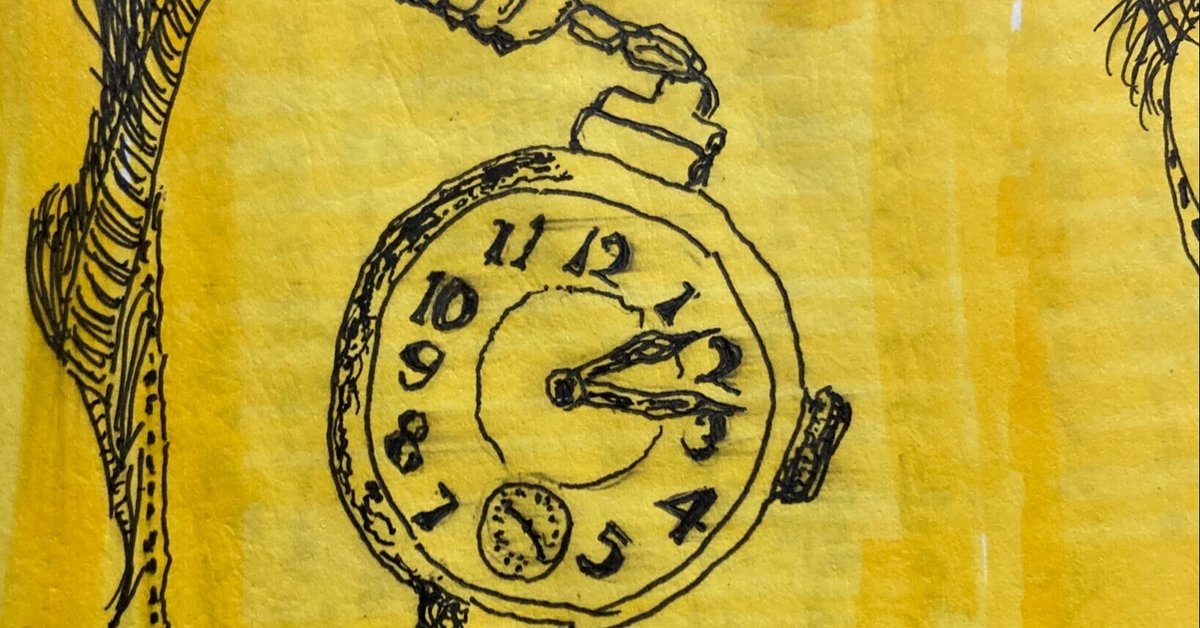
ひろしま神話(Toshi 山口)<第3話>
江戸の竹原
昭和の化石が
徘徊す
竹原市の「町並保存地区」の一画は、京都などとは趣が異なって何もかもこじんまりしていて、人混みも少なく、落ち着いて歩ける。江戸時代の頃から、竹原の遠浅の浜には、良質な塩を産出する塩田が広く開けていた。塩は今も昔も用途の広い戦略物資である。保存されているいくつかの旧家は、塩や薪の生産、卸や海運で財を成したようだ。造り酒屋もある。「儒教」の家は特に日本酒を愛好したようだ。商業が盛んになるにつれ、金融業も発展していった。
「頼山陽」の祖父「惟清」は紺屋を商っていた。英文ではトレーダーとあるから、卸業で生産者ではなかった、と推測できるが定かでない。商人としても文化人としても一流であったようだ。三人の子、「頼春水」、「頼杏坪」、「頼春風」に対しても教育熱心な父親であった。その町屋も見学することができる。
「藍(インディゴブルー)」は、高値の花だった。「紺」は、当時の流行色だったのかもしれない。「紺屋」は実入りのいい商売だったのだろうか。
「頼春水」が「頼山陽」の父である。「頼春水」は浅野藩に仕える儒学者として大成し、今日にもその業績は生きている。「頼杏坪」は、三次の代官を勤める傍ら「芸藩通志」を編纂した。また、「朱子学」に学んだ「経世済民」の思想を貫き、経世家として、地域振興にも尽力している。「頼春風」は医者として身を立てた。その屋敷も「春風館」の名称で残されている。才に長けた彼ら息子たちは、土地の人々から、尊敬の念を込めて、「頼三兄弟」と、愛称で呼ばれる。
町並の中央にある通りを尽きたところに、「昭蓮寺」がある。急な勾配の石段を登らないと境内に辿りつけないが、日頃から仏教の研究に余念のないJ・M氏は、ひとりその巨体を揺らせるながら石段を歩いて登った。この寺には「頼家」や文人の墓があると聞く。
竹原市「町並保存地区」初の探訪はそれで充分だった。
半日に満たない時間だったが、江戸の風情を残す町並で、ゆっくりすることができた。
原爆投下によってグランド・ゼロと化した焼け野原に築かれたのは、現代を身にまとった文明都市であった。ここひろしまは、時間は同じように流れても、竹原市のように、一部の区画でさえ、江戸と今日とが並存しない。
江戸時代の「浅野藩」は42万石を誇る当代有数の「藩」だった。石高は藩財政の規模を示すバロメーターである。広島城下には、多くの武家屋敷や町屋が立ち並んでいただろう。そこにどのよな生業があったかは、旧町名がヒントを与えてくれる。郷土史家によれば、川沿いには、賑やかな繁華街が開けていたとある。多くの才能がこの城下から育っていっただろう。
ひろしまに存在した江戸を知る多くの手がかりは、もはや広島城と林立するビルの狭間の史跡とかろうじて焼残った歴史史料以外に見当たらない。古地図を広げ、それらの断片をジグソーパズルのように根気よくつなぎ合わせてみる。
ひろしまの装っている何重もの文明の衣装を取り払ったら何が見えてくるだろう。竹原市の「町並保存地区」は、ひろしまのそれとは、等身大ではないが、このときいくつものインスピレーションを与えてくれる。この地区を彩る寺への小路や石段、匠の細工が美しい「竹原格子」、屋敷にひっそり置かれた縁台などは、町の通りの装飾として、城下町の景観を思い起す手がかりを与えてくれるだろう。
テキストに現れる一つひとつの言葉にイメージを重ね、行間に人びとの息づかいさえも感じることができるようになれば、当時のひろしまの町の姿になんとか迫ることができる。
近代的なビルの一室で、「頼山陽」の知の遺産を少しずつ紐解きながら、勝手に想像の翼を広げてみる。
ここ竹原市を訪れ、思い出した。この町から近い瀬戸内海に浮かぶ島、大崎下島に御手洗がある。かねがね一度は行ってみたいと思っていた場所だ。
御手洗は、かって潮待ち、風待ち港として栄えた港町である。瀬戸内海は平均して水深30メートルと浅い。潮の干満によっては、船底を海底に潜む岩礁にぶつけてしまう危険がある。また多島の瀬戸内海は海路が狭いし、潮流も複雑だ。大型の帆船だと風向きに影響されやすく、うっかりすれば、針路を誤ってしまう。御手洗は船を泊め、双方の危険が過ぎ去るのを待つ港として発展した。
この港が、北前船の寄港地だったことはうろ覚えに聞いて知っていた。
想像だが、多くの投錨料がこの港の利権者に落ちただろう。ガイドブックを見たり、郷土史家に話しを聞くと、港町の名残りを今なお留めているが、富くじがあったと言う以外、投錨料のことについてはどうもはっきりしない。それをいつか足を運んで確かめてみたいと思っていた。
北前船と言うとノスタルジックに耳に届くが、現代流に言えば、日本各地の主要港と生産地とを海運で結ぶ、一大物流ネットワーク網構築の立役者である。
江戸時代になって都市経済が発展し始めると、急増する消費需要を満たす物資の輸送インフラを整備する必要があった。何しろ首都、江戸は、人口100万人を優に超える世界屈指の大都会であった。一説には200万人だったとも言う。その台所を賄うだけでも、陸の東海道と海の新ルート開拓が急務だった。
旧来の浅瀬を陸伝いに荷を運ぶ小型船では、時間や積荷の量に限界があった。とは言え、明治に入って本格的な鉄道が敷かれるまで、大量物資の輸送は、もっぱら海路に頼るしかなかった。
大型船を建造する技術が進歩するとともに、沖合いのルートが海の物流の大動脈として俄かに注目を集めるようになった。これを境に、大量の荷の運搬を担う海運業が日本の物流の主役に躍り出た。
北前船は、日本の内海、近海における海運の雄だった。船主や荷を積んで沖合を航行する船にとって、御手洗は、人、物、船へのダメージを回避しながら、同時に大量の船荷の要求にも応えてくれる海路の中継地となっていく。
島の多い国は、何も日本だけとは限らない。このような役割を担った港は、公海の陸沿いには、無数とある。
だとしたら御手洗は、寄港するものを拒まない開かれた港、内海のカリドールだったのだろうか。
鎖国下ではあったが、外洋を航海してきた貿易船が、内海に針路をとり、目的地の大阪に向かう途中でこの沖合の港に錨を降ろしていたとも考えられる。ここ御手洗は、藩と藩との間の物産取引の拠点ともなってたようだ。
国内市場に向けて、物資の最大の集荷地であった大阪では、早くから国内先物市場が形成されていくが、オークションのシステムをオランダに倣った形跡があると言う。S・T氏は、そう考えている。貿易船は、海外からの積荷とともに決済、保険など海外との商取引に必要な制度もわが国にもたらしたのだろうか。
「頼山陽」の影響を受け、あの「大塩平八郎」の乱で知られる「大塩平八郎」の肖像画が大阪城史料館に保存されている。それを見ると端座する彼の膝元に地球儀が置かれてある。「大塩平八郎」は、大阪の与力であった。大阪は想像以上に世界の政治、金融情勢に敏感な、インターナショナルな交易都市だったと思える。
御手洗は内海のシンガポール?マラッカ?だった。
大阪は、日本のアムステルダムであったか?
ロマン尽きない話しだ。
歴史の落とし穴を粗探しをするわけではないが、話題が脱線、飛躍するのが、着眼点の異なる外国人との地方めぐりの魅力である。何かひとつでも確証が現れてくれば、しめたものだ。
ヨーロッパの物流のハブであるアムステルダムからさほど遠くないところにライデンと言う都市がある。ここにはオランダ最古の大学といわれる「ライデン大学」がある。その構内に、「シーボルト博物館」がある。現在では「日本学」のメッカとなっていて、日本史オタクの憧れの地となっている。
ライデン市と長崎市とは姉妹都市だ。いまは、ハウステンボスに変わっているが、以前あそこには、オランダ村があった。「頼山陽」も友人の誘いで、長崎を訪れている。
「御手洗」には、船の寄港地につきものの女性哀史、「おちょろ船」の悲話が残っている。
次は、全員一致で、まずは、近くの御手洗をめざすことにした。
御手洗に
和蘭船探す
ツーリズム
(2021.10.02)
