
雑09| 「8号室」のこと
2024年 10月 29日/記
(敬称省略)
1970年代後半、私は『毒薬大系』の編集発行と並行して、「8号室」活動に参加した。前にも触れたとおり、帰郷後は〈生活圏である「地域」から〉という方針の下、犬山で活動を始めたものの、あえなく挫折。今度は名古屋を広い意味での「地域」と見て、活動の範囲を広げたのである。で、たどり着いたのが「8号室」であった。そこには名古屋ではまだ少数派だった現代美術を目指す若者たちが集まり、自主運営で個展、企画展、討論会などをやろうとしていた。
この「8号室」については、以前に「8号室~国家から私まで~」という一文を書いている。書いたのはずいぶん前だが、認識や見解は今とたいして変わらないので、少し加筆して再録することにした。
8号室 ~国家から私まで~

名古屋市中区錦2丁目の長者町に「8号室」がオープンしたのは、1974年12月のことであった。
当時20代の美術家たちを中心にした自主運営のスペースであり、約6年間、個展やグループ展を頻繁に開催したのである。そのほか美術講座、読書会、パフォーマンス、コンサートなどを開催しているが、あらゆる機会に対話会と称して議論をくりかえしたのも8号室の特徴であった。
ただ、こうフラットに書いてしまうと、8号室の存在意義が見えてこないので、まずは当時の名古屋の美術状況に触れておかねばならない。というのは、現代美術に関心をもった若者の活動基盤となる場がほとんどなく、それどころか現代美術そのものが名古屋ではまだ市民権をえていなかったことなど、今とは状況がちがいすぎるからである。名古屋市美術館、三重県立美術館、岐阜県美術館、豊田市美術館、そんなものはなかった。愛知県美術館も今の姿ではなく、まだ文化会館美術館だった。
画廊はいくらかあったが、現代美術画廊は事実上ただ一軒、「桜画廊」だけであったし、その桜画廊も50年代作家や60年代作家の受け皿として満杯状態で、若手の活動基盤にはなりえなかった。
また、これは個人差があるが、70年安保闘争をへたことによって、現代美術に対する見方や関わり方において世代間に相当な差異が生まれ、若い世代の一部は名古屋の細々とした現代美術路線からさえもこぼれ落ちていたのではなかったか。こぼれ落ちた側に入っていた私にとっては、名古屋とはずいぶん淋しいところだ、というのが当時の実感であった。
私は1974年4月に京都から帰郷し、8号室オープンの少し前に8号室運営の母体である「名古屋美術家共同組合」のメンバーと出会っている。彼らは喫茶店「木曜日」で定例会を開いていて、そこで藤井一、鈴木敏春、宮野彰一、三品富康といった面々に出会ったと思うが、彼らすべて20代前半であり、宮野君と三品君など20歳くらいだった。その時の私は26歳くらいで、彼らよりほんの少し年長だった。
私の名古屋における人との関りは、大半が8号室を通してであった。8号室の運営メンバー、常連、その他いろいろな人に出会った。ノブコ・ウエダ、三浦幸夫、西島一洋、よねづたつひこ、鈴木あひる、朝比俊光、山田岩松、古橋欣治、大賀たいが、宇佐美知恵丸、峰田寛、栗本百合子、古川清、石橋勝久、音楽家の小林啓一、等々である。
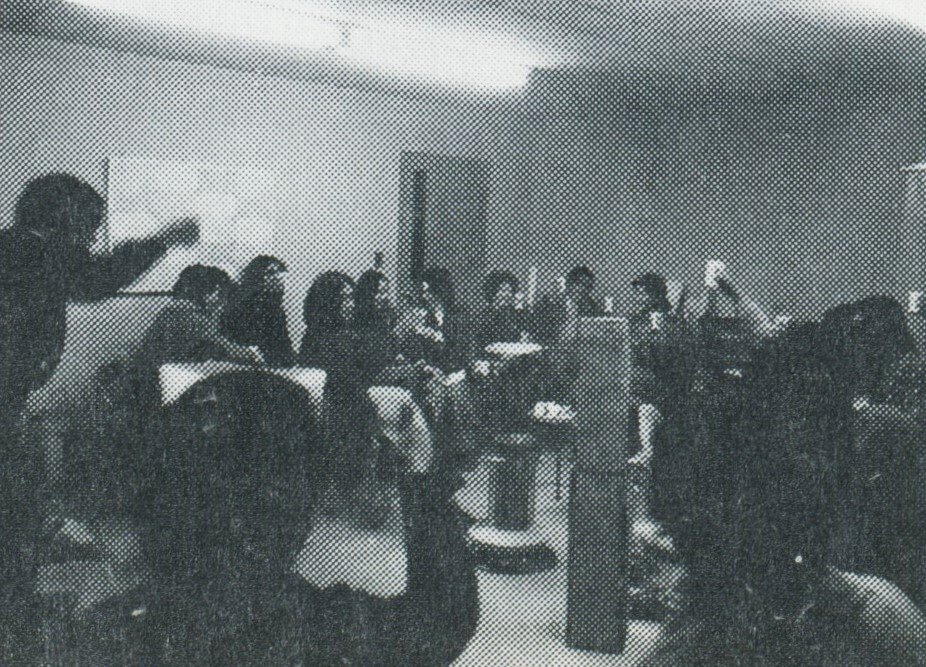
私が正式に運営メンバーに入ったのは、1975年5月以降の8号室2期からだと記憶している。作品発表などもしたが、この頃は雑誌『ゐまあごを』『毒薬大系』の編集発行や執筆に中心をおいた活動をしていたので、美術作品は余技であり、8号室との関わりは会友的立場という自覚であったような気がする。むしろ8号室閉室後に、その流れを新しく組織していくことで自分の役割を果たしたのではないかと思っている。
そのことについてはのちに触れるとして、まずはオープン時に配られたビラに書かれていた文の一部を引用しておこう。
ただ、ビラが手元にないので、ビラの文を引用している宮野彰一の「場所の問題と共同性をめぐって」(『8号室全資料集70/78』1979年刊)から孫引きさせてもらう。
◆〈私たちは美術を単に美的な、あるいは日常とは無縁のものとして自立させることよりも一つの運動の局面としてとらえたいと思います。それは制作者と見る側の人たちのサイクルであり、また社会的定位へのメッセージであると思います。(略) 私たちはこのスペースを一歩の現実的な局面として発展させつつ、文化総体の中で常に位置し、美術のみに固執するのでなく、美術を含んだ文化運動の志向性をかたちづくる拠点としたいと考えます〉。
全共闘運動の反映が明らかに見てとれる文面であるが、ずっとのちの回想で、鈴木敏春がもっと明確に当時の問題意識を語っている。
◆〈70年安保闘争やベトナム反戦、そして沖縄という政治の季節は、従来の美術のあり様や価値観を変革するのに充分だった。(もっともこの様に考えるのは美術の世界では少数派だった。今もいっしょか?) 当時の流行語でいえば主体性とでもいうか、個人が担うべき問題を表現として捉えなおして行こうと言うことになる。そしてその様な関係の場としてあえて実験室としての8号室を設定してみたのだ〉(「裸眼」第10号、1993年3月)。
ただし、鈴木とともに主要メンバーの一人であった藤井一の認識は、少しばかりニュアンスがちがっている。8号室の機関紙的位置にあった『漆黒の馬』第17号(1975年9月)で、8号室という運動体は〈外に向かって開きながら、目を運動体自体に向けている〉と彼は語っている。
◆〈「外に向けて~する」という視点に自らを集約する事ではなく、内に向けた視点をその時点での提示として、視点の検証状態を常に可能にしておく事、そんな空間を、8号室として現実社会の中で定着し続ける事だろう。政治団体が細胞を作るように私達は8号室という要素を持つのではない〉。
当時頻繁に口にされた用語が「共同性」で、あえて共同作業をおこない、共有する場を設置した8号室参加者にとっては、たいへん重要な理念であった。この理念によって画廊や美術館といった美術制度に対峙したであろうし、この言葉でもって個別表現にとどまらない何かを示唆しようとした。美術の自立幻想を揺さぶる運動性をもつための、あるいは生活問題や社会性をも視野に入れうる理念でもあった。
企画展では私たちより年長の世代の水上旬がしばしば出品し、たえず私たちの議論に参加してくれていたのが思い出されるが、彼から学んだことも多かったはずである。また、1975年にアーティスト・ユニオン名古屋が結成され、8号室を借りて月例展を8回開いている。水上旬、岩田信市、後藤泰洋、原智彦、山田彊一、大嶽恵子らである。
地声の大きい岩田信市に張り合って大声で議論したことまでは覚えているが、内容はすっかり忘れてしまった。岩田の回想によれば、〈僕の記憶では三頭谷氏が、社会主義的美術論を展開され、ポップアートの立場からこりゃ、どうしょうもないわい、と思った記憶だけが残っている〉 (『裸眼』第10号)ということらしい。この頃の岩田は、ゼロ次元をゴミ姦団にリメイクして原智彦らとともに活動し、1979年にはロック歌舞伎スーパー一座を立ち上げることになる。
藤井一の関係から東京の畠山崇らの雑誌『実験室』グループが参加し、逆に東京の「共同展79」に8号室メンバーが参加した。やはり藤井の関わりから、針生一郎に講演と討論会参加をしてもらったこともある。また、舞踏家田中泯の資料展が開催されているが、どういう経緯だったのか、残念ながら覚えていない。
ともかく、こうした広がりをもちながらも、8号室は閉室に向かうのだが、1978年後半にはすでに危機にあったと思われる。同年12月発行の『漆黒の馬』第21号が、象徴的な特集「作品論をめぐって」を組んでいるからだ。
8号室があまりにも美術的な「作品論」をテーマとすること自体が危機の表明であるし、特集論文は鈴木敏春が作品論についてやや戯画的に書いている1本のみで、あとは私が「美と科学技術」を書き、当時8号室と関わりをもった若手哲学者の工藤順一が荒川修作論を書いているだけなのである。私と工藤の論文は、ともに運動性とは直接的な連続性をもたない自立した評論である。8号室の共同性は相当に衰弱していたと思われる。
その1年後に藤井一が発言したとおり、〈僕らの問題は極端にいえば、国家から自分が生きていることまで語ってしまわなければならなかった。表現論が拡大し、自分のなかで拡散してしまっている〉 (『漆黒の馬』第22号、1979年12月)ということになったのではないか。
ギャラリーUやウエストベスギャラリーなどの現代美術画廊がぼちぼち増えてきて、ようやく名古屋の若手にとっても画廊を基盤とした活動が可能になってきたことなどが影響したとも考えられる。運営メンバーの一部は、そうした外部の現代美術画廊で作品を発表するようにもなっていた。
しかし、だからといって〈国家から自分が生きていることまで〉語った8号室の課題が解決したわけではない。8号室の課題は、1980年7月末の閉室をへて、新しい展開のなかに継承されていく。末期に関わりをもった嶋村博が当時を回想して、〈閉鎖直前の8号室から「現代美術・岡崎」が生まれたのは、種子を残そうとする植物のメカニズムに似ている〉(『裸眼』第10号)と語っている。
「現代美術・岡崎」とは、よねづたつひこの呼びかけで1979年に始まった現代美術展のことである。岡崎・豊橋・名古屋の若手作家による規模の大きい自主企画展であり、嶋村博、アマノ潤、森三子男、味岡伸太郎、金田正司らが参加し、1986年までつづいた東海地区にはめずらしいアンデパンダン展でもあった。第1回展の企画段階から8号室に協力要請があって関わりを深めていき、結果的に8号室の運動性の一部がこの岡崎展に継承されたと見てよいだろう。
私は1976年10月に「宵茶会(会式・団茶)」というのを企画している。これは米やら牛乳やらを混ぜ入れたお茶、とても飲めたものではない代物をすする茶会であった。私の場合は、共同性議論が堂々めぐりになる危惧を初期から感じていて、少しばかりイラだっていた。自分たちの議論を文化的な広がりに結ぶ必要があると思って、世阿弥『花伝書』、岡倉天心『茶の本』の読書会を提案し、その仕上げに「宵茶会」を企画したわけだ。
そして、こうした路線の延長として、閉室後に「思索過程としての日本・アジア研究会」を立ち上げた。会合場所はあちこちの喫茶店で、教材は岡倉天心、九鬼周造、ガンディー、柳宗悦などだが、当然ながら教材に縛られない自由な議論をしたはずである。常連メンバーは、私、鈴木敏春、西島一洋、よねづたつひこ、大賀たいが、三浦幸夫、中島智などであった。
この研究会メンバーによって研究会組織とは別に「ON THE BEACH」が発行され、1986年に研究会組織と統合することで批評誌『美術読本』が生まれた。ただ、アトリエ出版社による『美術読本』発売禁止事件(誌名の商標登録をめぐるトラブル)のため、第3号から『裸眼』に名称変更することになった。スタートしたばかりなのに、早くも現実社会の制度に衝突してしまったのである。『裸眼』については、今回の執筆依頼の対象外であるのでこれ以上は触れないが、8号室の種子が育った木の一本であることはまちがいない。
さて、8号室を総括するとどうなるのか。国家から私まで、8号室の課題はなるほど大きかった。しかし、大げさだったわけではなく、政治や社会、生活といった一人の人間としてなら誰もが抱えている課題を、表現や美術と結んで考えたかったし、結んだところで生きてみたかったにすぎないのである。そして、現代美術にベテベタと寄り添っていくことを避けたかった。60年代の熱狂からは距離があり、現代美術をいくらか醒めて見ることができる位置、否、そうしなければならない位置にあったと思う。
もちろんその位置からどれだけの成果をえたのかと問われたら、目に見えるようなものではないと答えるほかない。が、この時代を始発にした活動は継続したし、8号室をふくめて意義あるものという自負をもっている。
最後に余計なことに触れさせてもらおう。東京中心にコントロールされた現代美術との位置関係のことで、地域の美術活動はどうしてもこの問題から逃れられない宿命にある。なにしろ情報の流れが一方的であるばかりでなく、美術的な感覚や価値観がコントロールされていて、これはマインドコントロールに近いわけだから、影響は大きい。
やっかいなことに、地域の人たちが地域の美術を過小評価してしまっているのである。これには散々苦労した。その経験をいちいち語る気にはなれないが、過小評価をはねかえすために、ずいぶん余計なエネルギーを費やしてきたことも確かである。
自分の活動を振り返ると、そのために時代とともに戦術を変えてきたような気がする。ある時期からは、地域の歴史が把握されていないことが文化的弱点になっているのではないかと考え、朝日新聞(名古屋)に1999年1月から翌年3月まで連載した「化石の美術神話」で、名古屋戦後美術史の発掘を試みた。結局、これが名古屋の美術に関わる最後となった。
今は戦術どころか、戦略を変えたようなもので、昨年は『前衛いけばなの時代』(美学出版)を上梓し、さらに現在、山下清の研究に手を染めている。ただ、現代美術の誤りや欠落部分を見つめているということでは、8号室時代から連続する道を歩んでいると思っているし、自分の仕事の手法をたいへん名古屋的だと感じている。
以上、「8号室~国家から私まで~」
(『REAR』№6 2004年春号、リア制作室)に加筆
追 記
8号室には感謝しかない。帰郷後の文化的な「飢え」をここで凌ぐことができ、非常にありがたかった。本当に救われたのである。展覧会やイベントも楽しかったが、対話会と称して頻繁に議論したことが、飢えていた私には、とくに楽しい思い出である。この頃から自分の主軸を言論に移し始めていたのかもしれない、ともかく議論が好物だった。
明言しておきたい、こうした「場」は、美術館、画廊、学校教育、公式の講座といった美術システムでは生まれないし、成立しない、と。
