
「コロナ禍と出会い直す」を読んで
最後のお別れすら許さない病院、
火葬すら立ち会わせない予防策、
子どもたちへの黙食指導、
至る所に設けられたアクリル板、
炎天下でも外せないマスク、
連呼された「気の緩み」ーーー
あの光景から希望を紡げるか?
2020年にやってきたコロナ禍を、人類学者である磯野真穂さんが振り返る「コロナ禍と出会い直す」。

当時の思いを振り返りながら、自分には考えが及んでいなかったことも多かったと、とても興味深く読みました。
人類学の中でも、病気や医療に関連した事柄を文化的側面や社会的側面から研究する学問である、医療人類学を専門とする著者の磯野さん。
学問の詳しい分類はわからないけれど、医師や医療という視点ではなく、人類という観点からみた考えは、私たちの実際の生活に根差したもので、とても理解しやすかった。
一見、日本の感染対策を否定しているようにみえるかもしれないけれど、決してそんなことはない。
未知のウィルスがもたらしたあの状況に対して、どう対処すれば良かったのか、医師や専門家も、誰も「正解」はわからない。
けれど、その「わからない」ことに対して、自分で考えて判断し、責任をもって行動することがいかに重要か、同じような状況が再びやってくるその時までに、しっかりと考え直すことが必要だと感じました。
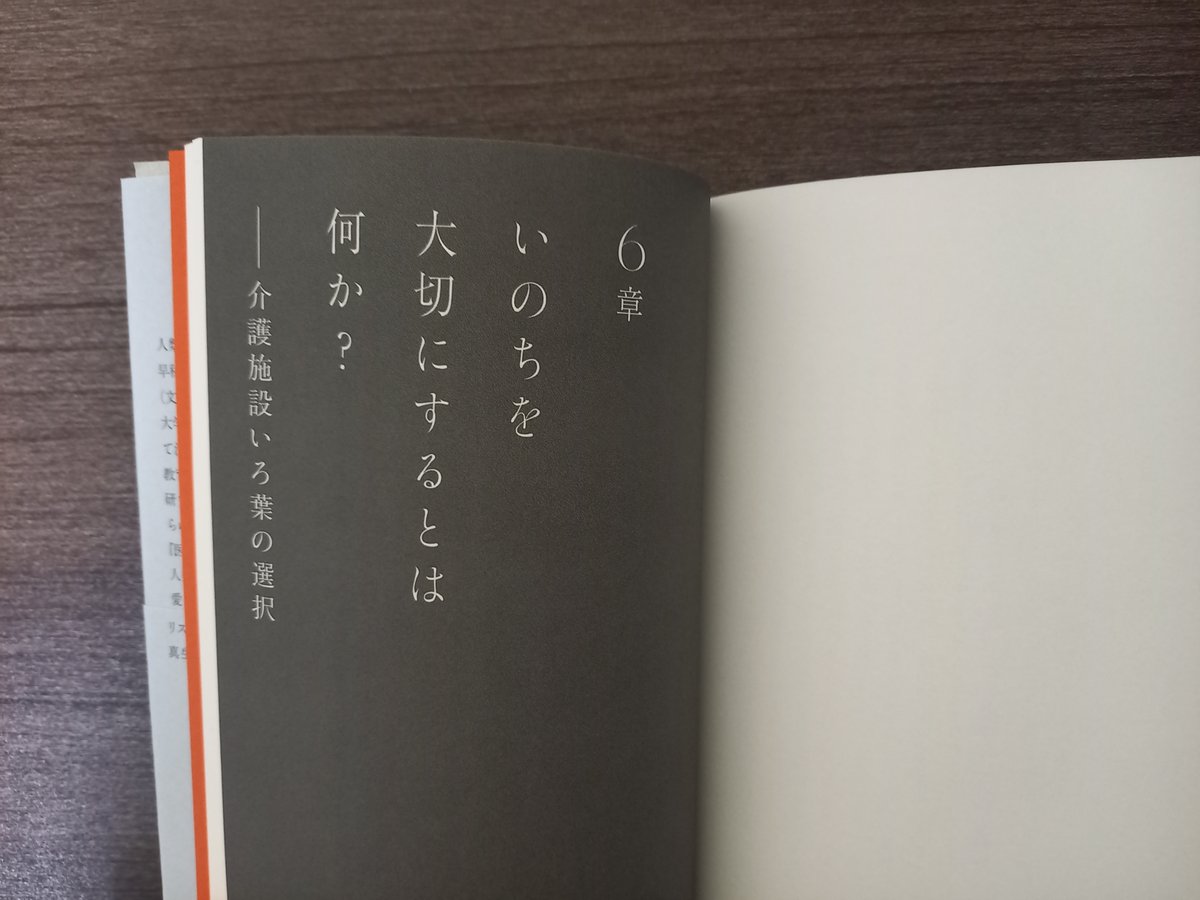
なかなか、自分の言葉で感想を書くのは簡単ではないので、印象的だった箇所を引用してご紹介します。
気になった方は、ぜひ読んでみてほしい。
2章
医療人類学にとって、病気とは何か
ある病気について生物学的、あるいは疫学的に正確に理解しているかどうかと、その病気に対してどう対応することが良いかを知っているかは、本来別の問題だ。しかし、こと病気に関してはそれが混同されやすい。その理由は、疾病の正確な理解が病気を治すことに多くの場合つながることが一つ。もう一つが、医学が生命保持に最大の価値を置く実学であり、それはほとんどの場合、疑われることがないからだ。
結果、「自分たちは専門家なんだ、おまえたちは素人なんだ」「おまえたちは分かっていないから教えてやるが・・・」という医療者や専門家にありがちな態度と、それに反論できない素人という構図が出来上がってしまう。
4章
感染拡大を招いたのは、国民の「気の緩み」?
日本は気の力でコロナを抑え込めると思っていたし、気の力で実際にコロナを抑え込んだ。そう言われたら皆さんはどう思うだろう?
そんな馬鹿なことあるはずない。今は21世紀ーー。
そう感じる人も多いかもしれない。でもそんなことはないのである。政府・自治体や専門家、さらに感染拡大を心配する街の人々は、感染者が増える度にその原因を「気の緩み」に求め、また緊急事態宣言などの制限が緩和される度に、その緩和が「気の緩み」を招いて感染の再拡大につながることを心配してきた。
