
物理重問シリーズ 2023復習編 問題86~90
2024年度東大入試(物理)に立ち向かう受験生の皆さま、こんにちは。
2023年8月24日(木曜日)、本日も私との楽しい触れ合いのお時間がやってまいりました。おかげさまで本日で1147日連続投稿となりました。
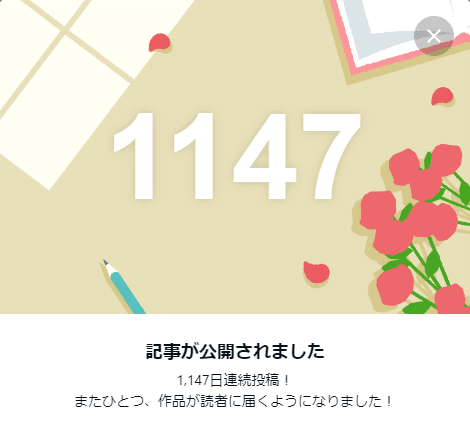
当記事はmitty note「物理重問シリーズ」の復習編となります。
2023年3月から8月にかけての6か月間にわたる通期講座(毎日講座)「物理重問シリーズ」で学んだ重要論点をざっと拾っていけるように、物理重問シリーズの各記事の最後のまとめの部分、すなわち
《今回の演習を通して学んで頂きたいポイント及びアクションプラン》
の部分を抜き出して大問ごとに提示していきます。
「そういえばそんな論点あったよなぁ」と思い返しながら目を通して頂ければよい復習になると思います。
復習はモチベを保つことが難しくて一人ではなかなかうまく進めることができないものです。当シリーズ復習編を重問の復習のペースメーカーとしてご活用いただければ幸いです。
🌟 これから物理重問シリーズを受講しようと考えていらっしゃる方への宣伝も兼ねていますので、復習編は一般公開(無償記事)とします。
【物理重問シリーズ 2023復習編】
《問題86》
《今回の演習を通して学んで頂きたいポイント及びアクションプラン》
① 屈折の法則は「n sinθ=一定」の形を使う。
② 全反射する条件は「入射角>臨界角」。(🌟 等号は入れてもいいです)
③ 波長が短いほうが屈折率は大きくなる。
④ 可視光領域での波長と色の関係「紫<青<緑<赤」を常識とする。
⑤ 紫色は~400 nm、青色は~450 nm。
⑥ 半導体発光素子LEDの正式英語名称は「Light Emitting Diode」。
《問題87》
《今回の演習を通して学んで頂きたいポイント及びアクションプラン》
① レンズの問題ではレンズの公式 1/a+1/b=1/f を使う。
②「レンズの公式」という用語は答案に使ってよい。
③ 次元を意識するとケアレスミスなどに気づくことができる。
④ b>0は実像、b<0は虚像。
⑤ 組み合わせレンズの問題の定石を身につける。
《問題88》
《今回の演習を通して学んで頂きたいポイント及びアクションプラン》
① 球面鏡の結像公式は1/a+1/b=1/f。(🌟 レンズの公式と同じ形です)
② b>0は実像、b<0は虚像。(🌟 レンズの場合と同じです)
③ b>0のとき像(実像)は球面鏡の前方にあり、b<0のとき像(虚像)は球面鏡の後方にある。(🌟 レンズの場合と逆ですので注意しましょう)
④ aとbが同符号のときは倒立、異符号のときは正立。(🌟 これはレンズの場合も球面鏡の場合も成り立ちます)
《問題89》
《今回の演習を通して学んで頂きたいポイント及びアクションプラン》
① 微小近似の計算を用いてヤングの実験の経路差を求められるようにする。
② ヤングの実験の経路差(光路差)は「下側ルート-上側ルート」と定義するのが便宜で通例。(🌟 x>0のときに経路差(光路差)>0となって両者の符号が合うので便宜だからです)
③ 干渉条件の式を立てられるようにする。(経路差バージョン)
強め合う条件:経路差=半波長の偶数倍 (波長の整数倍としてもいいです)
弱め合う条件:経路差=半波長の奇数倍
※ 経路差を使う場合は「経路差が生じている経路中の波長」を使います。
④ 干渉条件の式を立てられるようにする。(光路差バージョン)
強め合う条件:光路差=半波長の偶数倍 (波長の整数倍としてもいいです)
弱め合う条件:光路差=半波長の奇数倍
※ 光路差を使う場合は「真空中の波長」を使います。
※ 光路差=絶対屈折率×経路差 です。
⑤ 光波干渉の問題、特に状況が複雑な問題では、経路差よりも光路差で議論したほうが便宜となることが多い。
⑥「m次明線」とは「光路差がm波長、すなわち光路差の中にm個の波が入っている状態の明線」のこと。
⑦ 2001年度(前期) 東京大学 第3問 ヤングの実験 を演習しておく。
《問題90》
《今回の演習を通して学んで頂きたいポイント及びアクションプラン》
① 真空の絶対屈折率は1。
② 空気の絶対屈折率は特段の指示がなければ1としてよい。
③ 回折格子の場合、m次明線をm次回折光と言うことも多い。
④ m次回折光は経路差(光路差)の中にm波長入っている。
⑤ 経路差で議論するときは経路差が生じている経路中の波長を使う。
⑥ 光路差で議論するときは真空中の波長を使う。
⑦ 回折格子の強め合う条件(経路差バージョン)
経路差=波長の整数倍
※ 経路差を使う場合は「経路差が生じている経路中の波長」を使います。
⑧ 回折格子の強め合う条件(光路差バージョン)
光路差=波長の整数倍
※ 光路差を使う場合は「真空中の波長」を使います。
⑨ 回折格子の強め合う条件は「半波長の偶数倍」と書くよりも「波長の整数倍」と書くことのほうが多い。(🌟 まぁそうは言ってもどちらでもよいです。参考書/問題集によってもまちまちです)
⑩ ブラッグ反射の強め合う条件(ブラッグの反射条件)は「波長の整数倍」と書く。(🌟 ブラッグの反射条件は慣例的にそうします。「半波長の偶数倍」と書くことはしません。郷に入れば郷に従いましょう)
⑪ 可視光領域での波長と色の関係「紫<青<緑<赤」を常識とする。
【物理重問シリーズの受講を希望される方へ】
2023年3月から8月にわたる毎日講座「物理重問シリーズ」は先日無事に終了しましたのでアーカイブとして分野ごとにまとめた講座に再編しました。
アーカイブといってもこれまでと同様、質問相談などの対応も行いますのでどうぞご安心ください。
<物理重問シリーズの概要>
・重問の全問題(156題)に対して私の東大形式のオリジナル解答例を提示
・別解や重要論点なども補足資料で提示
・設問ごとに私のコメントあり(たまに雑談コーナーとかもあります…)
・分からないところは私に質問相談が可能
レジュメ教材(オリジナル解答例/補足資料)はPDFファイルとして提供します。全部で約500ページの大ボリュームです。印刷してコクヨフラットファイル(またはコクヨチューブファイル)に綴じ込んで製本してください。
参考:物理重問シリーズのレジュメ教材の見本
<重問37>


<重問89>


<重問140>

🌟 原則として高校物理の範囲内で解くようにはしていますが、必要に応じて微積も適宜使います。
受講を希望される方は以下のページをご覧いただいたうえでメンバーシップ「物理重問シリーズ」へご参加ください。
【お問い合わせ先】
ご不明な点やご参加前に相談したいことなどございましたらご遠慮なくお問い合わせください。
noteの「クリエイターへのお問い合わせ」
https://note.com/mitty77777/message
または
Blogの「お問い合わせページ」
https://mitty77777.blogspot.com/p/contact.html
📧 クリエイターへのお問い合わせ 📧
https://note.com/mitty77777/message
📔 note 📔
https://note.com/mitty77777
🐦 Twitter 🐦
https://twitter.com/mitty77777
🖊️ Blog 🖊️
https://mitty77777.blogspot.com
🌙 サポートもお待ちしています 🌙
いいなと思ったら応援しよう!

