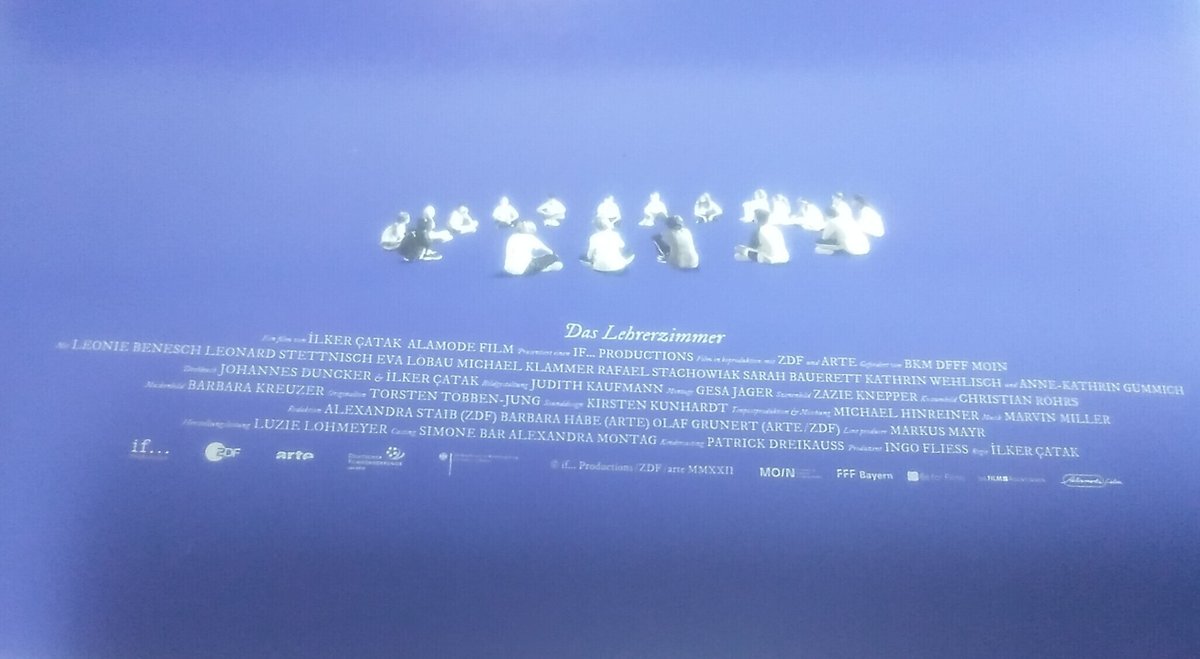【映画】真綿で首をしめるようなリアル「ありふれた教室」感想(ネタバレあり)
予告編を観て「公開されたらすぐに観に行こう」と思っていた映画「ありふれた教室」を、やっと観に行った。~と6月に感想を書きかけてから、何度も読み直して、なかなかUPできずに寝かせていた。かなりいい映画なので、ちゃんと書かなくては、という気持ちで。が、今、8月。
これは、映画「聖地には蜘蛛が巣を張る」を観た後になかなか感想をUPできなかった感じに似ている感覚だ。どちらも、深く考えさせられる、インパクトのあるいい映画。
早く感想をUPしたいとは思いながら、「よかった」と思えば思うほど、色々なことを考えてしまってなかなかUPできるような文章が書けなかった。結局まとまらず、とりとめのない感想にしかなっていないが、UPしておきたい。

学級崩壊を描いた映画「ありふれた教室」
最初はうまくいっているように思えた、とある中学1年生の学級が、盗難事件をきっかけにガラガラと学級崩壊していく様子を描いた映画。主人公は赴任したばかりの担任。ポーランド系ドイツ人女性カーラ・ノヴァク(レオニー・ベネシュ)。イルケル・チャタク監督の作品。
職員室あるある感のある、原題「教師の部屋」
ドイツ語のオリジナルタイトル「Das Lehrerzimmer」を直訳すると「教師の部屋」(英題「The Teacher's Lounge」)というだけあって、教室を描いているようで、職員室や事務職員など「大人側」のあれこれを描いている部分も大きい。(ちなみに、この映画のパンフによると、ドイツの学校には、各教師が自分のデスクをもっている日本のような職員室はなく、授業の合間の一時滞在所のような部屋があるだけで授業が終わると教員は基本的には帰宅するスタイルとのこと)
その描き方も、リアルだ。そこにいる色々な教師のタイプも、「いるいる」と思える色々なタイプ。国は違っても、教員の種類というのは似てくるのかもしれない、とも思った。
主人公はダメな教師ではない
主人公は悪い教師ではない。むしろ高い志をもち正しいことをしている。0.999と1が同じか違うか証明するように、0.001の違いも追求するような正しさ。でも、その生真面目さゆえに微妙な違いが澱のようにたまって学級崩壊につながっていく感じがジワジワと描かれている。リアル&コワイ。
前半、順調な頃のズレ
映画が始まってすぐ、主人公の教員が担任しているクラスで強制している朝の挨拶を観て、ギョッとした。思い当たる、似ている授業の様子があったからだ。とはいっても、人づてに聞いた話で。
私が中学校で教員をしていた頃、初任者が「初任者研修として参観した授業が気持ち悪かった」という話をしてきた時に聞かされた授業と似ていた。地域全体の研修として、小中の初任者全員で小学校の授業を参観する日だった。そこで「クラスのルール」としてしていたことが腑に落ちない、という。誰かが発言した後に、どんな発言でも、クラス皆で声を合わせて「いいね、いいね~」と決まったリズムで手をたたく、というルール。誰かが発言するたびに、全員そろってやっていた、という。その初任者は、ふだん教育について語るタイプではなかったけれど、その時だけは「統率がとれていればいい授業といえるのか?気持ち悪くなった。いい授業とは何か?」と熱く語ってきた覚えがある。
初任研は退勤時間くらいまで行われる。なので、いつも残業している初任者でも、初任研の日くらいは、所属校に戻ったとしても「終わりました」と報告してすぐに帰宅するか、電話で所属校に「終わりました」と連絡して直帰することが多かった。が、その日、直帰してもいいところ、わざわざ所属校に戻って語ってくる初任者は、「帰るよりモヤモヤした思いを話したい」という感じだった。その授業について疑問に思ったことを話してくる様子は、本当に戸惑った感じがして印象に残っている。とはいえ、完全に否定するほどダメなわけではない。「また聞き」では、なおさら。そのルールができた経緯やクラスのメンバーについての配慮などの結果、なのかもしれない。初任者にひととおり話を聞いて、考えられる色々なことを話したような気がする。とはいえ、本音では私も「確かに、いっせいにするというのは異様」と思った。立場上、完全否定はできないので色々な可能性は示したが。(関係者が特定されないように細かい設定はぼやかして書いています)
この映画の前半も、まさにそうで、「完全に否定するほどよくない指導をしているわけではない。けれど、ちょっとずつズレていて、それが気持ち悪い」という感じ。もし同僚に主人公のような教員がいても、何か言いにくい感じだ。思いっ切り的外れなことをやっていたら、まわりも気づいて指摘できる。微妙なヘンさというのが一番やっかいかもしれない。まわりが口を出しにくいというのは、まわりが助けにくい、ということにもつながる。しかも主人公は、何かというと子どもと二人きりにしてほしがるような自信家だ。
映画の後半、学級崩壊してしまってから、「朝の挨拶は先生のためにやっていた。あんなの幼すぎてやる気にならない」と子どもが主人公に本音をぶつけるが、まさに映画での最初の頃の平和で統率がとれた教室は「先生(主人公)のためのもの」に見えた。体育の授業も。「先生が一番楽しそう」と。
教員が楽しんでいけないわけではない。けれど、随所に子どもがおきざりになっている場面がみられる。例えば、最初の方で問題を解いている子ども達を主人公が机間巡視する様子があるが、主人公は全体をみているわけではない。目についた子どもにコメントをしながらリズムよく回っていく。主人公を目で追っている、主人公に質問したいような態度の子どもには気づかない。
主人公は悪い先生ではない。むしろ情熱をもって指導にあたるよい先生だ。が、ちょっとズレている。そのズレが、子ども、同僚、上司(校長)、事務員、保護者、カウンセラーと全方向に対して少しずつズレてしまったことにより、学級崩壊がおこる。始まりは少しずつのズレだけれど、それが重なると崩れる。そして、一度崩れると、もう、少しの何かではどうしようもない。
後半、学級崩壊にならない可能性はあったか?
教員を対象とした鑑賞会をやったら面白そうだとも思った。憂鬱にはなりそうだが。「主人公のどの言動をどうすれば事態が変わる可能性があったと思うか」というような観点でみて指摘してみたら、色々な着眼点があって面白いかもしれない。もちろん「絶対いいこと」ということはない。パラレルワールドのように、誰がどう指導を変えてみても結局は学級崩壊エンディングしかないのかもしれない。ただ、外国での架空の話として、誰も傷つけずに指導に関して考えるネタとして話すと面白いのではないか、と思った。現状で困っていることを出し合ったり話し合うような研修は、ともすれば当事者をよけいに傷つけることにもなるからだ。
すでに教職を離れて何年もたつ立場だけれど、私が気になった点としては…
主人公が子どもに「二人きりで話したい」と言われた時、二人きりになるべきではなかったのではないか、と思う。後半では、自ら子どもと二人きりになろうとするが、もめている時ほど他の教員に同席してもらった方がいいと思う。第三者が入ることによって、言った言わないという事態になるのを防いで自分の身を守ることにもなる。また、トラブルになってしまった今までの自分の観点が歪んでいることもありうる。自分の目で見たり感じるだけではなく、客観的にみてどう感じるか、第三者の感覚をきくことができる機会でもある。こちらから頼み込んででも同僚か上司に同席してもらった方がいいと思う。
また、もめている事務員クーン(エーファ・レーバウ)の息子オスカー(レオナルト・シュテットニッシュ)が放課後教室に残っているのに対して、ルービックキューブを渡していたが、ここでも母親について話したくて残っているオスカーとズレているように感じた。押し付けるようにルービックキューブを渡すより、子どもがどうして残っているのか考えて、子どもの話を聞いた方がよかったのではないか。
さらに、オスカーにパソコンで殴られて目をケガしたことは、同僚に隠すべきではないと思った。職員に周知して、それに対する罰を与えた方がよかった。子どもをかばうというより、「子どもに殴られた自分」を認めたくないだけのような印象を受けた。パソコンを奪うためとはいえ、結果的に教員に暴力をふるったのに、それをなかったことにされるのは、オスカーにとってもよくない。他の子どもにとっても。
また、子どもたちが作った学校通信についても対応に疑問を感じる。子ども達に対しても同僚に対しても溝を深める結果となってしまったと思う。内容が不適切だと気づいた時点で、校長などに言って発禁にするべきだったのではないか、とも思う。
最後、もめにもめているのに、鍵をかけてまで他の教員を締め出して子どもと二人きりになるのは絶対やめるべき言動。結局説得できずに警察を呼ぶことになっている。
主人公は、最後に同僚のトーマス(ミヒャエル・クラマー)に「助けて下さい」と言っている。もっと早い段階で同僚に助けを求めた方がよかった。いい支援が受けられるかどうかはわからないが、人間相手なので、自分(担任)と相性がよくない子どもが違う先生にはこんな面を見せていた、というような情報はもらえた方がよい。子どもの親がタクシー運転手だからといって見下したり偏見の強い、いけすかない同僚だとしても。子どもを一人で教育することは不可能だ。
主任のような教諭ミロス・ドゥデク(ラファエル・シュタホヴィアク)に「(オスカー以外の)他の子どものことも考えろ」というようなことを言われる。まさに、私もそう思った。問題を起こす子どもを指導することも必要だが、その子どもを追いかけていくことで、それ以外の子どもがおきざりにされるのはおかしい。
他にも色々と、「?」とズレを感じる部分はあった。教員が鑑賞した時にどう感じるのか、興味がある。
この映画の、最後の救いのようなもの
おそらく主人公は相当傷ついている。が、最後に同僚に助けを求めることができたのは救い。とはいえ、最後に校長や同僚を締め出して鍵をかけるほどに自分の指導には絶対的な自信をもっていたのに、結局説得できなかった。途中で主人公は、職員会議で「教員を辞めたい」というようなことをもらし、「教員不足なのに!」と同僚に一蹴されていた。自分の指導がうまくいっていないことへの自覚はある。せめて担任を外してあげられるといいのに、とは思うが、年度末まで叶わないのだろう。
最後の終わり方も秀逸だ。出席停止なのに登校してきたオスカーは、主人公が渡した水は飲まない。かつて主人公が「できるまで貸してあげる」と渡したルービックキューブをササッとそろえてみせて返す。主人公の気持ちと通じたのか?と思いきや、そこから場面は変わり…王様のように「自分は間違っていない」というような表情で椅子ごと警察に持ち上げられて運ばれて行くオスカー。
主人公の様子はわからない。オスカーを映し、映画は終わる。うちひしがれた主人公が目に浮かぶようだ。
が、本当に唯一の救いは、主人公が周りに助けを求めることができるようになったこと。信じきらなくてもいい。ほんの少しでも周りの力を借りながら、なんとか年度末まで乗り切ってほしいものだと思う。そうでなければ、鬱病で休職になってしまいそうな危うさを感じる。保護者会で過呼吸になっていた伏線もある。その保護者会の荒れっぷりを面白半分にからかってくる同僚。とはいえ、そんな同僚にも協力してもらわないと立ち行かないだろう。つらい状況だ。が、かなりリアルだ。まさに「ありふれた教室」。
学校のリアル
パンフに三楽病院の医師が寄稿していた。「学校のリアルを知ってほしい」という切実な。
三楽病院は東京都教職員の指定病院。現職時代には折々お世話になった。たぶん、そこの医師であれば教員を山ほどみてきているのだろう。実感がこもるメッセージだと思った。