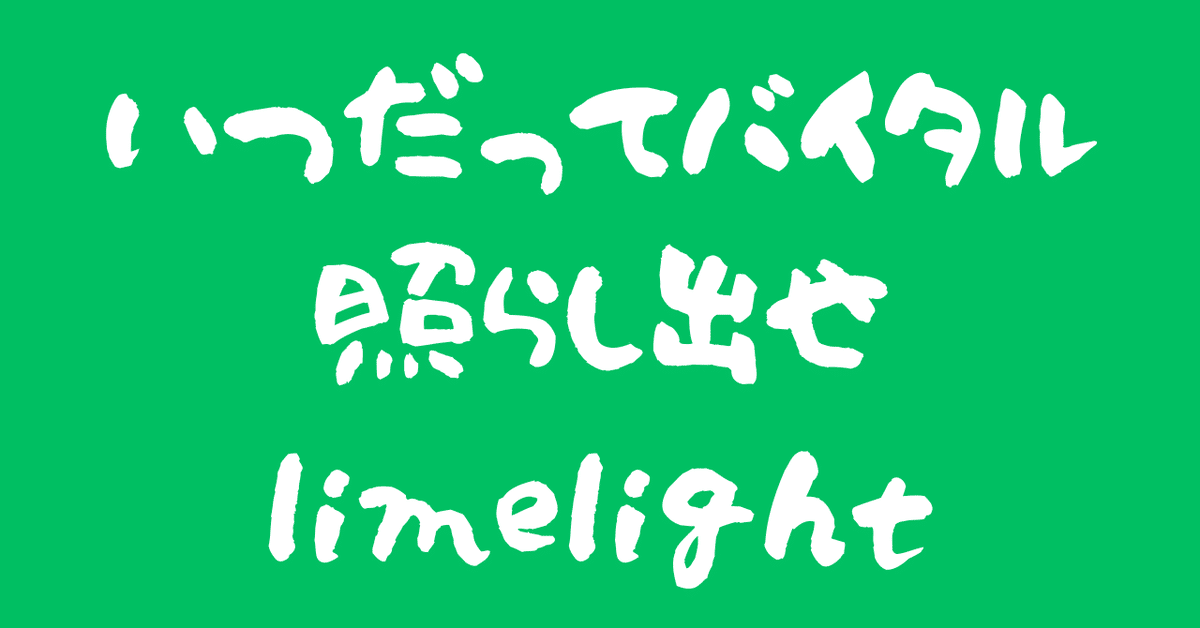
【音楽語り】この世は舞台、ひとはみな狂人「ライムライト」【ボカロ】
刺されてから気付く蜂の毒
ここに蜂屋ななしという天才がいる。
天才だと言い切らせてもらう。だがもちろん、天賦の才だけでトントン拍子に売れた方だとは言わない。むしろ、ご本人の蜂屋ななしさん(現在はボカロPとしての活動を卒業し、栗山夕璃さんとしてご活躍中)は、大学進学で大変な目に遭ったり、病気で入院生活を送ったり、インタビューの話を聞く限り並々ではない逆境に遭ってきた苦労人である。
(参考:https://nanamagazine.blog.jp/vocaloid005)
そんな蜂屋ななしさんのデビューは、我が身にふりかかる理不尽な出来事への負のエネルギーを込めに込めて聴いた人を不快にさせる曲を作ろうとしたのがきっかけらしい。すごい。アーティストとして模範解答であろう「聴いた人を笑顔にできる曲を届けたいです!」という光属性コメントの対極を行ってる。イメージするなら、聴いた人間が自殺するという噂で名高い曲「暗い日曜日」のやわらかめバージョンを目指していたということだろうか。下手すりゃ一種のテロ行為じゃねえか。
しかし、残念なことにこの目論見は外れた。
なぜなら、蜂屋ななしは天才だったからだ。
このボカロPから作り出される曲は、聴いた人を不快になどしなかった。
そればかりか……………………その向こう側に行った。
もし私が道を歩いていた時に、通りすがりの誰かが「蜂屋ななし? あー、ボカロPにキョーミないわw」などと言っているのが聞こえてしまったら、コンマ何秒で助走をつけて殴りかからざるを得ない。そしてそいつの頭を鷲掴んで固定し、耳にイヤホンをねじ込んで、この曲を大音量で流してやるのだ。
蜂屋ななし「ライムライト」feat.初音ミク/GUMI。
ライムライト最高! ライムライト最高! さあ貴様もライムライト最高と叫びなさい!
蜂屋ななしさんがインタビューで「1曲だけ自分の音楽を聴いてもらうとしたらこれ」と答えている、この「ライムライト」。
クラリネットを始めとし、ギターもベースもすべて音大の友人による生音の録音だというこの曲、ご本人も「とにかく『音がいい!』という曲」とおっしゃっている通り、音のクオリティも作り込みも圧巻だ。
また、タイトルの「ライムライト」には「lime right(名声)」の意味だけでなく、実は「rhyme(韻) light」の意味もかかっており、その名の通り英語も挟みながらさりげなく韻を踏んでいく歌詞はしびれるほどカッコいい。
さらにそこへ、古論さんによる中毒性のあるMV、間奏で差し込まれるワブルベースの機械的な重低音が加わり、そのすべてが融合してハイテンポなジャズ調のエレクトロスウィングに仕上がったのが、めちゃくちゃスマートでオシャレで知的で頭良くてクールなこの傑作というわけである。
なのだけれど、その根底に横たわっているのは恐ろしく冷徹な目で見つめられた狂気とでも言うべきシロモノであり、どうしても「ものすごく口当たりのいい劇薬」という印象を捨てられない。
そもそも蜂屋ななしさんの初期の曲は、狂気、退廃、憂鬱、病気、宗教などをテーマにしているものが多く、それらの重たいモチーフをクレバーに皮肉ってみせるような洒脱さが魅力のひとつだ。
だが、それだけでは済まないのは、そうやって冷笑している"こちら側"の正気の目線も、本当はどっぷりある種の狂気に浸かっているという、どうやっても逃れられない二重構造のせいだ。
それがこの「ライムライト」には比較的分かりやすく表れていると思う。
単に狂気を歌っただけの曲なら、それこそボカロにはかなりある。
しかし「ライムライト」は、あからさまな狂気からは一歩引いている。音の作りも歌詞もハイレベルに知的で、どこか危険な香りをただよわせながらも、それを上質のエンターテイメントとして昇華してみせる余裕がある。
冷静だし、正気なのだ。
言うなれば「狂気を演じる舞台の上の俳優」目線の歌のよう。狂ったかのごときポーズはしてみせるけれど、観客(=視聴者)を見下ろす目は冷静で、この脚本や舞台、狂気を演じる自分ごと冷笑している、そんな気だるげな俳優のイメージ。
実際、歌詞にも「ステージ」「ランスルー」「オーディエンス」と、演劇に関連するワードが散りばめられているし、そもそもタイトルが「limelight(名声)」だ。このくだらない舞台、この狂った世界にはうんざりするが、せいぜい上手くいい役を演じて名声を掴んでやろう、オレは正気だぜ。そんな野心をダルそうに語るアイロニカルな青年の姿が浮かんでくるではないか(妄想)。
しかしその昔、兼好法師は『徒然草』でこう言った。
「狂人の真似とて大路を走らば、すなわち狂人なり」と。
狂気的な世界観にうまく合わせることができてしまう”正気”は、既に狂気の内に取り込まれている。
青年は実は、もう手遅れだ。
クレバーなメロディと歌詞に魅せられている我々「オーディエンス」も、狂乱からは逃れられない。
あまりにも曲がカッコイいいものだから、初聴では気付かないかも知れない。だが、音のグルーヴに乗って身体を揺らしていると、ある時「あれ?」と気付くのだ。さながら、蜂に刺された毒が後から回ってくるように。
もしかして、ヤバいもの見ちゃった?
参加者大歓迎、野次馬お断り
Non stop talk tole.
Check, chik tap tip.
Fake! your part time sympathy.
Hold ,Tod's doll.
Let's nope hope.
いないいない、不甲斐ない有神論
さっそく歌詞の頭がいい!!!(あたまのわるいかんそう)
言葉あそびのように並べられた英単語は、まるで残酷なマザーグースの詩のような軽妙さとほんのりした不穏さを醸している。日本語になったかと思えば、さっそく皮肉げに踏まれる韻。
不穏なのは歌詞だけでなく、どこかの廃病院("abandoned hospital)を描いているらしいMVのアニメーションも、裏で何かのストーリーが進行していることを示している。しかし、使われる色彩が鮮烈で明るいこともあり、歌詞と同様、重たいモチーフをポップに表現しているのがすごい所だ。
Stop scoff smile.
Feel! zielen fool.
Sick.I'm chosen by god's world.
救いは無いけどね笑笑
この冷笑的な感じ! 「笑」を二連続させるところすごい鼻で笑ってる感あってめっちゃイイ!(語彙力の低下)
そのくせ「そのscoff smile(嘲笑)をやめてくれ」「オレは神の世界に選ばれたんだ」と言ってるところも、語り手の精神の不安定さが表れているようで実に不穏だ。もしくは、複数の人間の声が混ざり合っているのかもしれない。適当な言葉で聴き手を煙に巻いているようでもある。「zielen」に至ってはドイツ語だ。つまりめちゃくちゃ頭がいい(結論を放棄した)。
そもそも「ライムライト」は、歌詞もMVも暗示的なもので、こうして解釈すること自体が野暮なのだけれど、ここまできたら走り抜けてしまおう。既にファンの方はご自分の解釈と比較しながら、まだ聴いたことのない人は至急YouTubeに飛んで再生しながら、私の妄想にお付き合いいただきたい。
敵わない夢はGroovin'
贋作探し出して。Search light
生命賛否、笑えやDr.Shambles.
疎外感飲み込むCartridge
鬱憤さぁ吐き出すDead seed
賛美の感染症
あえて「叶わない夢」ではなく「敵わない夢」にしてたり、「賛否」と「賛美」の配置など、日本語でも言葉のあそびは絶好調である。
「Shambles」とは口語で「めちゃくちゃな状況、修羅場」であり、古い意味では「畜殺場」らしい。擬人化させたShamblesに生命を笑わせる皮肉っぷり、歪んだ知性。聴き手をそのゾクゾクする魅力で引きこんだところで、曲はサビへ突入する。
『散々究明』バカが鳴いて
ちゃちな命の痛みは度外視
眩んだステップ
Don't panic. Warning.
スタンバイステージ
雨まみれ、愛まみえ、踊れやOne scene
いつだってバイタル
照らし出せlimelight
語り手は踊る。
「ちゃちな命の痛み」を「度外視」するバカどもの世界を尻目に、語り手にしか分からない何か切実な思いを込めて、「照らし出せ」とlimelightにステージを託す。
冷徹な知性を持ちながら、この狂気の世界で堂々踊ってみせるのだ。私たちはそんな語り手を、聴き手として客席から見上げている。
MVでも、謎の人物との会話は進んでいき、過去の出来事、ペストルーム、見捨てることが出来なかった「彼」の存在などが暗示される。想像は掻き立てられるが、決定的なことは分からない。どうであれ、そこに容易に触れられない”何か”があることだけ、私たちは知ることができる。
あと個人的な話だが、サビの盛り上がりで駆け上がるピアノがすごいジャズっぽくてすごい好き(好き)。ほんと、雰囲気も歌詞も超いいんだけど、音楽として基本的な「音」がちゃんと最高なの、ほんと最高(最高)。
そうこうしているうちに、一番の余韻を残したまま曲は二番に突入する。
掠れちゃいない以来
追い追い年がら年再上映会
頭は a little bit sensitive
そうさ疾患 惨めな 焼香会
先ほどの間奏で暗示された過去の出来事を示しているのだろうか、トラウマのような光景は「掠れちゃいない」し、年がら年中「再上映会」を繰り返す。「疾患」を抱えて「a little bit sensitive」な頭、その脳裏にちらつく「焼香会」の記憶は、はたして誰の葬式だったのか。
ここを気持ちよく韻を踏みながらテンポよく歌い上げているのがまた、語り手自身が自分の苦しみを客観視して嗤っているようで実にいい。ここまでくると私たち観客は、もはやこの曲が持つ歪みの虜になっている。
全部 フェイク 君は錆れた
模造のスーパーセンス
異論は無いけどね笑笑
タイトルが「limelight(名声)」なのに、「全部 フェイク」で「錆れた模造のスーパーセンス」だと宣告される。それに対して、やはり二つ連続する「笑」が、本性を暴かれてもにやにや笑いを崩さない語り手の姿を彷彿とさせる。
この不安定さ、飄々としているくせに病的な態度。語り手はこの世界だけでなく、自分自身のことも嘲笑しているのだ。
What you gotta do is to lead the dance.
Welcome! doom dowdy doda .
What the take away?
Plants aren't (in) the planet.
怯えてら
All fall down!
『it's time to leave.』
I think You would be better off dead.
Apple is red yet taste is green meen seen.
「君がするべきはこのダンスをリードすることさ」「ようこそ!」
一番とは変わったBメロの曲調が、「You」……もしかしたら観客の私たちを、語り手の踊るダンスのステージに引き上げる。
「All fall down!(すべては終わった!)」「『今こそ去るべき時だ。』」「君は死んだ方がまし(better off dead)だと思うよ」
かと思えば、歓迎した直後に、急に手のひらを返して突き放してくる。おい、死んじゃえばいいはさすがにひどいぞ。
ただ、「better off dead」は役立たずな人間に対して「消えろ」という意味にもなるけれど、耐えがたい苦痛に対して「もう死んでしまいたい」という文脈でも使うらしい。もしかしたら語り手は、私たちにこれから降りかかるであろう苦痛を予期して、苦しむ前に死んでしまった方がいいと警告しているのかもしれない。
「りんごは赤いが、味はまだ青い」というラストのフレーズも意味深である。とりあえず言い回しがめちゃめちゃカッコいい(アホ)。
『臨床実験』罪を抱いて
君が破った約束を凝視
恨んでトリップ
ホルマリン 鑑賞 人生game
掻き出して 吐き出して 誰かのLast show
もういっそランスルー
始まりはlimelight
抱いた罪。破られた約束。ここで初めて「恨み」というハッキリした感情が歌詞に現れる。「掻き出して」「吐き出して」と続く余裕のなさからも、語り手の激情が初めてまっすぐ表現されている。
(「誰かのLast show」ってまさかさっきの「焼香会」の葬式のこと……? と頭をよぎったけど、こじつけかもしれないからカッコで……でもこの曲、誰かの死を引きずり続けている人間の無気力とトラウマと鬱、みたいにも聴けるような……)
「ランスルー」とは、テレビや舞台で、本番とまったく同じように行う通し稽古のことのようだが、リハーサルやゲネプロとは少し違うものらしい。予行演習なので本番ほど真剣に演じないものの、ミスしてもやり直しは無しなので本気度の高いリハーサル、という中間的な位置づけ。
始めから終わりまでぶっ通しのランスルー、それを「もういっそ」と投げやりに宣言して、歌詞は「始まりはlimelight」だったことを思い出す。
そしてぐわんぐわんとエコーがかかり、機械音が混ざり高まっていく音。今までの考察からの勝手なイメージかもしれないが、蓋をされていた過去へと意識がタイムワープしているかのように聴こえる。
記憶の反転。ぎゅんぎゅんと上がるボルテージ、最高潮のところで畳みかけるドラムから、一気に重低音。そしてワブルベースの間奏パートへ。
マジでここの流れ、この間奏がクールで狂っててカッコいい……ちょっと信じられんくらい…………いや良すぎる……良…………はぁ………………(限界)。
さあ、観客が急展開に魅せられているうちに、曲は勢いのままなだれ込むようにラストのサビへ突入する。精神も感情も何もかもめちゃくちゃになったまま、それでも舞台のダンスは続くのだ。
『再三懸命』バカになって
ちゃちな命の嫌みは度外視
望んだsmile
Don’t panic? Warning! SOS!
一番の歌詞を踏襲し、さらに意味を裏返していく秀逸なライム。
あの皮肉げで冷笑的だった仮面は剥がれ落ち、「望んだsmile」「SOS!」と明かされる身を切るような思い。このひりひりする狂おしさ、こんだけ追い詰められているのになお頭が良すぎる故にベスト・オブ・クレバーな韻を踏み続けてしまう語り手の愛おしさたるや。
だって「バカが鳴いて」って嘲笑していた彼(かは名言されてないけど)が「バカになって」ですよ? バカどもは「命の痛み」を度外視したけど、バカになった自分は「命の嫌み」を度外視するんですよ?
で、そんな風に暴走する自分のことを冷静に客観視できてしまっているこの歌詞ですよ?
もう…………もう! もう!! この「知的な狂気」感!!! 頭の良すぎる人が追い詰められてめちゃめちゃになってるこの感じ!!!
世界の無情!!! どうにもならない感情!!! 最高!!!!!
(テメーが一番狂ってる)
くたばったバイタル 要らない要らない
きゃ~~~~~!!!!!(鳴き声)
『精々救命』罪を消して
愛を期待し 罰の遺伝子
背負ったsmile
Shunt 生命証明 宗教ゲーム
嘘まみれ、垣間見え、切り抜いたmy scene
ここでメロディは更なる転調をし、歌詞もさらに一皮剥ける。
罪、罰、愛、生命、宗教、人生における重たいモチーフがてんこもりなのに、ボルテージが最高潮すぎて観客はわけの分からないままノリに乗せられていく。何一つ大団円じゃないのに、クライマックスを迎えてしまう。
そんな観客を置いてきぼりにして、舞台の上からこちらを見下ろす語り手は、いつのまにか成長を遂げているのだ。罪も罰も誰かのsmileも背負って、ついにこの狂った世界で「my scene」を切り抜く。
嘘まみれでもなんでも、ついに彼(妄想だけども!)は自分だけの舞台を手にしたのだ。それは彼が「完全に狂ってしまった」というバッドエンドかもしれないけれど、とにかく、鬱とトラウマの壁を突き抜けたのは確か。
踊る阿呆に見る阿呆、この世は狂人ばかり。
だったらあんたも踊ろうぜ、見ているだけなんて許さない。
熱狂する観客たちは、limelightの光に照らされた語り手のもとへ群がる。
さあ、みんな大好きお待ちかねのラストだ!
遊ぼうぜオーディエンス
野次馬はバイバイ
最高~~~~~!!!!!
はぁ……はぁ……。
こんな長い記事にするつもり無かったのに、書き出したら思いが止まらなかった……ずっと妄想解釈を語ってるだけなのに意味あるのかこの記事……。
改めて思うのは、鉢屋ななしさんは天才でもあるけれど、本当に卓越して頭がいい人なんだろうなぁ、ということだ。
狂気や鬱、トラウマ、その他のあらゆる危険なテーマをどこまでも冷静に観察して、最高品質の音楽に昇華してしまうその手腕。天才天才、狂気狂気と言ってきてしまったが、本当は作曲者である鉢屋ななしさんが一番ちゃんとしてて、一番正気なのである。
(まあ「正気すぎて逆にちょっとおかしいのでは???」という、頭が良すぎる故の逸脱はある気がするけども……!)
あと冒頭で「人を不快にさせる曲を作りたい」と、とんでもない発言を紹介してしまったけれど、鉢屋ななしさんの曲は負のパワーで作られた暗い曲だけじゃないんで……! 特に名義を栗山夕璃さんに変えてからは明るい曲も作るようになったようで、今後もめちゃくちゃ楽しみにしています。
でもとにかく、私が言いたいことは一つだけだ。
みんな「ライムライト」を聴け。蜂屋ななしにハマれ。
そんで聴いたらあなたも感想書いて私に見せて~語ろうぜ~!
