
「蘇る脚気細菌説」②故・松村䏋教授の脚気菌(Bacillus Beriberi)関連論文集
前回の記事↓より、脚気細菌説を追い続けている。
明治のエリート批判している連中は、医学者でもない素人小説家の創作を鵜呑みにしてんだよという内容であり、その続編としての本記事は、有力でありながら忘れられた学説を復活させることを意図するものである。その学説の提唱者たる人物こそ、タイトルにある松村䏋 教授(※以下敬称略)だ。

松村 䏋(まつむら すすむ[3]、1886年(明治19年)5月3日 - 1973年(昭和48年)6月9日)は、大正・昭和期の日本の衛生学者、大東亜官僚。医学博士[2][4]。千葉大学名誉教授。
~経歴~
1886年(明治19年)5月3日、愛媛県に生まれる。
1916年(大正5年)、東京帝国大学医科大学卒業。
東京帝国大学衛生学教室を経て、千葉医学専門学校講師[2]。
1920年(大正9年)、欧米に留学し、1923年(大正12年)、千葉医学専門学校教授となる。
1925年(大正14年)、医学博士の学位を取得した[2]。
1928年(昭和3年)、中国・フランス領インドシナなどへ脚気研究のために出張、
1929年(昭和4年)、米国および南米に出張[2]。
1939年(昭和14年)、興亜院文化部長となり、
以後、大東亜省参事官、南京大使館参事官[1]、赤十字成田病院顧問などを務めた[2]。
著書に『脚気病原論』がある[2][1]。
引用:Wikipedia
画像:相磯和嘉. (1974). 追悼. 千葉医学雑誌, 50(1), 1.
松村の存在を知った切っ掛けは以下の文献である。※顔貌が百●尚▽や★名木×行に似てるから■翼系かと思ったら思った通りだった。思想はどうでもいい。
松村康弘, & 丸井英二. (1986/01/30). わが国の『脚気菌』研究の系譜. 日本医史学雑誌, 32(1), 26–42.http://jshm.or.jp/journal/32-1/index.html
p33より
2-7 松村䏋の脚気菌説
鈴木のビタミンB発見以後、世界的には、微量の新栄養素という新しい概念がもたらされ、ビタミン研究の時代へと突入する。そしてまた、大正3年の第一次世界大戦の開始とともに医学の中心はドイツからアメリカへと移っていった。この頃の我が国の細菌学は第二期に入って居り、「それ迄の発見的細菌学から、いわゆるminute determinant bacteriology」に変わっていった。この時期の脚気菌説を代表するものが、松村䏋の脚気菌である。松村は緒方正規の門下生で、緒方のもとで細菌学、血清学を学び、緒方らとともに恙虫病 の研究に携わったこともあった。松村が緒方に師事している間、脚気菌に関してどれほどの示唆を得ていたか不明であるが、何等かの影響はあったと思われる。
松村は栄養学の立場から、主食物と腸内菌叢との関係を研究中に、この脚気菌を発見した。この菌にはA型とB型の二型があり、A型は神経作用を、B型はいわゆる中毒作用を及ぼし、ビタミン製剤はA型菌を検出する者には効果があるが、B型菌を検出する者には効果がないと述べている。また、白米食の習慣と脚気の伝播流行に関する観察を行った結果、脚気の流行は白米を常食する所にはよく起きるが、白米を常食する所でも、衛生施設の完全な所では脚気の流行がなく、白米を常食しない民族においても脚気の流行があるとして、脚気菌の病原的意義を強化した。そして、「脚気病は之を特殊の伝染病であるとする時に於いてのみ一切の病理解説を満足にかつ完全に解明し得る。」と自ら発見した脚気菌を脚気の特異病原菌とみなし、当時優勢であったビタミンB欠乏症説に反駁し、また中毒説にも反対している。これに対して追試が行われ、結果として脚気と脚気菌との関係が疑問視されることとなった。
重要な点を抜粋すると、
松村の研究室が発見した脚気菌にはA型/B型があり、それぞれ神経症状と中毒症状を起こす
ビタミンB1(チアミン)はA型感染患者には効くが、B型感染患者には効果がない
白米を常食していようと衛生状態の良好な環境では脚気は流行せず、逆に白米を常食しない民族でも脚気が流行することがある
松村の説が後世に語り継がれていないのは、他の研究室での追試に失敗したことにあるだろう。だが、だからといって定説だけで全てが説明できているかといったらそうではなく、特に3は完全に矛盾している。
脚気の定説(栄養障害説)と言えば、精米の過程で糠のB1成分が削ぎ落された米を日常的に摂取(※最近Twitter界隈は懐古主義的に白米食推しだが?)することで栄養の偏りが生じ、相対的なB1欠乏に陥るというものだが、現代のどの文献を読んでも、
白米を常食しない民族(アイヌ民族等)にも脚気が流行する
夏季に集中するという季節性がある
不衛生な密集地帯で発生する
当時からあった上記の批判に何一つ答えず、B1欠乏という定説を意固地に主張するだけであることが疑問だった。定説はこの点に関して、「夏は活動量が増えてB1消費量が増えるから」だと擁護するが、だとするならここに職業差や、後世に重症化遺伝子の特定があってもいいはずだ。しかしそんな職業・遺伝学研究は特に見当たらない。松村も、冬季はB1に富む野菜が不足し、条件としては冬季に流行するはずが現実は逆だと指摘[3,4]しており、定説は明らかに脚気の季節性という特徴を説明していない。
また、前述の引用だと、松村が菌のみを原因と主張したように思われてしまうが、松村は白米の関与を完全に否定したわけでもない。実験室で脚気菌感染を誘発するに当たり、素因として白米食の使用を認めており[6-3]、実験では白米に脚気菌を付着させて食餌させていたのだ。「他の研究室で追試に失敗した」というのは、松村が指摘する素因なくして、普通食と脚気菌のみで脚気を誘発すべきだという揚げ足取りをしていただけに過ぎず、松村もそれは無理難題だと苦言を呈している。とはいえ、脚気菌の"蔗糖 を分解して酸とガスを生成する"という特徴[4,5]からして、必ずしも白米である必要性はないようで、実際、松村の研究室では、白米以外の食餌と脚気菌の組み合わせで鳩以外の実験動物にも脚気様の麻痺症状の再現に成功している。
そしてこの松村の反論は的を射ている。我等がアントワーヌ・ベシャンの言葉を思い出そう。
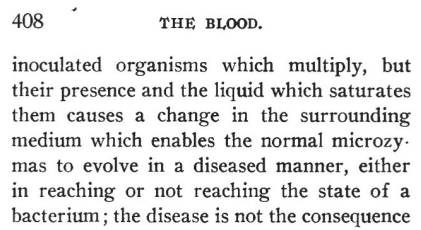
「移植された菌が増殖するのではなく、微生物の存在と、その微生物を飽和させる液体が周囲の培地に変化を起こすことで、健康なマイクロザイマスがバクテリア形態への到達の有無の何れかによる病的進化を遂げるのだ。」
-The blood and its third anatomical element, p408
解説:実験的な病原体の接種が直接病気を起こすのではなく、病原体自身と病原体周囲の液体が、侵入した環境全体に変化を起こし、体内に元々存在する健康なマイクロザイマス達が連鎖的に病的進化を遂げる。病気や発熱とは、その異常な進化を遂げたマイクロザイマスを正常形態に戻そうとする生体の努力(免疫系やヒートショックプロテインの殺到)である。
…誤解のないように付言しておくと、ベシャンは体外からの感染性病原体の存在を否定したわけではない。彼は疾患を「寄生性疾患」と「体質性疾患」に区別している。
つまり、実験室で病原体に疾患を起こさせるには、それに先んじて宿主の体内環境を変化させる必要がある。体内環境の変化が血糖、pH等生活習慣に左右される因子で構成されることは言うまでもない(※現代医学は「日和見感染」などという民衆を恐怖でコントロールする為の運命論的・確率論的出鱈目用語で誤魔化すが、暗に体内環境理論を肯定している)。病原体の作用は自らの増殖に最適な環境、即ち、自らの餌となる栄養成分に殺到して発酵・腐敗現象を起こすことだ。その発酵・異化産物を人間が「細菌毒素」と呼んでいるに過ぎない。現代は「感染症infectious disease」の名を「発 酵 病Zymotic disease」に戻す必要がある。
Zymotic disease was a 19th-century medical term for acute infectious diseases,[1] especially "chief fevers and contagious diseases (e.g. typhus and typhoid fevers, smallpox, scarlet fever, measles, erysipelas, cholera, whooping-cough, diphtheria, etc.)".[2]
発酵病とは急性感染症、特に発熱を主徴とする伝染病(腸チフス、チフス熱、天然痘、猩紅熱、麻疹、丹毒、コレラ、百日咳、ジフテリア等)に関する19世紀の医学用語である。
Zyme or microzyme was the name of the organism presumed to be the cause of the disease.
「ザイム」や「マイクロザイム」は疾患の原因と推定される微生物の名である。
>As originally employed by William Farr, of the British Registrar-General's department, the term included the diseases which were "epidemic, endemic and contagious," and were regarded as owing their origin to the presence of a morbific principle in the system, acting in a manner analogous to, although not identical with, the process of fermentation.[2]
>元々は英国登録局長のウィリアム・ファーが採用し、「流行病、風土病、伝染病」を含意する用語であり、その起源は、発酵の過程と同一ではないにせよ類似の方法で作用する病的原理の体内存在に起因すると考えられていた。
In the late 19th century, Antoine Béchamp proposed that tiny organisms he termed microzymas, and not cells, are the fundamental building block of life. Béchamp claimed these microzymas are present in all things—animal, vegetable, and mineral—whether living or dead. Microzymas coalesce to form blood clots and bacteria. Depending upon the condition of the host, microzymas assume various forms. In a diseased body, the microzymas become pathological bacteria and viruses. In a healthy body, microzymas form healthy cells. When a plant or animal dies, the microzymas live on. His ideas did not gain acceptance.[3]
19世紀にアントワーヌ・ベシャンが、細胞ではなく、自身がマイクロザイマスと命名した極小生物こそが生命を構築する基本単位だと提唱した。ベシャンはこのマイクロザイマスがあらゆるもの~動物、植物、鉱物~に、その生死に関わらず存在すると主張した。合体したマイクロザイマスが血栓や細菌を形成する。宿主の状態に依存して、マイクロザイマスは様々な形態をとる。病的な身体ではマイクロザイマスは病的なバクテリアやウイルスに変化する。健康な身体ではマイクロザイマスは健康細胞を形成する。動植物が死のうとマイクロザイマスは生存する。彼の構想が受容されることはなかった[3]。
The word zymotic comes from the Greek word ζυμοῦν zumoûn which means "to ferment". It was in British official use from 1839.[4] This term was used extensively in the English Bills of Mortality as a cause of death from 1842. In 1877, Thomas Watson wrote in a Scientific American article "Zymotic Disease" describing contagion as the origin of infectious diseases.[5]
Zymoticの用語はギリシャ語の ζυμοῦνに由来し、「発酵」を意味する。1839年から英国では公式に使用されていた。この用語は1842年以降、死因として英国死亡率表(English Bills of Mortality)にて多用された。1877年、トーマス・ワトソンは、Scientific Americanに「発酵病」と題した記事を寄稿し、「感染症infectious diseasesの起源」だと述べている[5]。
以上の真理に照らし合わせると、松村の脚気菌の存在は限りなく真に思われるのだが、定説を覆すならまずは定説の誤りを指摘しなければならない。ここで重要になってくるのが、感染性生物の存在を完全に制御し、純粋なB1欠乏の食事のみで脚気の再現に実験的に成功したのか?という根本的な問いだ。感染症理論を否定するならば定説自体が頑健でなければならない。
定説ではこれは「鳩白米病」で再現されたことになっている。鶏や鳩に白米を食べさせ続けると、人間の脚気に類似の症状が起きるという発見をしたのがクリスティアーン・エイクマン(1858-1930)であり、エイクマンはこの発見で後のビタミンの発見に貢献した功績でノーベル賞を受賞している。ではその鳩白米病は人間の脚気と本当に完全に同一なのかといえば、当時からこの二つは別の疾患だという批判があった(参考:山下, 2008)。この点に松村も言及しており[6-3]、その批判点を整理すると
白米食で脚気様症状を起こす鳩は全体の50%に過ぎない
中には、ただの偏食による分類不能な栄養障害(=脚気と全く無関係)になる鳩がいる
志賀潔の報告では、一年以上白米食の鳩を観察して何も発病せずに生き残った
…といった具合で、鳩の白米食による脚気は、動物モデルとしてあまりにもお粗末な実態があり、明らかに脚気の発症には白米以外の別の因子を想定する必要がある。ちなみに松村は鳩白米病の鳩からも、人間の脚気とは血清学的に区別される(が類似の)脚気菌を分離しており[6-3]、この時点で鳩"白米"病の存在も疑わしい。それに加え、前回の記事で黴米中毒説の復活、並びにペニシラム属の真菌のマイコトキシン が衝心脚気の原因だと言及したが、今となっては鳩の生活空間の衛生状態も、実験に用いられた米の品質なども調べようもない。
この時点で定説の綻びが暗示されるが、決め手として実験的B1欠乏食を食餌させた1953年の人体実験を参照する[10]。現代では倫理的に困難な実験になるが、明かに不自然な人工的B1欠乏食(※白米を亜硫酸ソーダで洗浄したり、実験食開始前に腸内細菌を薬剤で無菌化したり)で誘発される症状と、実際の脚気との比較を行ったものだ。僅か4名の心許ないサンプル数だが、その結果が以下の表となる。

黄:多少の違い
※Aschner現象(眼球心臓反射)
⇒眼球を圧迫すると徐脈が生じる。心臓の迷走神経が刺激状態になることが原因
脚気といえば、
①多発性神経炎
②浮腫
③循環器症状
以上3兆候を特徴とし、膝蓋腱反射の喪失で診断されるはずである。しかし、循環器症状を除いて(※それでさえ幾つか不一致が見られる上、そもそもこの実験の言う「脚気」が乾性脚気(神経系)と湿性脚気(循環器系)どちらを比較対象としているかも定義されていない)、神経炎や浮腫はおろか、肝心の膝蓋腱反射の喪失すら観測されていない。B1が著効する事実からして脚気の病理にB1が関与するのは疑い無いが、それは「脚気がB1反応性疾患」である証拠であっても、「脚気=B1欠乏症」という等式の証拠ではない。
何より著者自身が
B1欠乏の程度および期間(すなわち速度)の相違が両者の臨床像の差を惹起したものか、あるいは脚気はB1欠乏の他にさらに他の要約も加わって発生する症候群であると推察される。
と考察しており、結果として松村研究室の面々と同じ見解に至っている[8]。
決定的なのは、この実験での症状に血中乳酸濃度の上昇が観測されなかったことである。この実験の症状が循環器系に集中している実態に鑑み、暫定で比較対照を湿性脚気に設定したとしても、湿性脚気の本態は乳酸アシドーシスによる中毒症状であり、病理診断における鍵となる因子のはずだ。
心血管性(湿性)脚気は,チアミン欠乏症による心筋疾患である。最初の影響は,血管拡張,頻脈,脈圧増大,発汗,皮膚の熱感,および乳酸アシドーシスである。後に 心不全が発生し,起座呼吸ならびに肺浮腫および末梢浮腫を引き起こす。血管拡張が持続することがあり,ときにショックに至る。
以上より、白米食のみによる脚気の再現の試みは、人体実験ですら脚気の部分症状を起こしたに過ぎず、実態として脚気の再現には程遠いものだと分かる。
では松村の脚気菌による脚気の臨床像は正確であったか?が議論となるが、細菌学にはコッホの原則があることを忘れてはならない。コロナ騒動で何度も目にしたであろうこの原則を改めて確認しよう。
ある一定の病気には一定の微生物が見出されること
その微生物を分離できること
分離した微生物を感受性のある動物に感染させて同じ病気を起こせること
そしてその病巣部から同じ微生物が分離されること -Wikipedia
「病気」を「脚気」に置き換えて厳密にすると以下のようになるだろう。
1.脚気患者には、"健康な人間には存在しない"特異的な微生物が検出されること
2.その微生物を患者から分離すること
3.2で分離した微生物を感受性ある実験生物に感染させ、1の患者と同一の脚気症状を被感染生物で発症させること
4.3の被感染生物の病巣から改めて同じ微生物を分離すること
まさにこの「感受性」を決定するものが生物の体内環境であり、脚気の場合は白米食で操作が可能だと見做せるだろう。松村の手続きはまさにこの原則に則ったものであり
1,2→脚気患者の糞便から菌を採取
→患者の血清が菌に対して特異的免疫反応を起こす知見より、ツベルクリン検査の要領で経皮検査を実施し、患者のみに陽性のアレルギー反応を観測[6]
:菌は患者のみにしか存在しないことの確認
3→白米に1の脚気菌を付着させて実験動物に食餌、患者と同じ症状の再現
4→実験動物の病巣から再度分離
上記の手続きを踏んでおり[6-1][6-3]、文献を額面通りに読めば完全にコッホ原則を満たしており、細菌の分離報告への批判でよく言われていた「二次的感染症で紛れただけの細菌」ではないと考えられる。「脚気菌には神経系のA型/中毒型のB型が存在する」という主張から、それぞれが乾性脚気、湿性脚気に対応していると読み取れ、B1欠乏食の人体実験[10]より遥かに正確であった可能性が浮上する。
最後に、松村の報告した脚気菌は、師の緒方正規が1885年の官報で分離報告した菌[2]と同じ菌だった可能性を考えている。緒方と松村それぞれの脚気菌の共通点を列挙すると
腸で増殖する桿菌であること
脚気患者の血液中にも存在すること(※松村は更に患者の血清と菌との間に特異的な免疫反応を観測[6-2]して治療・予防用ワクチン開発までしている[7,9])
乳酸を生成すること
両者ともBacillus(バチルス)属に分類していること
唯一の違いが、緒方の報告した「芽胞形成性」を松村は観測していないようだ[4]ということだ。同じ可能性と言いつつ決定的な違いだが、松村がそこまで観察していないだけなのか、本当に異なるのかはわからない。明治時代、脚気細菌説を唱えた学者、例えばペーケルハーリングは追試の失敗を受けて自説を撤回した旨の記録はあるが、緒方が自説を撤回した記録が見つからず、ビタミンの熱狂に圧されて学界から自然消滅したようになっている。緒方の無念を松村が晴らしたとすれば、ここに師弟の絆が垣間見える気がするが、今の所それは私個人の"そうであってほしい"という願望に過ぎない。
参考論文集(出版年代順&全文書き起こし)
ここから先は
サポートで生き長らえます。。。!!
