
医学部4年、心電図検定1級合格 —— 微かな誇りと大いなる不安
どうも!試験マニアです。
去る2月12日に、第10回心電図検定の結果が発表されました。

以前の日記でも心電図検定の勉強をしていることは話していましたが、無事、勉強の成果が実りました。良かった〜。
錆びついた諸刃を伝う雨
最近ハマっているコンテンツは『メダリスト』です。少女の成長譚としても完成度が高いですし、その一方で、主人公の青年を通して我々世代には「夢に払った犠牲の精算」「選ばなかった過去の呪い」の存在を際立たせて心の奥底に迫ってくるため、天国と地獄が交互にやってくるアンビバレントな作品としても胸が熱くなります。また、作中ではフィギュアスケートも「ギャンブル」性のある種目だと説明されており、上記のdouble edgeは競技シーンにも織り込まれています。構成が上手い。とにかくひたすら面白い。挑戦する人間の有り様を積極的に肯定する人間讃歌的な側面もあるため、心電図検定に挑まんとするチャレンジャーの皆さんにはぜひ触れてほしい作品です。
『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とは、ワイドスクリーン・バロックを孕んだSF作品であるか否かで区別されますが、作品の熱量やメッセージ性には似たところを感じます。投稿日のアニメOAで花柳香子と西條クロディーヌを足して割ってないような娘が出て来る予定です。私は彼女が好きです。
閑話休題!本題に入りましょう‼️
なぜ目指したか
最終的には、「履歴書に書けそうな資格が1つ増えれば良いね」という俗っぽい理由が一番強固に残っているのですが、受検を考えた原初のパッションは、大学医学部における心電図基礎講義と臨床心電図読解との乖離に悩んだことでした。これだけだとわかりにくいので今から翻訳します。
心電図って医学部の学習項目の中でも特殊で、基礎でも臨床でもガッツリやるんですね。もちろん、電解質や呼吸機能や尿や生化学といった検査科学を始め、極論あらゆる疾患の病態生理まで基礎医学で一度学習しているといえばそれまでなのですが、心電図は、① 基礎でガッツリやる ② のに臨床で再登場してもわからん というところが特殊でした。einthovenの三角形はもちろん、心電図が心起電力ベクトルの一次元正射影の時間変化を記録したものという検査の本質の話や、そこから導かれる貫壁性心筋梗塞と非貫壁性心筋虚血のST変化の違いくらいまではやりました。が、臨床の講義を受けても、不整脈とか先天性心疾患はもちろん、ST変化性疾患もいろいろあってわからん、なんじゃこりゃ。
※以下、私が学内試験や医師国家試験・USMLEで出会った狭い範囲の話をしています。
電解質だったら、適度に単純化すると、各項目が高いか低いか x N次元の状況に対して1つの解を考えるというテーマ設定であることが多く、各項目は従属し合うことで実質的な次元が削減されたり、支配的なひとつの変数にだけ注目すれば解が見えてくるようなパターン認識的なアプローチが奏功しやすく、呼吸機能だったら、検査で得られた状況を2x2のMECEな分類のどこかに当てはめることができるという強力な原則が存在するため、思考が迷いにくいです。
そのため、基礎をしっかりやっていれば、臨床の範囲でこれらの検査が再登場しても問題に迷わず解答できるくらいの実力は、少ない労力で身につきました。
心電図ではどうでしょう。確かに、Brugadaや早期再分極、QT延長などの、ある所見が診断に支配的な影響を及ぼすような一発問題に近いものはありますが、そんなものはごく一部で、基本的には12(+α)誘導のすべてを確認して検討する必要があります。そもそも、基礎講義を受けただけではこれらの疾患が頭に入っていない場合もあります。一方で、電解質だったら、基準値より高いか低いかを評価するだけなら小学生でもできます。(突飛なようですが、これは3年のときの検査医学の教授のお言葉です。高いか低いかを評価した後それをどう解釈するかが我々の仕事なのだということでした。)
心電図では、P波やSTが変化してるのかどうかものさしで測ったとしても微妙という波形があったり、これは基線の細変動なのかどうか、これは粗動波なのかどうかなど、小学生にはわからないような変化を読み取ることを要求されるため、まず「目で見る第一段階」ですら一定以上の習熟が必要であると考えます。
では、いざ演繹的に波形を解釈していこうという話になっても、呼吸機能検査のように一発目に4分類に枝分かれしてほぼそれで勝負がつくという話ではないということは、検定に向けて学習中の方は痛いほどお分かりだと思います(呼吸機能の検査が簡単であることは意味しません。学生から見たときの演繹的思考の道のりの長さの話をしています)。まずP波と脈拍を見て、P波があったらこう、なかったらどう、その後PQ間隔と・・・と、結構複雑なフローチャートを漏れなく確認しながら進まなければなりません。すくなくとも学習者であるからには、これらを細かく覚えていないといけません。使い物になるために必要な単純な暗記量が多いのです。下壁と後壁と右室のST変化(近位か遠位かも)とか私は覚えにくかったです。
結論、心電図の「どこを見るか」という目と、「どこをゴールにするか」の知識に不足があり、基礎講義での自信を打ち砕かれたのでした。
いつか時間ができたら受けようと思っていたところ、少し時間ができたため受検することにしました。
どう目指したか
2024年8月13日
実力心電図を一周したらしい。今考えるとこれは明らかに「見た」だけであり、通読には当たらないと思います。とはいえ、ちゃんと前もってから対策するだけのやる気はあったみたいです。
1時間26分で問題を一周し、「この感じだと2級は受かる」と言っていましたが、これは今考えても概ね間違っていなかったと思います。

同じ日に、勢いそのままで青マイスター本に着手。
そもそもちょくちょくマイスターチャンネルさんの動画も観ていたらしい。

4時間くらいでイッキ読みできたらしい。当然、習得まではさらなる復習が必要だったのですが、自分のことながら勢いだけは本当にすばらしい。

11月18日くらい
余暇の時間はこの日記を書くためにめちゃくちゃ時間を取られていたが、10月に発売した黄色い心電図マニュアル本を購入して学習していました。個人的には黄色い本の方が自分の頭に定着しやすく、結局受検までこちらをメイン教材に据えました。以下の日記では、各人における教材ごとの向き・不向き論についても書いています。誰にでも使える「最高の方法」は限りなく少ないが、各人に使える「最適の方法」は探せば見つかるという理論で、私は学習教材の浮気については肯定的です。

上の日記にも同じことが書かれていますが、
以下のようにして学習していました。
心電図完全攻略マニュアル(以下、黄色本)は疾患ごとの心電図を題材として、疾患当てクイズ⇨次のページでポイントを解説という形式で作られている。
1. 普通に問題を解き、解説を読む。わからないことがあれば『実力心電図』やインターネット検索などで調べる。
2. 必要があれば、上の写真のようにメモ用紙に必要事項を記録しておく。
3. 黄色本を開いたまま、『実力心電図』でその疾患を解説しているページを開き、黄色本の上にかぶせる。(本を重ねることにアレルギーがあるなら、栞を挟んで本を閉じるなどで、とにかく黄色本を視界から消す)
4. 『実力心電図』の波形を見て、その波形がノーヒントで読めるか、また、黄色本に書かれてあったその心電図を読むときのポイントがどれだけ思い出せるか(負荷の大きいアクティブリコール)を確かめる。
5. 黄色本と実力心電図の解説を見て、答え合わせをする。
6. これを繰り返す
11月24日
みんなde心電図(アプリで心電図の問題を回せる。医学部6年の先生が制作したらしく、すごい)に出会う。
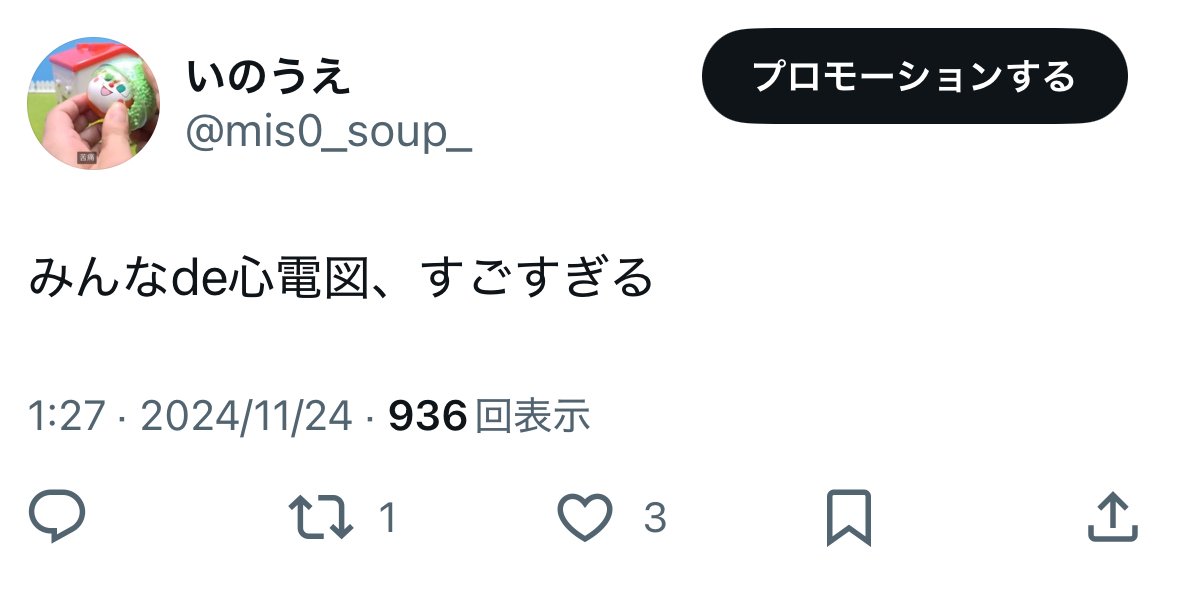
12月11日(試験10日前)
ようやくpre-excited SVTの疾患概念を理解したらしい

12月13日(検定8日前)
Twitter(現X)で心電図検定対策の問題集を提供していただき、いざ力試し。本当にありがとうございます。
心電図検定対策 1〜2級想定QUEST IIがDL期限切れになっていたようなのでUPし直しました!
— T.Hayakawa@EP大学深読み学部 (@tempest_no3) December 12, 2024
パスワードは0903です!
さぁさぁ心電図検定1級の力試しに解いてみてください!
マイスター狙いの方も楽しめる内容になっていますよ。。。笑https://t.co/sHVN8SJB8E pic.twitter.com/qRnflqClvO
結果↓ 悪くはなさそう。なお、本番の合格点は35/50付近と言われています。青い本と黄色い本の演習問題の正答率は6~7割だったと思います。

12月14日(検定7日前)
みんなde心電図の1級モードで50問解き、ふたたび39点を取る。

1級出題とされる水準の難易度の問題に対しては、根拠をもって解答できる問題が多く、出題がこのレベルの範囲内で、かつここから先に事故が起こらなければ、受かるかな、という根拠のある自信と不安の両義的な状態でした。
12月18〜20日(検定3〜1日前)
メンタルがすこし険しくなる。これは仕方ありません。相対評価で安全ラインには8割を要求し、受検者は現場で働くプロ集団。今まで受けてきた試験の中ではかなり厳しい部類に入ります。自分の中では、ずっと受かってない英検1級と近いラインです。

受検体験
12月21日(検定当日)
直後の時点で、多分受かったかな〜とは思えていました。でもとても難しかったと思います。


2025年2月8日(結果発表4日前)
問題再現や解答速報などいろいろ見て、結局50-50だろうという結論に至り、本当にソワソワしていました。

2月12日(結果発表当日)
番号を探しながら久しぶりに心臓がバクバクしました。心電図検定は心臓に悪いです。

一問目は外してしまいましたが、最終問題の二択で当てたのが、合否の分かれ目だったかもしれません。ちゃんと勉強量は積んできたのですが、安全圏には到底及びませんでした。今回の合格に関しては運も味方につけられたのだと思います。
2月14日
合格祝いにチョコレートケーキを焼く

感想戦
幸いなことに私の周りの友人たちは合格した方が多かったようでした。そのうちの一名(某旧帝医卒 研修医)が仰っていたことをパクツ…引用↓

私も彼も、世間的に厳しいとされる試験をいくつかパスしてきましたが、心電図検定もそれらに比肩する過酷さであったと思います。
まず、やはり受検者のレベルが高いです。毎年の合格者の一部が、翌年のマイスター狙いとしてキャリーオーバーしていく仕組みになっていくので、実質倍率は年々厳しくなっていきます。この人たちとそれを追いかける受検者との戦いをしなければならないため、生半可な学習だと返り討ちに遭うと思います(その分、合格の価値は担保されるので嬉しい)。それに加えて今年の合格率は50%を割り(過去最低?)、振り返っても壮絶な戦いだったと思います。
また、受検した感想ですが、シンプルに問題が難しくて、目安とされる7~8割が見えません。問題が回収されて自己採点もできない仕組みになっているし、一回落ちたら次は1年後だし結果発表まではそこそこ時間が空くしで、受験後の苦悶の時間が通常の試験より長いです。私は米国医師国家試験の第一段階にPassしていますが、心電図検定1級の方が難しいし精神を削ると思いました。
兎にも角にも、私の学習を助け、成長の機会を与えてくださった先生方、本当にありがとうございました。
夢から目醒めた先には夢
晴れて1級にPassしましたが、これからはこれをどのように活かしていくか、で真価が問われると思います。「履歴書に書けそうな資格が1つ増えれば良いね」などという資格の持つ形而上的な価値に終始してはいけません。我々は現実を生きているので。
しかし現状、医学部4年生の分際では、プラグマティックな価値を考えることができていません。私が学習して習得し、検定試験で発揮したものは、「心電図検定1級」にPassするためでしかない能力であり、これは私の現場での能力を保証しません。検定会場でゆっくりそれだけ考えて正解を選べることよりも、現場の目まぐるしく変わる動的な世界であらゆるファクターを考慮しながら迅速に対応している専門職の方々のスキルのほうが優れているのは争いのない事実だと思います。私には、「感度」や「瞬発力」が足りません。
今後の実習や研修医生活に役に立つではないかという結論は早計であるとも考えています。心電図検定1級の学習内容は、たしかに基礎的な読解レベルの向上によって専門職的な臨床力のバックボーンになるとは思うのですが、学生・レジデントレベルで頑張りたいところとは別方向のスキルツリーを伸ばしているとも思うのです。もちろん、STEMIやVTなど必修的な心電図への理解は進むため、まったく無意味ではありませんし、無駄とも思いません。が、学生や研修医としては、より専門的な心電図が読めることよりは、まずは胸部の緊急疾患への対応がまんべんなくできることが優先されるべきであり、医学生における「心電図検定1級受かったぞ〜やった〜」という姿勢は、物事の優先度を見失っている状況であると考えることもできます。まさか合格後にこのような苦悩に直面するとは思いませんでした。私は、肩書きに見合った医者・ひいては人間になれるのだろうか…。
浮かれず粛々と、自分に必要なスキルを伸ばしていこうと思います。

以上の解釈は、穿った見方でしょうか。
私は今、絶望しています。
