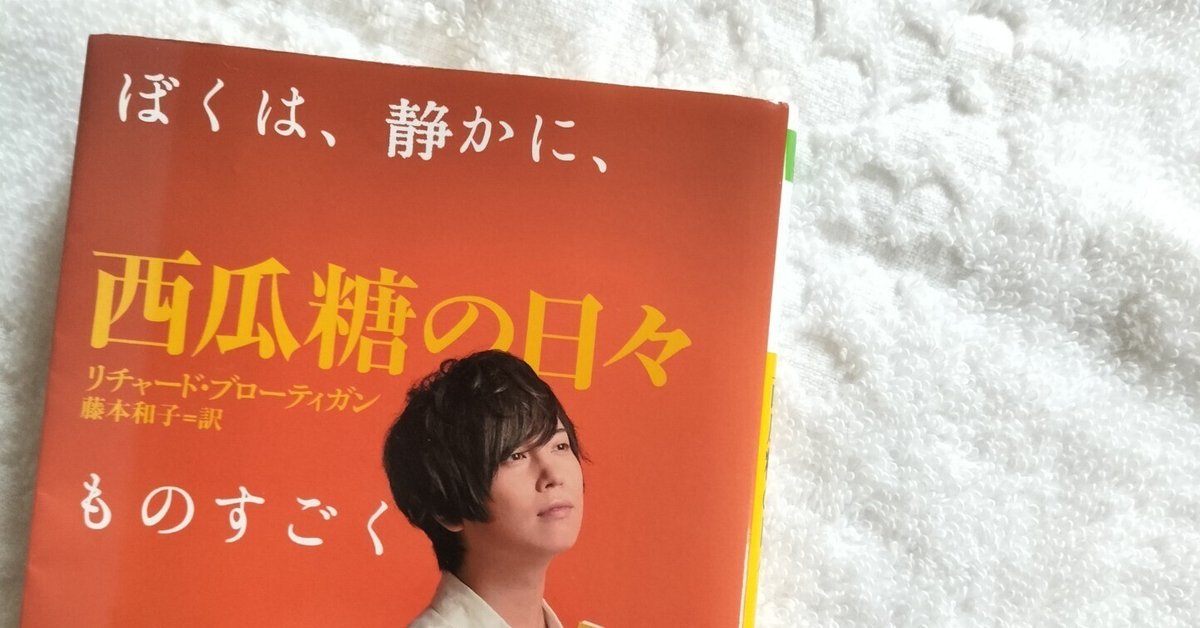
リチャード・ブローティガン『西瓜糖の日々』藤本和子訳、河出文庫
これは再読。最初に読んだときに不思議な本だと思ったという記憶しかなくて、また読んでみた。なるほど、こういう本だったか。
まず西瓜糖という語に惹かれる。英語ではwatermelon sugarのようだが、西瓜糖の方が音がさわやかでいい感じだ。とにかくこれは何もかもが西瓜糖でできている世界の話である。橋も家も窓ガラスさえ西瓜糖で出来ている。1章がひどく短くて断片的だが続いているひとつの話だ。アイデスというユートピア的なコミュニティに暮らす人たちが描かれるが、それ以前は熊の時代で、熊が人を食べてしまったりしていた。最後の熊を殺してから平和に暮らすようになった。(主人公の両親も主人公の目の前で熊に食べられるのだが、その最中に子どもである主人公はその熊に算数の問題をおしえてもらったりする。熊は必ずしも悪ではない。)
そのコミュニティの中心には食堂があって、人々はここで素朴だがおいしい食べ物を食べている。この食堂の造りが不思議なのだ。台所への廊下が川底にあるというから、食堂自体が川に作られているのか。
コミュニティ内には彫像があちこちにたくさんある。野菜好きの人が作ったという野菜の彫像なんかもある。夜はランプがともる。主人公も一時は彫像を作っていたが、いまは本を書いている。この世界には本がないので、人々は彼が書く本が出来上がるのを楽しみにしている。
アイデスから離れたところには「忘れられた世界」という場所があり、ガラクタのような物がいろいろと積まれているようだ。アイデスの者たちはこの世界には行きたがらない。やがてコミュニティ内から造反する者たちが現れて、初めは「忘れられた世界」の手前の小屋に住んでいたが、やがてアイデスを攻撃しようとする。が、自滅してしまう。
全体が夢のような話で、やや幼児的な気がするが、面白いことは面白い。とにかくわたしは西瓜糖という言葉が気に入り、読んでいる間も本のページから西瓜糖の香りがたちのぼるような気がした。西瓜糖なんて想像の産物だと思っていたが、実際にそういう食品があるらしい。買ってみようかな。
英語のwatermelon sugarでも調べてみたが、殆ど出てこないのはどうしてだろう。アメリカにはそんなものはなくて、ブローティガンが想像したものなのだろうか。
追記 上の写真。このごろ文庫本のカバーにタレントを使っているのがあって(その下には本来のカバーがある)、個人的にはあんまり好きではないけれど、本を若い人に売るためにはこういうのも必要なんだろうなぁと思う。出版業界にはがんばってほしい。
