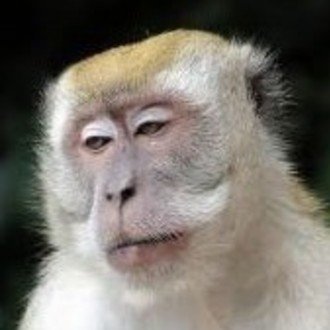ボン・マルシェに想うこと03
ボン・マルシェは、さまざまな意味でベル・エポックの象徴だ。
産業革命によって立ち現れた大量の消費者たちが、小金を持って集う場所。
消費が欲望の中心になって、その欲望のために人々は働き、達成されることで悦楽を得る。百貨店と云う業形態に、こうしたものがすべてシステム化され具現化されている。
ゾラは、このボンマルシェをモデルとした小説を書くに当って、店名ボヌール・デ・ダム「ご婦人がたの幸福」とした。
なんというゾラらしい冷徹な視線だろう。
ゾラは、ボヌール・デ・ダムを近在の小さな小売店と明暗分けて描いている。凋落する旧世界。台頭する新世界という図式である。しかしその華麗な見かけに比して、内部は暗い。嫉み歪みが渦巻き、女性従業員は薄給で劣悪な労働条件で酷使される。しかしその採用基準は厳しく、そう簡単には採用されない。それが働く女たちに無料で配る「新しい女性たちの栄華の象徴である」というキャンディとなる。
「欲望と充足」が幻想として刷り込まれる場。ゾラは、そんな新時代の象徴として百貨店というステージを描いている。
ブシコーBoucicaut夫妻が、万国博覧会を見て「此れを我が店のモデルにしよう」と決心したとき。そこまで考えただろうか?そうは思えない。
しかしアダムスミスが言うとおり、一番売れるためにはどうすれば良いか?職人が/商人が考えた結果は、必ず神の見えざる手として、最も合目的として適合するものなのだ。
ボンマルシェのファッション館を歩いているとき。
「やっぱりボンマルシェも男性衣料のコーナーは小さいわね。」嫁さんが言った。どうやら何か僕のものを買うつもりだったらしい。
「デパートは、女性の花道だからな。ショッピングセンターとは違うもんだ。対々にはならない。」
「どうしてかしらね。買うのは男性だって女性だって一緒だと思うんだけど」
「デパートが成立してきた歴史的な背景のためだろうな。ボードレールが言うとおり、男たちのファッションは"葬式帰りのような黒とダークグレー、ダークブラウン"が、長い間基調だったからな。オスも着飾る"ピーコック現象"は20世紀後半になってからだ。20世紀的な大量消費型大規模小売店であるデパートメント・ストアにとって、男は相手にしても大して儲からない連中なんだ。」
「そんなもんかしらねぇ。」と何となく不満そうにしていた。

いいなと思ったら応援しよう!