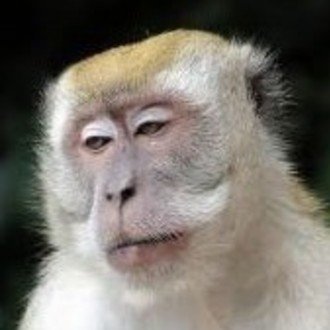ボージョレーと十字軍/beaujoLais nOuVEauに秘められたLOVE#07

荘園制度は当初高機能でしたが、少しずつ経年疲労を起こしはじめます。それと黒死病が定期的に起こり始めると、経済的に不安定になり飢饉も定期的に起きるようになりました。こうして西暦1000年代に入ると、各地の荘園の中に閉じ込めれていた人々は、不満と不安で爆発寸前になります。そのガス抜きの手段として唐突に始まったのが十字軍です。
聖なる地エルサレムをモスレムの手から奪い返せ!という運動です。人々は畑を棄て、村を棄て、暴徒となって東へ進みました。その数は数十万人と云われています。もちろん何も携帯するものはない。通り道で略奪を繰り返しながら人々はエルサレムを目指しました。
その暴走に大慌てした正規軍もその後を追います。しかし彼らもまた携帯するものは殆んどない連中です。調達と称して略奪を重ねながらエルサレムへ向かいました。
たしかにエルサレムは奪還した。しかしこの略奪と死の行進に参加した人々は、ほぼ100%、聖地へ辿り着く前に死んでしまったのです。それでも正規軍は相当の戦利品を手に入れて戻っています。彼らは「十字軍は儲かる」という印象を各地の諸侯に植え付けてしまいました。
以降、諸侯らは教会と図り、経済的に苦しくなると東方へ十字軍を出し略奪を行うようになります。合計8回(細かいものを入れると14回前後)西暦1096年から200年余り、十字軍による略奪は繰り返されました。
第1回十字軍遠征に参加した年代記者・ラウールは、こう書いている。 「マアッラ(地中海に近い今日のシリア領)で、我らが同志たちは、大人の異教徒を鍋に入れて煮たうえで、子どもたちを串焼きにしてむさぼりくった。」
また、ある聖職者は、次のように書いている。
「聖地エルサレムの大通りや広場には、アラブ人の頭や腕や足が高く積み上げられていた。まさに血の海だ。しかし当然の報いだ。長いあいだ冒涜をほしいままにしていたアラブの人間たちが汚したこの聖地を、彼らの血で染めることを許したもう“神の裁き”は正しく、賞賛すべきである。」
一方、アラブ側の年代記者、ウサーマ・イブン・ムンキズは、こう書いている。
「フランク王国に通じている者ならだれでも、彼らをけだものとみなす。ヨーロッパの人間たちは、勇気と、戦う熱意には優れているが、それ以外には何もない。動物が力と攻撃性で優れているのと同様である。」
絶対的な帰依を要求するキリスト教が内包する独善性・攻撃性が最も極端に出たのが十字軍の遠征だった、と云えましょう。

いいなと思ったら応援しよう!