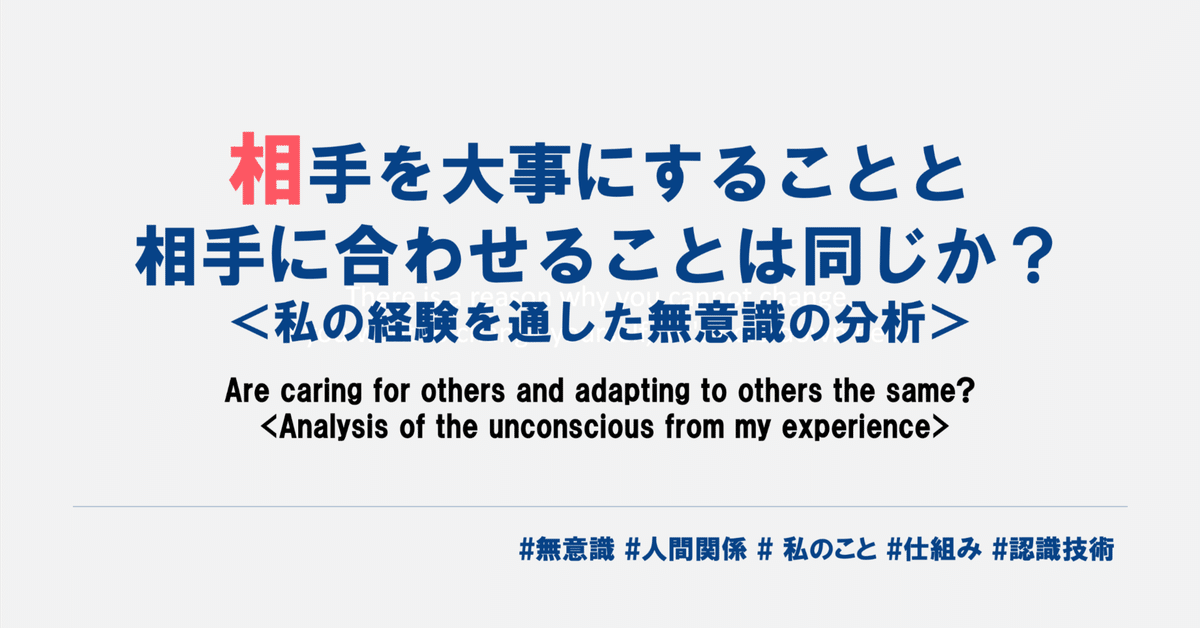
相手を大事にすることと相手に合わせることは同じか?<私の経験を通した無意識の解析>
こんにちは、美談年民です。
AI時代に心スッキリ、歓喜あふれる生き方を!
人間と現実の仕組みがわかる21世紀の悟り教育を案内しています。
本日は「相手を大事にすること」と「相手に合わせること」は同じか、というテーマです。
実はこの話題、私自身がハマっていた問題でもあり、題材としてとても面白いので今回取り上げてみました。
相手に合わせてばかりだと大変
「相手を大事にすること」と「相手に合わせること」は同じか?
さて、この命題、
改めて問われると「違います」と言いたいところですが、言うは易く行うは難し。実際はイコールになっている人がとても多いように感じます。
特に日本人は「自分勝手」に対してとても悪いイメージがあります。目の前の相手と関係を築こうと思うほど、自分の我を抑えて相手の言い分を受け入れる方も多いのではないでしょうか。
それでは「相手を大事にすること」と「相手に合わせること」がイコールになると、どうなってしまうでしょう?
我慢して合わせることになるので、相手を大事にするほど大変になってしまいますよね。
日本のおもてなし文化のように自分を抑えて相手を立てたりもてなすといったこと自体は悪くはないのですが、これしかできないと大変です。
人に会うほど人の数ほど相手に合わせなければならないと、人との出会いが嫌になってしまいますよね。
一体、どうしたら良いのでしょうか。
人類共通の根本問題は観点の問題
関係性の問題は自分だけの問題ではなく相手がいる問題なので解決は難しそうに思えますが、認識技術を使えば、シンプルに観ることができて仕組みで解決ができます。
まず、この問題のいちばん根本にある問題(原因)とは何でしょうか?
一言で言えば【観点の問題】です。
(観点には深いイメージがあるのですが、ここでは一旦「物の見方」とか「視点」という意味で受け取ってもらえたらOKです)
観点の問題は人間なら誰もが抱えている人類共通の問題であり、すべての問題の根本問題です。観点が何かもわからず、観点から自由になれないから、私たち人類はいつも不信・不安・恐怖から解放されず悩み心配が尽きません。
観点から自由になるためには、観点が無いところから観点が生まれる仕組みを理解する必要があります。
仕組みを理解できた時に、観点から自由になり問題が自然と解決されていきます。そして「人間とは何なのか」「現実(宇宙)とは何なのか」「生きるとは何なのか」といった本質的な問いについても整理が起きていきます。
私の実例を通した考察①
抽象度が高いので、少しだけ具体的に書いてみますね。
例えば、私の頭の中にあった最初のイメージは冒頭でお伝えした通り
【相手を大事にする = 相手に合わせる】
ということでした。
これをより具体的にすると以下のようになります。
【相手を大事にする = 相手の望むことや相手の主義主張を受け入れる】
私はこれが本当にイコールでした。
相手を大事にしなきゃ!と思ったら、無条件で相手を受け入れることばかりします。
ですが、相手の主義主張を受け入れることが本当に相手を大事にすることにつながるのでしょうか。
必ずしもそうではありませんよね。
例えば、受け入れることは相手に甘えや依存をつくり、成長や気づきの機会を奪っているとも考えられます。
そういう視点では、相手を大事にできていません。
相手を受け入れるという行為は、相手を大事にする絶対的な行為ではなく、ある条件でのみ効果を発揮する相対的な行為といえます。
このように少し視野を広げると、相手を大事にしたいからこそ取る行為は色々あることがわかります。
・相手を大事にしたい から 相手ととことん意見をぶつけ合う
・相手を大事にしたい から 過保護に育てる
・相手を大事にしたい から 厳しく接して自立心を育む
・相手を大事にしたい から 距離を置いて干渉しない
冷静に考えると他の選択肢も考えられるのですが、当時の私は他の選択肢の発想がなかったし、そもそも他の選択肢を模索しようとも思いませんでした。
つまり私は無意識で【相手を大事にする = 相手に合わせる】という因果は絶対だと思い込んでいたといえます。
私の実例を通した考察②
さらにもう一歩踏み込んで考えてみます。
私は、本当に相手を大事にしたかったのでしょうか?
※あくまで私を題材にしながら深めています。
これに関してはYESでした。
本当に相手を大事にしたいからこそ選択していました。
では、もう一歩踏み込みます。
本当に相手に合わせたかったのでしょうか?
これに関してはNOでした。
大事にしなきゃと思ったら、常に相手に合わせることを選択していましたが、いつも心は我慢していました。
私の無意識
【相手を大事にする(心もYES) = 相手に合わせる(心はNO)】
ではなぜ相手に合わせることを選択するのか?
改めて考えてみると、相手に合わせる以外のイメージがなかったので、私は相手に合わせるしかなかったと言った方が正確な表現となります。
相手を大事にしたい状況に出会う
→【自分だけが我慢したくはないが、どうしたら良いかわからない】
→【環境(この場合は相手)に合わせる】
整理してみると確かに私は【わかる】課題なら主体的に取り組み自ら変化を作れるのですが、自分では洞察できない【わからない】課題に出会うと、オートで環境に合わせて耐え忍ぶ選択をよくやっています。
わかるか・わからないか、このスイッチが私がハマる大きなポイントになります。
答えが出せない(洞察できない)課題と出会うと、
【わからない】=【環境に合わせて耐える】
この因果(考えの走る道)が絶対となり、機械的条件反射を繰り返していました。
私の実例を通した考察③
ここまで見えてくると次の疑問が湧いてきます。
なぜ、わからないと環境に合わせる道しかなかったのでしょうか?|
他の選択肢がわからないからという話でしたが、わからない状態だったとしても、必ず合わせなくてはならないわけではありません。
・わからない から わかるまで考える
・わからない から 相手に答えを問う
・わからない から あきらめて関係を断つ
・わからない から 相手を攻撃する(困らせるな!)
色々選択できる行動はありますが、私は
【わからない】=【環境に合わせて耐える】
をオートで選択していました。
ここにどんな原因があるのでしょうか?
ここで大事になるのが、どこから観ているのかという視点(=自己認識)です。
自分自身をどう思うのか。
このシンプルな自己認識に私たちの人生は大きく左右されます。
そして、私自身どんな自己認識を持っていたかというと
【自分は洞察ができず耐えるしかない無力な人間だ】
という強烈な無意識を持っていました。
この自己認識があるので、少しでも難しい課題、自分一人では解決できそうにない課題に出会うと常に「わからない!(洞察ができない!)」「耐え忍ぶしかない!」という考えが走ります。
【洞察ができず耐えるしかない無力な自分】が課題と出会うと、
【わからない】=【環境に合わせて耐える】と考え行動が一瞬で決まります。
・洞察ができず耐えるしかない無力な自分だから、どうせわからない!
・洞察ができず耐えるしかない無力な自分だから、どうせ耐えるしかない!
同じ事象に出会ったとしても、自分自身をどう思うかによって解釈の方向性が変わり、考えの走る道が決まります。
観点から自由になって無条件ワクワクする自分へ!
このように自分自身をどう思うのかによって、人生は大きく影響されます。
人間は誰もが自分の生い立ちのなかで作られた観点を持っています。そして、自分の固定された観点で、無意識に人や物、仕事や人間関係に意味付け価値づけをしています。この自分の固定観点から自由になれないから人生がうまくいきません。
私の場合は無意識深くで【無力な自分】として自分を決めつけていたので、どうしたら良いかわからない事象に出会うと、オートで耐え忍ぶしかない生き方ばかりを選択してきました。
では、無力な自分ではなく【何でもできる自己肯定感の高い自分】を自分だと思い込めば良いのでしょうか。
一旦はそれで解決することもあるかもしれませんが、自己肯定感は条件付きのものです。ある時は良くても条件が変わればあっという間に自信を失ってしまいます。
ですので、ここでは知恵が必要です。
条件状況に左右される観点の中で生きるのではなく、観点の外(無観点!観点から自由!)にポジションを置くことです。
観点が生まれる仕組みがわかって、観点の外に出れば条件状況に左右されない無条件の自己絶対肯定感を得ることができます。
以上、長くなりましたが(本当に長くなってしまいました・・)
なんとなく仕組みを理解しながら解決ができるイメージがついたでしょうか?
今回は私を例として書きましたが、観点は誰もが持っています。
そして、私で言うところの【洞察ができず耐えるしかない無力な自分】という自己認識を皆さんもそれぞれ持っています。そして、そこに観点が固定されているから自分の可能性を思いっきり発揮させることができていません。
ご自身の観点に関心を持ち、観点を知り、観点が生まれる仕組みが理解できれば人生は自然と上手くいきます。
知れば知るほどすべてが整理されていくのでとっても面白いです。
今回の記事では、観点を知ること・観点が生まれる仕組みを理解することの核心パートまでは語っていないので、もし興味があればぜひセッションやセミナーを受けてみてください。
①観点を知る → 無意識エンジン発見セッション
②観点が生まれる仕組みを理解する → Industry5.0セミナー
観点から自由になればワクワク人生スタートです!
まずは自分の観点を知ることから始めてみませんか?
美談年民
