
【詩】明けの明星
盲いた、油ぎった者が、人を喰らっている。背丈は5メートルを優に越えていて、呼吸の音は聴こえない。かわりに駆動部のいくつかが、金属の摩擦音のような、いや、それそのものの音を不快にも響き渡らせている。あれは機械だ。潤滑油を滾らせ、全身を嘶かせながら、ただプログラムによって対象を喰らう獣だ。そして喰われているのは、俺だ。俺の肉体だ。その光景を眺めながらも、そう直感した。
捕食の光景は、血飛沫が飛ぶとか、臓器が漏れ落ちるとか、そんなスプラッターな光景ではなくて、例えるなら紙に描かれた俺がシュレッダーにかけられて消えていくようなものだ。機械の口腔からはちり紙が漏れ出て、俺の肉体であったものの痕跡はたったそれだけしか残らない。しかしその痕跡からは人間であった証が毛ほども見あたらない。臭いも、熱も、何もかも。らしさがない。何が人間を人間足らしめているのか。この場合においては、血肉の有無であったのだろう。死の際に血肉を残せなかった俺は、人として認められない死を迎えたのかもしれない。
紙屑になる俺の後ろで、泣き叫ぶ人がいる。俺の亡骸がこの世からなくなった今、機械の口腔が次に目指す宛は明白だった。しかし俺は、その人が果たして何者だったのか、明確に思い出すことができない。その人の今際の際に、感慨さえも湧かない。
機械の傍らで、食われる人間を見てほくそ笑む人もいる。その人も、笑みを浮かべたままで、金属の塊の巨躯に押し潰された。あいつが俺たちをこんな死地へと追いやったのか、と感情の矛先を向ける暇さえなく、宙ぶらりんに残されてしまった。
あとには何もない。塵すらも、風に吹かれてどこかへ行った。ここにいたのは、たぶん、人間ではなかったのだろう。
機械の頭部が辺りを見回している。それがこちらを向く前に、俺は直感的に逃走を始めていた。
その逃走はなぜか、足を駆け出すでなく、上空へと意識が向けられていた。
一対の翼が俺の体を支えている。それは腰部から広がっていて、寒暖を感じる神経がしっかりと通っていた。翼に意識を向け、水泳のバタフライのように大きく漕ぎ出せば、空へと飛び去ることができた。垂直に。
出鱈目な方法だが、現に俺は飛んでいる。何も考えずとも、その使い方を知っていた。違和感がないことに、違和感さえなかった。吐き気さえもなく、その行動を俺の意識は受け入れていた。
見下ろせば黒い都市が広がっている。機械は何体も都市を駆け回っているようだが、もはや手のひらほどの大きさに見えて、俺にはまるで他人事だった。これ以上、上へと逃げる必要もない。滑空して横に飛べないか、と思ったら、するりとできた。自然に体は、空を駆けた。
生温い蒸気の風が不意に空く
黒い都市はぽつぽつと消えやがては完全な緑や湖に埋め尽くされる。少し気持ちが落ち着いて、太陽のほうを見やると厚い雲がそう遠くないあちらこちらに広がる。日差しが目に入ってたまらないから、盛る深緑の地上へと視線を戻して、少しばかり目をこすっていると、あたりの風景とは別な挙動をする物体が目に入った。
赤・黄・青の装飾をそれぞれ身につけた子供のような風貌の幼女たちが上昇してくる。その背には光を通過する薄羽が広がっている。彼女たちを形容するならば、妖精、と呼べる風貌だった。しかしその羽は、飛行に使用しているとは思えないほどに、表情豊かな伸縮を繰り返していた。三人は談笑しているようで、ちょうど通学路で、自分たちを取り囲む空間以外には目もくれず、それぞれ思い思いの興味へと一直線な様のようだった。
彼女たちの足元に架けられた透明なエスカレーターは、瞬く間に空の天井へと誘っていく。その進路は俺と交差する間近に感じた。
彼女たちはこちらには一瞥もくれない。あの機械のように、悲鳴を上げた人のように、いまの俺には微塵も関心を示していない。
それでも俺は、手を伸ばした。あと数秒で、互いの描く放物線が交わる。きっと。あと、3秒。2秒。1秒。
高鳴りが 証明するのは ×××××
伸ばした手は腕五つ分くらい届かずに空を掴んだ。それでも俺の視線は、彼女たちの進路からしばし離れず、伸ばした手はもとの位置に戻ろうとしなかった。三人の影が遠くなる。そのすぐ近くに、いま、俺はいたのだ。その感慨に、誰一人、目もくれない。それはまるでーー
そうして轟音が聴覚を奪い、黒い影が視界を覆った。
まるで森の風景には似つかない旅客機が、俺の眼前を通り過ぎたらしい。そう認識する頃には鉄の塊は過ぎ去り、視界はふたたび開けていて、さきほどまで彼女たちの影が、少しずつ消えていくところだった。思わず声が漏れ、その方へ向かって飛びたくなるが、この体でも、急な方向転換は叶わないらしい。
青、黄と色彩が消えて、最後に赤が消えていった。水彩がキャンバスに滲むのを、逆再生しているかのようだった。
それがあの轟音の固体によってもたらされた消滅なのか、それとも彼女たちが厚い雲を通り抜けて見えなくなってしまったのか、俺には判別がつかなかった。しかし俺は、この世界のどこかに、また彼女たちが現れることを知っている。だから、そのどちらだとしても、関心のある違いではない。
もう我慢ならない。俺はひどく高揚していて、歪む口元を覆った。それは長年待っていた映画やゲームの最新情報が満を持して公開される瞬間のように、ずっと応援しているスポーツチームの快進撃を友人と見るかのように、青春とともにあった最愛の曲の生演奏を間近で見たときのように、大好きな作家さんの新作を本人から手渡しで購入するときのように、叫び出したい気持ちがあった。それをもう、抑えきることはできなかった。
全身を擲ち放り向かい行く 人に成るため人を棄て 己への情けとうに棄て 人への情を見棄てるな その狂った道理に 俺は往く
それほどまでにこの身をも 棄てた果ての地あるものを どれほど言葉を尽くそうと 説明できはしないから 人を遠ざけ人を去り それでも人を想い往く その曲がった摂理に 俺は去ぬ
明けの明星その入らぬ 闇に沈んで人でなし 願うど伸ばせど 人ならず 梦であろうとした俺は ただの実なき者であり その証明を誰もせぬ 罪状はなく罰もない ただ中空に放られた 根無し草たる俺だけが 俺を蝕む、俺は去ぬ
明けの明星 俺なしに 夜空を駆ける その軌跡 俺の手にもあったのだ 確かに胸にもらったよ 心の臓から取り出して 叶うのならばお見せしたい あなたの熱のそのために 今日まで生きてこれました
伸ばした腕は届かない 抱えた熱は空に消ゆ 誰にも渡せず朽ちるのか 熱など俺の錯覚で はじめから既に無かったか 納得するにはあまりにも 大事に抱えてしまったよ
ああこの熱がこの頬を 伝って消えるそれだけで 誰一人にも届かない それが俺の行く道の果て いやそうなのだとしても、確かに在った、在ったんだ 誰にも否定させはしない 土台、肯定もないのだろう けれども無ではないんだよ なかったことにはならないよ
なかったことには、ならないよ




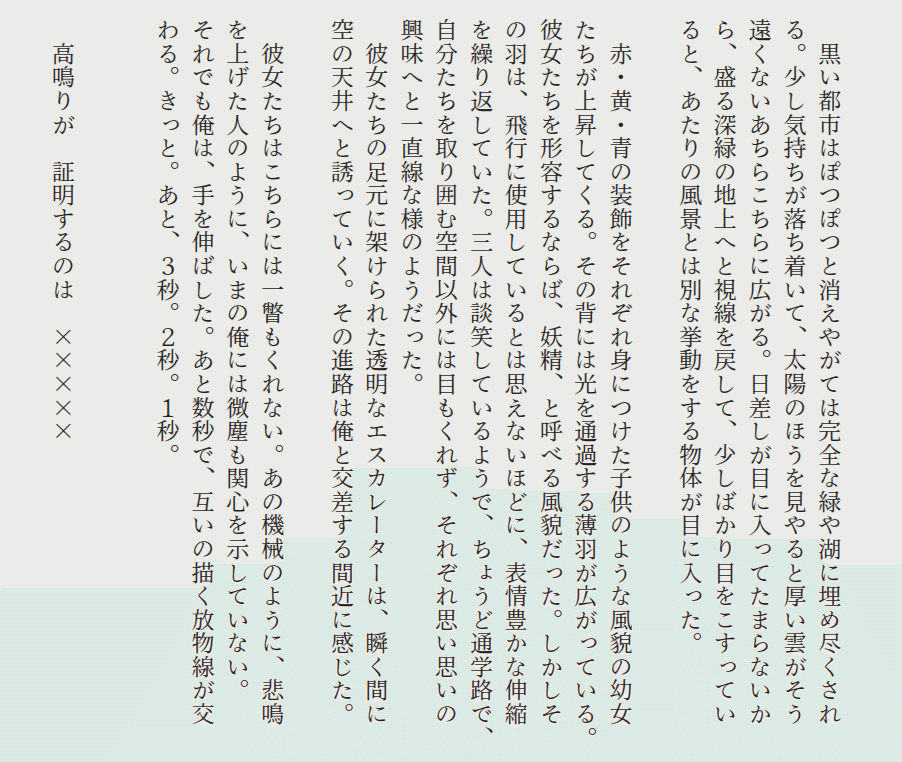


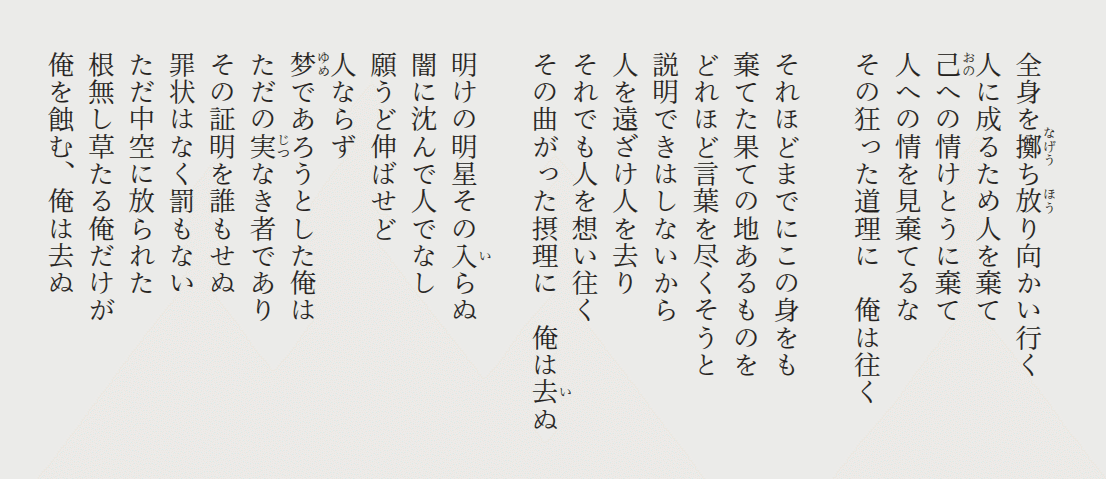

※東方Project(東方三月精)の二次創作です
