
植民地支配への過程を丁寧に論述した好著~森万佑子「韓国併合:大韓帝国の成立から崩壊まで」(中公新書)
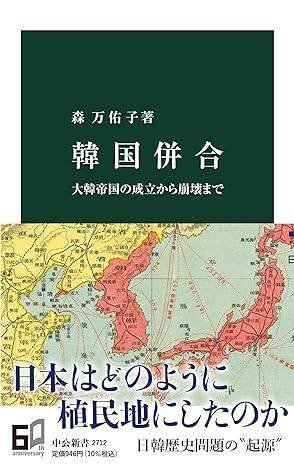
少し前にこの著者とこの著作のことをネット記事で読んで、興味が出たので読んでみた。著者は1983年生まれで、専門は朝鮮近代史、韓国・朝鮮地域研究。東京大学&ソウル大学両方の大学院博士課程を経て現在は東京女子大学現代教養学部准教授。著者自身があとがきで書いているように、本書は「冷戦も韓国の民主化運動も記憶にない世代」が、最近の地域研究という学問成果や論争を踏まえて論述したものである。これまでも多くの歴史書で大日本帝国が朝鮮半島を植民地化していく過程が描かれてきたが、それらは「日本側の動き」が軸になったものがほとんどで、その中での民衆の抵抗は描かれていても、当時の朝鮮王朝~大韓帝国へと続く流れの中での「政権中枢・支配層の動き」がもうひとつよく見えてこないもどかしさがあった。この著作はそういう意味で、「朝鮮半島側の(特に政権内の)動き」を軸に論述されているので、私も改めて学ぶところも多かった。著者はこの著作の中で、当時の帝国日本の「帝国主義的侵略性」について良くも悪くもほぼ言及することなく、個人の視点を入れずに非常にフラットに論述している。ここでの著者の「客観性」を批判する人は必ずいるだろうし私も多少違和感を感じながらの読書ではあったが、しかし一方で私にはかえって当時の朝鮮側の動きがよく見えてきて有益だった。以下、この著作の要点を私なりに簡潔にまとめておく。
①中華秩序の中の朝鮮王朝
朝鮮王朝は1392年李成桂(イ・ソンゲ)による建国以来、中国明王朝の冊封を受けてきたが、この「朝貢と冊封関係」での朝鮮の立ち位置を著者は「属国」と称するが、これは歴史学会・政治学会などで定着した語法なのだろうか?確かに中国の近隣諸国(朝鮮・ベトナムなど)は大国との良好な関係維持のために「冊封体制」に組み込まれていたが、政治的主権は確固として維持されていたし、「属国」とは少々違うのではないか?朝貢による冊封体制とはひとえに「儀礼的関係」だろう。そこの「定義」に私はかなり違和感を感じた。しかし、こうした「朝貢・冊封関係」と西欧近代国民国家間の「条約」による国家関係との差異と、その間で揺れ動く朝鮮王朝の姿~というのはよく分かる。そして中国が明から満州族による清に王朝交代した後での、「明こそが正当な王朝でそれを引き継ぐ朝鮮こそが正統派」と清を軽視する朝鮮の支配層と「小中華思想」。1864年の朝鮮王朝最後の国王:高宗(コジョン)即位から続く、米商船シャーマン号による開国通商要求やフランスの条約締結要求などことごとく拒否し、また、明治維新による新政府樹立を伝える日本の「書契」も「中国皇帝のみ使える勅・皇という文字」の使用を巡り受け取りを拒否するなど(後に受領)、一貫して「中国との関係」を最重要視し他国の影響を排除しようとする姿勢。結局、1876年に日本が軍艦を派遣した「江華島(カンファド)事件」で日朝修好条規が締結され、「武力による開国」が強制的になされるが、その後の清王朝の「条約」による宗属関係改変の試みとも併せて、当時の「世界観の転換」が容易ならざるものであったことが分かる。
②甲申政変による近代化の試みと挫折
名門両班(ヤンバン)出身の金玉均(キム・オッキュン)ら若手「開化派」は、アジアで唯一近代化に成功した日本に学ぶため留学し、福沢諭吉らに教えを受けて朝鮮の近代化のために1884年クーデターを起こすが、あえなく失敗。袁世凱ら清軍の駐屯を許し、開化派の若者たちは亡命を余儀なくされる(金玉均は上海で客死)。一方、朝鮮王朝は自主拡大の試みとして各国に全権大使を派遣するなど、当時の王朝内で清に依存しようとする守旧派と近代化を目指す勢力がせめぎ合っていたことも事実。
③日清戦争~朝鮮での利権を巡る争い
全琫準ら非両班指導者による東学党の乱(甲午農民戦争)は、官吏の腐敗汚職や列強諸国による圧迫への反発が原因だが、朝鮮王朝は清に派兵依頼。それに対抗する日本の派兵。この勝敗によって朝鮮は清との宗属関係を断絶。日本によって様々な近代化改革案が提示されていく。これらは日本軍駐屯という武力による威嚇を常に伴う朝鮮への圧迫外交でもあった。そして、国王高宗の妻:閔妃(ミンビ)がロシアと手を組み日本の勢力を排除しようと画策する中、日本公使や軍部による王宮侵入と閔妃殺害~それへの朝鮮民衆反発と高宗のロシア公館避難。この頃からロシアは朝鮮の「中立化」を主張していて、満州地域への進出はあっても朝鮮半島への露骨な権益画策はなかった。
④大韓帝国の成立
1897年の高宗の皇帝即位と大韓帝国成立。明朝中華を意識した新国家の樹立と、高宗のあくまで君主が全権を掌握する「君主制維持」の意思。一方、開化派による「独立協会」設立と日本のような立憲君主制への希求。皇帝のロシア接近と独立協会の反発~そして強制解散。この頃の高宗のあくまで儒教を軸とした国家体制への意思と、それでも国を改革していかねばならない潮流との衝突と葛藤は、やがて欧米列強が見て見ぬふりをする中、日本の軍事圧力の波に呑まれていくようになる。
⑤日韓議定書から第二次日韓協約まで
1904年2月に締結されたこの議定書は、日露戦争に伴い漢城(ハンソン:現ソウル)を軍事占領する中で強要された、日本の本格的植民地支配の布石であった。これにより大韓帝国の外交権は、「大日本帝国の承認」という足枷をはめられていく。そして「第一次日韓協約」での「顧問」による内政支配。当時の大韓帝国閣僚らも様々に抵抗を示しながらも、結局は日本の威圧に押し切られていく。そして1905年「第二次日韓協約」による大韓帝国の保護国化と統監府設置。当時、親日派団体:一進会などはこれを推奨し伊藤博文らと「支配の既定路線化」を図っていく。この頃の所謂「親日派」の多くは日本留学を経て朝鮮近代化を目指した者たちでもあり、そうした若者たちが大韓帝国支配層への不信・不満から、日本のアジア主義者と共に結局は帝国日本の植民地政策に加担していく流れは、今から見ると何とももどかしい限りである。ちなみに第二次日韓協約締結に関わった5人の閣僚~李完用(イ・ワニョン)らは今では「乙巳(ウルサ)五賊」として「売国奴の象徴」のように捉えられている。その後の高宗による「ハーグ密使事件」などでも、欧米列強がいかに朝鮮の状況に冷淡であったがか如実に表れている。
⑥第三次日韓協約と大韓帝国の終焉
1907年の第三次日韓協約から1910年「日韓併合」による大韓帝国消滅まではまさになし崩し的に流れていくが、その当時も「義兵闘争」という一般民衆・農民などによる武装闘争が展開されていて、決して朝鮮民衆は「座して死を待って」いたわけではない。そしてそうした抵抗の一環としての満州ハルピンでの独立運動家:安重根(アン・ジュングン)による伊藤博文暗殺。
<付記>「韓国併合」を巡る日韓両国の論争について詳細に踏み込むことはしないが、総論的には、当時まだ近代国家として整備されていない朝鮮の国家制度の中での各種文書の保管状況の日本との違い、各種国家間文書の解釈の相違~そこには中国冊封体制・儒教的世界と西欧近代国家との価値観の違いが現れていて、容易には決着しない問題。しかし、脅迫や強制性の有無などについては、日本の研究者の見解は「客観性」という名の「責任逃れ」にしか見えない~と言えば言い過ぎか?さらに両国協約締結時の大韓帝国閣僚の印章を日本官憲が盗んでいたという疑惑。間違いないのは、著者があとがきの最後に記しているように「多くの朝鮮人が日本の支配に合意せず、歓迎しなかったこと」であり、「日本が『合意』や『正当性』を無理やりにでも得ようとしたこと」である。
